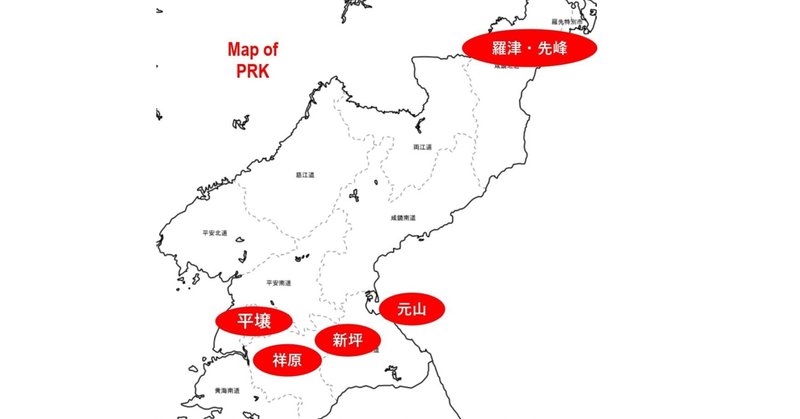
長編小説「平壌へ至る道」(112)
がたん。
連結器の音が響き渡り、列車が再び動き始めた。李が背中を叩いてくる。
「毎度のことながら緊張するなあ。でももう大丈夫」
町のざわめきが遠ざかっていく。相慶は床の隙間から目を凝らしたが、網膜に映るのは相変わらず線路と枕木、敷石だけだった。
「列車は今、操作場に向かっているはずだ」
李昌徳が相棒の懸念を和らげるように説明した。間もなく君の長い旅のゴールだよ。
その言葉を裏打ちするように、鉄の擦れる音を発しながら再び列車が完全に停止した。先ほどの靴音とは明らかに緊張感の違うーと相慶は思うようにしたー足音が床上で鳴る。貨車の床板、隠し部屋からすれば天井板の隠し扉に手がかけられる音に混じって、鼻歌が微かに聞こえてきた。
安州からの脱北者たちはそうっと安堵の息を吐いた。兵士ならば鼻歌を歌いながら作業を行う場面ではないはずだ。
天井板が外された。
眩しい光が飛び込んでくる。
「さ、鄭さんも辺さんも降りようか」
相慶もチャンスクも顔をしかめ、なかなか明順応が進まない中、即座に強張った体を起こすこともままならず、長い時間をかけて這いつくばるようにして貨車の荷台へと移動した。貨物車は完全にもぬけの殻となっていた。
中国鉄道局のものらしい制服をきた二名の男が、李昌徳と中国語で談笑している。チャンスクが耳元で囁いた。
「今回も死に損なったな、と言っている。笑えない冗談だけど、少なくとも冗談を言える場所に来たということね」
安州の協力者と違い、丹東の方には笑顔があった。
相互に密告の恐れもないのだろう、貨車を降りた二人の鉄道員は線路のそばで相変わらず何らかの冗談を言い合いながら茶を淹れていた。その香りもまた、ここが既に国境の向こうであることを教えてくれている。
李昌徳が大きく伸びをした。
「さて、僕は直ぐにでも駅舎に引き返し、大連行きの列車に乗る。そこから仁川への船で帰国だ。これは君の丹東での一時滞在用ホテルの住所。君の名前で昨夜から明々後日の朝まで予約済だそうだ。部屋に盗聴器はないし、安心してテレビをつけて、日本の衛星放送だって大音量で楽しんでくれ」
「本当にありがとう。日本に来ることがあれば連絡してくれ。浴びるほど飲もうや」
二人の男は握手を通じて、メモの受け渡しも完了させた。
「じゃあ、私も行くわね」
「どこに?」
「前に言ったでしょ?私は下世話な中国語なら話せるし、延吉あたりに移動して、そこで朝鮮族のコロニーにでも入るわ」
「チャンスク、今は危険だ。そこには北朝鮮の工作員が何人も潜入しているはずだし、君の人相書きも出回っているだろう」
「相慶オッパ、あなたはあなたの心配だけしておけばいいのよ」
「チャンスク、もう時間も遅い。せめて一晩だけでも、このホテルで一緒に過ごそう。宿泊代だって浮くだろ?」
彼女はしばし思案し、渋々答えた。じゃあ、一晩だけ。
待避線から丹東駅まで歩き、駅舎を周回し駅前広場に出る。
「何これ」チャンスクが息を呑んだ。
高層ビル、看板、ネオンサイン、照明、通りを過ぎ行く自動車、通りを歩く人々。それらは様々な色で彩られていた。
モノクロの世界から突如として総天然色の世界へ。
色と共に国境を挟んで大きく異なるのは、町中に響き渡る音の種類と数量だった。
車がクラクションを鳴らし合い、人々は大きな声で怒鳴り合うように自由に会話していた。中国の辺境都市ですら、朝鮮民主主義人民共和国というフィルターを通して眺めてみれば、自由、平等、博愛の精神に溢れた桃源郷のように見えるのだった。
雑多な色彩と騒音を背景に、駅前広場には巨大な毛沢東の像があった。
その高さ、大きさ、コート姿で右手を掲げた様子は、まさに万寿台の金日成像と似通っていた。首から下は大量生産した汎用型モデルで、その上に載せる顔だけをすげ替えているようだった。あるいはこれがアジアの独裁国家における偶像の建築基準なのかも知れない。
但しこちらは毎晩清掃する者などいないのだろう、自動車からの排気ガスを浴び続けている赤茶色の石像は、平壌のそれに比べるとくすんで見えた。
「なんか、おかしいね」チャンスクが嗤った。
「私は世界一の裸の王様です、と言ってるようなものなのに、本人は気付かないんだね」
「本当にそうだな」
「ねえオッパ、今夜この像にも落書きすれば?」
「勘弁してくれ」
駅周辺には煮込んでジャムにできそうなほどヤミ両替商で溢れ返っていた。適当な売人に声をかけ、人民元を米ドルと交換し、二人はタクシーに乗った。チャンスクはカネさえ払えば自分の行きたい最終目的地まで乗せていってくれる個人専用の交通機関、という概念自体が初めての体験で、これは覚えなければならないことがたくさんある、とひとりごちた。
李昌徳から渡されたメモにあったホテルの前にタクシーが到着した。それは中に床も壁もちゃんと入っている、川沿いにそびえる高層の建物で、上階からは夜間も人工光で不夜城の様相を呈している我が方の街と、新鴨緑江の向こうに漆黒の闇が無限に広がる貧しき属国の光景を一度に楽しめる趣向になっているらしかった。いかにも富裕層の中国人が好みそうな、底意地と趣味の悪さを象徴していた。
「お帰り。成功したようだね」
部屋に入ると、議長がそこで待っていた。
「可愛らしいお嬢さんという土産まで付けてきたのか」
シャワーを浴びた。温水で体を洗うのは、相慶にとっては日本海を船で出る前の晩以来のことで、そしてチャンスクにとってはおよそ十年ぶりの出来事だった。彼女は二時間近くバスルームから出てこず、二人の男を心配させた。
「一体どういう土産だ。彼女が朴泰平が言ってたソヨンなのか?」
「話せば長い。今は疲れている。頭も割れるようや。ビールを一杯くれ。すぐ寝る。話は明日」
帰還した工作員は、その言葉も終わらぬうち、眠りに陥った。
目が覚めたのは翌日の昼過ぎで、部屋には誰もいなかった。チャンスクのわずかな荷物も消えていて、彼女が去ったことは直感的に察せられた。
テーブルに残された短い手紙。
『あんたについていったのは、あの元山の地獄から逃げ出したかったから。そしてお金のため。それだけ。あなたの仲間が余った工作資金から一万ドルを渡してきたから、その半分だけ頂戴しました。私の話を聞いてくれたことには感謝している。無事に日本に帰ってね。辺昌淑』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
