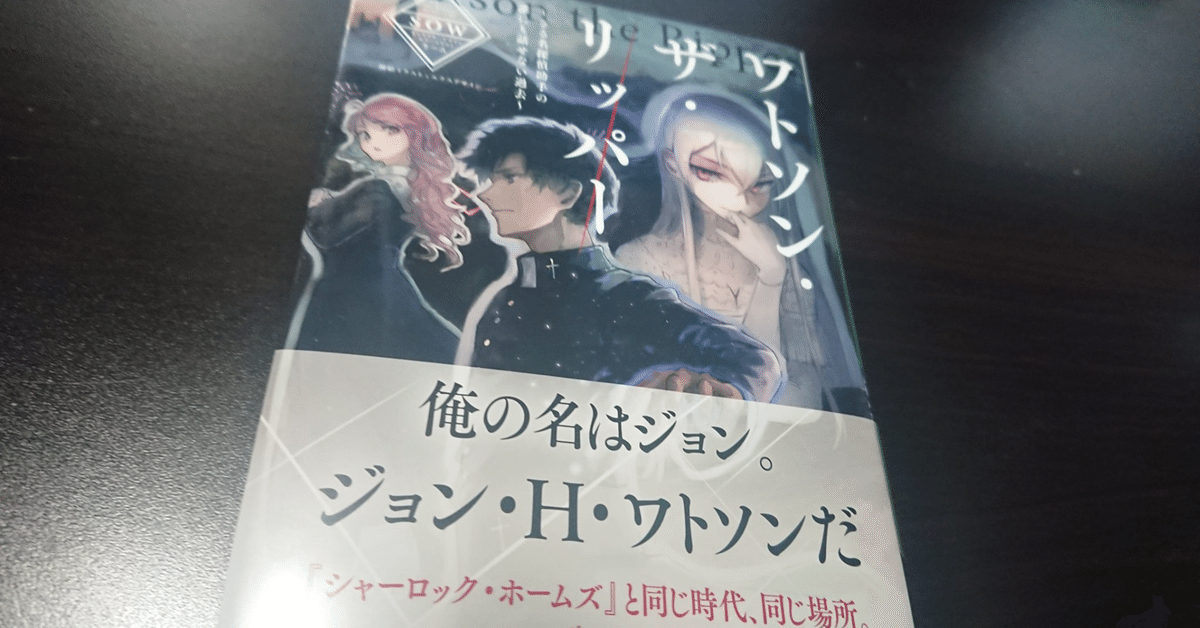
ワトソン・ザ・リッパー 四章(4)
翌日の夜――
フェイが用意した隠れ家は、ロンドン市街の郊外……いわゆる「ロンドン・ウォール」の外側に位置するエリアにあった。
古来より、貴族とは複数の邸宅を所有していた。
特に、地方の荘園領主などは、ロンドンに訪れた際、滞在用の「宿」としての邸宅を所有する習慣があった。
これら「タウンハウス」は、時代の流れとともに、交通網の発達や習慣の変化などとともに使われなくなり、市内の富裕層の住人の屋敷として転用されるようになる。
彼女の屋敷も、そういったもののひとつなのだ。
そして、その屋敷の敷地に、不穏な影が近づいていた。
「………………」
ガシャリ、ガシャリと、思い足音を響かせる。
そのフォルムは、教会の襲撃を行った、オーランドに返り討ちにあった、あの“切り裂きジャック”と同じであった。
両肩の突起から、煙を吐き出す。
その煙は周辺を覆い、まるで霧のように一帯を包み込んでいく。
「来たか」
屋敷の入口に迫ろうとしたところで、声がかけられる。
全身甲冑の、霧のバケモノは、その声の方を向く。
「招待状は、目に入ったようだな」
そこにいたのは、オーランドであった。
その目には、激しい怒りと憎しみがこもっていた。
「お前が、“切り裂きジャック”の本体か?」
「………………………」
全身甲冑の大男は答えない。
ただ無言で、手の持った巨大な槍を構える。
「今度は槍か!」
一度戦って、相手の正体はわからないが、「どういうものか」は概ねつかんだ。
あれは、バケモノや怪物のたぐいではない。
科学の産物だ。
常人なら纏えないほどの重く、分厚い鎧。
それを、なんらかの動力によって動かしている。
鎧と言うよりも、乗り物の一種と考えたほうが近い。
だが、自分の能力が「効きづらい」点が不可解であった。
「……………!!」
唸りを上げ、“切り裂きジャック”が襲いかかる。
大砲のような突進で、オーランドに槍を打ち込もうとする。
(本当に大丈夫なんだろうな………!!)
先の戦いでの話をしたところ、フェイは興味深そうに聞くと、笑いながら言った。
「なんだ、どうとでもできる相手じゃあないか」――と。
そして、わずか一日で、対抗手段を用意した。
その上で、「邸宅の、できるだけ見通しのいい居場所に追い込め」と、オーランドが餌になるように命じた。
(無茶苦茶を言いやがるが、今はアイツを信用するしかない!)
正体不明の敵に対抗できるのは、予測不可能な存在しかないのだ。
“切り裂きジャック“の槍が迫る、その寸前、それは起こった。
「―――――――!?」
突如として、横にふっとばされる大男。
直後、響き渡る、野獣の咆哮のような轟音。
「なんだ!?」
まるで、見えざる巨人の大槌に殴り飛ばされたかのような光景であった。
「グッ……ガッ……」
困惑は、直撃を食らった大男のほうが深刻であった。
地面に転がりながらも、再び立ち上がろうとするが、そこにまたしても、「音よりも速く」起こったなにかに殴り飛ばされ、ふっとばされた。
二度目の衝撃には耐えられなかったのか、そのまま、“切り裂きジャック”は倒れ、動かなくなった。
「なにが………あった……?」
呆然とするオーランド。
自分が死力を尽くして戦ったのと同じ存在が、いともあっさりなぎ倒されれば、なんとも言えない複雑な気持ちになろうというものであった。
「やーやーやー、計画通りで予定通り! ……あんまり思い通りに進むと、却って拍子抜けで面白くないな」
言いたい放題言いながら、茂みの中から現れたのは、ライフルを肩に担いだ、フェイであった。
「それは……なんだ……その猟銃のバケモノのようなものは……?」
フォルムだけならば、一般のライフルとさほど変わらない。
だが大きさが、二倍近い。
「うん、前にな。携行できる小火器が、どこまで威力を高めることができるかなと思ってな。ドイツのガンスミスの兄弟に発注したんだ」
ドイツ人というのは、総じて凝り性である。
発注した仕様以上のスペックのものを作り出すきらいのある、「誰がそこまでやれと言った」の国とも言われている。
「だがあまりにも威力が高すぎてな、反動がすごい。常人が撃てば肩が外れるな」
「それはもはや銃じゃない………」
さあに呆れ、呆れ果てるオーランドであった。
「しかし……銃で倒せるとは………」
人外の力を行使する、怪物のような敵が、あまりにもまっとうな方法で対処できたことに、これまた、複雑な気分になった。
「なにを言うか、こいつらは要はな、超常の力を持って、お前のような人外の力を持つ者に対しての防御を仕込んでいた。だが、物理攻撃に関しては、分厚い装甲という、物理の防御しか行っていなかった」
それでも、大砲の一撃でも耐えきれそうな装甲である。
「それならば、それ以上の物理の力でぶん殴ればいい。簡単な話だ。オマエたちはいかんな、難しく考えすぎた、物事はシンプルな方がいいぞ」
とはいえ、フェイの使った巨大ライフルは、まともな人間を殺す武器ではなかった。
こんなものの使用用途など、全体を鋼鉄で覆った馬車を撃つくらいのものだろう。
ちなみに、世界初の実用戦車が現れるのは、この四半世紀後。
そして、その戦車を倒すための、対戦車ライフルが作られるのは、そのさらにもうちょっと先に、ドイツのマウザーM1918が元祖となる。
「ふむ……さてと」
仕留めた獲物を確認しようと、フェイは全身甲冑の大男に近づく。
「おや……貫通はしていないか……威力に問題があるのではなく、弾頭の問題だな。この使用結果をレポートにまとめてフィードバックさせれば、さらにいい銃ができそうだな」
だが、弾丸は貫通しなくとも、衝撃は通る。
「中の人」は、それこそ、棍棒で殴られたような状態であろう。
「さてと……これはどうやって引っ剥がすのかなぁ~♪」
お人形さんの服を脱がせるように、喜々としてあちこちをいじり、鎧の接合を解除する。
数度のアプローチの結果、留め金の一つが外れ、ヘルメット部分が取れた。
「さぁて、御開帳だ」
現れたその顔は――老人、であった。
「これは………誰だ……?」
歳の頃七十くらいの、かなりの高齢。
身なりは整っておる。
市井の人間ではない。軍人、警官のたぐいではない。
むしろ、肉体労働者のそれではなく、頭脳労働者のそれであった。
「ははぁ、なるほど、こうきたか」
フェイは、その老父の顔を知っていたようだ。
「何者なんだ、こいつは………?」
マーガレットを殺した犯人、“切り裂きジャック”の正体――
「サー・ウィリアム……知らんかね、御典医殿だよ」
「御典医……王宮に仕える、医師だと!?」
サー・ウィリアム――正確には、サー・ウィリアム・ガル。
三代に渡って、英国王室の主治医を務めた医師である。
後世においては、神経性過食欲症……「過食症」の名付け親として名が残っている。
「なんで御典医が、“切り裂きジャック”なんだ!?」
わけの分からぬ話に、オーランドはさらに混乱した。
「うっ……ううう………」
そう言っている間に、気絶していたガルの意識が戻り始める。
「ううっ……君たちは………」
「動くな、喚くな!!」
目を開き、口を動かしたガルに、オーランドは怒りを込めて怒鳴りつける。
「答えろ! なぜマーガレットを殺した! 貴様らの……お前らの目的は何だ!! 離せ! 首を切り落とすぞ!」
脅しではなく、本気であった。
今この段階でも、怒りを抑えるのに、苦労するほどだった。
「落ち着け、ジェイムスくん」
「落ち着けるか!」
「そこをなんとか落ち着け」
フェイは取り乱すオーランドの腕を掴むと、くるりとひねって、投げ飛ばした。
「がはっ!? な、なんだ!?」
「東洋の神秘だ」
「あのなぁ……」
受け身も取れず、したたか背中を打って、声が出せなくなった彼に代わり、フェイが問いただす。
「こんばんはウィリアム卿、お会いできて光栄だよ。招待状は見ていただけたようだな」
「君らは、そうか……あれは……誘い出されたか……」
「ああ、いともあっさりな」
ガルの言葉に、フェイはにんまりと笑う。
この日の朝、フェイは新聞各社に、数行の「伝言」を載せた。
曰く「アルバート様、マーガレット嬢のご子息は、当家にてお預かりしております。至急、ご連絡いただけますよう、お願いいたします」と。
そして、この屋敷の住所を載せ、来訪者を待った。
「貴様がここに来たということは……なるほど、ようやく全景が見えてきた。マーガレットとやらとの間に子をなした男……アルバートとやらは……」
「やめろ……」
ガルが止めようとするが、フェイは止まらない。
「アルバート・ヴィクター………だな?」
「!!!」
フェイが口にした名前を聞いて、ガルは目を見開き、声を発せなくなる。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
