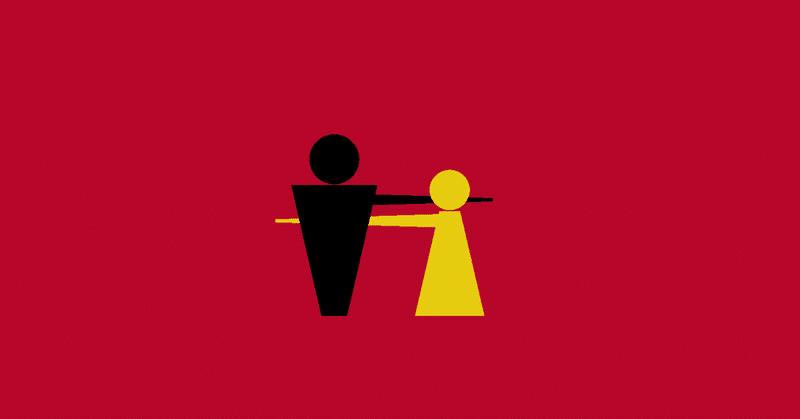
互い咎の処方 5話
作品情報
https://note.mu/sowano/m/m45bec0c01b32
1話
https://note.mu/sowano/n/nf8615209be2f
***
ぼくが部屋に帰ってくると、ほどなくして薫ももどってくる。
「ほんと、つまらない人たち」と笑顔で肩をすくめると、自分のベッドに飛び込む。「今、わたしが死体だったらどうしてた?」
「きみがそう簡単に死ぬものか」ぼくは、ベッドの縁に腰掛け、ビデオテープをじっと見つめる。
あの2人の不快さに我慢ならず離脱してしまったが、今からでも全員を集めるべきではないか?中身を見せる必要は無い。ただ、危険を周知し警戒を呼びかけるだけでよい。なにか対策もとれるだろう。
「お悩み中」薫が寝転がりぼくに言う。「優柔不断な執一君がいるぞー」
「うるさい」
……ビデオを置いた奴の狙いはなんなんだ?先ほどの他の参加者の様子を見ている限り、このビデオは、ぼくらにだけ与えられたようだった。薫のいうとおり、単に混乱させるだけなら、ぼくたちにだけビデオを見せる意味はない。全員に見せてしまったほうがより混乱は大きなものになるはずだ。
「ぼくらを、他の参加者から孤立させたかった……?」ぼくらだけに警戒させ、こうして、部屋に引きこもらせることが目的ということはあり得ないだろうか?
「違うんじゃない」薫がいう。「普通の人は、不安に駆られたら、誰かに相談して、共有しようとすると思う。私たちがまだビデオのことを触れ回ってないほうが、あちらとしては、イレギュラー」
「このビデオを知らしめるだろうって思うなら、どうして、ビデオを全員に配らなかったんだ?」
「わかんない」薫は笑う。「ダビングするのがめんどくさかったんじゃない?」
「そんな馬鹿な……」一応ケースからビデオテープを取り出してみる。曖昧な知識では、そう、ラベル面横の『爪』が折られていると、ダビングができなかったはずだ。「……折られてる」まさか、本当にそんな間抜けな理由でビデオを用意できなかったっていうのか……?
「……危ないよ。執一君」薫がうつぶせになって、自分の腕を枕にしていう。「相手がなんのために、これを渡してきたのか……、それも大事だけど、一番は、自分の身をできる限り安全にしておくこと、今はそれ以外どうでも良いこと」
「今この状況が安全だとは思えないけどな」
「危険の中に潜ってるんだから、どうしようもないもの……でも、安心してよ」薫が腕枕から顔を覗かせていう。「もう少し見たら、わかるから」
――寒気がした。
「……もう、犯人がわかってるっていうのか?」
「ううん。敵じゃない人が、何人かわかるだろうっていう予測かな」
ちょっとずれがあるのかな、と薫は言う。
「推理小説みたいに、犯人を言い当てられれば勝ちって、執一君は思ってるんじゃない?でも、違うよ。これは、『戦争』だよ」
——戦争。
「……犯人を特定しても、意味のない状況もありえる、と?」
「そう。その前に片をつけないと、殺されるかも」
一瞬、緊張が走った。
「……」ぼくは気がつく。『敵じゃない人がわかる』『片をつける』……もし、『敵』を見つけたら薫はどうするというのか。もしかしたら、薫は――
そのときだった。ぼくはわずかな揺れを、続いてなにかが落ちたような音を聞いた。
「地震……?」しかし、地震とはなにかが違った。
少し間を置いて、男性の叫び声が聞こえた。ぼくらの部屋のすぐ側からだった。
「待って」振り返ると、薫がぼくに鞘に入った果物ナイフを差し出している。
「準備の良いやつ」ぼくはそれを受け取る。
「私も持ってるよ」と薫はTシャツをめくって見せる。ジーンズとお腹の間に同型のナイフを挟み込んでいた。
「怪我するなよ」
「ありがよ」
ぼくらは部屋を出た。
悲鳴が聞こえたのは、ぼくらの隣の部屋からだった。それは、絵美さんと、武広さんの泊まっている部屋だった。ぼくと薫がドアを開けたときには、すでに一つ向こうの美紀とマスオさんがドアから顔を覗かせていた。
「あの、どうも」美紀が頭を下げる。「今のって、この部屋からですよね?」美紀がドアを指さす。
「たぶん、そうだと思う」ぼくは応じる。
「なんか、すごかったですよね、どーんて」
「一応確認してみよう」マスオさんが悲鳴の聞こえた部屋のドアをノックする。「もしもし?すみません、どうかされましたかー?」
しかし、呼びかけに応答はなかった。
「管理人さん呼んできた方が良いよね?」美紀が言う。
「マスオさん、行ってきてもらえます?」薫が言う。
「ぼくう?まあ、良いけど……」マスオさんは階段を下り、下の階降りていった。それと入れ替わるようにして、向こうからおじさんおばさんがやってくる。
「今のは、その部屋からかね?」
「みたいですね」ぼくはうなずく。
「おーいどうしたー!大丈夫かね!」おじさんがドアを叩く。
「今、管理人さんを呼びに行ってます」
やがて、マスオさんが管理人さん――藤山老人を連れ立って戻ってきた。藤山老人はドアをノックして、
「村田様。……村田様?入らせていただきますよ?」といって、鍵――マスターキーだろう――を使って、ドアを開けた。
部屋の中は、灯りがともっていて、明るかった。ぼくと薫が泊まっているのと同じレイアウトの部屋だった。二つ並んだベッドの奥、窓の前に、武広さんが両手で頭を抱えて、へたりこんでいた。目を見開き、固まっている。
「どうかされましたか?」藤山老人が尋ねる。しかし、その声は武広さんの耳には届かない。
「村田様?――うん?」藤山老人は、眼鏡を直して、目を細める。なにか窓の向こうに見つけたようだった。
その視線を追う。半分開けられた窓。はためくレースのカーテンの向こうに誰かが居た。
ひときわ強い風が部屋の中に吹き込み、カーテンが持ち上がる。
彼女は、ベランダから身を乗り出し、外を眺めているようにも見えた。
しかし、それは不可能だった。彼女は、頭部を失っていたのだから——
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
