
津野海太郎、ベンヤミン、サブカルチャー
小野二郎と晶文社のことについて知ろうと思えば、それなりにいろんな文献や資料がある。たとえば、すでに挙げた世田谷美術館での展覧会カタログは格好の入り口だろう。身近な人たちが見た小野の人柄について知りたければ、1983年に晶文社から出された追悼文集『大きな顔』が素晴らしい。もう絶版になっていて、古本でも少し値が嵩むけれど、私は図書館で借りて読んだ。
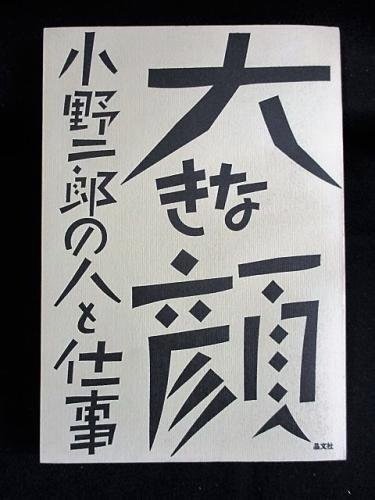
もう少し突っ込んで、彼の仕事ぶりや晶文社という出版社の成り立ちについて知りたいと思えば、私が見渡した限りでの話だけれど、津野海太郎の『おかしな時代:「ワンダーランド」と黒テントの日々』(本の雑誌社、2008年)が、特上のお薦めだ。なにしろ、小野氏のもと、長田弘と二人で初期晶文社の屋台骨を支えた名編集者の回想ルポルタージュなのだから、面白くないはずがない。
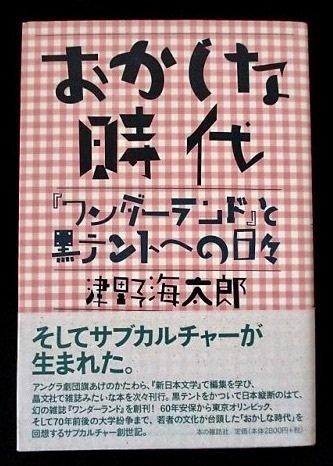
それにしても、この小野ー津野ー長田というトライアングル・フォーメーション。今から見ると、まあなんと贅沢だったのかとため息が出る。
小野は若くして亡くなってしまったけれど、モリスやイギリスの日常生活をめぐる著作を多く残しているし、津野も長田も、その後編集者の枠を超えた目覚ましい著作活動を展開している。小野は学究という側面が強く、長田は詩人としての資質がその核にある。そういう意味で津野は、私の勝手な見立てでは、3人の中でもっとも編集者らしい編集者だ。ちょっと大袈裟な言い方かもしれないが、方法意識としての「編集」が彼の仕事の全体を貫いているように見える。
もちろん、上記の本の副題に「黒テント」の一語があることからも見当がつくように、「演劇」も彼の力強いもう一本の軸である。『悲劇の批判』『ペストと劇場』『物語・日本人の占領』など、彼のそれぞれに忘れがたい著作は、その軸なしには考えられない。
だけど、津野が残してきた「本」あるいは「読書」についての著作の充実を見れば、彼が、資質的にも意志的にも「編集」という方法に囚われ、没入し、その可能性の鉱脈を手探ってきた人であることは明らかだろう。『本はどのように消えていくのか』『読書欲・編集欲』『編集の提案』『花森安治伝』、あるいは雑誌『本とコンピュータ』など、ネット上で少し調べれば一目瞭然なので、すべてを挙げることはしないけれど、著作で辿れる彼の思索は「本」というメディアの来し方行く末に寄り添うようにして展開されている。
(演劇と編集はたぶん、別のことではなくて、楕円の二つの焦点のような関係なのだろう。そして余談だが、私は彼のエッセイ集も大好きだ。忘れ難いのは『歩くひとりもの』。収められたエッセイ群ももちろん面白いのだが、その、後書き〔ちくま文庫版〕での「懺悔」には吹き出してしまった。興味のある人はぜひ読んでみて欲しい)。
そして、ここが肝だと思うのだが、彼の「編集」をめぐる思索の背景には、いつも、本というメディアが栄光を誇った時代から過去のものへとなっていく過程を不可逆的なものとして経験した者の、だけどそれを単に悔しがるだけではない、明るい寂しさとでも言いたくなるような微音がずっと鳴っている。
つまり、本が元気だったあの頃を懐かしむノスタルジックな構えではなく、寂しさを抱えつつも、むしろ、時代遅れのものの中から未掘の可能性をとりだして「現在」の上に接木しようとする、言ってみれば、弁証法的な眼差しに貫かれていて、その意味で私は、ちょっとヴァルター・ベンヤミンのことを想起してしまうのだ。なにも、ベンヤミンが津野に影響を与えたとか、そういうことを言いたいのではないけれど、時間の捉え方が直線的ではないところが、どこか似通っているように感じるのだ。
そういえば、余談だが、ベンヤミン著作集は、植草甚一の一連の著作と並んで晶文社の「看板」のひとつだったけれど(少なくとも70年代までは)、あの15巻にわたる充実の著作集は、ベンヤミンの海外翻訳として世界的にかなり早いものだったということは、どれだけ知られているのだろうか(翻訳の質が一定していなかったうらみはあるけれど)。
少なくとも英語文脈では、長い間ベンヤミンの文章は、80年代になるまで『Illuminations』 と 『Reflections』 という2冊の論集しかなく、日本語の方が格段に多くの文章を読める状態にあったということは、意外と知られていない(だから、60年代後半の日本の美術批評やデザイン批評の中ではベンヤミンに対する論究は頻繁にあるのだけれど、英語文脈では格段に少ない。その後、山のようにでてくるのではあるが)。

ベンヤミンが示した、子供の文化への関心、既成の分野による学問の垣根を越える在野の「勉強」的な態度、時代遅れのものへの弁証法的な関心、映画やミュージカルなどの大衆文化への関心、そういった特徴は、みな晶文社の出版物がひらいてくれた世界と重なる。これはむしろ、モリスー小野、そして植草が準備した土台から、そうした関心が晶文社の中で自然発酵し、その眼差しがベンヤミンを捕捉したと考えた方が実態に近いのかもしれない。津野の『おかしな時代』には、以下のような文章がある。
植草さんの本を最初に企画したとき、これをきっかけに大衆文化や若者文化や生活文化にかかわる本を持続的に出してゆこう、と小野さんとなんどか相談したことがある。
そのとき「サブカルチャー」という耳なれない言葉をつかったかどうか。私ならいかにも60年代的な「カウンター・カルチャー(対抗文化)」、小野さんであればウィリアム・モリス直伝の「レッサー・アート(小芸術)」といった語のほうをえらびそうだから、おそらくそうは呼ばなかったと思うのだが、ともあれ「あの線をもういちどつなぎなおしたいんだよ」と小野さんがあとをつづけた。「そうなると、やはりきみに中心になってほしい。テツオ(高平哲郎)も手つだいたいといっている」。(309頁)
つまり、まだ、サブカルチャーという言葉が耳なれない時代から晶文社は、そこに目を定めていたのだ。そこに深く関わっていたのが津野海太郎という編集者であり、ここでチラッと言及される高平哲郎(小野二郎の義弟で当時まだ大学生だった)であり、そして植草甚一だったということになるのだろう。小野自身が、モリスから受けとった「レッサー・アート (lesser art)」という概念をすでに胸中にあたためていたことも示唆されているが、そういった思考の系譜がベンヤミンと共鳴現象を起こしていっただろうことは、想像に難くない。
そして、その思考のネットワークは、ベンヤミンやモリスだけにとどまらない、もっと大きく複雑な広がりを持っていた。これはひとり津野や晶文社だけにおさまる話ではないのだが、晶文社をひとつの恒星とする星座を成していたとは言えそうな気がする。そんな方向にも話の穂を継いでいければと思うが、とりあえず今日はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
