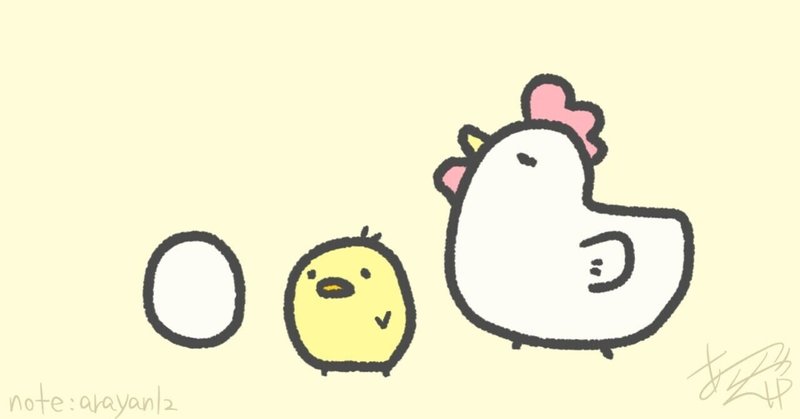
第9話:煙草
僕が煙草を吸い始めたのは大学4年の春、21歳の時である。そう言うと「20歳になったら煙草はやめるもんだ」などとバカ呼ばわりされることが多く、中には「何故、どうして。失恋?」とかその理由を追及されたりもして、ひどく迷惑なこともあったわけである。
失恋を全くしたことがないと言えばそれは嘘になるのかもしれないが、僕は男三人兄弟の中に育ち、高校もほとんど男子高のようなところだったので、女性とは割合に無縁に育って来た。
大学は学科100人の中に80人の女子がいて、そういう僕には一種のカルチャーショックだったのだが、女性が苦手な僕は学科の女子と話をすることはほとんどなかった。だからロマンスなど生まれようがなかったのである。
ついでだから書いておくが、大学2年のころだったと思う、こんなことがあった。
ある日講義が終わって図書館の前を歩いていると、同じ講義を取っていた女の子に呼びとめられた。その女の子はゆっくりと僕のほうへ歩いて来たのであって、僕は何が起こるのだろうと正直ちょっとドキドキしたりしたのだが、相手の女の子の方も「あのー」と何か言いにくそうにしている。
そういう時には思わず目が合ったりなんかしてしまい、これは困るわけである。そこで平静を装って「何か?」と聞くと、
その女の子は「あのー、セーターの肩のところが大分切れていますよ」と言う。
虚を突かれて一瞬唖然としたのだが、よく考えれば自分の灰色のセーターのことを言われているわけで、彼女は講義の最中僕の肩を、いや、セーターの破れ目をじっと見詰めていたらしい。
僕は僕で一枚しかないセーターのことであり、寒さをしのぐために破れているなんぞは百も承知で着ているわけである。デパートの1000円均一などと書かれている箱の中を引っ掻き回して掘り出した代物で、そんなに丈夫なはずもない。
そこで僕は素直に「あ、これですか。知っています」と返事をすると、今度は彼女の方がキョトンとして「あ、そうですか。すみません」と申し訳なさそうに言って去って行ってしまった。
少々の惨めさも感じたが、何かまたひとつロマンスを逃したような惜しい気持ちもした。大体がこんな調子であり、実を結びそうな恋などありようもなかったのである。
なお、ついでながら書いておくが、このセーターには後日談がある。
このセーターは大学1年の冬に買い、教員3年目にとうとう断念するまでの6年間、シーズンにはほとんど一日も欠かさず着ていたことになる。当然ガタが来るわけで一生懸命あちこち縫い合わせながら着ていたのだが、同僚には「あんたそれは着ていればセーターには見えるが、脱いで置いてあれば単なるボロだよ」などとバカにされたものだった。
ところが7年目にして僕が新しいセーターを買って来ると。その日は教室で拍手やら歓声やらが湧き起こったのだが、そのボロボロのセーターを欲しいという人が現れた。
何とも珍しい妙な人がいるものだと思ったが、人からものを貰うことが多かった僕は多少得意になってそれをくれてやったのである。その後、そのセーターがどうなったのか僕は知らないが、ただその妙な人と僕はその後結婚することになったのである。
ロマンスをひとつ今度はものにしたことになるのだが、落ち着いてよく考えてみると僕は甚だ妙な人を貰ってしまったことになるわけであった。
さて、ちょっと寄り道が過ぎた。今日は煙草の話をしていたのである。
とりあえず当時の日記があるので恥ずかしながら紹介してみようと思う。状況が分かりにくいだろうが、夜、クラブの連中と飲み、途中から口論になり夜通しもめた末結局物別れに終わった、その朝のことである。
《3・25》(前略)こうした結果が誰の責任というのではないにしろ、とにかく何かが壊れてしまったのである。僕らは一体何を壊してしまったのだろうか。
初めて自分のために煙草を買う。ほとんどの人が興味半分に口に覚えるという煙草をこんな風にして自分が吸うようになるとは思わなかった。煙草に対して抱いていた何がなしの嫌悪感とは一体何ゆえのものだったのだろうか。
さほどの抵抗も感じないまま一本を抜き出し、火を付ける。煙が気管を通って肺に落ちて行くのが分かる。胸に圧迫感があり、少し持ち上げられるような感覚があってから、喉に軽い刺激を感じる。煙を追い出すように深く息を吐き出すと、息をはき終えるころ軽い咳におそわれ、煙草の臭みが口の中に広がって消えた。
たいしたことではなかった。
ただ、だるかった。
自分がこうして下宿に帰りついていることが不思議だった。何故自分はここにこうしているのだろう。何もできず、何もすることがなく、ただここにこうしているのである。(後略)
今にして思えば取るに足りないささいな出来事だった。口論の末の後輩の何気ない一言に僕はつまづいてしまった。失恋とても同じことであるが、客観的に見れば「何をそんなことに」と言いたくなるような、本当にささいな何気ない一言に僕らも見事につまづいてしまったのである。
ましてクラブを盛り立てようと必死でやって来た末のことであり、大事な試合を目前に控えて皆ピリピリしている時でもあった。テニスに対する思いだけは真剣であり、僕にはやはり真剣につまづくよりほかに能がなかった。
更に悪いことに、僕はその後の練習で転んで肩を打ち、ボールが打てなくなった。怪我などそれまで一度もしたことがなかったのだが、ラケットを握ってもどうしても肩が動かない。朝、布団から起き上がろうとすると激痛が走る。トイレで屈むのにどうしたら痛まないように腰を下ろせるのか思案し、まして右手で紙が使えずトイレの中で脂汗をかいたりしたことを記憶している。
結局2週間ほどでボールが打てるようになったが、精神的にも技術的にも最悪の状態で迎えた試合は、当然のように全敗した。ゲームは競ってファイナルまで縺れ込むのだが、必ず競り負ける。どうしたら良いか分からず、今までどうやって試合をして来たのかも分からないうちに一日目が終わり、また二日目も終わってしまう。もう自分はこのまま負け続けるしかないのではないか、そんな思いがいつも頭の中をチラチラしていた。それは言いようもなく惨めな感覚であった。
相前後して僕の生活全体も変わって来ていた。
目前に差し迫ったことから逃げ、たいして強くもない酒を一人で店で飲むようにもなっていた。講義にも出ず、街や武蔵野の野っぱらをぶらぶらすることも多くなった。気が付くとそんなふうになっていたのである。
今振り返ってみると「どうでもよいではないか」という感覚の中にどっぷりと浸かっていた、あるいは「どうでもよい」ということを「仕方がない」という言い方で許そうとしていた、ということになるのではないかと思う。
自分自身が楽な方へ楽な方へと傾斜しているのを感じながら、何も楽しくはなく充実感もさらさらなかった。どこか寂しく取り留めもなかったということになろうと思う。
試合は負け、主将として不甲斐ないと部員やOBから責められる。前年の戦績がほとんど全勝であったことを考えれば全敗は責められても仕方のない成績だった。
クラブを引退し、空気の抜けたゴムまりのようにして暫く過ごすと、就職について考えなければならない時期にさしかかり、次いで卒業論文の作成に当たらなければならなかった。よく言う歯車がひとつ抜け落ちた状態で僕はその時期を過ごした。
卒論も規定枚数に達しないまま提出日を迎え、就職の二次試験も受けに行かず、寒い部屋で毛布にくるまりながら「ああ終わったな」などと他人事のように考えていた。
この時期、僕は小さな電気ストーブの前に転がりながら煙草を吸い、カーリー・サイモンの曲を聞きながら日を送った。何を考えているわけでもなく、何をするでもなく、ただそこにいて取り留めもなく過ごしたのである。その時の僕の心持ちを有り体に言えば、それがそのまま「倦怠」であっただろうと今思う。けだるいだけの毎日であった。
煙草について言えば、僕は吸い始めて2カ月ほどで日に2箱を吸うようになっていた。次第に3箱吸うようになり、卒論で徹夜でもすれば一晩で灰皿が一杯になった。
貧乏症のゆえか一本の煙草を吸い込む煙が熱くなるまで吸ってしまう。身体に良いはずはなく、煙を吸い込みながら吐き気がし、歯を磨こうとして歯ブラシを口に突っ込むとまた吐き気がした。朝、目が覚めると口はべとつき、喉は重く痛く、気持ちが悪い。それでもまず真っ先に煙草に手が伸びるのである。
何故そうまでして吸うのか、と思う人がいるかもしれないが、自分でもよく分からない。愚かしいことに違いないが、不思議なことでもあった。体力も落ち、体重も12、3キロ減った。街を歩きながらショーウインドーに写る影を見て、今のが俺だったかな、などとはっとすることも有った。
どこかで自分を立て直さなければいけないと思いつつ、反対に自分のすべてを狂わしてしまいたい、そんな衝動が働いていたようにも思う。
結局僕は周囲の人々の限りない善意に支えられて次第に自分を取り戻して行くことになるが、僕と煙草の付き合いはおよそ以上のような経緯で始まった。
決して人に誇れるようなことでもないし、恰好の良いことでもない。自分でもわからない投げやりな自分がいた。煙草は僕にとってそういう日々の一つの臭いを持つ思い出となっている。
単なる感傷、と一笑に付していただいて結構だが、僕自身はその臭いを、僕を支えてくれた人達の暖かさとと共に大切に覚えていたいと思っている。良し悪しは別としていつでもそこに自分を立ち戻らせる必要を感じるのである。
高校生でも煙草を吸う人がいる。
何年か前、ある駅の待合室で煙草を吸っている高校生と出会った。制服のまま薄いカバンを傍らに置いて足を組み、ふんずりかえるようにして吸っていた。
その態度にカチンと来て「君は高校生じゃないの」と言うと、
「あんた誰だ」と言う。
「誰でもいい。君は高校生だろう」と言うと、
「あんたにとやかく言われる筋合いはない」と答える。
「高校生がこんなところでふんずり返ってタバコを吸うもんじゃない」と言うと、
「うるせえ」と言う。
更に二言三言やり合うと、彼は面倒臭そうに「捨てりゃいいんだろ」と言ったなり煙草を吸い殻入れに突っ込んで待合室を出て行った。
煙草を吸って指導を受ける生徒が出るたび、また街で制服にあらぬような制服を着て群れている高校生を見るたび、僕はその理由を知ってみたいと思うのだが、それは別に厭味ではなく僕にとっては素朴な疑問なのである。
人には理由がある。それは説明できないものであったとしても。
取り留めもなく煙草について書いてきたが、今僕は、日にコンスタントに一箱を吸う。夜、寝る前にボーッとしてふかす煙草は実にうまい。手元に500円しかなく、メシを食うか煙草を買うかとなれば、まず恐らく煙草を買うのだろうと思う。
「だからガリガリなんだ」と人は言うが、一人暮らしの夜をずっと共に過ごして来た煙草は僕には唯一無二の親友のように今は思われる。
そういう僕の楽しみを壊そうとするのが、あの実に妙な人であるカミさんで、彼女は煙草を憎み切っている。
「結婚したらやめるっていう約束です」と言うから、
「結婚は新しい出発だから過去は水に流すんだ」と説明するのだが分かってもらえない。
そこで「じゃあジャンケンで決めよう」と持ちかけるのだが、
答えは「馬鹿」なのである。
何か良い対策はないかと思いながら、ベランダの隅で小さくなって煙草をふかしている今日このごろである。
(土竜のひとりごと:第9話)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
