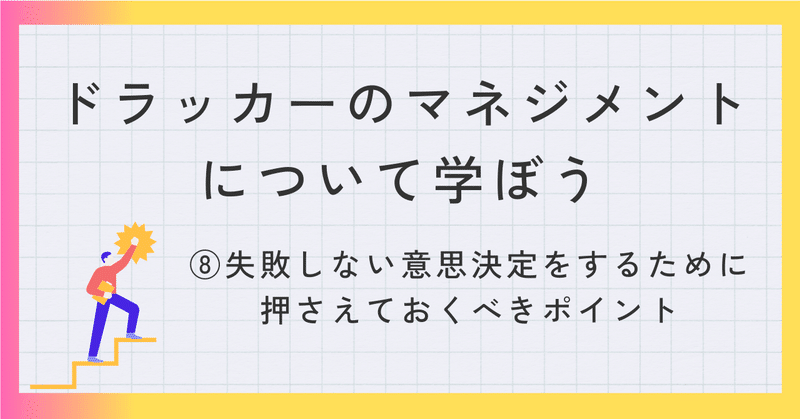
ドラッカーのマネジメントについて学ぼう -⑧失敗しない意思決定をするために押さえておくべきポイント
さあ、金曜日だ。
金曜日は、ドラッカーの「マネジメント」について学ぶ日だ。
この本は非常に緻密に書かれており、記事としてはドラッカーが書いた内容を順になぞっていくようなものになってしまうかもしれないと思っているが、可能な限り現代的な解釈をして、わかりやすく解説を加えていきたいと思っている。
先週は「凡人の組織に必要なもの」について書いたが、今日は「失敗しない意思決定をするために押さえておくべきポイント」について書こうと思う。
日本式の意思決定方法
ドラッカーはこの本の中で、日本式の意思決定方法を引き合いに出し、アメリカ企業も真似るべきだと書いている。
マネジメントが書かれた当時、TOYOTAや資生堂などが海外の販売拠点を置き始めた頃だったので、ドラッカーもそういった企業の営業マンとアメリカ企業とのやり取りを見ていたのかもしれない。
日本式の意思決定は「合意(コンセンサス)」によるもので、そもそも契約をすること自体が必要なのかを検討する段階で、契約締結後に関わりを持つことになる人たちを全て巻き込んで、それらの関係者全員が意思決定(その契約を行うこと)が必要だと認めることによって、決定が行われるというところだ。
そこからやっとアメリカ側との交渉が始まるわけだが、当時のアメリカ企業には「なんてまだるっこいことをやってるんだ」と映ったのかもしれない。しかしドラッカーは、この日本式の意思決定について以下の5つのポイントを挙げ、これこそが効果的な意思決定の基本だと説いている。
1. 問題を明らかにすることに重点を置く
2. あらゆる見解とアプローチを検討する
3. 複数の解決案を検討する
4. 決定権者を明確にする
5. 議論の中に決定後の実施方法を組み込む
対立意見の重要性
意思決定を行う際には対立意見が出ることが重要だ。
そして、議論をする際には、意見の相違を尊重しなければならない。自分の意見が正しく、他人の意見が間違っているという前提で会話するのではなく、明らかに間違っていると思われる意見であっても「その人が何か自分と違う現実を見ており、自分と違う問題に関心を持っている」という視点で、「なぜ意見が違うのか」を明らかにしていく姿勢が必要だ。
対立意見によって得られる期待値は以下の3つだ。
1. 優位性を持った人物が発した不完全な意見や誤った意見に惑わされない
2. 実行段階になって、意思決定の不完全さや誤りが明らかになったとしても、その代案を用意しておくことができる
3. 対立意見を元に議論することで想像力を引き出すことができる
行動したときのコストと行動しなかったときのコスト
外部(既存クライアントや新規ターゲットなど)から求められて、ビジネス上の意思決定をしなければならない場合だけでなく、内部からの意見に対して意思決定を迫られる場合もある。その場合「意思決定自体が必要なのか」ということも問わなければならない。
「意思決定をしない」という選択肢もひとつの意思決定である。何も手を付けなくても「上手く行く」という答えが出たときや、「たいした問題ではない」という結論に達したときに、無理やり何かの決定を下そうとするのは、逆にリスクを大きくする可能性がある。
しかし、往々にして答えは中間地点にある場合が多い。
放っておいて何とかなるというわけではないが、いきなり危機に陥るというわけでもない、チャンスではあるが、何か大きな改革が起きるというよりは小さな改善につながる、というような判断事案の場合だ。
そういった場合は、行動したときのコストと行動しなかったときのコストを比較して、コストの安い方を選択すべきとドラッカーは説いている。その時に注意しなければならないのは、行動するかしないかのどちらかの決定をするべきで、二股をかけたり妥協したりしてはならないということだ。
意思決定とは行動と成果のコミット
意思決定とは行動と成果をコミットすることだ。
意思決定した後は、関係者それぞれが成果を出すために迅速に行動しなければならない。なので意思決定の時点で、実行に関係する人や部門を全て巻き込んでおき、責任を持たせておく必要がある。場合によってはその中に社外のステークホルダーも含めておく必要もあるかもしれない。そして、意思決定の中に実行の手順を組み込み、その実行状況がフィードバックされる仕組みも含んでおかなければならない。
組織が誤った意思決定をしてしまうと、求めるべき成果を得ることができなくなる。また、組織が意思決定を先延ばしにするようであれば、それはその企業の存続に影響を及ぼすことにもなりかねない。
マネジメント(組織の管理や育成を行うチーム)は、それをしっかりと肝に銘じておかなければならない。
(続きはまた来週)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最後まで読んでくださってありがとうございます。
これまで書いた記事をサイトマップに一覧にしています。
ぜひ、ご覧ください。
<<科学的に考える人>>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
