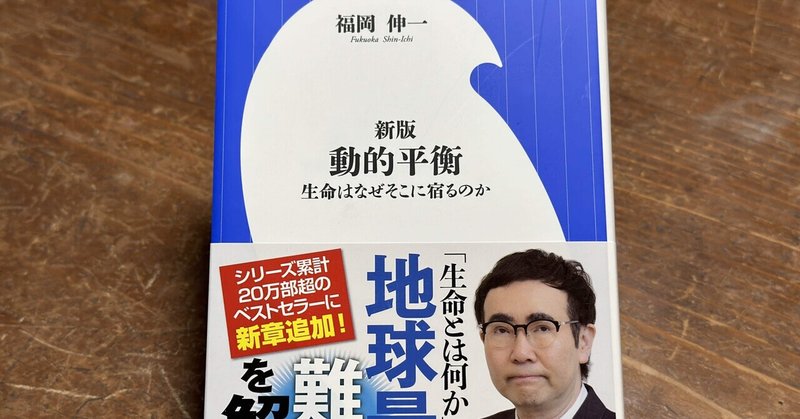
「自然の歌を聴く」ための新たな生命観とは——福岡伸一さんの『動的平衡』を読む
18世紀前半を生きたフランスの医師ラ・メトリー(唯物論の哲学者として知られている)は、人間を特別扱いする必然は何もなく、人間もまた機械論的に理解すべきものだとした。
現在のわたしたちもまた紛れもなく、この延長線上にある。生命を解体し、部品を交換し、発生を操作し、場合によっては商品化さえ行う。遺伝子に特許をとり、臓器を売買し、細胞を操作する。これらの営みの背景にデカルト的な、生命への機械論的な理解がある。
この考え方に立つ思考は現在、一種の制度疲労に陥っていると私は思う。
生命科学者である福岡伸一さんについては、過去の記事でとりあげた(記事「生命の本質とは何か——福岡伸一氏『生物と無生物のあいだ』を読む」および「西田幾多郎の生命の哲学と動的平衡——『福岡伸一、西田哲学を読む』より」を参照)。福岡さんは生命を「動的平衡状態にある流れである」として定義しており、絶えず分解と合成が行われるなかで、その本質は分解が合成に先んじて起こること、つまり時間を先回りして分解が行われることであるという。その理論の詳細は、本書の最後に「ベルクソンの弧モデル」として説明されているので、ご覧いただきたい。
生命の機械論モデルの出発点にはルネ・デカルトがいる。彼は、生命現象はすべて機械論的に説明可能だと考えた。心臓はポンプ、血管はチューブ、筋肉と関節はベルトと滑車、肺はふいご。すべてのボディ・パーツの仕組みは機会のアナロジーとして理解できる。そして、その運動は力学によって数学的に説明できる。数学者であり哲学者でもあったデカルトらしい発想だ。このモデルはあまりに単純であるが、現在の生命科学も基本的には、このデカルト的モデルの延長線上にある。18世紀のフランスの医師ラ・メトリーも、唯物論の哲学者でもあり、生命の機械論モデルの提唱者であった。
福岡さんは、この生命の機械論モデルに対してアンチテーゼを唱えた「忘れられた」科学者として、ルドルフ・シェーンハイマーを挙げる。彼が行なった実験は、生物に取り込まれた分子(アミノ酸)は、数日すると体全体に、さまざまな臓器にまで広がっているという驚くべき結果を示した。つまり数ヶ月もすると、私たちの身体を構成する物質はすっかり入れ替わっている。私たちを構成するのは、分子という物質ではなく、分解と合成が絶え間なく行われる動的平衡状態にある「流れ」のようなものではないか。福岡さんが受け継ぐ生命観は、デカルト的機械論モデルのアンチテーゼとして、シェーンハイマーの生命観を継承するものである。
そして福岡さんは、この生命の機械論的モデルは、一種の「制度疲労」に陥っていると考えている。新しい生命観、生命のモデルが必要と考えているのである。その生命観は、「動的平衡」という概念とともに、「自然は歌に満ちている」という比喩でも説明される。生命の機械論モデルが「ロゴス」(論理)のモデルだとすれば、動的平衡状態で定義する生命観は「ピュシス」(自然)のモデルだと言える。自然が歌に満ちているピュシスのモデルの例として、クジラとゾウの低周波音コミュニケーションの例や、豚が「心の理論」(他人にも心があると理解すること)を理解しているとする『思考する豚』の実験の例などが紹介される。生命の機械論モデルでは決して説明しつくせない現実である。
遺伝子操作、臓器再生、アンチエイジング……私たちの現代の「医学」はまさに機械論モデルを謳歌しているようにみえるが、その影で実は「制度疲労」を起こしているのではないか。そのとき、私たちに必要となるのは、新しい生命観、つまりデカルト的機械論ではなく、自然(ピュシス)の歌を聴くような生命観なのではないか。そのことを深く考えさせてくれるのが、福岡伸一さんの本である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
