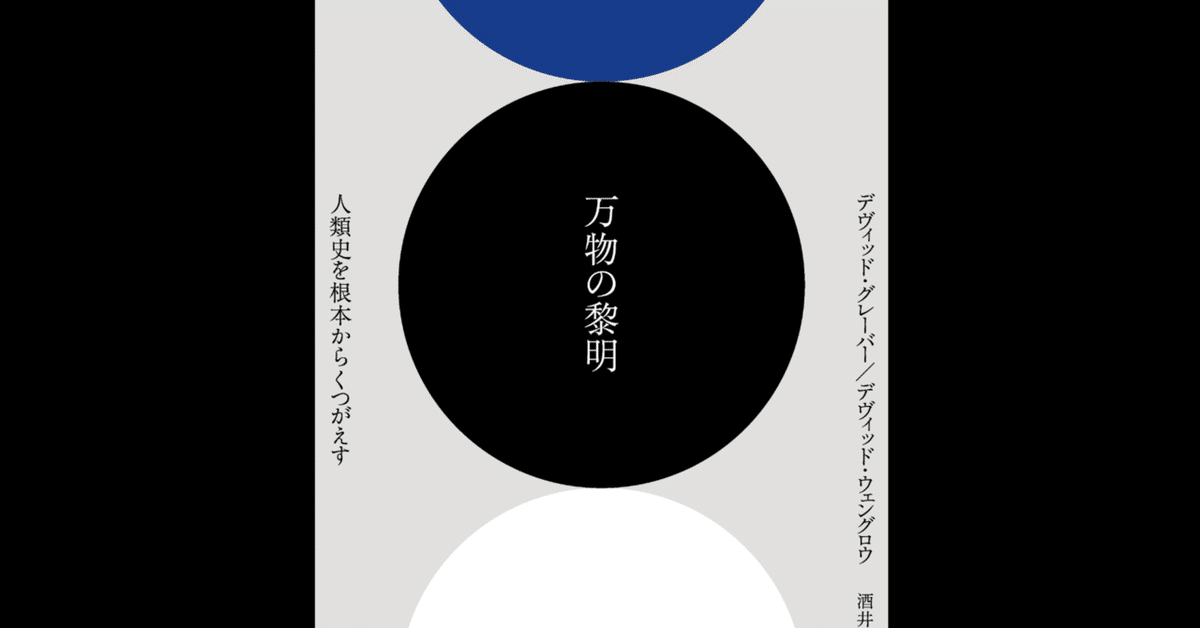
主権、官僚制、カリスマ的競合の偶然の合流としての近代国家——グレーバー=ウェングロウ『万物の黎明』を読む
エイブラムスいわく、政治的実践を理解するためには「国家が存在するという感覚ではなく、国家が存在しないという感覚」に注意を払わなければならない。これらの指摘が、現代の政治体制と同様——すくなくとも同程度には——古代の政治体制にも強くあてはまることが、いまやわかるだろう。
「国家」の起源は、長いあいだ、古代エジプト、インカ・ペルー、殷の中国など、さまざまな場所にもとめられてきたが、現在、わたしたちが国家とみなしているものは、歴史の定数ではなく、青銅器時代に端緒をおく長い進化の帰結でもなく、異なる起源を有する三つの政治形態——主権、行政管理、カリスマ的競合——が合流したものであることがわかった。近代国家とは、たんに支配の三原理がたまたま合流したひとつのありようにすぎないのだ。しかし、近代国家のばあい、[かつての]王の権力を保持しているのは「民衆/人民」(または「国民」)と呼ばれる存在である。官僚制はそのいわゆる「民衆/人民」の利益のために存在するとみなされ、古い貴族的競合や報奨の変異体が「民主主義[民主政]」と呼び直され、それも、多くのばあい、国政選挙というかたちをとることになった。しかし、ここにはなんの必然性もない。それを証明する必要があるとすれば、この特殊な仕組みが、いまやいかに崩壊しているかを観察すればよい。先に述べたように、現在、地球規模の官僚機構(IMFやWTOから、JPモルガン・チェースや各種格付け機関まで官民を問わず)が存在しているが、それに対応する世界主権の原則や世界的競合政治の場はなく、暗号通貨から民間のセキュリティ機関まで、あらゆるものが国家の主権を浸食している。
グレーバーとウェングロウの『万物の黎明——人類史を根本からくつがえす』は、国家とは何か、社会の進化は私たちが想定する常識的なもの以外にどのような可能性があるのかを問うた意欲作である。それは、国家の成り立ちがホッブズ的な思考(必要悪としての国家装置)かルソー的な思考(国民が下から組み上げる主権としての社会契約)の二極だけに私たちの思考が囚われている中で、さまざまな考古学的・人類学的証拠を挙げながら、人類史にはその他にもさまざまな実験的な社会の支配・統治のあり方がかつてあったのだと説明する。
グレーバー=ウェングロウは、国家の成り立ちは異なる起源を有する三つの政治形態(主権、行政管理、カリスマ的競合)が合流するときに起こると説明する。彼らは、近代国家とは、単にこの三つの支配形態がたまたま合流した一つのありように過ぎないと説く。ここで彼らは、社会学者フィリップ・エイブラムスの言葉を紹介する。それは「国家が存在するという感覚ではなく、国家が存在しないという感覚」に注意を払わなければならないとするものである。国家が存在するのは近代社会では当然とされているが、それはある意味幻想に過ぎず、「国家は実際には存在しない」ということに気づく必要があるという。その証拠に、かつて三つの支配形態のうち、一つだけを主軸に成り立つ形態(これを彼らは第一次レジームと呼ぶ)や、二つだけが合流して成り立つ形態(第二次レジーム)もかつては存在したのだ。
実は「国家」とは何かについて社会理論家のあいだでも今もってコンセンサスがないのだという。最初に体系的な定義をしたのはルドルフ・フォン・イェーリングというドイツの哲学者だったが、彼の定義は「国家とは、所与の領域内で合法的な強制力の使用を独占することを主張する機関である」とした。彼の定義は近代国家にはかなり有効だったが、人類史のほとんどにおいて、支配者はそのような大仰な主張をしていなかった。例えば、ハンムラビのバビロン、ソクラテスのアテネ、征服王ウィリアム支配下のイングランドなどではその定義があてはまらない。グレーバー=ウェングロウは、はたして「大規模で複雑な社会には必ず国家が必要だという想定」は正しいのか?と問う。そして考古学的証拠を挙げながら、最初期の都市には国家装置と呼べるものをもたず、さらにはフォーマルな統治機関のすべてを欠いていたと指摘する。国家が不在であっても、君主支配、貴族支配、奴隷制、極端な形態の家父長制支配は可能だった。
グレーバー=ウェングロウが挙げる三つの支配形態、主権、行政管理(官僚制)、カリスマ的競合とは、個人の財産(所有権)を守るための三つの原理、つまり暴力の統制、情報の統制、個人のカリスマ性に対応している。近代国家が成立する前、個人の財産を保障する原理としては、暴力を駆使するか、情報統制して秘密を保持するか、個人のカリスマ性に頼るしかなかった。これが近代国家になると、暴力の統制は「主権者」となり、情報の統制は「官僚制」となった。しかしこの二つが組み合わさると監視国家や全体主義体制へとつながる危険性をはらむ。これを相殺するため「民主主義」的体制、つまり「競合的政治フィールド」が必要となる。しかし、この三つの支配形態は、大規模な社会においては必ず三つがそろって組み合わさるということはなく、過去においては一つだけが突出した社会(第一次レジーム)や、二つが組み合わさっただけの社会(第二次レジーム)が多く存在した。
なぜ現代の社会科学者が、一貫した定義がないにもかかわらず「国家」や「国家形成」という言葉を好むようになったのか。一つには「国家」と近代科学という二つの概念が同時期に生まれ、ある程度互いに絡み合っていたからかもしれない。事実上、いまやこの地球のほとんどは国家に覆われている。そのためこの帰結をうっかり必然であるかのようにみなしている。しかし、現在の社会構造のある顕著な特徴が、過去に投影され、社会がある程度複雑になった時点で、それが存在するというように推定してしまうということはありえることである。さらにいえば、もし「国家」に意味があるとして、その主張の背後には、王の命令にひれ伏すような「儀礼」を永続させたいという願望、つまり全体主義的な衝動があるのかもしれない、とグレーバー=ウェングロウは指摘するのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
