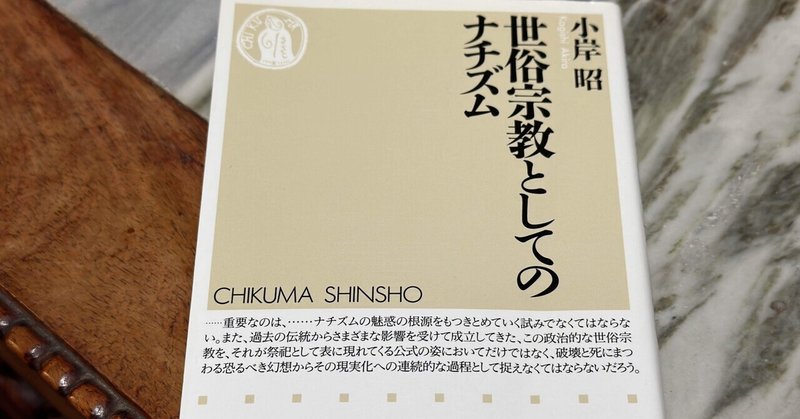
ドストエフスキーがゲッベルスに与えた影響——小岸昭『世俗宗教としてのナチズム』より
ゲッベルスは神秘的な指導力をかぎわけるその鋭い嗅覚によって、「神を孕める民族」の未来の救済にかかわるこの言葉を『悪霊』全編から正確にさぐりあてたと言える。(中略)
ところで、メラー・ファン・デン・ブルック監修になるドストエフスキー全集(全22巻)は、敗戦前後のドイツの知識人に衝撃的とも言える影響を与えた。ドストエフスキーはほかならぬドイツにおいて派閥間の争いになり、反自由主義の象徴とさえなったのである。(中略)それは、ドストエフスキーの作品と、多くの巻に序文を書いたメラーの神秘的・政治的なドストエフスキー解釈が、西欧を敵として戦って破れたドイツ人の目には、西欧の圧政からの解放と民族の内なる魂の発見に道をひらくための福音書のように映ったからである。
著者の小岸昭(こぎし あきら、1937 - 2022)は、ドイツ文学者、京都大学名誉教授。1965年、日本ゲーテ賞受賞。1966 - 68年にフランクフルト大学へ留学。ユダヤ思想研究を軸として、スペイン、ポルトガル、インド、イスラエル、ブラジル、中国などを旅し、ディアスポラ・ユダヤ人の足跡を追究した。著書に『スペインを追われたユダヤ人』(ちくま学芸文庫)、『マラーノの系譜』(みすず書房)、『離散するユダヤ人』(岩波新書)などがある。
本書『世俗宗教としてのナチズム』は、ナチズムの黙示録的な鉤十字運動が、どのように人々の心を魅了したのかを、ドイツ文学者の小岸昭氏がナチズムの「世俗宗教」としての側面に注目して解説した本である。「神話」と「象徴」に彩られ、無意識の想像力を緻密に体系化したナチス運動はどのように成立したのか。世俗宗教としてのナチスにおいて、ヒトラーが「祭司」とするなら、宣伝相ゲッベルスは「伝道師」であったと言えるだろう。
そのゲッベルスが、ドストエフスキーの影響を多分に受けていたと知ったら読者は驚かれるだろうか。なにせ、ナチスはユダヤ人とともに共産主義者を敵とし、独ソ戦ではスラブ民族を殲滅しようとした当事者である。しかしながら、実は第一次世界大戦後のドイツの知識人たちに、ドストエフスキーは絶大な影響を与えていたのであり、それが間接的にあの熱狂的なナチス運動にもつながっていったと小岸氏は本書で解説している。なぜなら、当時のドストエフスキーが、ドイツ知識人たちに「衝撃的とも言える影響」を与え、「反自由主義」の象徴とさえなったからだ。それは一種の「悪用」であったわけだが、当時のドストエフスキー解釈が、ゲルマン民族の「西欧の圧政」からの解放と映ったのである。
ナチスの宣伝大臣であったヨーゼフ・ゲッベルスは、実は挫折した文学者であった。ボン大学では歴史と文学を中心に学び、特にゲーテの劇作を熱心に研究した。またハイデルベルク大学では、やはり文学(さらに歴史、言語学、美術)を学んでいる。32歳時には『ミヒャエル』という小説まで書いているのである。ゲッベルスは熱心なドストエフスキーの読者でもあった。彼の博士論文の扉には、ドストエフスキーの『悪霊』からの引用がある。つまりゲッベルスは、「ドストエフスキーの世界の基底にある絶望と救済のテーマを、一方的にナチズムの水路へ引き入れ、そこから野蛮な政治的エネルギーを汲み上げ」たのだと、小岸氏は述べている。
そのゲッベルスは、1933年に「焚書(ふんしょ)」という野蛮極まりない反文学運動を主導している。これはドイツ国内の本のうちで、ナチズムの思想に合わないとされた書物が、ナチスドイツによって儀式的に焼き払われたものである。しかし、その反文学運動を扇動した張本人が「文学者」ゲッベルスであり、彼にとっては最も親しみを覚えていた文学において、これを否定する運動を先導するということは、彼にとって最大の敗北だっただろう。反ナチス的とされた書物にはロシア作家が多く入っていたが、自らのナチ・イデオロギーの形成に影響を与えたドストエフスキーの書物はそのリストから外されていた。
こう考えると、ドストエフスキーの歴史への影響は計り知れない。それを小岸氏は「ドストエフスキーはただ読まれるだけではなく、信仰の対象となるから」であると説明している。しかしながら、アルベルト・カミュやヴァルター・ベンヤミンが、ドストエフスキーから「人間的・普遍的なもの」を読み取っていったのに対して、ゲッベルスはただ「アーリア民族」という幻想のみをドストエフスキーに投影したのであり、そのゲッベルスが、ついには数百万人の人間を死に追いやることに手を貸したという事実を決して忘れてはならない、と小岸氏は記している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
