
ローエングリーン
知人から一枚のチラシをもらった。

聞けば、社会人になった娘が市民吹奏楽団に入り、近々演奏会があるから、是非、見に行ってくれ、という。
なかなか収束しないコロナや、いつまでもやまない戦争に心が晴れないところに、個人的にも面白くない事が続いていたので、気乗りがしなかったが、チラシの中の、その日の演目を見て、気が変わった。
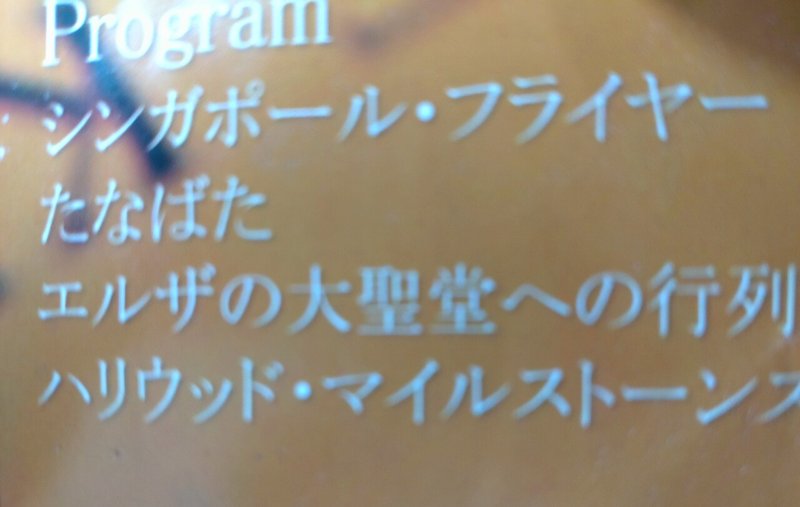
エルザの大聖堂への行列
それが大きく目に飛び込んできた。
歌劇ローエングリーンの中の一曲。そのあまりに美しい旋律を久しぶりに聞いてみたい、と私はもう何をおいても演奏会に行く気になっていた。

ワーグナーを好きだとは、何故か言えない。
ドイツロマン派を代表する大音楽家の、その比類なき才能に圧倒され、淡麗とまで感じられる旋律やドラマ性、オーケストラのダイナミズムに激しく心を惹かれながらも、ワーグナーが好きだということを、ためらう。
何故だろう?
ヒトラーが敬愛した、という、ワーグナー。エセ平和主義者ぶりを発揮して、私はそのことを気にしているのか?
昔見たフランシス・コッポラ監督の映画「地獄の黙示録」の象徴的な場面。ヘリコプター連隊がベトナムの村を攻撃するシーンでは「ワルキューレの騎行」が使われた。そのことも重なっているのか?
ワーグナー自身の生涯は波乱万丈であった。始終借金を抱え、その返済に追われ、私生活は奔放で多くの女性とも交わった。その人生は華やかな経歴にも関わらず、私は何か落ち着かない印象を持つ。
歌劇ローエングリーンについては、あまりに有名で、素人の私が語るまでもないが、拙文を進めるために簡単にあらすじを説明する。
歌劇ローエングリンは、アーサー物語やケルト神話に登場する伝説の騎士がモデルになっていると言われる。物語の舞台は10世紀中ごろのアントヴェルペン。主な登場人物は5人。中でも主になるのは、エルザ、ブラバント公の娘。そして、その後見人のテルムラント伯とその妻のオルトルート。それから勿論、この歌劇のタイトルにもなっている白鳥の騎士ローエングリン。最後に国王のハインリヒ。話はハインリヒ王がブラバント公国に来るところから始まる。ここで後見人であるテルムラント伯が現れ、ブラバント公の娘エルザが弟のゴットフリートを殺したと訴える。エルザが亡きブラバント公の権力を独り占めするために、弟を殺したのだという。そこで、その弁明のために連れてこられたエルザだが、彼女は弁明することなく、私は騎士が自分を助けに来る夢を見た、とだけ言う。テルムラントはなおもエルザの弟殺しを主張するため、ハインリヒ王は神明裁判で決着をつけると宣言する。神明裁判とは神の裁きのもとで、二人の人間が決闘すること。負けた方は有罪になり、勝った方は無罪になる。エルザは女性なので代理が認められる。だが周囲には代理になって決闘するものが現れない。そこに現れたのがこの物語の主人公である、白鳥の騎士、ローエングリン、だった。ローエングリンはエルザを助ける代わりに、ある条件を出す。それは自分の素性を一切詮索しないこと。つまり、そうしたことを質問しないように、エルザに言い、彼女もそれを承諾した。結局、ローエングリンはテルムラントと決闘し、勝利する。テルムラントは追放され、ローエングリンはその国にとどまり、国を守ることになり民衆一堂に歓迎される。なにもかも上手くいったように見えたが、ここで登場するのが、負けたテルムラントの妻、オルトルートである。もともとオルトルートは昔ブラバント公国を治めていたものの子孫であり、エルザを失脚させ自分が国の権力を握ろうと画策していた。そこで夫のテルムラントをけしかけたのである。まさに影に女あり。諦めないオルトルートはエルザに近づき、素性の分からないローエングリンに対する疑念を植え付けようとする。さて、第2幕第4場、ここで流れる音楽が、エルザの大聖堂への行列、である。その後、オルトルート夫婦とローエングリンの小競り合いがあるが、結局、エルザはローエングリンを信じ、結婚することになる。有名な第三幕。結婚行進曲。二人は結ばれるが、エルザの心の中には、オルトルートから植え付けられた疑念がまだ残っていた。ローエングリンとの会話の中で、妄想に取りつかれ、素性のわからないローエングリンはいつか自分を捨ててまた白鳥に連れられ帰っていくかもしれない。そう思ってしまった。思い余ってエルザは禁断の質問をしてしまう。そこへ何故かテルムラントが現れ、ローエングリンは彼を殺してしまう。その弁明のために、ついには、ローエングリンは民衆の前で自分の素性を明かすことになる。しかも約束を破って禁断の質問をしたエルザを訴える。結局、ローエングリンは再び去り、そのショックでエルザは息絶える。ふたりの結婚生活はたった一日でおわってしまった。その経緯で、ローエングリンと共にいた白鳥が実はオルトルートの魔法で変えられたエルザの弟ゴットフリートであることが判明し、ローエングリンにより、魔法は解かれ、元の姿に戻った。国は安泰。めでたしめでたし・・・ん?
ツッコミどころ満載なのは歌劇である以上仕方ないが、どうしてもひっかかるのは、その結末である。
なぜ、ローエングリーンはいなくなり、エルザは死ななければならなかったのか?
あの、エルザの大聖堂への行列の美しい旋律の中、人々に祝福され、おそらくは世界中の誰でもが知っている明るい結婚行進曲で祝福され、結婚の誓いをした筈の二人が、その幸福は少しも続くことなく、終わらなければならなかったのか?
無論、その台本を書いたのは、ワーグナー自身である。
その結末に、作者ワーグナーの人生観が表れている気がしてくる。芸術においても、作者の人生観が、反映されるものだと考えるならば、私はそんなところに、ワーグナーが好きだと言えない自分を発見する。
大芸術家のワーグナーがどんな人生観を持っていたか、人間というものををどう捉えていたか凡人の私には測りかねる。
しかし、人間というもの。人生というものに、消せない疑念を持っていたのではないか。歌劇だから、当然に、ドラマチックな筋立ては必要だが、くどいようだが、エルザが死ぬことはなかった。祝福された愛のカタチがあれほどあっさり壊れる必要はなかった。邪推すれば、人間の持つものの中で、最も尊い愛や信頼や信念等さえも、ワーグナーは信じていなかった、のではないか?
人間や人生がもともと油断のならないものと決めつけてしまえば、こんな悲しいことはない。これは私の勝手な推測である。

前回の投稿で紹介した、アインシュタインとフロイトの往復書簡。
そのなかでも、人間はもともと破壊的行動を起こすものを保有している。それが作用して戦争を引き起こす。と、そのことに言及して、否定しない。実際、それはそうなのだろうけど、だからと言って、人間や人生自体がが否定されるものではない。これは歴史的に繰り返されてきた戦争という命題に、ふたりの知の巨人がフランクに語り合った素晴らしいものだが、底流に流れる人間、人生に対する諦念が感じられて、正直、私の希望にはならなかった。
人生がそんなに楽なものとは思わないが、それほど捨てたもんでもない。いつもそう思っていたい。
本来人間はたとえどんな人でも、何か、尊い使命を持って、この世に生を受けたのだ、と信じていたい。時には邪な何かでその生が曇ることはあっても、それが甘い幻想だと思う日があっても、そう思い続けることには微かな希望がある。
少なくとも、エルザの大聖堂への行列を聴いている時の、私はささやかな幸せを感じている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
