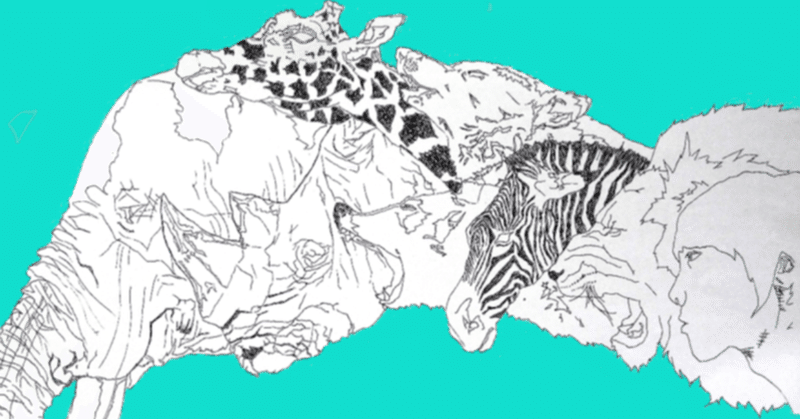
「飽きる」ことの重要性
こんばんは。
シンガーソングライターのソーダ・ヒロです。
なぜあんなに好きで聴いていた音楽を"飽き"てしまうんだろう?
こんな疑問から『飽きる』という人間のメカニズムにとても興味が沸いたので、
『飽きる』理由と効果について考察してみたいと思います。
『飽きる』メカニズムについて
ネットで「飽きる 理由」で検索をかけると、
『飽きる』とは「依存を回避させるため」「脳がその事柄を記憶し切って刺激のない状態」
を指すのだそうです。
また、長期記憶と短期記憶というものを使い分けている、とのことでした。
何か自分にとって胸を打ち震わせるような作品に出会った時、
「これは自分に必要だ!」と感じて、それを取り込むために、自分の中の長期記憶にダウンロードをしようとします。
そしてそのダウンロードが完了するまでの時間稼ぎとして、
まずは短期記憶に"高揚感"として何度も何度も反復してそれを叩き込み、
ダウンロードが完了し、自分の記憶の引き出し(長期記憶)に取り込めたら『飽きる』という状態になり、高揚感などを冷まします。
一度ダウンロードが完了した情報は時間が経っても思い出すことができます。
それは、好きな音楽をいつでも歌詞を見ずとも歌えるのと同じように。
『飽きる』という“リスク回避”
とりわけ、『飽きる』という感覚は、一つに固執して依存してしまうことを防ぐことでもあります。
食べ物なら、同じものばかりだと偏食となり健康を害してしまう。
"音楽を『飽きる』"という状態に関しても同じことが言えると思いますが、人間とはとても流動的な生き物で、多種多様な感情を持ち、状況や環境の変化によっても心は縦横無尽に動き回り、その形を留めません。
そうした中で、一つの作品から得たある一つのシーンだけの感情だけを持つより、様々な場面で発生する感情と出会い、理解し、そして、それらを受け止めるためにも様々な情報や考え方が必要となります。
だからこそ、『飽きる』ことでまた"高揚感"という甘い蜜を何度も求め、この社会や人間関係に必要な情報を獲得していくようにプログラムされているのかもしれません。
『飽き』て新しい情報を得ようとすることは、
俯瞰してみれば、"人間"という『感情を扱い、人間だけの社会を築く知的動物』として、その種の繁栄のために必要なことなのだと思います。
逆に『飽きない』ことのリスクは先にも述べました"一つに固執して執着する"ことです。
そのことによって生き方や他者との関わり方での選択肢が狭められ、生きづらくなってしまうのだと思います。
「知らない・分からない」ということは得てして"リスク"となる。
『飽き』て様々な新しい情報を得る先にあるもの
流動的に変わり続ける環境や価値観の中で、常にそこにフィットした新しい目線、新しい価値観も取り入れていくことが人間の寿命を延ばす行為そのもの。
そうして『飽きる』ことで、喜び、痛み、悲しみ、苦悩、快楽、など、様々な感情と出会い、自分にとって、また他者との関係性の上で必要な情報を取り込み続けたその行為の行き着く場所は、
きっととても"普遍的"なものではないかな、とも思います。
それはシンプルに、
愛すること。
思いやること。
親切にすること。
大切にすること。
許すこと。
認めること。
人と人とが共存し、それぞれが"個"として居場所やその存在を確保し、満足感をもって生き長らえるために、結果としてそうしたシンプルで揺るがない根源的な感情に辿り着くのではないかと思います。
『飽きる』ことのまとめ
まとめると、
『飽きる』ということは、
環境が目まぐるしく変わっていく中で、一つの情報(感情)に依存することで生存確率を減らすことを防ぎ、
その変化の中で人間がその時々の環境や感覚へ適応するために様々な情報を取り込む、という必要不可欠な現象。
表現の発信者としてやるべきこと
なので、表現などで発信する側として必要なことは、"常に今体感している状態や感情を細やかに目一杯注ぎ込む"こと。
そのことで現代の人が抱えている問題や求めることに応えることができる、そしてこれから必要とする人にもそれを情報として落とすことができると思います。
長期記憶に留めたくなるような"普遍的"な感情を現代の問題の中からアクセスできるように、僕はいつでも今を目一杯生きて、問題にぶち当たっては解決策を探して、そして作品として残し続けることをしていきたいな、と思います。
『飽きる』ということは、その状態の前に『"高揚感"を味わい尽くした』ということ。
そしてその結果『自身の中にダウンロードされた』という状態。
だから僕はまず『飽きられるほど聴かれる魅力的な音楽』を作ることに全力を尽くしたいと思います。
このテーマ、もう少し別の観点からも考察していきたいと思うので、
今度は『流行』という事象を取り入れながら考察してみたいと思います。
まとまったら書いてみます!
ではまた!
ソーダ・ヒロ official website 「音楽と絵と生活と」
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://soda-hiro-ff.amebaownd.com
ソーダ・ヒロ YouTube オリジナル音源公開中!!
チャンネル登録1000人目指しています!
よろしければチャンネル登録もお願いします!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
