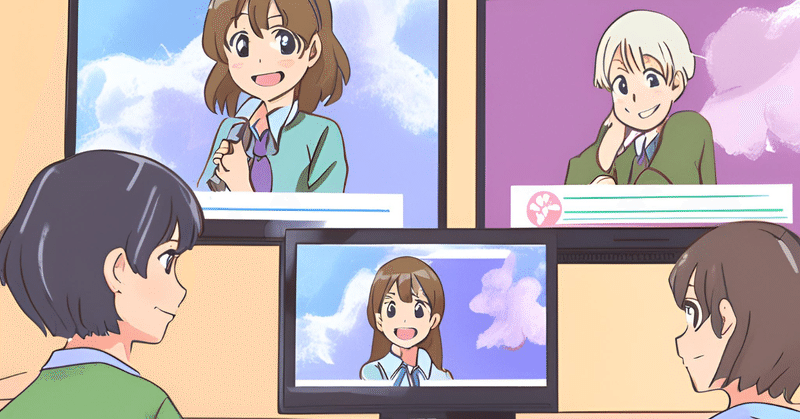
双方向型学級通信への挑戦と現実【足並みバイアスを乗り越え…】
小学校教員のsmyle(スまイル)です。
今年度、6年生の担任をしています。
ここ数年、私の学級経営の軸になっているのが
学級通信です。
通算で1500号以上。
今年度も、5月18日現在
登校28日で、46号発行しています。
(書きたいことがあり過ぎて、すでに52号まで起案済です。)
もともと、学級通信に力を入れていた年もあったのですが、
改めて力を入れていこう、
ひいては学級経営の軸にしていこう、と思い立ったのは
渡辺道治先生の影響です。
渡辺道治先生は、ご著書の中で
「双方向型の学級通信」を提案しています。
学級通信で保護者とつながる
今年度、保護者の方に
何かの用件でお電話した際や、お会いしたときなど
折に触れて「学級通信楽しみにしています」
という声をいただきます。
そのたび、
涙が出るほど嬉しい気持ちになります。
疲れていても、力がみなぎります。
1つのメッセージで、寿命が1週間延びます。(大袈裟じゃない)
それほどに、お家の方のメッセージは
教師を勇気づけ、奮い立たせてくれます。
それなら、
そもそもの学級通信の機能を、
担任からの一方通行の媒体ではなく、
双方向の媒体にしてしまうのはどうだろう。
つまり、
保護者の方にも参画してもらう
学級通信にできないだろうか。
そうすることで、
学級通信を介して保護者の方との結びつきが強まり、
「共に子どもたちを育てていく」意識も
双方に高めていくことができる。
しかも、保護者の方の1つ1つのメッセージは
教師に頑張る力を与えてくれる。
もう、良いことづくめではないでしょうか。
参観日の感想募集。しかし…
保護者の方に「学級通信」に参画してもらう方法。
一番わかりやすいところで言うと、
感想など頂いたメッセージを、
学級通信に載せさせていただくことかと思います。
まず、その第一歩は
「担任の先生に感想を送って良いんだ」
と思っていただくことです。
時々、行事の感想などを
連絡帳で寄せてくださる保護者の方もいらっしゃいますが、
「そもそも感想なんて送っていいものだろうか」
「先生がお返事を書くのが大変じゃないだろうか」
など気を遣ってくださり、
感想を抱いていても、送れないでいる方もいらっしゃるようです。
ですから、教師の方から
「気軽に感想などお寄せくださいね!」と
意図的に戦略的に門戸を広げておくことは
大切かなと思います。
感想をいただく最初の機会として最適なのは、
初めての学習参観でしょうか。
前任校では、参観授業を行う教室に、
感想用紙を置いておきました。
手書きはもちろんのこと、
感想入力用GoogleフォームのQRコードも用紙に貼り付けておきました。
手書きでもデジタルでも感想をいただける形にしました。
(ちなみに1名が手書き、他の方はQRコードでした)
機会や手段があれば、感想を送ってくださる方は
意外といらっしゃるものです。
たくさんの温かなフィードバックをいただくことができました。
そして異動した今年度、
4月の初めての学習参観で、同じく
感想を求めてみることにしました。
感想用紙ではなく、参観日当日に配る学級通信の、
下部に感想記入欄(及び切り取り線)を設け、
さらにはGoogleフォームのQRコードも貼り付けました。
プラスのフィードバックばかりとは当然限りませんが、
それも含めてどんな声をいただけるのか
とても楽しみ!
…でしたが、
しかし!しかしです。
管理職に起案したところ、
NGが出てしまいました。
理由は、他のクラスと足並みがそろっていないから。
まず、QRコードで感想を送ってもらうというシステムを、
この学校ではとったことはない。
今後、学校単位でやってみるのは面白いとは思う。
だから、学級単位で動くのは待ってほしい。
とのことでした。
なるほど。なんとなくわかります。
ただ、
QRコードのみならず
学級通信に感想記入欄を設けることにも
難色を示されてしまいました。
理由は、他の学級がやっていないから。
足並みがそろっていないから。
足並み…足並み、かぁ。
言いたいことはごまんとありますが、
そこで盾ついても不機嫌になっても
組織にとって、子どもたちにとって、
自分にとってプラスはありません。
今回は、感想記入欄は排除し、
「ぜひ連絡帳にお寄せください!」と訂正して発行することにしました。
そして、有難く連絡帳にいただいたご意見を
学級通信に載せさせていただくことができました。
足並みを揃えるかどうか
足並みって、揃えなきゃダメでしょうか。
もちろん、最低限揃えなければいけないもの
揃えるべきものはある、というのは
当然とした上で、です。
いったいその足並みは、
誰のために、何のために揃えているのでしょう。
どこを向いて、誰の方を見て、
揃えなきゃと思うのでしょう。
教育の個別最適化が叫ばれる中で、
当然、教師にも得意や不得意があり、
学級によってやり方や進め方、進度に違いがあって当然です。
教師1人1人が自分の特性に合った方法をとった方が
よっぽど豊かな学級経営・学校づくりができる気がします。
例えば、ピアノが得意な先生が居て、
その方はピアノを弾いて音楽の授業をするけれど、
片や得意でない方は、CDなどの音源を使って授業をする。
じゃあ、足並みをそろえるために、
「あるクラスだけピアノ演奏はズルいから、
みんなが共通してできるCDで授業しましょう」
と言われたら、そうするのでしょうか。
そうはならないと思うのですが…
学級によって違っていいし、違いが当たり前。
先生が違えば、もちろん子どもも。
同じ学校の同じ学年であっても、クラスが違えば
子どもたちのカラーは全然違う。
宿題など「となりと一緒にしてください」と
おっしゃる保護者の方も稀にいるけれど、
違いにこそ価値があることなど、
教師のもつ想いや意図をしっかりお伝えすれば、
概ね分かってくださると思うのですが。
何か保護者の方に言われる前に、
勝手に教師の側が揃えなきゃと不安になって、
揃えてしまっている気がしてなりません。
そんな先生たちの姿を見て、
子どもたちは何を感じ、何を受け取るのでしょうか。
教師と子どもたちは「学びの相似形」であるのに。
「動く学級通信」にも挑戦。しかし…
実は「学級通信で感想を募集する」案が却下された後、
懲りずに別件で
管理職に起案したものがあります。
それは、坂本良晶先生がnoteでも紹介していた
動く学級通信です。
「動く学級通信」とは、
動画や音声、作品のPDFなどを
QRコードから見られるようにするもの。
普段、家庭からは見られない学校の中の様子を、
文面だけでは伝わらない空気感や熱量を、
少しでも垣間見ていただくことができる
素敵な方法だと思っています。
心配されるであろうセキュリティ面も、
動画などをteams等にアップして
そのリンクをQRコード化することで、
児童に配付されたアカウントでしか見られないという
セキュリティばっちり仕様になっています。
しかし、
これもダメでしたー。
なぜなら足n(略)
運動会練習の熱量、伝えたかったんだけどなー。
足並みバイアスを
発行は保留です、と返却された起案文書には
「素敵な取り組みだから、どの先生もできるように
研修などで広めてからしてね♡」
と管理職のコメントが添えられていました。
色々と思うことはあっても、
それをただぶつけても仕方がありません。
管理職のみなさんにも、
足並みを揃えなきゃと思わせる背景が、
学校や地域性などの文脈が、きっとあるのでしょう。
それなら、やったります!
夏休みあたり、
情報教育部として先生方にICT研修して
実践を広げちゃいます。
何ならあわせて
Canva研修なんかもしちゃおう。
良いと思うものを、自分にできることを、
じわじわ広げていこう。
少しずつ、価値観を崩していこう。
少しずつ、足並みバイアスを乗り越える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
