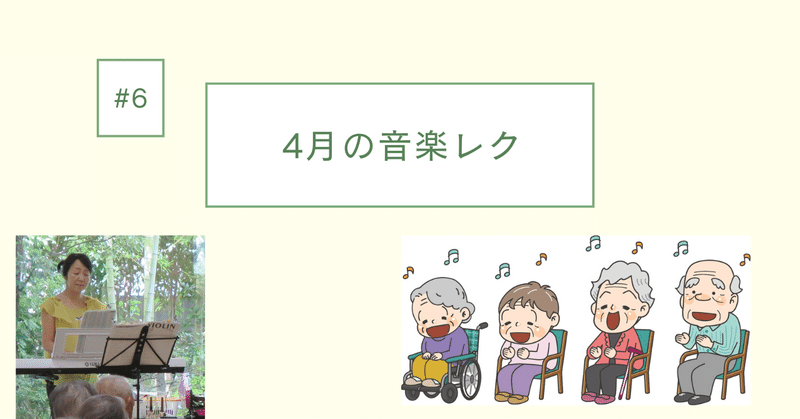
4月の音楽レク【桜とアメリカ】

毎年桜が咲きだすのが待ち遠しいですね。
日本古謡の《さくらさくら》は「弥生の空は~」という歌詞ですね。
3月に歌うにしても4月に歌うにしても、咲き始めに歌うにしても盛りの時に歌うにしても終わりのころに歌うにしても、ひとこと、なぜ「今」なのか、をお話ししてから歌いましょう。
桜が日本人に好まれるのは「散り際の潔さ」だからと言われますね。
これはアメリカ人にも理解できることなのでしょうか。
アメリカ ワシントンにも綺麗な桜並木があるそうですが、これは1912年に日米の平和と親善の象徴として日本から贈られたものだそうです。
1912年には親善の意味で苗木が送られましたが、65年後には敵国となったという歴史があります。
桜の苗木の返礼としてハナミズキが贈られたそうです。(アメリカハナミズキは最近では街路樹にたくさん採用されていますね)
デイサービスなどでこの話をしますと、ご存知の方が何人もいらっしゃいました。
軍歌に《同期の桜》という歌があります。
男性でこの歌をお好きな方は結構いらっしゃいます。
時期や必然性を加味したら、歌うことはそう問題にはならないと思いますが・・
1番の歌詞です。
「貴様と俺とは同期の桜 同じ兵学校の庭に咲く 咲いた花なら散るのは覚悟 見事散りましょ国のため」
戦争と桜と靖国神社は深い関係があります。
こんな時代背景を理解すると歌詞の意味がよくわかってきます。
今回のテーマは「桜」そして「アメリカ」です。
『さくらさくら』
日本古謡
花びらが風に舞っているような風情が想像できるメロディですね。
ペンタトニックのベルやトーンチャイムを使って、散る花びらを表現するのもいいでしょう。
『荒城の月』
土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲 明治34年
「春高楼の花の宴」
日本では平安時代から「花」と言えば「桜」を指します。
「昔の光今いずこ」
これも、はかないもの、散りゆくものへの美意識の表れでしょう。
『花』
武鳥羽衣作詞 滝廉太郎作曲 明治33年
「花」とはもちろん「桜」のことです。
隅田川沿いの桜や浅草など、楽しい話題を提供し、参加者同士の心の通い合いができるといいですね。
以上3曲はかなり認知の重い方でも歌える可能性があります。
歌っていなくても、近くで歌いかけたり、マイクを向けたりしてみてください。
ここからはアメリカにちなんだ歌です。
『桑港のチャイナタウン』
佐伯孝夫作詞 佐々木俊一作曲 渡辺はま子歌 昭和25年
渡辺はま子は《支那の夜》《蘇州夜曲》など中国風のメロディのヒット曲もたくさんあります。
『ミネソタの卵売り』
佐伯孝夫作詞 利根一郎作曲 暁テル子歌 昭和26年
歌っているだけでとても楽しくなる歌です。
「もう1回歌いたいわ~」
「子どもの頃、庭で鶏を飼っていて、どこに産んだかわからない卵を見つけるのが楽しみだった」
参加者が笑顔になることうけあいです!
『聖者の行進』
作詞作曲不詳 黒人霊歌 ディキシーランド・ジャズ
CDやクラリネットソロに合わせていろいろな楽器で合奏しましょう。
自由に鳴らす部分と、ルール(決まりごと)を決めて鳴らす部分があるといいでしょう。
レクの担当者は大きなアクションで参加者にわかるようにリードしてください。
(例)
○タンバリン、ドラム、サウンドシェイプ、マラカス、鈴などのグループごとに鳴らす。
○リズムを決めて鳴らす。
『夢見る人(夢路より)』
スティーブン・フォスター作曲
色楽譜によるベル(トーンチャイム)の和音奏
楽器活動については会員登録の上「音楽療法のヒント!」をお読みください。
(参考)その他桜にちなんだ歌
『花かげ』『港が見える丘』『春の歌』(桜の花の咲くころは~)
『青い山脈』『東京だよおっ母さん』『花笠音頭』『美しき天然』
『同期の桜』『東京音頭』『祇園小唄』
(参考)その他アメリカにちなんだ歌
『青い目の人形』『赤い靴』『赤鼻のトナカイ』『雨のオランダ坂』『冬の星座』『星の界』『旅愁』『私の青空』『故郷の廃家』『真白き富士の根』『もろびとこぞりて』『雪山讃歌』『リンゴの木の下で』『テネシーワルツ』『憧れのハワイ航路』『アロハオエ』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
