
「早く」「しっかり」は子どもを見ていない、就職は自立ではなく依存、さいかちどブンコ読書記録
こんにちは。越谷こどもさんぽの中川です。
さいかちどブンコで借りて読んだ本の感想です。
6月9日日曜日にブンコに返却に行く予定ですので、興味があればぜひブンコを覗いてみてください。
①「12歳までの自己肯定感」ばなな先生著
子どもの自己肯定感を高めるため親子で取り組めるワークを色々紹介しています。
著者の方は20年強小学校教師をした後、自分で学校を立ち上げました。
小学校で当初受け持った子ども7割が「自分が嫌い」と答えたそうです。
自分を好きな子も、サッカーが上手などの条件付きの「好き」だったそうです。
ばなな先生はありのままの自分を好きな子が少ないことに危機感を覚えたそうです。
さまざまな研究機関の調査によると、自分を嫌いな子どもの割合は小学生の高学年から中学生で上がるようです。
このため、この本ではその年頃までに身近な人に「あなたはそれでいい」と受け入れてもらう土台を作ることを提唱しています。
著者の人が書いた子どもの特徴がとても素敵で、
・すぐ夢中になる
・どんなこともおもしろくする
・誰とでも一瞬で仲良くなれる
ことで、どれも良くわかります。
どれも大人になると失くしがちな、素晴らしい特徴ですね。
大人になると他人の目や過去例との比較、将来への影響の打算などで、なかなか自分の心に素直に動くことができません。
子どもがこの素晴らしい特徴を失くしていくのは、小学校から中学校にかけて他人から評価されたり、周りや将来のことを考えるよう口酸っぱく言われるからなのかなと思いました。
親が子どもにかける良くない言葉として、
「早く」、「ちゃんと」、「しっかり」
が挙げられているところにハッとしました。
どれも子どもを応援して良い結果に導く言葉のように思えます。
ただ、これらの言葉を使うときに、大人は目の前の子どもを見ていないそうです。
次にやるべき用事や、それができなくて困っている自分を見て、忙しさのあまりに子どもを見たふりをしているそうです。
たしかに、子どもが夢中になっている「今」や、「子ども自身の体験」をないがしろにしてしまっているかなと思いました。
子どもが水の入ったコップを運びたがったとき、「ちゃんと気をつけて」など私も声をかけますが、もっと子どもに任せて見守る方がいいですね。
私の子どもが、床に転がっているポールの上に足を乗せて、バランスを取って夢中になっているときがありました。
私が「危ないよ」と声をかけたら、子どもからは「そういうこと言わないで」と、とても不満そうに言われました。
親としては怪我してほしくない思いの声がけでも、子どもにとってはせっかくの楽しみに水を差される行為なんですね。
これらの言葉はばなな先生自身も、小学校で教えていたときによく使ってしまっていたそうです。
子どもを思う気持ちから出てくる言葉だから使ってしまっても自分を責めなくてよいそうです。
責めなくていいけれど、忙しさに追われている自分に気づいてくださいとのことでした。
これらの言葉を使わないのは子どもを尊重することだと思います。
コップを運ぶ子どもをそうっと見守ったり、任せて心の中で応援したり、一足ごとに揺れる水面の揺れの緊張に共感したり、こぼしたら一緒に楽しく床を拭くのが、ゆっくりした自己肯定感を高める経験になるのかなと思いました。
やってみたいと思ったワークは、
カタツムリが這うようなゆっくりしたスピードで目と手を動かして葉っぱの絵を描くワーク、
磁石に何がくっついたら面白いか考えるワーク、
今の気分を伝え合うワーク、
好きなものと嫌いなものを伝え合うワークです。
小学生がやりやすそうなワークですが、後ろ2つはうちの4歳の子どもともできるのでやってみました。
まだあまり教えてくれないときも多いですが、思い出したときに聞いていきたいです。
ちなみに私の子どもの嫌いな食べ物は、しょうが、からし、とうがらし、大根だそうです。
どれも辛いものですね。大根は生の大根です。
大人の食べ物を食べてみたがったので、試しに一口あげると、辛い食べ物は学習してもう食べなくなりました。
中学生くらいになると食べられると思うので、その頃までに自己肯定感を大切にしていきたいなと思います。
さいかちどブンコのとも子ブンコで読めます!
②「『小商い』で自由に暮らす」磯木淳寛著
千葉県いすみで好きな物作りをして生活する人たちに暮らし方を取材してまとめた本です。
いすみは休日のマーケットが多く、マーケットでの販売だけを売上として、実店舗を持たずネット通販も行わない個人が多いそうです。
自分の好きな物を作ることで仕事と遊びの境がなくなり、楽しんで仕事ができ、趣味を持つ必要がないほど物作りに打ち込んで高いクオリティのものを作ることができるそうです。
実店舗を持たないことで、固定費が減り、自由時間が増えて仕入や研修に行きやすく、マーケット出店で別のお店やその顧客とつながるチャンスを得られるそうです。
人とのつながりを楽しんでいるからインターネット通販を行わない小商いも多いそうです。
その商品を欲しい人が、わざわざマーケットに足を運ぶことで、他のお店が気になったり道中飲食し、さらにいすみ全体の収入になります。
ただ、マーケットは土日が中心なので学校や保育園がない土日、子どもを預けられないのはジレンマになるそうです。
家族で遊びに行けないのと、子どもが大きくなると一緒に来なくなるのが心配という声がありました。
一つの答えとして、遊びに行かないことに負い目を感じないで、親が仕事している姿を見せるいい経験をさせていると自信を持つと書いてありました。
中学生くらいになると自分で遊びに行くようになるからそれぞれ自由に過ごせそうですね。
インタビューにあるソーヤー海さんの言葉に感銘を受けました。
一般的に言われる自立は企業への依存であること。
まず自分で動いてみて、それから周りのサポートを得て、そうして自分のやりたいことを作り出すのが本当の自立であり、ひいては共立であること。
自給自足は孤独に畑を耕すイメージだけど、それは豊かではないこと。
周りと支え合い、大変なとき誰かが手を差し伸べてくれて、お互いにできることをし合うことが本当に豊かであること。
豊かな生活は、会社の雇用やお金を求めることではなく、1人や家族だけで奮闘するのではなく、周りの人と協力し合える関係づくりだと思いました。
働けなくなったとき、勤め人は傷病や育休や失業についてお金を得られますが、勤め先自体がサポートしてくれたり、居場所を与えることはありません。
お金で割り切ること、働けない状態で会社に行ってもやることもなく、かえってじゃまになることなどから、働くこと以外求められておらず、どうしても虚しさが生まれるんだと思います。
家族は個人が自由に移動しにくいところ、少人数でスキルや体調が限られるところが難しいと思います。
ご近所さんと気軽に立ち話できる関係、地域で共に場づくりをしていける仲間がいる暮らしがいいなと思いました。
さいかちどブンコのshizukibooksで読めます!
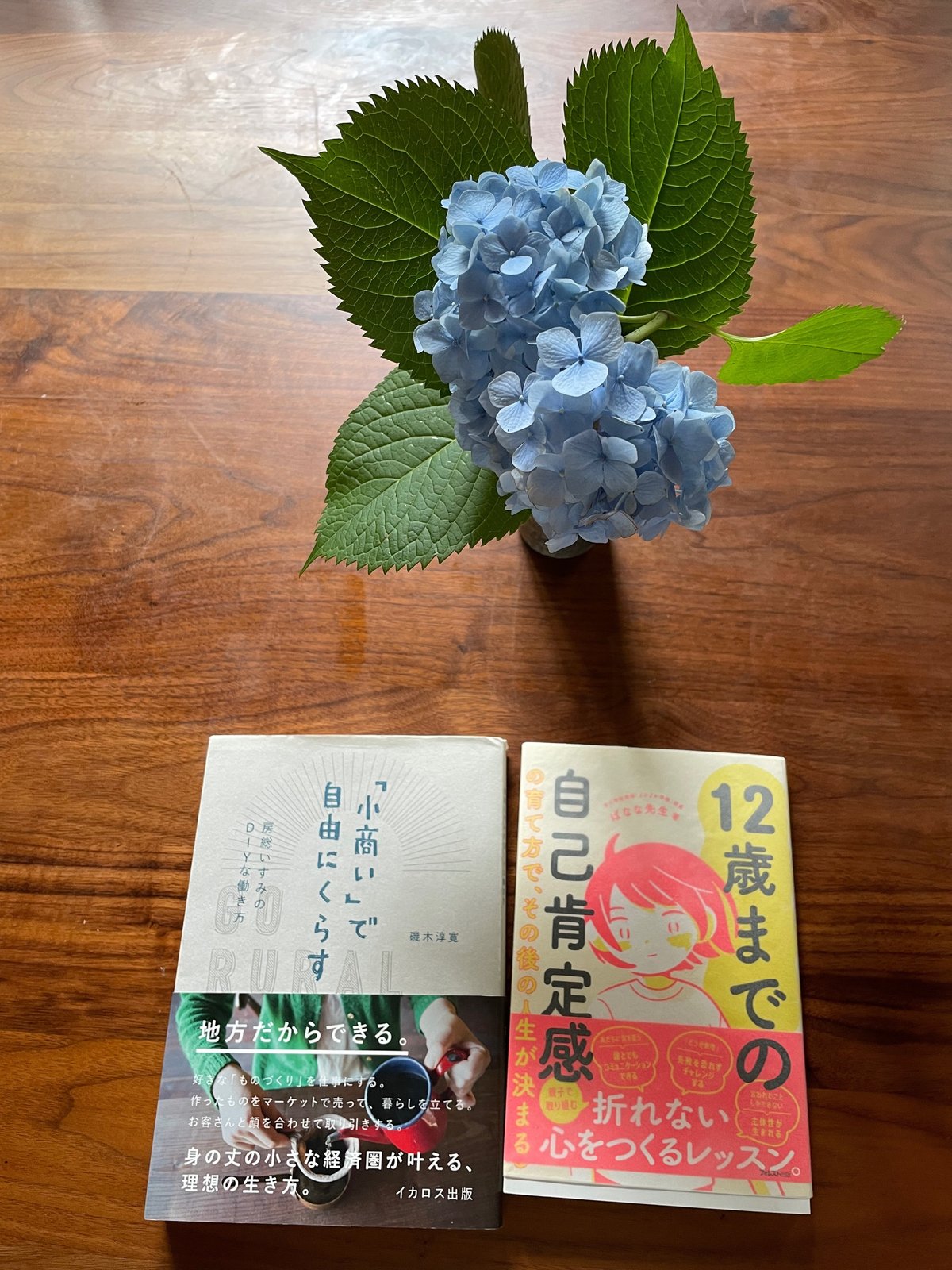
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
