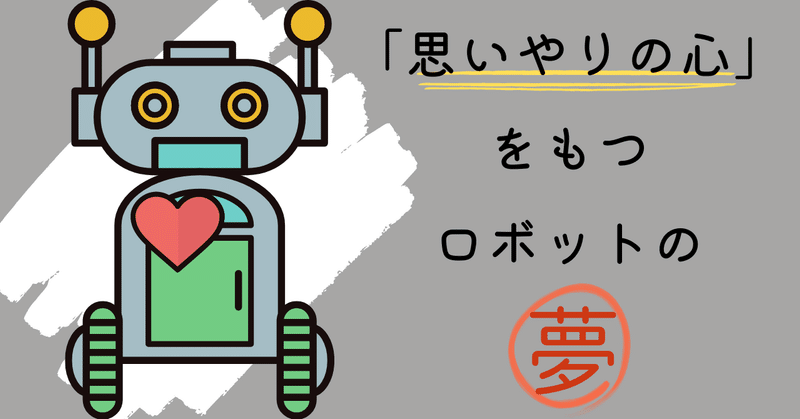
「思いやりの心」を持つロボット〜三流大学院生の見た夢〜
私はロボットの制御を専攻する大学院生でした。
そして昨日、私が2年間苦楽を共にした研究用ロボットを後輩に引継ぎました。
私は今年度で大学院を卒業し、一般企業に入社します。
ですので、この研究ともお別れです。
この2年間の成果としては、海外論文誌への投稿1本と国内学会発表が1回。
論文誌の査読者3人のうち、"interesting"と言ってくれたのは1人だけ。(めちゃくちゃ嬉しかったですけど)
画期的でも、何かインパクトのある研究でもありませんでした。
きっとこのまま誰にも注目されず埋もれていきます。
でも、手放した研究だけど、その存在は誰かに知っていて欲しい。
目指したビジョンや、アイディアは、きっと別の場所で役立てられるはず。
だから、この場を借りて、少しだけお話をさせていただきます。
私の研究のコンセプト、実現したかった事について。
「思いやり」の実装
論文には、こんなに抽象的なコンセプトを書くことはできませんでした。
いつも何かの課題を(無理やり)設定して、それを解決するための手法だという体で論を構成しました。
でも、本当に私が目指していたのは、ロボットに「思いやり」を持たせることでした。
「思いやり」の本質。
相手の立場に立って、自分が何をすればいいか考えること。
これを制御工学的に言えば、他者の内部状態の推定、及びそれを「良い」方へ持っていくために自分のとる行動を決定することです。
まさに制御工学の目指すところなのです。
心と物理学の相似
ドアがゆっくりと閉じるときの運動は、運動方程式として表すことができます。
これと同じ方程式になるように、電気回路を作ることもできます。
このことを指してある先生が「互いが互いをシミュレートできる」とおっしゃっていたのを、鮮明に覚えています。
ドアが電気回路を、電気回路がドアを、シミュレートすることができるのです。
「共感」とはまさしく、自分の神経回路で相手の神経回路をシミュレートすることなのだろう、と思います。
(実際、ミラーニューロンというのも観測されているそうです。)
周囲の様子を逐次推定して、人間に教えられた道徳と合わせ熟考して、自分の最良の行動を決めていく。
それが、私の夢見た未来のロボットです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
