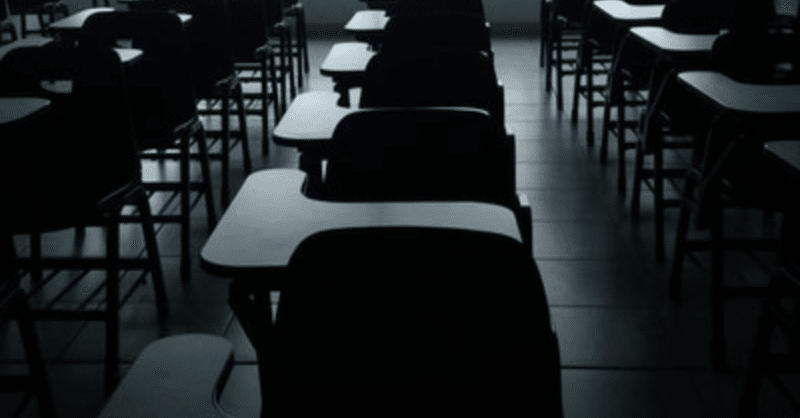
ぶっちゃけnightふりかえり・義務からクリエイティブは生まれない
こんにちわ、プロ雑用です!
月曜から夜ふかし・ぶっちゃけnight、第二回配信のふりかえりです。
そもそも義務とは何か?クリエイティブとは何か?/1:42
クリエイティブを辞書で引くと以下のように記されています。
クリエイティブ(Creative)とは、一般的には創造的、独創的であること。
日本では特に広告やデザインの分野で語られる場面が多い言葉です。
しかし、本来の意味から考えれば、分野によらず幅広く使われる考え方と捉えることができます。
特に、昨今の時代では変化が激しく、旧来の価値観や仕事の仕方が通用しない場面が多くみられます。そのような時には、従来からの脱却、新しい価値を生み出す、という意味でクリエイティブ思考というのは重要ですね。
一方で義務の意味を辞書で調べると以下のように記されています。
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「義務を果たす」⇔権利。
2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。
3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の義務」⇔権利。
簡単に言えば「やるべきこと」、と捉えられます。
この義務という言葉は、日本では、明治時代に使われ初めた言葉です。
中国の万国公法という国際法律の翻訳書から、「権利」と共に引用される形で、この国でも使われるようになりました。
明治政府は、日本で初めて誕生した中央集権国家であり、その統治には全国一律で適応されるべき”法”整備が急務。その中で、義務は、現在で言うところの”法的義務”の意味で使われて始めました。
現代では、法的義務のほか、道徳的・倫理的義務、社会的義務などの考えもありますが、いちように何か「させられている」感覚がつきまといます。
やらされ仕事に創意工夫は要らない/7:04
前回第一回目の配信でも散々繰り返しましたが、
仕事は、他責か自責かによって、その過程や成果が大きく異なります。
他責のやらされ仕事には、創意工夫は生まれません。ただこなすだけです。
「あぁ、はやく時間すぎないかなぁ…」
「つまんないな、やりたくないな」
自責で自ら行動する仕事では、創意工夫に頭を捻ります。
「これをこうしたら、もっと早く仕事が進むのではないか」
「この仕事、めちゃくちゃめんどくさい。どうやったら楽になるのか」
どうせ「やらなかいけない」のなら、
やらされ仕事でだらだらやるより、楽して楽しくやるほうが、いろいろ結果も付いてくるのではないでしょうか。
クリエイティブの根っこは、考え続けること/11:01
指示されたことを、指示通りこなすことは、大切なことであり、仕事の基本です。一方で、いつまでもそれだけでは、成長しませんし、少なくとも私はあまり楽しくありません。だって飽きるし。
クリエイティブ、仕事の創意工夫の根本は「考え続けること」で「疑問をもつこと」、つまりは思考力です。
これからの時代に、人間に求められる能力は「クリエイティビティ、マネジメント、ホスピタリティ」の3つだと、おおくの研究者が指摘しています。
※ただし遠い将来では、これら3つもAIとロボットに取って代わられるだろうとも予測されています。
つまり、ただ指示されたことだけをこなしている人は、これからの時代、働く場所がなくなるということです。
それはそうです。いちいち事細かに説明し、時に何度も説明が必要なコミュニケーションコストがかかる人より、ボタン一発か簡素な指示で仕事をこなす機械のほうが便利なのは考えるまでもありません。
ここでレンガ職人の話が出てまいります。
ダイジェストにすると以下のような内容です。
旅人が旅の途中、大きな教会の建築現場を通りかかった。
最初に出会ったレンガ職人に「あなたは何をしているのですか」とたずねると、その職人は「見てのとおり レンガを積んでいる」と答えた。
次に出会ったレンガ職人に同じ質問をすると、彼はこう答えた。「レンガを積んで壁を作っています。この仕事は給料がいいんですよ」
最後に出会ったレンガ職人にも質問をすると「すばらしい教会を作るためにレンガを積んでいるのです。この教会が完成したら多くの人が喜ぶでしょう!私はこの仕事ができて、とても幸せです」
ビジネス書籍などでよく引用される話で、私も便利なのでよく使うのですが、こちらも木こりのジレンマと同様、イソップ寓話には含まれない創作話です。ググるとイソップ寓話が出典と書かれてる記事が多いのですが、全てソース未確認の嘘情報です。ちょっとぐらい調べろと言いたい笑
おそらく元ネタは、ドラッカーのマネジメントに書かれている「石切り工」の話なのでは、と言われていますが、ドラッカーはこの話を働く側の目的意識うんぬんの観点では書いていないので注意が必要です。あくまでそういった人たちをマネジメントする側として、どうすべきかを論じています。
ま、話の出どころは別として、この話は仕事、働くということにおいて、動機づけがどのような役割をはたすのか、ということに示唆を与えてくれます。つっこみどころが多いのですが、わかりやすいですよね。
単に本当にレンガを積んでいるだけであれば、この3人の生産性という点については、あまり差が出ないかもしれません。ただ、何か問題が起こった時、単に作業しているか、先を見据えているかでは大きな違いがあると思います。
ダメなところ、本当は気づいてるでしょ?/14:03
世の中には、思考停止したまま進んだであろう仕事のあとが沢山あります。
「どうしてこうなった…」とあとから見ると思うような成果は、身近にあふれています。やむにやまれぬ事情があったのかもしれないが、もうちょっと何とかならんかったの?と。
本当は、途中で誰か気づいてるんです。気づいておきながら、スルーしてしまった。それを指摘した誰かがいたかもしれないけど、そういう人を潰しちゃうパターンもあるでしょう。
レンガ職人の例で言えば、最初の人が、最後の人の上司だったらそういうことが起こりえます。「親方!これってこうじゃないんじゃないですか??」「うるせえなぁ、だまって言われたことだけやっとけ!」みたいな。
ツイッターでこんな話を見かけました。
読みました?
それじゃ、言わなくてもわかるな?笑
日本人は特に共同体ムラ社会の文化的背景をもっているので、同調圧力という名の空気を重要視します。これは良いことも多い反面、悪くすると、組織的な仕事においては足かせになってしまうことがある。
人は、自分ごとでないと、本気になれない/23:15
どんな人間でも、他人のことより我が身がかわいい。
勝手なんですよ、人間てやつは。
いやいやそんな人ばかりじゃないよ!という意見もありますし、実施いるでしょうが、そういう人はほんとうに稀。
あなたは、その稀な人ですか?そうであれば素晴らしいことですね!
なんでもいいんですが、自分の部屋や持ち物はキレイに保とうとか、大切に使おうとか、掃除しようとか、そういう意識があります。
一方で同様に他人の所有物に対して、あるいは公共の所有物に対して、自分のものと同じように接することは、なかなか難しいことが多いのでは。
自分のものだと思うから本気になれる、というのは仕事でも同じですね。
では、仕事をクリエイティビティにするためには、自分ごととして捉えるためにはどうすればいいのか?
いろいろな手法があると思いますが、一つにはアウトプットしてもらうというのがあるかと思います。自分の仕事を詳細に書きだしてもらったり、マニュアルを作ってもらうなど、言語化・図式化してもらうという方法があります。
よく、人に教えることは何よりの学びになる、と言いますが、それと同じように、客観的に自分の作業を見つめ直す機会をつくることで、あらためて自分の仕事に対しての理解が深まり、その結果自分ごととして捉えられるようになります。(もちろんそうならない場合もありますが)
あらためて書き出したものを自分で見直すと、
「あれ、ここの手順、いままで何も考えずにやってきたけど、なんでやってるんだっけ…?」「ちょっと意識してなかったけど、手順おおすぎるな…」などと気づくことも多いのですね。
クリエイティブは疑問から始まる/30:13
その時代のあたりまえを破壊する。
これは、普段、とくにルーチン化している仕事なんかでも、なかなか難しいです。ですが、先程記したとおり、アウトプットしてみると「あれ?」と思うことがたくさん出てきます。
そういった時に、その疑問やひっかかりを放置せず、なぜなんだろう?と考えることが、新しい発見につながることが多いのですね。
源義経のガケ下りの奇襲しかり、織田信長の鉄砲三段構えしかり。
歴史を学ぶと、大きな転換期に負けた側は、それまでの慣習や義務に縛られていることが多い。何かを変えよう、もっと良くしたい、と思うなら、まず客観的に仕事を見てみることも、クリエイティブには重要なことです。
終わりに
ぶっちゃけnight第二回目「義務からクリエイティブは生まれない」のふりかえりでした。いかがでしたでしょうか?
今回の話は、義務が悪い、クリエイティブが良い、という話ではありません。どちらも必要だが、変化を求められる時代、あるいは変化しなければ生き残れない状況になったとき、義務だけでは無理だ。では、どうやったらクリエイティブな仕事ができるのか?というお話でした。
長文、お付き合いいただきありがとうございました。
よかったら動画もぜひご視聴くださいませ。(倍速再生がおすすめです)
またMOVEDのチャンネル登録もよろしくおねがいします。
それでは、次回は第三回目の配信、テーマは
人の足を止めるのは絶望ではなく諦め。
人の足を進めるのは希望ではなく意志。
のふりかえりをお送りいたします。
それじゃ、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
