
地域の生業を継承する「継業バンク」創業者が、「ハルキゲニアラボ」に参加して得たものとは?

左から、SIIFインパクト・オフィサー 田立紀子、古市奏文、ココホレジャパン代表取締役社長 浅井克俊氏、小林俊仁氏(個人投資家) 場所:ココホレジャパンが現在会員登録中の東京都主催スタートアップ支援施設NEXs Tokyoにて撮影
2020年4月から6ヶ月間実施した、SIIF(社会変革推進財団)の新しいアクセラレータープログラム「ハルキゲニアラボ※1」。地域に新たな資源循環を生む事業アイデアを持つ団体に対し、研修や事業開発支援を行ってきました。今回は、ラボに参加した4団体のうち、岡山を拠点に継業プラットフォーム「ニホン継業バンク」を運営するココホレジャパン株式会社 代表取締役社長の浅井克俊さんをお迎えし、創業の動機や今後の課題、ハルキゲニアラボ参加の感想と、今後に期待することを伺いました。
タワーレコードから社会起業家に。事業構想の背景は「ままかり」

SIIFインパクト・オフィサー 田立紀子
田立 浅井さんはもともとタワーレコードでブランドマネジメントやライブイベントを手掛けていらしたそうですが、なぜ社会起業家を目指すようになったのですか。

ココホレジャパン代表取締役社長 浅井克俊氏
浅井氏 タワーでは環境NGOのサポートとしてロックフェスでゴミ袋を配ったり、リサイクル活動をしたりしていました。2006年頃に街の清掃活動を行うNPO・グリーンバードの渋谷チームを立ち上げたときも担当でした。その頃から環境問題やソーシャルビジネスに関心を持ち始めたんです。ただ、職場では管理職を任されるようになり、一方で結婚して子どもが生まれ、なかなかシフトチェンジに踏み切れずにいました。トリガーになったのは東日本大震災で、発災の翌年に思い切って会社を辞め、岡山県瀬戸内市に移住したんです。
田立 最初は地域おこし協力隊として移住したと伺っています。そのときから起業を視野に入れていらしたわけですか。
浅井氏 地域おこし協力隊は期間が3年と決まっているし、そもそもソー シャルビジネスに取り組みたかったので、いずれにせよ起業しか選択肢はないと思っていました。けれども、具体的なビジョンがあったわけではないんですよ。
田立 地域おこし協力隊では、岡山特産の小魚「ままかり」の商品化から始められたとか。
浅井氏 東京のデパートで瀬戸内市のフェアを開催しようという話があり、何かオリジナル商品が欲しい、という話が持ち上がったのがきっかけでした。それで「ままかりでアンチョビをつくってはどうか」と提案したんですが、結局のところ商品化も自分でやるしかなく、ままかりの仕入れから手探りで始めました。地域のいいものを東京で売れるようにブランディングするなら、自分たちのスキルが活かせるし、地域貢献もできるので、自分で事業化しました。
田立 ままかりビジネスをされてみて、いかがでしたか?
浅井氏 当時はまだ地域ブランド商品が珍しかったので、デパートや駅で 扱ってくれて、かなり売れましたね。そうしたら、今度は製造量が追いつかなくなって、在庫切れで販売店に頭を下げることも度々でした。ままかりの漁獲量って、その日の朝にならないと分からないんですよ。漁師さんから「今朝は100キロ揚がったけどいる?」なんて電話をもらって、車を走らせて取りに行ったりしましたね。大変だったけど、いい勉強になりました。
田立 ままかりビジネスは、既に他の会社に譲渡されたんですよね。事業承継ビジネスである「継業バンク」の着想はそのあたりのご経験から生まれたのですか。
浅井氏 ままかりの商品化に取り組んだときから、いずれは事業を誰かに譲ることが前提でした。地元の人が気付いていない価値を掘り起こしてスモールビジネスをつくり、それが地域の生業になるといいな、と考えていました。しかし、いざ譲る相手を探そうとしたら、そもそも探す手段が存在しないということに気付いたんです。
田立 小規模事業の継業を困難にしている社会課題を発見したわけですね。
浅井氏 たまたま他の仕事で全国の継業事例を取材する機会があり、どこも跡継ぎ不足、担い手不足で困っていることを実感しました。自分も当事者であるうえ、これまで培ってきた広告のメソッドもある。このスキルを使って何か解決策ができるのではないかと。そんなことを考え始めた時期に、ちょうど古市さんと出会ったんです。

SIIFインパクト・オフィサー 古市奏文
古市 2018年の前半ぐらいでしょうか。
浅井氏 当時はまだ考えが浅かった。色々な方に地域の継業をビジネスにしたいと話しては、「M&Aで事業を買っても、社長は地元に行ったりしないよ」とダメ出しされることも多くて。それで、僕らがやりたいのは、従来あるような“B to B”のM&Aではなく、“C to C”のM&Aだと気付いた。でもそれでは手数料が取れないから、ビジネスにはならない。目指す方向とマネタイズの方法が合致しなくて、壁にぶつかってばかりでした。
古市 今ある「継業バンク」の構想はどうやってまとまったのでしょうか。
浅井氏 当初は、僕らのスキルを活かして、継業にストーリー価値を持ち込むコンテンツを考えていたんです。しかし、それではいかにクオリティが高くても量産はできない。何百万社という廃業の危機は救えません。そこで、僕らのアイデンティティーはいったん捨てて、引き算で考えようと、頭を切り替えました。マネタイズについても、事業の譲り手と継ぎ手から手数料をもらうつもりだったけれど、改めて、地域から事業者がいなくなって困るのは誰だろうか、と考えた。すると、地方自治体や商工会議所が浮かんできたわけです。そうか、「空き家バンクの事業承継版」をつくればいいんだと。それがブレイクスルーでした。
ハルキゲニアラボを通じて、起業家として成長できた
古市 浅井さんに初めてお会いしたときは、エンターテインメント分野で活躍してきたプロデューサーの印象が強くて、この方は起業家ではないのかも、と感じました。
浅井氏 実際、そうだったと思います。自分でも、ハルキゲニアラボに参加した半年を挟む1〜2年で、ようやく起業家として成長できたと感じていますから。
古市 近くで拝見していて、考え方も発言も、すっかり起業家らしくなられたと感じています。その成長に、ハルキゲニアラボが貢献できたのならいいんですが。
浅井氏 ハルキゲニアラボに参加したことには、とても大きな意味がありました。多くの経営者や投資家と接する機会が得られたし、ずいぶん勉強もしました。それまで言語化できていなかったことが言語化できたり、解像度が低かったところが高まったり。僕自身はもちろん、スタッフにとってもまたとない機会になったと思います。
田立 ハルキゲニアラボのプログラムの一つであるインパクトマネジメント。自分たちの事業がどのようなアウトカムを生み出し、どのように社会的インパクトとつながっていくのかについて、ロジックモデルなどのツールを使用し、浅井さんとスタッフの方々が協力して設計していかれました。浅井さんが「社内ではできないスタッフとの議論ができた」とコメントしてくださったのが印象的でした。
浅井氏 社内では、僕の言葉が答えになってしまいますからね。ロジックモデルの議論を通じて、僕自身にとっても、スタッフにとっても、継業バンクの目指すところが整理され、明確になったと思います。KPIも組みやすくなりました。
田立 ロジックモデルでは、目指すゴールに向けて必要となるKPIが何なのかを解きほぐすことができます。そのことによって、どのKPIが今、重要なのかを判断しやすくなると思います。
浅井氏 継業バンクは、跡継ぎが見付かって事業承継が実現することがゴールではあるけれど、それには一定の時間がかかります。初期の段階では、まず継業バンクを開設した自治体や地域の側にアウトカムが生まれなければならない。例えば、事業説明会を開催したら、継ぎたいという人が現れて現地まで来てくれるだけでも喜びはあります。そこをさらに掘り下げて、地域の仕事に本質的な価値を見出して言葉にすることは事業者にとっても嬉しいことだし、地域の魅力にも直結する。最終的に「地域のすごい仕事図鑑」みたいなものが継業バンクに蓄積していけば、経済合理性だけでは語れないアウトカムになるはずです。それをうまくKPIに吸い上げられるといいんですが。
ハルキゲニアラボに参加したことで、新たな資金調達も実現
古市 SIIFでは、ハルキゲニアラボ終了と同時にJ-KISSによる出資を提案させていただきました。 浅井さんはどう受けとめておられますか。
浅井氏 ハルキゲニアラボを通して評価していただき、投資していただくことが目標でしたから、もちろん嬉しいです。J-KISSは初めての経験ですが、これは僕たちのようなスタートアップに配慮した手法ですね 。
古市 投資家にとってもJ-KISSは、バリュエーションの妥当性が上がる、スピーディーに意思決定できる、などのメリットがあるんです。
田立 SIIF以外に、エンジェル投資家さんからも出資を受けられましたね。
浅井氏 その投資家さんには日頃から相談にのって頂いており、以前から話はあったものの、結果的にSIIFの出資が契機になりました。
古市 エンジェル投資家も具体的なスキームがないと出資に踏み切れないでしょうし、ハルキゲニアラボによる助成から出資への流れが、他の投資家の方からの新たな資金調達につながったのなら、SIIFとしても成果です。
浅井氏 社会起業家にとって、資金調達の手段は限られています。NPOなら寄附や補助金が受けられるけれど、株式会社では使えなくて、かといってVCもソーシャルビジネスは儲からないといって出資してくれない。ハルキゲニアラボのような仕組みには、スタートアップがよりソーシャルな方向に転換していく可能性が秘められていると思いました。今後は、ソーシャルビジネスへの出資やインパクト投資が、当たり前の 選択肢に位置付けられていくといいですね。
経済だけで測れない、継業の社会的価値の評価が必要
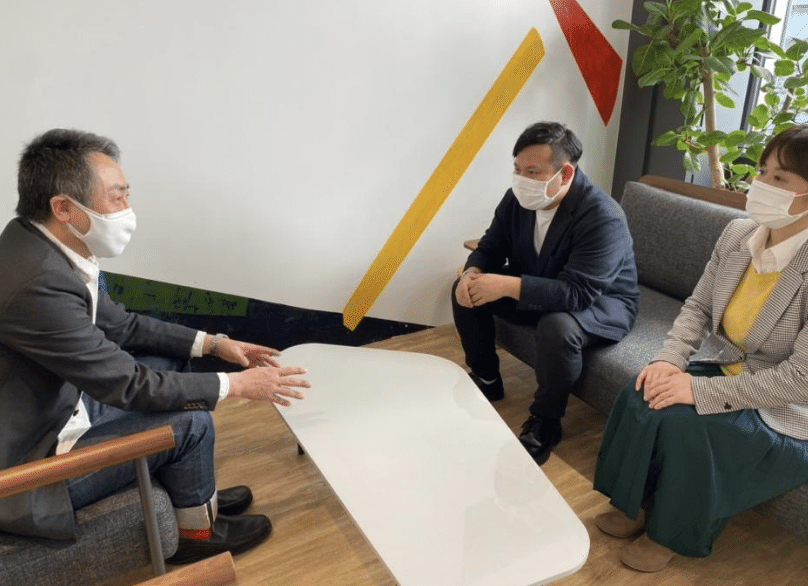
古市 これからの継業バンクの取り組みについてお聞かせください。
浅井氏 目下の最重要課題は開設自治体を増やすことです。今でも相当数のアプローチはしているんですが、なかなか決断を下してもらえない。複数の部署にまたがる課題なので、行政の縦割りが壁になりますし、予算計上してもらうのに年度を待たなければならないのも非効率です。地域連携協定を結ぶことを条件に実証実験を提供するといった方法も考えているところです。また、自治体以外に、最近は保険会社や大学からの打診もあります。これから人口減少が進めば、後継者不足がさらに顕在化するのは間違いない。継業バンクの連携先は、必ずしも自治体に限らないのではないかと考えています。
古市 SIIFに期待する支援はありますか?
浅井氏 どこかの自治体で、インパクト評価を組み合わせた実証実験をご一緒できるといいですね。ハルキゲニアラボにも参加していたソーシャルセクターの移住支援や空き家活用事業も、継業バンクと相性がいいと思いますし。
田立 今後、継業バンクがあることで生み出される社会的インパクトについて、行政に分かりやすく説明できるようなインパクトレポートをSIIFと共同で作成しようかというお話も出てきていますね。
浅井氏 行政にとって、議会や住民に説明しやすいインパクトを示す必要がある。そこは自治体にもヒアリングしながら検討したいですね。
古市 これまでの事業承継では、経済的なインセンティブが優先されてきたと思いますが、インパクト投資の可視化により、社会関係資本や文化資本といった経済以外の資本や価値を強調していくことで、また違ったインセンティブで流通していくことができるのではと考えています。
浅井氏 経済だけではなく社会的価値を評価する指標が必要ですね。事業の価値は、売り上げだけでは評価できない。特に、僕らが手掛ける継業は、高齢者から若者に引き継いだだけで、単純に稼働時間が伸びるから売り上げが上がる、といった現象が起きる。けれども、事業を継ぐ人の動機はそこにはなくて、譲ってくれた人や技術に応えたいという想いが大きいし、そこに幸せがあります。
田立 事業を譲る人も継ぐ人も、どちらも幸せになりますよね。
古市 継業の社会的評価を明らかにすることで共通理解をつくる。それは我々としてもやっていきたいですね。
※1 ハルキゲニアラボについて https://hallucigenia-lab.com/
ハルキゲニアラボとは「新たな資源循環の仕組みづくり」を目指し、社会的なエコシステムづくりを行う事業者の支援・開発に特化したアクセラレータープログラムです。多様な生物の誕生が爆発したカンブリア紀において、奇妙な構造を持っていたとされる生物「ハルキゲニア」を名前の由来としており、一見不自然であったり、非合理的であったりする事業アイディアを「社会的に必要なユニークでチャレンジングな取り組み」として捉え、社会の中に複数生み出していくことを目的としています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
