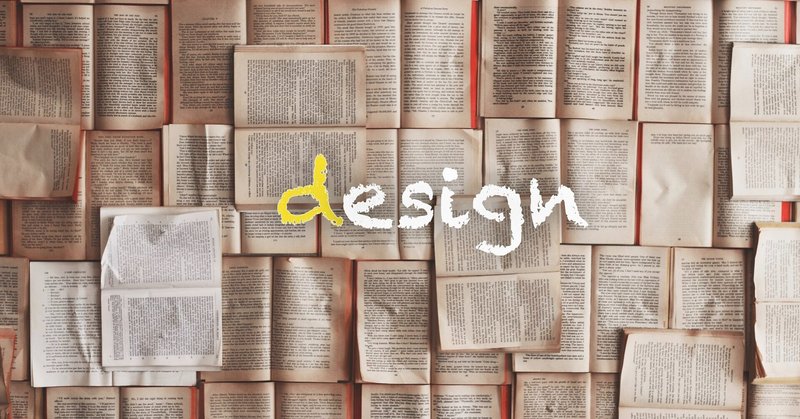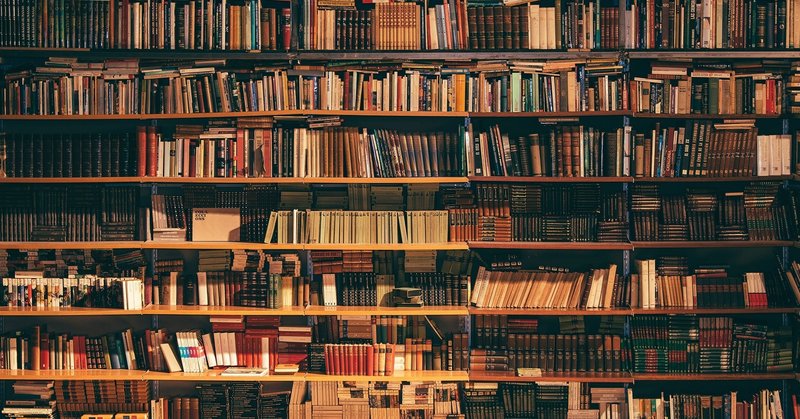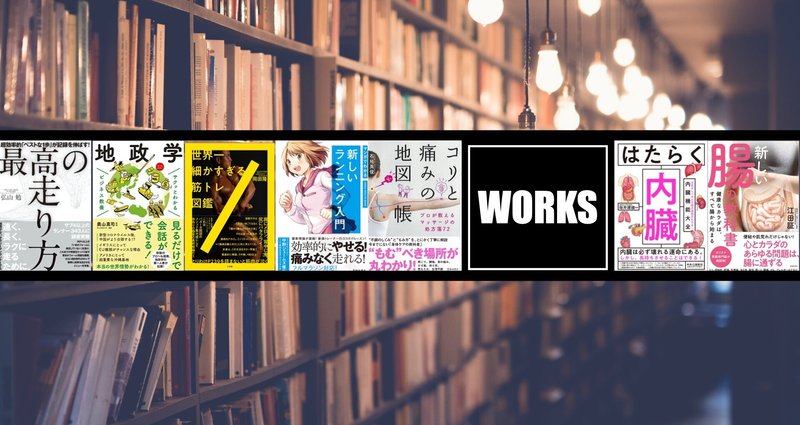
- 運営しているクリエイター
#編集

発信者目線で「面白いだろう」と捻り出した本は売れず、こんな本が「必要だよね?」とユーザー目線でふんわり生まれた本ほど売れる問題
今宵、本の深みへ。 編プロのケーハクです。 主に実用のジャンルですが、これまでたくさんの本を企画したり、つくったりしてきました。 出版社からのオーダーを受け、企画立案から制作までマルっと一式請け負うわけですが、最近は「とにかくヒットする本をよろしく!」的な恐るべき依頼が増えてきました……。 特にはじめて取引をする出版社の場合は期待が大いに膨らんでいるようで、「すでに成功する気満々」で依頼してくることがほとんど。 こちらも継続的な受注がかかっているため、失敗が許されない