
司法試験の勉強法(国際公法選択)
令和2年度の司法試験に合格しました。私は、国際公法を選択しましたが、国際公法は受験者数自体少なく、対策についての情報が限定的です。そのため、今後国際公法で受験される方のために、その記録を残そうと思います。
①おもな勉強法
勉強法としては、以下が重要と思います。
〇過去問をすべての年度解く。
〇プラクティス国際法の演習問題を解く。
〇予備校の本、基本書を通読する。
〇短めの判例集と百選を読み、ポイントだけ押さえる。
〇重要な概念についてまとめノートでおさえておく。
〇司法試験六法記載の条約で、過去問で出た条文をマークし、参照できるように練習する。
②使用した教材
〇基本書
・杉原高嶺「国際法学講義」第2版(2013年)
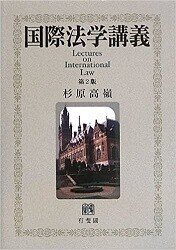
体系的、網羅的な記載があるため、重要な概念のところを繰り返し読みました。
〇判例集
・判例百選
・国際法基本判例50選
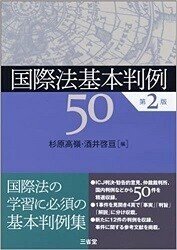
判例百選を使いつつ、国際法基本判例50選というすこし薄めの判例集を用いました。事例問題では、判例を想起して記述することが求められますし、論述中に、要件や、概念を記述するときに、ICJ○○事件などと言及すれば、加点されるはずです。
出題趣旨、採点実感では、以下のように判例への言及が求められています。
「設問3は(中略)国際司法裁判所「在テヘラン米国大使館員人質事件」を思い浮かべて解答すればよい。」(H20年度出題趣旨)
「トレイル熔鉱所事件などが,よく出来ている答案では遺漏なく触れられていた。」(H22年度採点実感)
「「バルセロナトラクション事件」判決にも言及し,乙社が事実上甲と同視できるから乙社に関する損害の賠償も請求できる旨をきちんと分析した優れた答案も幾つかあった。」(平成23年度採点実感)
「核実験事件のような先例にも留意し,先例を踏まえて,先例で示された一方的宣言が法的効果を持つための要件が論じられている答案もあった。」(平成26年採点実感)
私は、上記判例集の事案をおさえつつ、論述で使えそうな部分にマークをして勉強していました。
〇演習書
・演習プラクティス国際法

演習問題が充実しており、過去問以外に解くのであれば本書が最適だと思います。私自身は、本書の問題を自主ゼミ2人でお互い担当する問題を決めて解き、添削しあうという方法で取り組みました。
〇参考書
・公務員試験対策1冊で合格シリーズ7 国際法
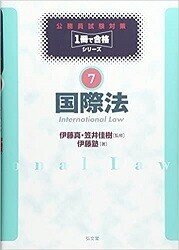
端的にポイントが記載されており、短時間で重要なことだけ復習するのに用いました。この本で記載されているポイント、特に各要件についてはふせんを貼り、必ず書けるように準備しました。
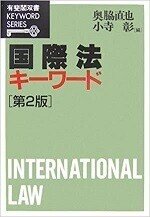
51のテーマについて、4頁ずつで記載されており、問題意識などをもったり、概念について網羅的に理解するために用いました。
〇予備校の講座
辰巳法律研究所の、合格者講義「国際公法2位の答案はこう書いた」を聞き、勉強法や、合格できる答案の水準について把握することができました。
また、選択科目の答練を受講し、書く訓練をしておきました。
③対策のポイント
過去問対策が最重要であると思います。
時間の許す限り、全ての年度を解くべきだと思います。ただ、ほかの科目との兼ね合いもあり、国際法ばかり勉強しているわけにもいかないため、過去問は答案構成にとどめ、出題趣旨と採点実感と自分の構成を比較し、できたこと、できなかったこと、その年の受験生ができて自分ができなかったことはないか確認する作業をすべての年度で行うようにしました。
過去問に出たことが、再度出題されるため、過去問対策は重要です。令和2年の出題も、平成24年に出題のあった主権免除が再出題されていました。
司法試験六法に記載のある条約については、適用することが求められることがあるので、過去問を解く際に、どの条文が頻出であるのかを確認しつつ解くようにしていました。
過去に出題のあった条文は以下の通りです。
・国連憲章 2条3項、2条4項、10条、11条2項、12条1項、24条、25条、27条、39条、51条、94条1項、94条2項、103条
・ICJ規定 36条2項、41条、59条
・外交関係条約 2条、9条、22条、29条、32条、39条2項、41条
・条約法条約 2条1項、18条、60条、61条、62条
・UNCLOS 17条、19条1項、19条2項、30条、33条、45条、73条、76条1項、77条3項、83条1項、111条、295条、309条、310条
・難民条約 1条A
また、司法試験六法に記載はないのですが、国家責任条文は、出題趣旨などに言及があり、論文で正確に言及すれば加点事由となるかと思います。
国家責任条文は、8条~12条、30条、48条、50条、54条などが過去に出題趣旨などで触れられています。
平成27年度は、モントリオール条約が参考資料として問題文に記載されており、7条の「引渡しか訴追か」などについて問う問題が出題されています。こうした出題に備えるためには、国際法の知識を網羅的に、授業や基本書で押さえたうえ、代表的な事件で問題となった条約は出題の可能性があるとして、判例学習の一環で条文も見ておくのがよいのではないかと思います。
国際法の過去問を解きつつ、この年はこのテーマが出たのか、と星取表を作っておくことをお勧めします。
私は、以下のような星取表を手書きで作っていました。
あとは、過去問で出題されたところを中心に、書きたい概念、要件などについてまとめノートを作っておくとよいと思います。過去問で出たところが何度も出るため、さっと見返せるものを作り、記憶に定着させておくと、本番でも論述できると思います。
④まとめ
国際公法は、受験者数が少なく、情報量が少ないということで難しい科目です。しかし、対策をきちんとすれば、合格できる科目だと思います。また、国際公法を勉強してみて、これが好きであるとか、難民支援や国際協力に関心があって、国際公法に関心があるといった場合は、これを選択科目にしてよいのではないかと思います。
辰巳法律研究所の合格者講義は役に立ちましたし、最近ではアガルートの講座もあるようなので、そうした講義を活用することも対策としてとても効果的なのではないかと思います。
国際公法受験の方は、仲間を見つけるのも大変だと思います。私は、ツイッターをやっているので、相談や添削の希望があればいつでも対応したいと思います。私の先輩も、国際公法で受験し、勉強法を教えてくれました。国際公法を選んでいる方の参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
