
ポケモンカードにおける正しい「反省」の仕方を考える〜負けをきっかけに反省をする意識からの脱却〜
・ジムバで〇〇に負けたから〇〇をデッキに入れよう
・○○はケアせず負けたから今後はこんな立ち回りをしよう、
・〇〇は○枚じゃ引けなくて、負けたから採用枚数を増やそう
ポケモンカードに本気で取り組んでいると誰しもの頭に上記のような「反省」が頭をめぐるのではないだろうか。
次は勝てるように、あの大会で結果が出せるようにとプレイヤーは頭を働かせる訳である。
今回はこの「反省」について、深く考えてみたい。
反省とは
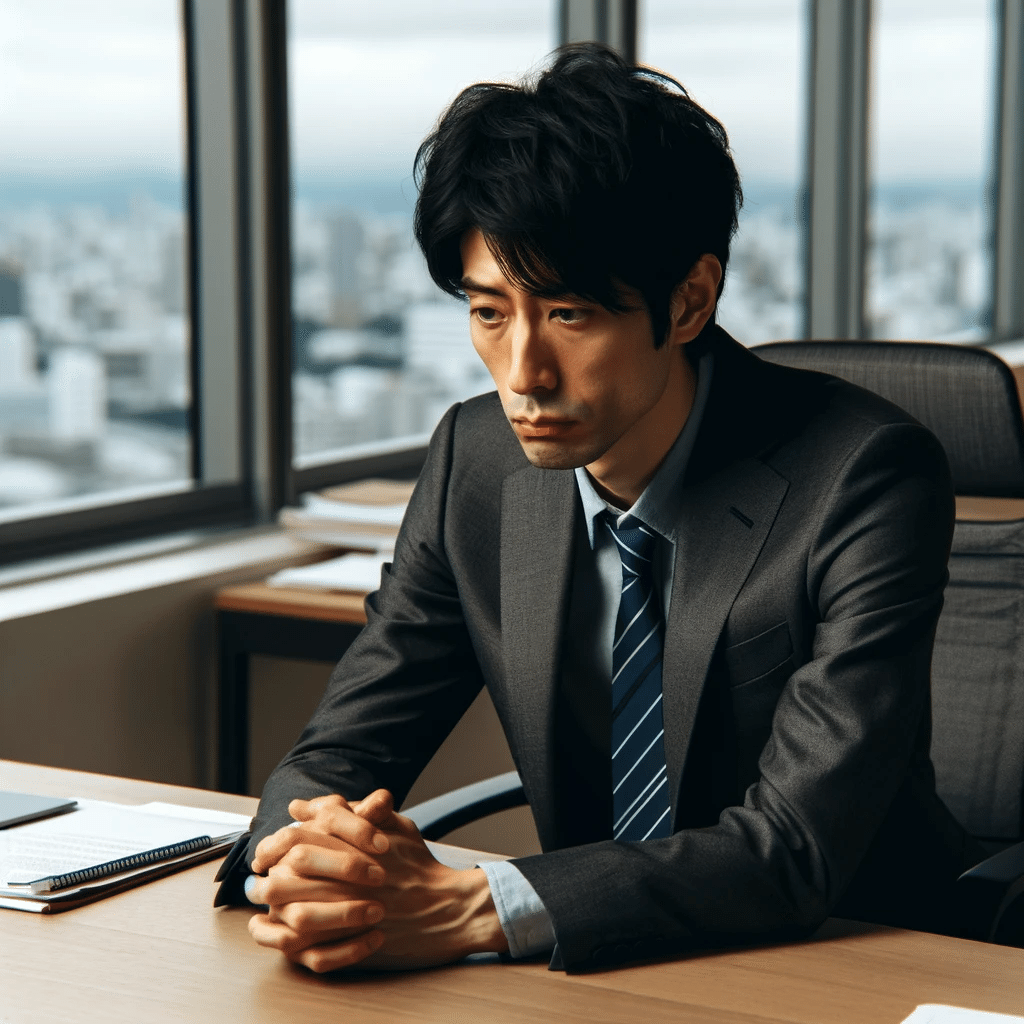
まず一般的な反省について辞書で調べると以下の通りの記載となっている。
はん‐せい【反省】
1 自分のしてきた言動をかえりみて、その可否を改めて考えること。「常に—を怠らない」「一日の行動を—してみる」
2 自分のよくなかった点を認めて、改めようと考えること。「—の色が見られない」「誤ちを素直に—する」
しばしば反省においては、何が悪かったのか、それが再発しないようにするための明確な計画を立てることに重点が置かれる。
ポケカにおいても同様で、悪かった点が再発しないようにPDCAを回す事が上達に繋がると考えられる。
ここで問題になってくるのが、ポケカにおける「悪かった点」とは何になってくるのか?という事だ。
勝負事における、最も悪い事とは「負け」に他ならない。であるとするならば、負けた事を起点に負け試合の反省を行うのがセオリーと考えたくなる。
しかしながら、ポケカにおいてそれはかならずしも正しいわけでは無いようである。
不完全情報ゲームの特徴

ここで考えなければいけないのはポケカが「不完全情報ゲーム」であるという事だ。
ゲームには完全情報ゲームと不完全情報ゲームが存在する。
完全情報ゲームとは
ゲームをしているプレイヤーが、次の動作の判断をする時点で他のプレイヤーがこれまでに行った動作を確認することができるゲームのことを指し、将棋、囲碁、オセロ、チェスに代表される。
一方、不完全情報ゲームは、
ゲームをしているプレイヤーが、次の動作の判断をする時点で他のプレイヤーがこれまでに行った動作を見ることができないゲームの事を指し、麻雀や花札等がそれに当たる。
不完全情報ゲームは相手の情報を元にした駆け引きが楽しめる一方で、運の要素が大きくなるのも特徴の一つとなっている。
筆者はポケカもカテゴリ分けをすると不完全情報ゲームに属すると考えている。
不完全情報ゲームにおける反省
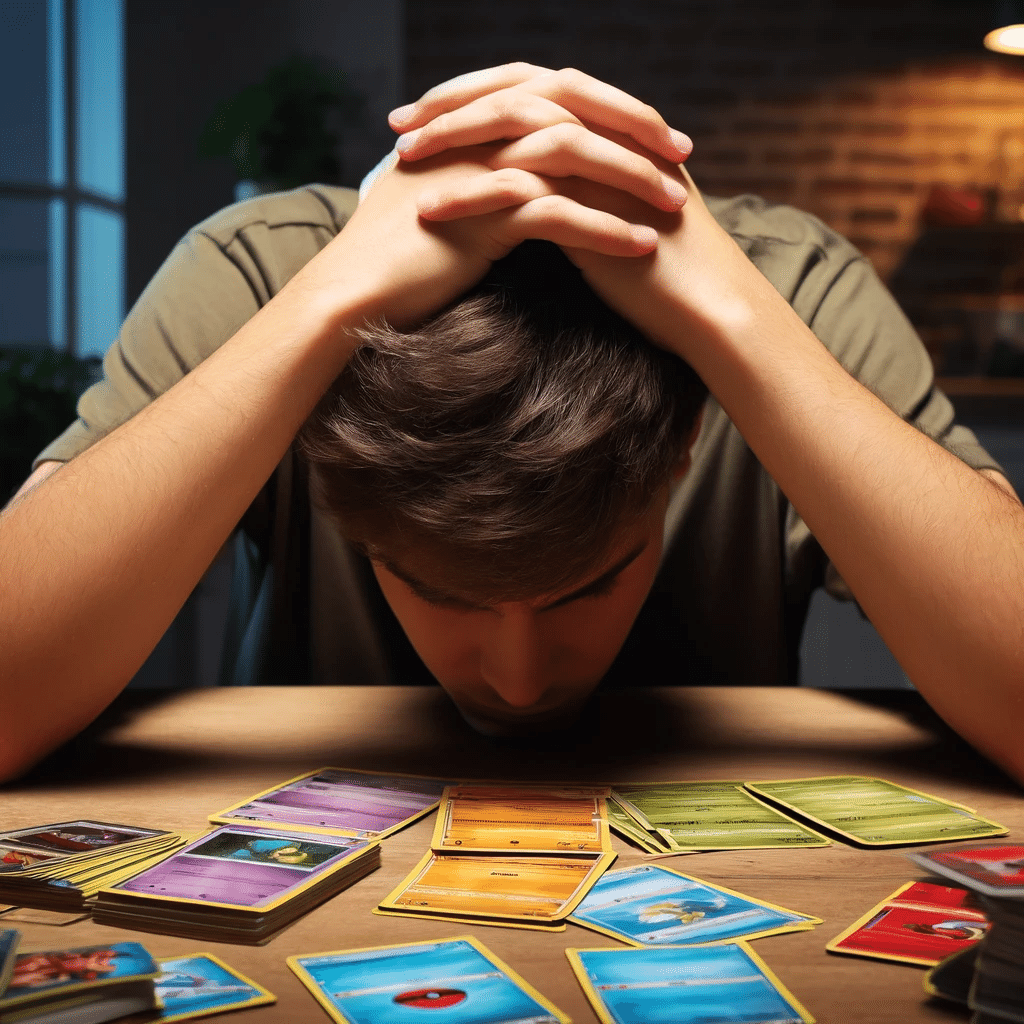
再度記載するが、ポケカ上達の為の反省において考えなければいけないのは、
ポケカが運の要素が含まれる「不完全情報ゲーム」に属しているということだ。
この不完全情報ゲームにおいて、目の前の試合に負けたという結果を元に反省をするとどツボにハマる可能性がある。
同じ不完全情報ゲームの麻雀について
正しい反省の仕方が示された参考になる動画を以下に示す。
動画の内容を要約すると、
・不完全情報ゲームの麻雀において、起きた結果(勝敗)を元に反省をしても状況の再現性が低く上達に繋がりにくい
・再現性の無い事項についてPDCAは回すべきではない
・結果に関わらず内容を元に反省をするべき。
・負けが混むと不安になり、落ち着く為に理由を求めたくなるが、その為の安易な反省はむしろ自分を弱くする
という内容である。
筆者はポケカにも一部これらが当てはまり、極端な運勝ちや運負け、また確率の偏りが反省点を誤認させる可能性があると考えている。
また、山の順番がランダムに並ぶカードゲームにおいて、ドローソース使用の順番等については、引けた引けないの結果論でPDCAを回すと正しい知識が積み上がっていかない可能性が高い。
この辺は有識者のnote等で学んでいくしか無さそうだ。
※環境デッキのベンチ構成や立ち回りなどは一部再現性が高くPDCAを回すことが有用な可能性もある
麻雀と大きく違うのはカードプールが常に更新され、環境の変遷が激しいという事だ。
この点がPDCAを回す上で大事な再現性をより妨げていると考えられる。
ポケカの反省に潜む2つの落とし穴

ポケカにおける、上達に繋がらない誤った反省のパターンとしては以下の2点が考えられる。
①反省点の見過ごし
反省すべき点が、運によるものであるという認識や結果として勝つ事により見過ごされる
②反省点の誤認
正しいプレイングや選択をしているが、結果として負ける事により、反省点と誤認される。
では、これらの落とし穴にハマらないようにする為にはどのようにすれば良いのだろうか?
勝ち負けに囚われず、試合の内容を元に反省を行うという事

一つの回答として、試合内容を元に反省を行う事に拘るという事が挙げられる。
内容を元に反省を行うということはすなわち、結果に関わらず、勝ち試合にも負け試合にも反省点は存在するという事になるので、対戦後は常に振り返りを行いたいところだ。
「負けをきっかけに反省をする」という意識から「常に反省をする」意識への転換が重要になりそうである。
練習段階では、相手に対する目先の勝ち負けでは無く、相手に対して一定以上の勝率を出すという事を目標に取り組む事が大事そうだ。
反省点を間違えない為に

しかしながら、
100点のプレイングで負けた、正しい負け、
20点のプレイングでも運で勝てた、誤った勝ち
これらを主観で正確に判断して反省を行うのはなかなか難しい
ネット麻雀のように、対戦の流れが牌譜として残ってそれを研究できると良いのだが、ポケカというアナログゲームではなかなか難しい。
PTCGLでより細かいログが見えるようになるととても有難いのだが、実装の予定は無さそうだ。
ポケカyoutuberのように、練習を動画に残して、振り返りを行えると一番良いのだが、場所や機材の問題もあり、なかなか現実的ではない。
となると、やはり複数人で練習を行い、第三者視点も含めて検討をするのが正しい反省を行う上では最適解になりそうだ。
まとめ

これまでの内容をまとめる。
不完全情報ゲームで運の影響を受けるポケカの反省においては、勝ち負けの結果よりも、内容を元に反省を行うべきと考えられる。
「負けをきっかけに反省をする」という意識から「常に反省をする」意識への転換が重要。
負けが混むと不安になり、負けに理由を求めたくなるが、安心を得る為の安易な反省は上達に繋がらない。
勝ち負けに関わらず、冷静に試合を見返し、内容の問題点を洗い出す事が重要。
場合によっては負け試合で反省点が無い事もある。
また勝ち試合こそ素直に反省ができる良い機会と捉えたい。
内容の良し悪しを主観のみで正しく判断するのは難しいので、複数人での練習を行い、第三者視点からの意見も参考にする事が望ましい。
尚、本noteでは、プレイング、構築、環境読み、このどれを反省するのか、どの様に問題点を見分けるのかという大事な点に言及していない。
理由は、筆者の経験が浅く、ここを語れるだけの知識も技量も不足しているからである。
今後の課題である。
さいごに

遅くなりましたが、私ぺいこーと申します。
通常の口調に戻します。
これをまとめてみようと思ったのは、最近負けが混み、その度に握るデッキを変えてみたり、デッキのパーツを変えてみたりとあまり合理的ではない対応をしていた自分への戒めからです。
最近栃木から東京(秋葉原近辺)に引っ越してきて、これまでの仲間と離れた為、練習はなかなか行えず、ジムバトルにでて対戦を繰り返しているという状況でした。
今、改めて栃木で練習してくれていた仲間の存在が有り難かったなと身に沁みています。
これから、都内の練習会など積極的に参加していきたいなと思っております。高い熱量で練習取り組みますので、もし機会がありましたら何卒よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
