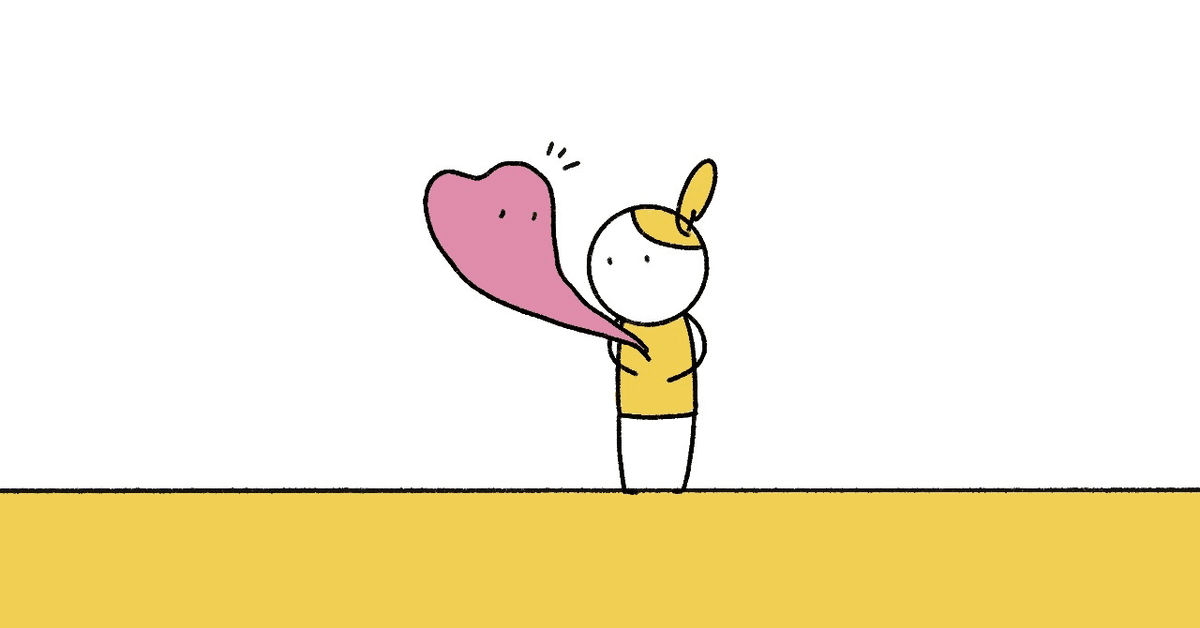
施工業者の限界 言ってもできない対策
はい、施工管理見習いのしゅんです。
現場監督をしていて業者に指示・施工をお願いする中で起きる現象、それは指示してもちゃんとできない、やりきれない、理解ができない、業者の見積りはヒアリングでは相手の会社の技量は計りきれないことはある。出来ないことが悪いのではなく、それが彼らの限界であることも見ればわかる。
今回はそんな業者との対面した時のポイントについて書いてまいりたいと思います。
ポイント3
⬜︎技量不足、理解不足、なにが不足か見極める
⬜︎上流で会社の仕組み、やり方をヒアリング
⬜︎次に活かすため、未来の選択をかえる
⬜︎技量不足、理解不足、なにが不足か見極める
結果 業者の何が不足しているかを決めること
会社の技量、職長の技量、作業員技量
管理仕方、言葉の意味がわかっていないのか
まず、監督として出来る許容できる管理の改善
1施工計画見直し、施工資料の作成
1施工前の手順説明、職長打合せ
1現場施工時、ポイントチェック
2施工全数チェック
3隣に寄り添い常に指示・確認
まずは数字の小さいものからやってみる
そして、品質の出来型実績に伴い数字を上げた管理を行う、3番に関してはやばいレベルです。
今回の業者は3番を行っても、隣で違うよと言いながら修正していくらクオリティでした。
職長は理解できていても、作業員の大多数が理解、出来ていない真実。
そして、頑張っているのに出来ないという現象。
作業員レベルの問題として、下請け会社に相談することに決定しました。
⬜︎上流で会社の仕組み、やり方をヒアリング
結果 作業員は作業員であるから1次請の会社と改善・問題を解決するための仕組みを話し合う
▶︎施工業者を変える
▶︎やり方を調整する
職長と番頭さん自体が出来ても、結果現場の品質が保たれないのであればそれはゼネコンの指導にも限界がある。
一生懸命でもこえれられないものは一定存在する。その作業員さん達が悪いんけでわない、舞台が、違うだけであり、能力にあった適材適所な配置を行えば良いだけ。
今の施工の課題を達成できる技量の人間への配置が必要。
⬜︎次に活かすため、未来の選択をかえる
結果 自分で業者を決める。
▶︎一緒に乗り越えて成長できる関係となる
▶︎プロである前提上、2度その業者を使わない
▶︎選べる立場でなくても会社に業者の質は言える
現状の自分の与えられた環境(業者)を変えることは簡単でわないので、ちゃんと一次請業者と素直に話合うこと。
咎めるわけでなく、みんなで良いものを作る方法を模索検討すること。
誰でも最初はプロでわない、経験を通してプロになる循環がある、そのためにも技量にともなうリスクを想定・許容して良い方向進む方向をちゃんと話合うことが重要。
よし、明日も頑張るぞー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
