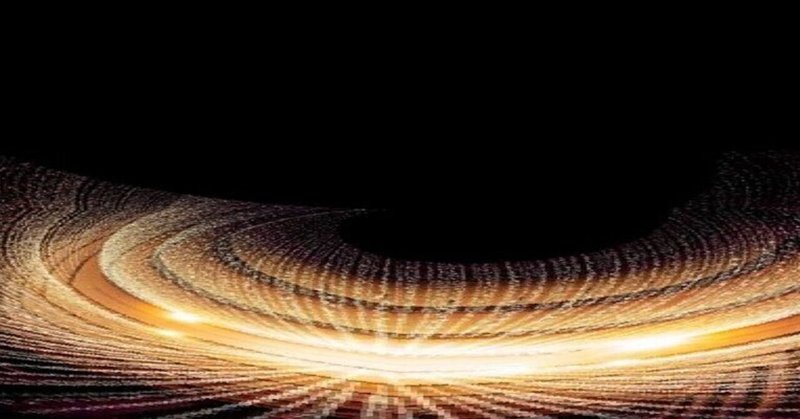
ロッホローモンドの畔で
杜紀夫はジャケットの内ポケットから取り出した鍵を右手に軽く握り、ドアをノックした。勿論、ドアの横にいわゆるドアチャイムのボタンはある。それでも彼は、白い手袋を着けたその手で、静かにドアを叩いた。
愛用のサコッシュを斜め掛けしてその横に立っている刀記は、不思議そうに彼の様子を眺めていた。杜紀夫はその視線を感じつつ、一瞥をくれることもなく「失礼します」と声を発し、それとほぼ同時に、握っていた鍵を挿して捻った。見かけに反するほど重量感のある解錠音がして、そのドアは開いた。刀記は、杜紀夫が室内に足を踏み入れたのを確認してから、後ろに続いた。自分も「お邪魔します」と、小声で言った。誰も居ないのはわかっているのにと、おかしくてちょっと笑った。
最上階のセミスイート。別の建物にある刀記の部屋とは内装の格がまるで違うし、こちらのほうが広く見える。但し、壁一面にほぼびっしり本が並んだ本棚。本棚の谷間には、レコードプレーヤーとステレオセット。片隅にはミニバーもあり、お約束のビーフィーター等が並んでいる。その手前には45度の角度で外窓に向けて配置された机。と、その上で異様な存在感を保っているのが、件のパソコン。恐らくはデータ消去処理も実施済みで、今は電源を入れてもOSが立ち上がるだけの状態だと聞いている。刀記は自分の主治医でもある杜紀夫に頼まれて、その中身を調べに来たのだった。机の方にまっすぐ向かった彼の動きを左目で追いながら、刀記が部屋の中にもう一歩踏み込んだその時、再び、ガチャリという無骨な音を立てて、背後のドアが閉じた。
弾かれたように振り向いた杜紀夫が左手を口元に遣り、何かまずいことを思い出したような顔をしていた。
「何? どしたの?」
明らかに動揺しているのが一目瞭然で、刀記は完全に笑顔になっていた。いつもほぼ完璧なポーカーフェイスのこの男が、こんな表情を見せることがあるのかと。
【つづく】
