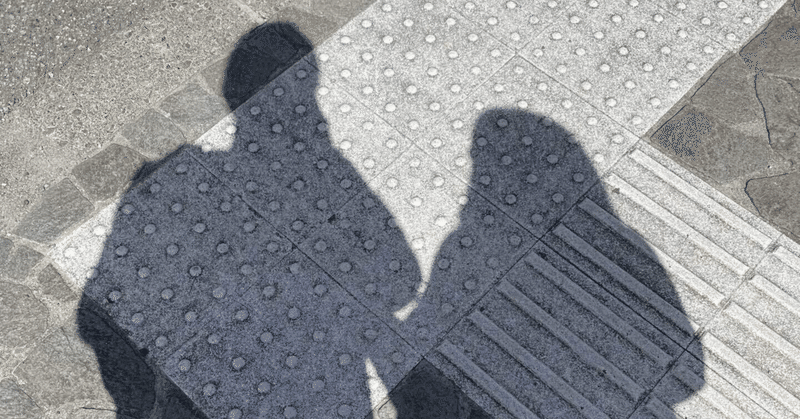
たとえば愛【ジャンププラス原作大賞応募作品】
たとえば愛とは、何だと思いますか?
こんな話がある。
あるえらい菩薩様が、ひとりの目の見えない男に会った。男は「何とかして目が見えるようになりたい」と言った。菩薩様は男の願いを叶えるため、自分の目玉をやることにした。それはそれは地獄のような苦しみに耐え、菩薩様は目玉を取り出した。
するとそれを見た男は「何だこんな汚いもの」と言い、目玉を捨ててしまった。菩薩様は怒りを覚えたという。
この話は、大学の授業で先生が話してくれた。あの修行を積んだ菩薩でさえ、怒りを覚えることがある。そんな話だったと思う。
そんなことをふと思い出したのは、彼と一緒にいるときだった。
私の名前は、山名由香。隣にいるのは彼氏の、北村宗介。
私は彼の左腕を、自分の右腕にからませて歩いている。恋人同士だけど、それだけが理由じゃない。歩いてきた子供たちに、彼がぶつかる。
「大丈夫?」
「平気」
彼が笑った。よかった。彼が笑うと、私も嬉しい。
「あ、20メートルくらい先、右側に自転車が並んで停めてあるから、気を付けてね」
「OK」
彼は右手に持った白杖を少し上げた。私の彼は、目が見えない。
出会ったのは大学生のときだ。横断歩道の真ん中で、白杖を持ちながらウロウロしてる彼を見かけた。
(あの人、大丈夫かな…。あ、信号がチカチカいってる。あ、あ~、赤になっちゃった。)
あの人はまだ、横断歩道の途中に立ち尽くしてる。他の誰も助けに入る気配はない。
気がついたら、私は飛び出していた。彼の手をつかむ。彼がビクッと手をこわばらせた。
「あ…」
「こっちです!」
手を引っ張って、反対側の道に渡らせた。
「ここで大丈夫です」
「ありがとうございました…」
彼は、軽く会釈した。
「あの…よかったら、お礼にお茶でもおごらせてください」
数分後、私たちは近くのコーヒーショップにいた。同じ大学に通ってることもあって、話ははずんだ。
それから、会うたびに仲良くなっていった。二人で色んな場所に行った。宗介は一人だったら行くのを躊躇してた場所に、私と一緒に行った。私も自分のお気に入りの場所、気になってた場所に宗介を連れて行った。
視覚障害者についての勉強もたくさんした。最初、私が歩行の誘導をしても邪魔になってて、むしろ一人で歩く方がずっと早かった。だけど慣れてくると、二人で一緒でもスムーズに移動できるようになった。
ときどき喧嘩もした。きっかけは、ささいなことだった。
宗介が部屋に遊びに来た朝、私は寝坊して会社に遅刻しそうだった。あわてて支度をする。
「ごめんね。朝ご飯適当に食べて」
「ねえ。ジュース買いに行きたいからさ、出るとき一緒に行って」
(家から一番近い自販機、駅と反対の方角なんだよな~。)
「何度も行ってるから、一人で行けるでしょ?」
「…一人じゃ買えないだろ」
「…あ、そうか」
宗介が舌打ちした。
「たく、そういうトコあるよな」
「そんな怒んなくたっていいじゃん。ほら、一緒に行くから」
「もういいよ」
その夜、帰ると宗介はいなかった。ドッと疲れが出てカバンを置くと、ため息をついた。
「突然失礼いたします」
振り向くと、背の高いダークスーツ姿の男性が部屋の中に立っていた。思わず足の力が抜ける。
「だ、誰!?」
「驚かせてしまって申し訳ありません。実は私…」
すると男性の背中から、こうもりのように真っ黒の巨大な羽が広がっていった。
「悪魔なんです」
悪魔と名乗る男性は、閉じた窓を抜けて外に出て戻ってきた。
「信じていただけましたか?」
私は頭の中が真っ白になっていった…。
「……おい、由香。しっかりしろよ!」
目を覚ますと、目の前に宗介がいた。
「どうしたんだよ、来たら倒れてるし」
ぼんやりした意識の中、さっきの出来事を思い起こす。
「…そうか。夢だったんだよね」
よかった。
「いいえ、夢ではありませんよ」
宗介の後ろに、にやけたあの男の顔が現れた。
「ギャー!!!!」
数分後。私と宗介は並んでダイニングの椅子に座っている。向かいには、悪魔が鎮座していた。宗介が口を開く。
「…え? つまり、今俺の前にいるのは人間じゃなくて、悪魔?」
「はい、そうです」
「その悪魔が、何の用?」
宗介、よく冷静に話ができるな。見えてない分、怖さも薄れるのか…?
悪魔はテーブルの上に頬杖をついた。
「単刀直入に申し上げます。宗介さん、あなたは目が見えるようになりたくありませんか?」
「…いや、そりゃまあ」
宗介の視力は、現代の医学でも回復の見込みがほぼないそうだ。
「私なら、見えるようにして差し上げますよ」
「マジですか!?」
「もちろんお金だの魂だの、その他一切の品物はいただきません」
「宗介、信じちゃダメだって」
だけど宗介は、前のめりになっていた。
「本当に、見えるようになるんですか?」
「はい、方法がひとつだけ」
そう言うと、悪魔は長い指を立てて私に向けた。
「由香さん、あなたの視力を宗介さんにあげることです」
「え?」
「私なら、由香さんの視力を宗介さんに一瞬で移すことができます」
「でも、そうしたら由香の視力は…」
「もちろん、なくなります」
「そんなことできるか!」
宗介が声を荒げる。
「嫌なら、無理にとは言いません。気が変わりましたらこちらにご連絡を」
悪魔は、なぜかスマホの連絡先を記した名刺を置くと、窓から抜けて飛び去っていった。
「…何だったんだろうね、今の」
「何にしろ、とんでもない奴だ。俺の目が見えるようになる代わりに、由香の目が見えなくなるなんて…」
そう言った宗介の顔は怒りに震えていた。私はその顔をじっと見ていた。
数日後。私は病院の廊下を走っていた。白い壁と天井に、靴音が反響する。
「宗介!!」
病室に入ると、宗介はベッドの上に体を起こしていた。その上半身を思わず抱きしめる。
「よかった、生きてて…」
「おい、大げさだって。軽い打撲と捻挫なんだから」
「…だって」
宗介が駅のホームから落ちたと連絡をもらったのは、会社に着いた頃だった。家族でもない人間の怪我で早退する訳にもいかず、お昼休みの時間に駆け付けた。宗介は出勤する途中の駅で、転落したらしい。
視覚障害者のホームからの転落事故が多いことは私も知ってる。命を落とす人も少なくない。だけど、実感が湧いたのは今日が初めてだ。
「宗介を失うのが怖い」
初めて本気でそう思った。
「生きててよかった…」
そうつぶやくと、涙があふれてきた。私は看護師さんがいるのも構わず、また宗介に抱きついて泣いた。
退院して、宗介が私の家に来た。二人でココアを飲んでいるとき、私は言った。
「…ねえ、結婚しない?」
「え? どうしたの、急に?」
「今回みたいなことがあったとき、家族じゃないと色々面倒でしょ?」
「まあ…」
「それから…」
私はココアから顔を上げ、宗介の方を真っすぐ見た。湯気の向こうに愛しい人の顔が見える。
「…私、宗介に視力をあげる。宗介の目を見えるようにしてあげる!」
その週末。スマホの番号に連絡すると、悪魔はすぐに来た。
「もう一度尋ねますが、本当によろしいんですか?」
私は頷いた。
「お願いします」
「では…」
悪魔は私の顔の前に手をかざした。いざとなると怖くて、目を閉じ宗介の手を握った。
そのとき、私の頭の中に、昨日の夜ベランダで見た光景が蘇ってきた。
明日は視力を渡す日だというその夜。夜空の景色を目に焼き付けたかった。私がベランダで星を見てると、宗介も出てきた。
「なんか、星ってこんなに綺麗だったんだ…。これで最後だと思うと愛おしいなあ…」
私は、自然と泣いていた。宗介が私の肩に手を置いた。
「やめてもいいんだよ」
私は首を振る。
「宗介に、この景色を見せてあげたい」
宗介は「ありがとう」とお礼を言って、私を抱き寄せた。
気がついたら、私の目は開かなくなっていた。
「…宗介?」
「由香」
隣から宗介の声だけが聞こえる。
「お前、こんな顔だったんだな」
自分の顔がほころんでいくのがわかった。
「宗介、見えるようになったんだね!」
「ああ!」
私たちは抱き合って喜んだ。悪魔は役目を終えると、すぐに帰って行った。
私は既に会社を辞めていた。宗介は見えるようになったため、もっと稼ぎのいい会社に転職した。歩くときの誘導など、私が今まで宗介にしてきたことを、今度は彼がやってくれることになった。
そして私たちは、二人だけで結婚式を挙げた。
今までと何も変わらない。幸せだった。
だけど、前と違ったこともある。喧嘩をしなくなったことだ。いや、喧嘩しないというか…。
「ねえ、下の自販機に一緒に買いに行ってほしいんだけど…」
「ああ」
上の空の返事。こういうときは大抵、スマホをいじってる。
「ねえってば」
「…ちょっと待って、もしもし?」
宗介は隣の部屋に行った。
最近お互いの距離が、喧嘩するほど近くはなくなった気がする。私は、彼が話すかすかな声をぼんやりと聞いていた。
ある日、宗介がお風呂に入っていた。私がタオルを置きに脱衣所に行くと、スマホのバイブの音がした。何となく気になって、手に取ってみる。記憶をたよりにどうにか通話ボタンを押し、耳に当てた。
「あ、宗介?」
若そうな女の声だ。しかも、下の名前で呼んでる。
「今度の土曜日だけどさ、待ち合わせ場所どこにする?」
「…もしもし」
「あっ」という声が聞こえて、電話が切れた。今度の土曜日…。宗介は仕事だと言っていた。
もう間違いない。私は、呼吸が荒くなってくるのを感じた。全身の血がてんでバラバラに動いて、体が燃え立ってるみたいだった…。
宗介は、駅のホームに立っていた。隣には、腕を組む露出の多い服の女性。もう白杖がなくとも、落ちる心配はない。
電車がホームに入ってきた。そのとき、彼に近づいた手が背中を押した。彼の体はバランスを崩し、線路の方に飛び出していった。
「え?」
電車がすぐそこまで迫ってきた……。
私は、白い壁と天井に囲まれた廊下を歩いていた。この前と違い、急ぐ必要などない。看護師に案内され、ある部屋へと入った。
電動車椅子が動いて、近づいてくる音がした。
「目の前にいらっしゃいますよ」
私は、涙があふれるのを止められなかった。
「…お父さん!」
体をかがめて、お父さんの膝の上に両手を置く。
「…由香なのか?」
なつかしい声がする。私はお父さんにすがって泣いた。
両親は、私が小学生のとき離婚した。女手ひとつで育ててくれた母も数年前に亡くなった。二人きりで結婚式を挙げたのは、私に親がいなかったからだ。
その父が最近、介護施設に入っていると知った。父は進行性の病気を患っていた。だんだん体が硬直してきて、やがて呼吸もできなくなるという。
「ごめんね。せっかくお父さんに会えたのに、私、目が見えなくなっちゃった…」
「いいんだ。会いに来てくれてありがとう…」
父が涙声で、私を抱きしめてくれる。
そのときだ。突然、目の前に光が飛び込んできた。
「え!!?」
私の目は、開いていた。
「どういうこと…?」
「確かに願いを叶えました」
背後から声がして振り向くと、悪魔が立っていた。悪魔はすぐに窓を通り抜け、どこかへ飛び去っていった。
「まさか…」
お父さんの顔を見ると、記憶と違ってやせ衰えた顔の、その両目が閉じられていた。
「お父さん、そんな…」
「俺はもうすぐ死ぬ…。由香に、父親らしいことを何もしてやれなかった。だから…」
閉じた両目から、一筋の涙が流れる。
「お父さん…私の顔を、もっとよく見てよ。せっかく会えたのに…お父さん!!」
私たちはお互いの体を暖め合うように、長い間抱き合っていた。
線路に転落した宗介は、誰かが非常ボタンを押したおかげで、間一髪で助かった。ホームでは、意味不明のことを叫ぶ男性が駅員に連行されていった。
数日後。私は海に向かって立っていた。その横に、宗介が来る。
しばらくの間、沈黙が流れる。宗介が口を開いた。
「…ごめん。俺、二回ホームから落ちて、二回ともお前の顔が浮かんだんだ。だから」
「許さない! あなたのことは一生許さない!」
宗介が目を伏せる。
「…だけど、ここにこうしていたいから、いる」
宗介が私を見た後、海の方を向いた。私と同じ方角を見ている。
「こうして、一緒に海を見ていたいから…」
二人で海の方を見つめる私たちを、波の音だけがいつまでも包んでいた。
たとえば愛とは、何だと思いますか?
『星の王子さま』の作者、サン=テグジュペリはこう言った。
愛はお互いを見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
