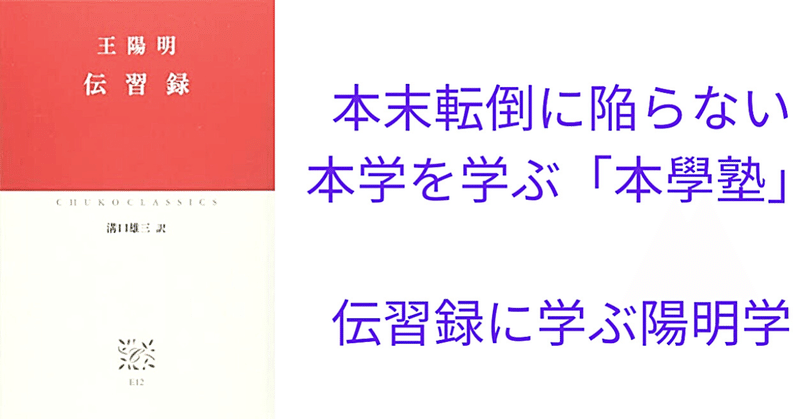
知行合一 〜知ってるとやってるは一体なのか?〜
本末転倒と言うことわざの意味は、学びには本学と末学があり、人のあり方、真理に基づいた考え方を学ぶ本学を置き去りにして、やり方、手段ばかりを学び行使することを指しています。私が20年近く学び、実践し続けてきた原理原則系マーケティング(外部環境に左右されない独自の市場の構築)の極意は「あり方に始まり、あり方に終わる。」でした。結局、長年掛けて学び取ったのは本学を収めることで経済性も兼ね備えられるようになるとの結論です。私が所属している、本業で社会課題の解決を目指す経営者の集まり、経営実践研究会でアドバイザーの小山邦彦先生からその本学を学ぶ本學塾なる勉強会があり、この度、陽明学を学び直す機会を頂きました。自分自身への備忘録を兼ねて、全6回の講義での気づきをここにまとめておきたいと思います。
革命の学問
この度、第2回目の講義が行われ、陽明学の中でも最も有名な概念の1つである知行合一についての解説とそれを踏まえて自分の中で咀嚼する時間を持ちました。王陽明は明の時代に活躍した中国の武人であり官僚であり、思想家です。王陽明の思想は革命の学問とも呼ばれ、大塩平八郎の乱、明治維新で多大な活躍をした吉田松陰先生とその門下生、上杉鷹山の経済学を幕末に実践し斬新な改革を断行して藩の財政を立て直したとする松山藩の山田方谷、その弟子でもうすぐ映画が封切りされる「峠」の主人公で最後のサムライと呼ばれた河井継之介など、世を憂い、行動を起こした先達たちがこぞって学んだ学問です。それらの先達の共通点は圧倒的な実行力であり、学んだことの実践です。学ぶ事に価値なし、行動を起こし、それを継続出来てこそ学びに価値が生まれるのは自明の理ではありますが、知っている事と出来ていることの間には大きく高い壁があり、伝習録の初めに知行合一が語られている事からもその重要性が垣間見れると感じました。
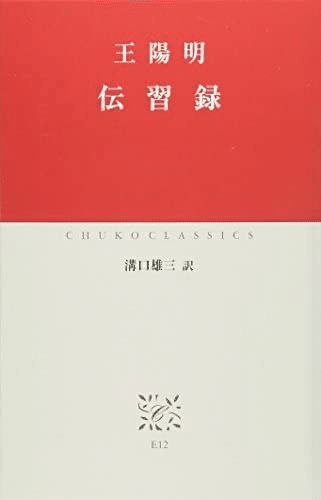
王陽明「伝習録」

私欲と本体
小山先生がご用意下さった書き下し文を読むと、徐愛の問いは知ってる事とやってることが違う人があまりにも多いのは知と行は別のものでは無いか、との誰しもが感じる当たり前の疑問です。それに対して王陽明は知と行が分断されるのは私欲があるからで、出来ていない事の本質は知らないから、聖賢の教えは本来合一されている本体に戻るべきだと示している。と応えています。この王陽明の言葉の中で注目すべきは知行を分断する「私欲」そして「本体」と「本体にかえる」ことの意味です。小山先生の解説では近景、中景、遠景と視座を変えてこれらの説明をされて、徐愛の問いは近景で、もう少し視座を広げると以下のように分断の本質が炙り出されると示されました。更に遠景として視座を高め、広げると誰もが持っている(知っている)良心が知であり、それを思った時点で既に行になっているとの難解な解釈を示されました。
中景
・そもそも表裏の関係にあるものは分けられない。
・分けてはいけないことが分かれて見えてしまうのは、己の心が私欲に覆われているからだ。
・私欲を去ることが工夫(修行)の要諦である。
遠景
・思考(アタマで思うこと)すら既に「行」である。
・「知」とは「良知(心の本体)」のことである。
・良知とは~「私」を包含する万物一体の仁、境地。
・良知を実践すること(致良知)が「知行合一私欲を良知が凌駕
私欲を良知で凌駕すべし
以上の問いに対して私が自分の中で咀嚼し感じたたのは、人が誰しも良知を持っているのと同じ様に私欲も持っていて、それは生半可な修行で消すことなど不可能であり、受け入れるしかないとの諦めというか受け入れです。そんな聖人君主はこの現代社会にほぼいないとの現実を正面から見つつ、ただ、言行一致にしたいとの願望や生まれながらに持っている良知に従って生きたいと思うことも皆が考えることで、そもそも私欲と良知が一体になって人の中に存在するのだとの気づきでした。吉田松陰先生が辞世の句で「やむにやまれぬやまとだましい」と読まれたのは私欲を良知が凌駕したことを端的に表していると思いますし、私が事業の収益よりも職人の育成や業界では異端とされる社会保障の付加を行ってきたのも程度の違いはあれども私欲と良知のせめぎ合いの結果です。私は学校に通っていない無学な経営者ですが、学ぶにつれ、知るにつれ、少しずつ私欲よりも良知を発現する意味や意義を理解するようになりました。本体とは自分自身の魂のことであるならば、知行合一は常にあるが、低レベルから良知に至ると言われる高いレベルまで人によって様々なのだと理解しました。
良知に至るには実践しか無い
知行合一、知っていることと行っていること、その一体化は決して難しい訳ではなく、そもそも表裏一体である。ただ、私欲にまみれていては本体事自体に大した価値が無いままになる。そんな意味も意義も無い人生を送るのはどう考えても勿体無いと思うし、一回きりのぶっつけ本番の人生の時間を使うなら、良知に従って気持ちよく生きたいと改めて感じました。たとえ少しずつでも段階を踏んで致良知を目指したいと思います。そして、どちらかと言うと物事を分け隔てて考える思考の方が本体を毀損することに繋がるし、分断が世界を悪くしているのも自明。徐愛が疑問を呈したように、知っていることとやっている事が違うのは見え方とレベルの問題なのだとひとまずは受け取って、今後はこれまで以上に良知を躊躇なく発現できる様に心を整え、身体を整え、状態を整えることに注力したいと思います。実践しか良知に至る道は無し。今回も素晴らしい学びの機会に心から感謝します。
______________
小山先生が登壇されるシンポジュウムの翌日のフォーラムでは私も少しだけ話します。チケット申し込みはこちら
→https://www.shokunin-kigyoujyuku.com/application/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
