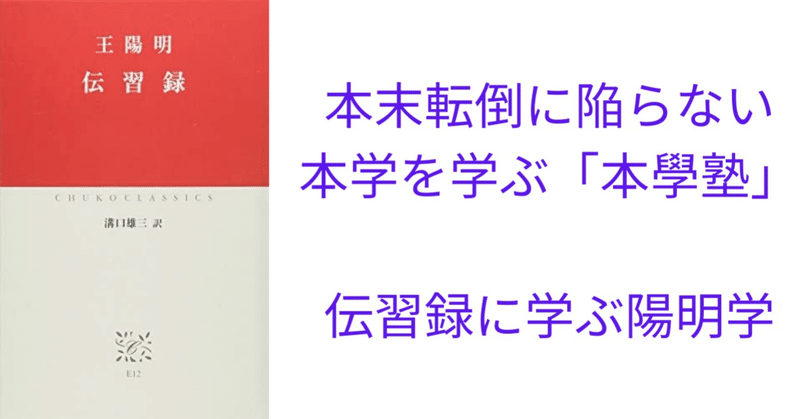
立志 〜志を以て万事の源と為す〜
本末転倒と言うことわざの意味は、学びには本学と末学があり、人のあり方、真理に基づいた考え方を学ぶ本学を置き去りにして、やり方、手段を学ぶ末学ばかりを行使することを指しています。私が20年近く学び、実践し続けてきた原理原則系マーケティング(外部環境に左右されない独自の市場の構築)の極意は「あり方に始まり、あり方に終わる。」でした。結局、長年掛けて学び取ったのは事業は本学を収めることで経済性も持続可能性も兼ね備えられるようになるとの結論です。私が所属している本業で社会課題の解決を目指す経営者の集まり、経営実践研究会でアドバイザーの小山邦彦先生からその本学を学ぶ本學塾なる勉強会が催され、この度、陽明学を学び直す機会を頂きました。自分自身への備忘録を兼ねて、全6回の講義での学びと気づきをここにまとめておきたいと思います。
志を剛く持て。との呪い
今回は第3回目、陽明学の中でも最重要と位置づけされている概念「立志」です。私はこの世に生を受けた際、名前に剛い志、英語に直訳するとstrong purposeとなる「剛志」と名付けられました。名前は(良くも悪くも)人生の呪いであるというのが私の持論の一つにあるのですが、まさしく私は物心がつき始めた15歳頃から「俺は何者で、何をするために生まれてきたのか?」との問いを持つようになり、アイデンティティーを探す長い旅を彷徨いました。その時はそれほど意識していなかったかもですが、今振り返ると完全に志を立てる、その志を全うする人生に執着していたように思います。なので、目的を明確に持てないまま惰性で入学した高校に通い続けることはどうしてもできなくて、17歳で高校を早々と中退して社会に飛び出したのもそんな流れからだったと違和感なく思います。ま、学校を辞めると言っても誰にも止められなかったので、周囲から見てもごく自然な行動だったのかも知れません。

自分のことで精一杯・・・
17歳で社会に出てから随分と紆余曲折ありました。正直、ロクでもない人生を歩んでおりましたが、幸運なことに何度か人生を立て直すご縁と機会に恵まれました。結局、辿り着いたのが25歳と少し遅まきながらの大工という職業でした。もちろん、学歴マイノリティーの私に職業選択の自由は非常に限られていたので、表面的には自ら望んで大工の修行に入ったのですが、本当は半ば消去法での選択でした。その時点で私に志が有ったかというと、恥ずかしながら実際のところ全くありませんでした。とにかく、当時は自分と弟子の家族を食わせることで精一杯、なんとか今を凌ぐのが精一杯で自分達の事しか考える余裕も思考もありませんでした。そんな私が志を立てたのは大工としての起業が一応、なんとか落ち着き出して、法人化した頃のことです。それは大工の待遇や身分に対して大きな憤りを感じて、事業を通じてその不条理を解消したい、職人の社会的地位の向上を果たすと誓ったのでした。
志の源となる原体験
その頃はまだ若さと勢いに任せて目の前にある仕事は全て取りに行き、いつ暇になっても良い様に少しでも蓄えを貯めようと必死になっていた時分でした。ひどい時はひと月に35日働くこと(数日間、昼夜とも突貫で働いていた)までありました。そんな時、起業前からついて来てくれていた苦楽を共にした弟子が辞めたいと申し出てきのです。「やっと少し安定した売り上げができて来た時やのに何故?」と質すと、彼は「銭金では無いんです、このままの暮らしでは家族がバラバラになってしまうんです。」と目に涙を浮かべながら訴えられました。その時、職人が将来に不安を持たずに働ける環境を整えないとならん。このままでは職人は絶滅してしまう。と強い憤りと不条理を感じたのです。それが私が志を立てた原体験です。それから20数年間、様々な事業に取り組み、現在も3つの法人の代表を務めておりますが、全ては職人の地位向上を果たす、との志の実現の為に衝き動かされるように走り続けて来ました。

立志とは念々に天理(良知)を存すること。
今回の本學塾でのテーマである立志は私がこの30年間、頑なに守り続けてきた想いをいわば答え合わせするような時間でした。以下に王陽明の伝習録の原文と書き下し文を引用、転載します。


伝習録によると、志を立てるということと、目的や目標を設定するのと大きく違うのは天理を存するところであり、講師の小山先生は天理とは良知と同じものであると解説されました。私は、天理とは宇宙にある法則とか、自然の摂理といった人の外にある「大いなるもの」との解釈をしており、誰しもが生まれながらに持っている良知とは存在する場所もスケールも違っており、内なる想い(良知)が天にある大いなるものと同じ軸に1本に通った時に志が立つのだと思っていました。そんな疑問を小山先生に確認したところ、良知の定義は非常に広く、人が持つ良心だけに止まらず宇宙の摂理までを含むと教えられ、なるほど、そういうことかと腹にストンと落ちました。

狂うとは真摯に一途に生きること
もう一つの気づきは、志を立てることと時間軸は切り離せないと言うことです。志は一瞬にして立つものではなく、片時も忘れることなく想い続けることで固まるとは要するに実践の積み重ねであり、継続することで練られて固まり世の中を変える、もしくは少しでも世の中を良くするような大きな影響力を発するようになる。その源こそ志を立てることであり一生を賭けて行うべきことなのだと理解することができました。そして、その入り口こそ私は何者か?何のためにこの世に生を受けたのか?との根源的な問いに向き合うことであり、内から湧き出る感謝や憤り、悲しみや愛情が形となって天理(良知)と繋がることで立志となるのだと整理することができました。
吉田松陰先生が「かくすれば かくなるものと しりながら やむにやまれぬ やまとだましい」との句を遺して処刑されましたが、それは天理(良知)に誠実に向き合い、真理に触れたからこそ引き下がることも曲げることも出来なかったのだと思います。その純粋さこそ共感を生み、明治維新で日本を変える原動力になったのだと改めて感じると共に、
「狂愚まことに愛すべし 才良まことに恐るべし、諸君、狂いたまえ」
との松陰先生の言葉を心に刻み、誠実に真摯に狂おうと思った次第です。志に生きて、志に死ぬ覚悟を今一度固めたいと思いました。素晴らしい機会を頂けた事に心から感謝致します。
_____________
志を明らかにして、貢献と収益の両立を図る研修を行っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
