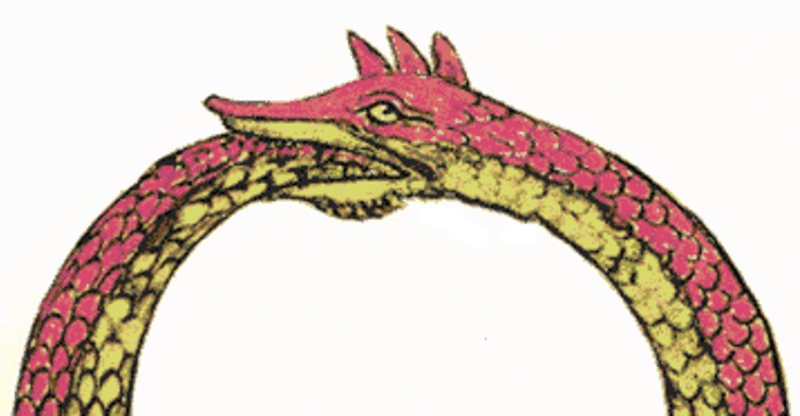
連載小説|ウロボロスの種
▲ 前回
一日目
私は港にいた。
一人の漁師が、濡れてもつれた網を解きほぐしていた。
「網は結ぶことによってこしらえられるのではない。ほどくことによってこしらえられるのだ」
そう漁師は言った。
私は悟った。言葉は紡がれるのではない。ほどかれるのだ。ほどかれることによって、言葉は網となり、広がり、書物となる。
漁師は嘆かわしそうに言った。
「この港町も昔は、ほどかれた網のようだった。街路と街路がもつれることなく、広げられた網のようだった。それが今はもつれにもつれ、大きな結び目までできてしまっている」
「どうしてそうなってしまったのですか」
「人が迷わないですむよう、わざとそうしたのだよ。それがかえって人を迷わせることになるとも知らずに」
私は港町を歩いた。
すれちがう人はみな、しかめ顔をしていた。まるで顔に結び目があるかのようだった。
私は立派なバロック様式の大聖堂を見つけ、その中へ入っていった。
壮麗な大聖堂に、パイプオルガンの音色が響き渡っていた。私はその中をゆっくりと歩いて回った。礼拝室にいる人が、両手を固く結び合わせていた。
私は最前列に腰をかけ、美しい装飾を眺めていた。正面を見上げたところにあるステンドグラスがとくに美しい。放射状に広がる金色の光。その中央にいる白い鳩が、こちらをめがけて飛んでいる。白い鳩を中心にして広がる金の後光。それが、鳩のこの世ならぬ白さと速さとを際立たせていた。
そのうちに、パイプオルガンの音が鳴り止んだ。オルガン弾きが立ち上がり、こちらへ歩いてくると、私の横のほうに腰をかけた。オルガン弾きは青みがかったツイードのジャケットを着ていた。
「ここにはよく来るんですか」
オルガン弾きは親しげに話しかけてきた。笑顔だが、眉間には深い皺が刻まれている。
「いいえ。この町は初めてで」
「そうでしたか。夜になったら、酒場へ行ってみるといいですよ」
「酒場ですか」
「ええ。この港町の人々が、束の間の解放感を味わう場所です」
「美しい海があるのに、酒場で束の間の解放感を味わうのですか」
「海は人を解放しません。海はくり返しです。反復です。くり返すものは本質を備えていますが、未来はありません。しかし、人間には未来があります。未来こそが人間を真に解放するのです」
オルガン弾きは話を続けた。
「種が何の種なのかは、その種が何の植物になるのかによって決まります。それと同じように、人間がはたして何であるのかは、人間が何になるのかによって決まります。つまり、人間が何であるのかは、人間の未来によって決まるのです」
「人間以外の生物に、未来はないのですか」
「生物はくり返しを続けてきました。誕生、生長、生殖のくり返しです。そのくり返しの先端に、人間はいます。ですから、生物がはたして何であるのかは、人間の未来によって決まると言ってもいいでしょう。いわば人間は、生物が実らせた種、生物が託した種なのです」
そう言うとオルガン弾きはこちらに手を伸ばし、
「私はフェデリコです」と言った。
私たちは握手を交わした。そのとき、私は自分に名乗るべき名前がないことに気がついた。
私には過去がないのだ。過去のかわりに、夢の記憶があるのだった。
フェデリコは言った。
「あなたは旅人です。旅人には役割がありません。役割は反復です。役割には未来がありません。反復から自由なあなたは、未来ある人間として、この町を見ていってください」
夜になると、私はフェデリコの勧めに従い、酒場を探して歩いた。
多くの人で賑わう酒場を見つけたが、そのすぐ横の階段に、小さな看板が灯っているのを見つけた。
〈バー・ニュクス〉
私は階段を上り、木製の重い扉を開けた。
カウンターだけの店内に、客は一人だけ。女性バーテンダーと話をしている。
私は端の席に座り、ジン・トニックを頼んだ。
すると、もう一人の客がバーテンダーに言った。
「リリィ、僕も一杯。カルヴァドスを」
リリィと呼ばれたバーテンダーは、丁寧な手つきで、ジン・トニックを作ってくれた。私の目の前に、華やかに泡立つグラスが置かれた。
「ありがとう」
次にバーテンダーのリリィは、琥珀色の液体を、小振りのグラスにゆっくりと注ぎ、もう一人の客に差し出した。そして、ボトルをグラスの隣に置いた。
ボトルの底には、林檎の実がゴロリと沈んでいる。
はて、と私は思った。林檎の実は、どうやってボトルに入ったのだろうか。
もう一人の客は、琥珀色の液体を一口飲むと、深呼吸をして、
「副交感神経が生き返るねえ」と言った。
「この町の昼間は、交感神経でできているようなもんだ。緊張しっぱなしで、重苦しいったらない」
客はバーテンダーに向かって話を続けた。交感神経が集中のシステムだとしたら、副交感神経は拡散のシステムだということ。人体にその対が備わっているように、この町もそれにあたる対を備えるべきだということ。そのための制度設計が必要だということ。
バーテンダーのリリィは、ただ微笑みながらそれを聞いていた。
私は得心しながら耳を傾けていたが、制度設計の話になった途端、違和感を覚えた。
「あのう、この町の人たちは昼間、何にそこまで集中しているのですか」
私は気になってもう一人の客に尋ねた。
もう一人の客はグラスの液体を飲み干し、
「未来ですよ」と答えた。
未来への集中。それがこの町の昼間のしかめ顔の原因だとしたら、制度設計もまた、未来のための設計ではないだろうか。未来への集中を促すものではないだろうか。
「ご旅行ですか」
私はそう訊かれたので、
「はい」と答えた。
「町はずれにブランデーの蒸留所がありますから、行ってみるといいですよ」
私は小切手で支払いを済ませた。小切手を財布から出したとき、サインをどうしたものか困った。私には過去がないのだ。
私は内ポケットのペンで、小切手に適当な文字を書き、バーテンダーに渡した。
「ありがとうございます、Ж様」
Ж。私は自分をそう名付けたようだ。
領収証と一緒に受け取った名刺には「バー・ニュクス リリィ」と書かれていた。
「またのご来店をお待ちしています」
▼ 次回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
