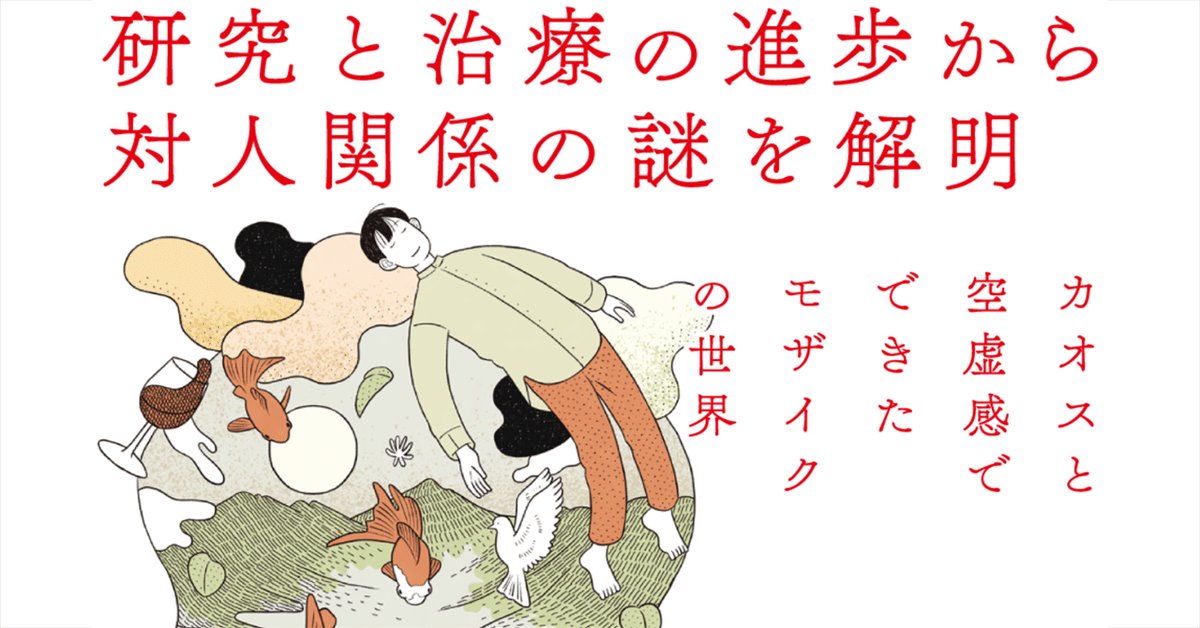
境界性パーソナリティ障害(BPD)の人たちが生きる世界
境界性パーソナリティ障害(BPD、Borderline Personality Disorder)を世に知らしめ、その実像や治療法を臨床精神科医ならではの視点で描いてアメリカでベストセラーとなった『I HATE YOU DON'T LEAVE ME』。
その第3版(2021年刊)の邦訳が、『境界性パーソナリティ障害の世界 I HATE YOU DON'T LEAVE ME』として翔泳社から6月21日(水)に発売しました。
本書はアメリカを始め日本など世界15か国で翻訳され、BPDを知るためのバイブルとも呼ばれています。メンタルヘルスの専門家はもちろん、BPD当事者やその家族の方がBPDについて理解を深めるのにふさわしい1冊です。また、当事者や関係者ではなくともBPDについて学びたい方にもおすすめです。
今回は本書から、BPDの人たちがどんな世界の中で生きているのか、BPDにどんな症状があるのかが語られた「第一章 BPDの人たちが生きる世界」の一部を抜粋します。興味のある方は、ぜひ一読してみてください。
◆著者について
ジェロルド・J ジェイ. クライスマン(Jerold J. Kreisman)
医学博士。アメリカ内外で広く講演活動を行っている著名な臨床精神科医、研究者、教育者。論文や記事を執筆し、Psychology Today 誌にブログを掲載している。著書にハル・ストラウスとの共著Sometimes I Act Crazy: Living with Borderline Personality Disorder(『BPD(境界性パーソナリティ障害)を生きる七つの物語』星和書店、2007 年)がある。アメリカ精神医学会生涯会員。
ハル・ストラウス(Hal Straus)
心理学、健康やスポーツをテーマとした7 冊の著書や共著がある。American Health、Men's Health、Ladies' Home Journal、Redbook など、学術誌や全国誌に多数の記事を掲載している。米国眼科学会の出版部門責任者を務めていたが、退任した。
◆訳者について
白川貴子(しらかわ たかこ)
翻訳家、獨協大学非常勤講師。訳書に『境界性人格障害(BPD)のすべて』(ヴォイス、2004 年)、『帝国の虜囚 日本軍捕虜収容所の現実』(みすず書房、2022 年)、『ファシズム』(みすず書房、2020 年)などがある。
◆本書の目次
第一章 BPDの人たちが生きる世界
第二章 カオスと空虚感
第三章 ボーダーライン症候群の原因
第四章 BPDを生みだす社会
第五章 SET-UPコミュニケーションを活用する
第六章 BPDの人たちに対応する
第七章 よりよい治療を求めて
第八章 精神療法のさまざまなアプローチ
第九章 薬物療法の科学と未来
第十章 疾病を理解して治癒へと向かう
補 遺 BPD診断の代替モデル
社会の中のBPDの人々
日常生活で顔を合わせるBPDの人とは、どのような人たちでしょう。
例えば、小学校以来の友人のカルロッタがそうです。ほんのささいなことで自分を裏切ったと腹をたて、これまでも本当の友人として接してもらったことなど一度もないとあなたを責めておきながら、数週間か数ヵ月がたつころには、何事もなかったようにいつもの調子で機嫌よく電話をしてきます。
それから、上司のボブ。今日はあなたの仕事ぶりを褒めちぎったかと思えば、次の日には取るに足らない小さなミスを怒鳴りつけます。打ち解けないよそよそしい態度でいるときもあれば、軽口をたたくひょうきん者になることもあります。
それに、息子のガールフレンドのアーリーン。前の週に会ったときは絵に描いたようなお嬢さまと見えたのが、次の週には今どきのギャルに変わっています。もう二度と会わないと息子に絶交宣言をしたはずが、その数時間後には戻ってきて永遠の愛を誓っているのです。
隣に住むブレットもその一人。崩壊しつつある結婚生活に向き合うことができないまま、妻の明らかな不貞を間髪を入れずに否定しますが、次の瞬間には、こんなことになったのもすべて僕のせいだと言って自分を責めています。罪の意識と自己嫌悪にとらわれつつ、「不当に」自分を非難する妻と子どもたちへの怒りを抱いて、その間をピンポン玉のように行ったり来たりしながら、必死で家庭にしがみついているのです。
ここに簡単に紹介した人々が矛盾に満ちた振る舞いをしているように見えても、驚くには値しません。このように矛盾する態度は、BPDの目印ともいえる特徴なのです。矛盾を受け入れることのできないBPDの人たちは、自分自身が不条理にとらわれた、いわば「歩くパラドックス」を体現しているといえます。BPDの人々に見られる一貫性のなさこそが、精神保健の専門家たちに、この障害に対する普遍的な診断基準を定めることを難しくしてきた大きな理由のひとつなのです。
先に挙げたような人たちに身近に心当たりがあるとしても、驚くような話ではありません。配偶者や親戚、親しい友人や同僚などにBPDの人がいることも、十分に考えられます。読者の中には、BPDについてすでに多少の知識をもっているか、自分自身にBPDの特性を見いだしている人もいるかもしれません。
BPDの罹患者数を正確に掌握することは難しく、患者がふえているのはセラピストの認識が深まってきたことの反映にすぎないと考える人たちもいますが、おおむね精神保健の専門家たちは、人口におけるBPDの割合がふえている──それも急速──と見ています。
BPDは、はたして現代の「悪疫」なのでしょうか、それとも「ボーダーライン」とは、診断のための単なる新たな命名にすぎないのでしょうか。いずれにしても、この障害はかかわりのあるさまざまな領域について、新たな心理学的枠組みを提示することになりました。この十数年の間に飛躍的にふえてきた拒食症や過食症、ADHD、薬物乱用、十代の自殺などがBPDに関係していると報告する研究も、数多く発表されてきました。
ある研究では、摂食障害で入院している人のほぼ半数がBPDを患っていることが示されています。また、薬物乱用者の半数以上がBPDをもっているという調査結果もあります。
BPDの人々には、自己破壊的な行為や自殺のそぶりがよく見られ、この症候群の診断基準のひとつになっています。自殺を試みたことのあるBPDの人は七十パーセントにものぼるのです。自殺は、BPDの人の死亡要因の八パーセントから十パーセントを占め、青年期のBPDの人にはそれよりさらに高い数字が示されています。
過去に自殺の試みや、混乱した家庭環境、支援態勢の不備などがある場合は自殺の割合がいっそう高くなりますが、抑うつや双極性障害、アルコール依存症、薬物乱用などに苦しむBPDの人は、さらに何倍にも危険性が増大します 。
医師はどのように精神疾患を診断するのか
1980年以前に発行されたDSM-IとⅡでは、精神疾患は説明的な記述によって定義されていました。しかしDSM-Ⅲ以降は、カテゴリーべつの構造化されたパラダイムに沿って定義づけられています。言い換えれば、特定の診断を示唆する複数の症状のうち、診断基準となる特定の数が満たされている場合には、その人は診断のカテゴリー条件を満たしているとみなされるのです。
1980年以降に四回にわたり改訂されたDSMでは、興味深いことに、BPDを定義する基準についてわずかな調整しか加えられていません。BPDにはこれからみていく九つの診断基準が関連づけられています。この中の五つ以上が当てはまる場合に、BPDと診断されます。
現実に、または想像の中で見捨てられることを避けようとするなりふりかまわない努力
不安定で激しい対人関係
明確な自己像や自己感覚の欠如
自分を傷つける可能性のある衝動的行動。例えば、薬物乱用や危険なセックス、万引き、無謀な運転、むちゃ食いなど
自殺企図、自殺の脅しや自傷行為の繰り返し
激しい気分の変化や、状況的なストレスに対する極端な反応
慢性的な空虚感
しばしば癇癪を起こし、不適切な状況で怒りをあらわにする
ストレスによる一過性の非現実感や妄想
ここで用いられているカテゴリー分類形式のパラダイムは、パーソナリティ障害の診断に関しては特に、精神科医の間で論争を巻き起こしました。ほかのほとんどの精神疾患とは異なり、パーソナリティ障害は一般に成人期の早期に発症し、長期間持続すると考えられています。
パーソナリティ特性には時間の経過と共に徐々にしか変化しないという、持続的な傾向があります。しかしカテゴリー形式の定義体系を取った場合、診断が非現実的なほど唐突に変更されることになり
かねません。BPDを例にとると、診断基準となっている五つの症状を示すBPDの患者は、そのうちひとつでも症状が変化すれば、理論的にはBPDとはみなされなくなるのです。そうした急転直下に陥るような治療は、パーソナリティの概念からみれば矛盾していると考えられます。
そのような理由から、一部の研究者や臨床家はDSMに「ディメンショナル」なアプローチを取り入れるよう提案しています。ディメンショナルなモデルは「BPDの程度」と呼べるものを定めるものになるでしょう。ほかの人より明らかに高いレベルで機能しているBPDの人もいるのです。
このアプローチを提唱する人たちは、BPDであるかどうかにもとづく診断ではなく、障害をスペクトルに照らし合わせて診断する考え方を提示しています。ディメンショナルなアプローチでは、研究によって一般的かつ持続的であると示された症状に応じ、診断基準の重みに違いをもたせることになるでしょう。こうした方法を使用すれば、ボーダーラインの「純粋」な原型を示すことが可能になります。
患者がそこに記載された事項にどの程度合致しているかを見るために、測定値を標準化することもできるでしょう。ディメンショナル・アプローチは日常生活を管理する能力を識別するために用いることも可能です。日常生活をうまくこなせるかどうかの指標をつくれば、どのレベルで機能しているかを測ることができるでしょう。
衝動性、新奇性の希求、報酬依存性、損害回避性、神経症的傾向といったBPDに関連づけられている諸特性の判定を併用することも考えられます。例えば神経症的な傾向については、ストレスに対する脆ぜいじゃく弱性、衝動制御の低下、不安、気分の不安定さなどを見ることができます。
ディメンショナル・アプローチを適用すれば、障害の有無を判断するだけにとどまらず、症状の変化と改善程度をより正確に評価する可能性が開けることでしょう。
二通りのアプローチがどのように異なるのかは、「ジェンダー」(性別)のとらえ方を考えてみるとよくわかります。ある人が男性であるか女性であるかを分けているのは、身体的特性、遺伝子やホルモンといった客観的な要因にもとづくカテゴリー分類型の定義です。
それに対し、男性性、女性性(男らしさ、女らしさ)と呼ばれているものは、個人や文化などの客観性に欠ける要素が反映されたディメンショナル(次元的)な概念なのです。診断基準については三通りの三次元モデルがあり、改良作業が進められています。これらは「パーソナリティ障害群の代替DSM−5モデル」(AMPD)、「国際疾病分類の第11回改訂版」(ICD−11)、「精神疾患の研究領域基準」(RDoC)と呼ばれ、巻末の補遺で詳細を解説しています。将来DSMが改訂される際には、ディメンショナルな診断法に移行するであろうと考えられます。
感情があふれ出して止められない
BPDという臨床的な名称の向こう側には、BPDの人々、その家族や友人たちの苦悩があります。BPDの人々の生き方は止まらない激情のジェットコースターのようなものですが、それは共に暮らしたり、気にかけたり、治療にかかわったりするそこに同乗する人たちにとってもまた、同じように苛立たしい、望みが見えない旅路です。
何百万人ものBPDの人たちは、誰よりも大切に思っている人たちに対しても抑制の利かない怒りをぶつけてしまいます。矛盾した感情のせいで自分のアイデンティティがばらばらになってしまい、無力感と空虚感を抱いているのです。
唐突に激しい気分の変化に襲われ、幸福感の極みから一気に絶望の谷底に突き落とされてしまいます。あるときは怒りに我を忘れていても、そのあとはけろりとしていますが、なぜ激情に駆られたりしたのか、多くの場合は本人にもわかりません。あとになって、そんな態度をとってしまう理由すら説明できない自分に自己嫌悪を募らせ、いっそう気分を滅入らせます。
BPDの人たちは、出血が止まらない血友病のように、あふれ出した感情を抑えることができません。感情の起伏を和らげるのに必要な凝固メカニズムが欠けているのです。情熱に針を突き刺し、感情をナイフで切り裂けば、BPDの繊細な「肌」から噴き出してきた感情は凝固せずに、死に至るまであふれつづけてしまいます。
満足感が持続する状態も、BPDの人たちには無縁です。絶え間なく押し寄せてくる虚しさに押しつぶされそうになって、そこから逃げ出すためにはなんでもします。そうした耐えがたい状態に陥ったときは、薬やアルコールに溺れたり、とめどなく食べつづけたり、拒食、むちゃ食い、ギャンブルや買い物狂い、無節操なセックス、自傷行為に走ったりするなど、さまざまな衝動的な自己破壊行為に向かいがちです。
「何か」を通じて自分が生きているあかしを得たいという気持ちから、多くの場合は本当に死ぬつもりのない自殺行為まで試みます。
「こんな自分の気持ちが耐えられません。自殺を思い浮かべると、そうしてみたいという誘惑に駆られてしまうんです。それしか考えられなくなるときもあります。自分を傷つけたいという気持ちが抑えられないんです。自分で自分を傷つければ、不安も苦しみも消えてくれるとでもいうように」と打ち明けるBPDの人もいます。
BPDの人々の不安の根底にあるのは、核となるアイデンティティ感覚の欠如です。自分について語ろうとするBPDの人は、彼らよりもはるかに明確に自分自身を捉えているほかのパーソナリティ障害の人たちにくらべて、混乱した、あるいは矛盾した自己像しか描くことができません。大部分が否定的な色合いをもつ曖昧な自己イメージの虚しさを埋めるため、俳優のように演じることができる「いい役」を求め、その「役柄」になりきることでアイデンティティの空洞を埋め合わせようとします。
多くの場合、周囲に合わせて外見も人格もアイデンティティも変えてしまうウディ・アレンの映画『カメレオンマン』の主人公のように、その場の状況、環境やそこにいる人たちに応じてカメレオンさながらに自分を適応させるのです。
セックスや薬物といった手段で得られる恍惚となるような体験は、BPDの人たちにとって圧倒的な魅力をもつことがあります。そのように陶酔感にひたれる状況では、自己と外界が融合する、ある種の第二の乳児期のような原世界に退行(子ども返り)することができるのです。深い孤独感や空虚感に苛まれているときには、薬やアルコールに溺れたり、一人もしくは複数のパートナーとのセックスにのめりこんだりする行為が何日間もつづくこともあります。まるで、アイデンティティを求める葛藤にそれ以上耐えられなくなると、アイデンティティを放棄してしまうか、感覚を麻痺させ、自らを痛めつけることで偽りの自分を築き上げようとしているかのように見えます。
BPDの人が育ってきた家庭環境には、アルコール依存症やうつ病、情動障害の問題などがかかわっていることが少なくありません。BPDの人の多くは、両親の不在や無関心、拒絶、愛情飢餓、常習的な虐待などの傷跡に彩られた、戦場に独りたたずむような孤独な小児期を過ごしています。
大部分の研究で、BPDの患者には心理的、身体的、性的に重度の虐待を受けた人が少なくないことがわかっています。BPDをほかの精神疾患と区別する大きな要素として、虐待、暴力の目撃、ネグレクト、両親や保護者からの不承認環境などが見られるのです。
そのような過去を背負っている患者はほかの病気にもかかりやすく、ホルモン、炎症、遺伝過程その他の神経生物学的過程で攪乱が生じやすい傾向が見られます。
小児期に逆境に耐えていた経験をもつ妊婦を対象に、その子どもたちの染色体パターンを調査した研究では、母親が過去に受けた虐待の程度が高いほど、子どものテロメアが短くなることがわかり、直接的な因果関係が認められると報告されています(テロメアとは、染色体の末端部を保護する役目をもつ構造物です)。このことは、一歳半になった子どもに目立ち始める問題行動にもかかわりがあると考えられています。
不安定な対人関係は、青年期を経て成人に達しても継続し、恋愛でも強い緊張をはらみ、総じて短期間で終わってしまいます。必死になって追いかけた相手を、手のひらを返すように追い払ってしまいます。長くつづく恋愛―それも数年というよりは、たいていは数週間か数ヵ月間ですが―の場合も、怒り、不安や刺激が渦巻くものになることがめずらしくありません。
研究によると、小児期に非道な処遇を受けた人はスキンシップに過敏に反応し、他者との間に距離を置きたがることがわかっていますが、このことにも関連している可能性が考えられます。
スプリッティング──BPDの人々のモノクロの世界
BPDの人々の世界は、子どものそれと同じように、ヒーローと悪者に二分されています。子どものような感情世界に生きるBPDの人たちは、人間のもつ矛盾や曖昧さを許容することができません。良いところと悪いところを併せもつ対象として、一貫した視点から他人を見ることができないのです。どんな場面においても、他者は「いい人」か「悪い人」のどちらかに分けられ、その中間のグレーゾーンがありません。微妙で曖昧な陰影をとらえるというのは、BPDの人にとっては大変難しいことなのです。恋人、配偶者、親やきょうだい、精神科医たちは、あるときは理想的な人と見なされ、またあるときは全面的に受け入れられない軽蔑すべき相手に変わります。
理想化された相手についに失望させられるときがくると(遅かれ早かれ、誰にでもそれはありますが)、BPDの人は自分の融通の利かない概念を根本的に再構成する必要に迫られます。それまでのアイドルを地下牢に閉じ込めてしまうか、さもなければ相手の「完全無欠」のイメージを壊さずにすむよう、自分のほうを島流しにするのです。
こうした行動は「分裂」(スプリッティング)と呼ばれる、BPDの人々にとっての基本的な防衛機制です。専門的な解説をするなら、分裂とは、自分や他者に向ける感情や考え方を肯定か否定のどちらかにはっきり区別すること、言い換えれば、肯定と否定の感情や考え方を統合する能力の欠如を意味します。たいていの人は矛盾する二通りの感情を同時に受け入れる融通性をもち合わせていますが、BPDの人の特徴は、どちらか一方の感情にとらわれていると、もう一方はまったく念頭にない状態で、二つの感情の間を行ったり来たりすることです。
スプリッティングは、不安から逃れるための脱出口のようなものと言えます。BPDの人たちは、親しい友人(仮に「ジョー」としましょう)や親族に、そのときどきに応じて異なる二人の人間を見ています。あるときは非の打ち所のない「いい人のジョー」を手放しで賛美します。欠点はまとめて「悪人のジョー」のほうに押しやられ、どこにも否定的な要素はありません。
ところがべつなときには、なんのためらいもなく「悪人のジョー」に容赦のない怒りをぶつけ、徹底してこき下ろします―そこにはもはや、美点はひとつもありません。ジョーは怒りを向けられて当然の存在に変わっているのです。
次々に襲いかかってくる矛盾した感情やイメージから身を守るため、そしてそうした感情やイメージを受け入れる不安から逃れるためのこの分裂のメカニズムは、しばしば皮肉にも、正反対の結果に結びついてしまいます。パーソナリティという布地のほつれがやがてぼろぼろにほころび、自分と他者に向けるアイデンティティがますます不安定に揺れ動くようになってくるのです。
よろしければスキやシェア、フォローをお願いします。これからもぜひ「翔泳社の福祉の本」をチェックしてください!
