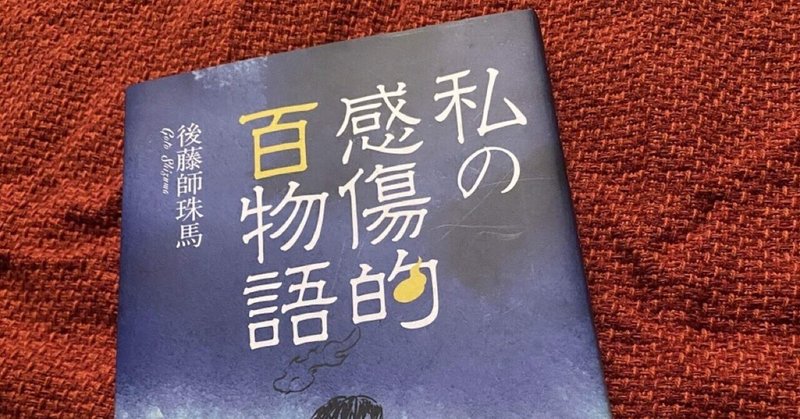
【私の感傷的百物語】第十九話 踊る骸骨
骸骨は踊ります。洋の東西を問わず、踊ります。なぜかは分かりませんが、踊るのです。
大学時代の恩師に、T先生という方がいます。先生は古代インドの仏教哲学が専門で、僕は水産学専攻の学生であるにも関わらず、その知識と人柄に惹かれ、担当されている講義にはすべて出席しました。
その中に「生と死の文化史」というテーマの講義があり、授業用テキストの冒頭には「一休骸骨」という絵が掲載されていました。骸骨が、扇子を持って踊っています。これは一休さんでお馴染みの一休宗純の法話にまつわるもので、人と骸骨、つまり生と死は同じものである、という意だといいます。また、同じ講義でペスト大流行時のヨーロッパにおいて描かれた「死の舞踏」という絵画も紹介されていました。ここでも死の具象化たる骸骨たちが、実に楽しげに踊りながら、生者を黄泉の世界へと誘っています。
「骸骨たちは踊っている」、この共通点を講義の後で先生に話してみたことがありました。先生は、
「そうだねえ、骸骨はなぜか踊るんだねえ……」
と、感慨深げに呟いていました。
他にも調べてみると、日本の民話にも、同郷の男に殺された男が骸骨となって踊り、村人(殿様の場合もある)に事件のいきさつを語るという、もの悲しい話が各地に残っています。アメリカでも、ウォルトディズニーが「骸骨の踊り」というアニメーションを制作していました(「死の舞踏」の影響が見られます)。さらにチベットにも「骸骨踊り」という、派手な骸骨が踊る行事があるといいます。探せばまだまだありそうです。
といっても、ただ単に似たような場面を寄せ集めただけであって、そこから「人類普遍の踊る骸骨の法則」などとても導き出せません。ただ、骸骨はなんだか踊りそうな気がするのです。僕もそう思いましたし、外国人にも、日本の先人の中にも、そう思った人がいたのでしょう。
『生きた骸骨が 踊るよ 踊る』
大正時代の演歌師、添田唖蝉坊の歌です。
『髑髏よ 髑髏よ 何故躍る 肉の縛りから解かれて 嬉しいのか』
これは、夢野久作のパクりです。

実際の作者や成立時期はよく分かっていないという。
骸骨たちがちょっとカワイイ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
