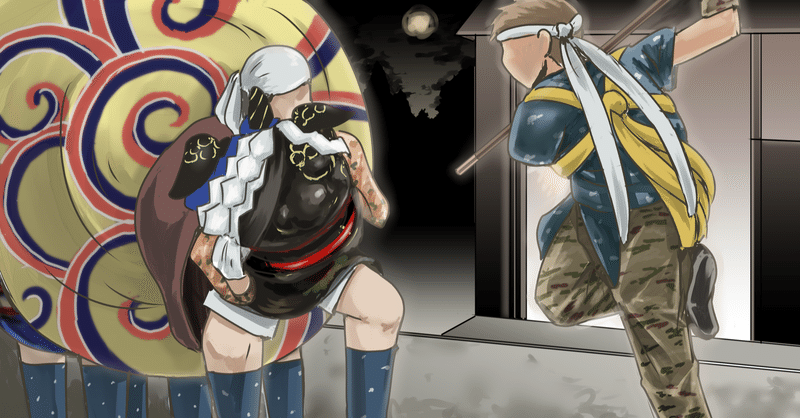
僕の獅子舞日記 第百二十六話【今年が最後かもしれない】
練習が始まる前日の金曜日の夜に、僕は音羽と駅前で待ち合わせをしていた。
仕事終わりに二人で飲みに行く約束をしていたのだ。
「ごめん。待った?」
少し遅れてやってきた彼女は、白い襟付きのシャツにオリーブ色のカーゴパンツを履いていた。
こういう格好はオフィスカジュアルというのだろうか。
「いや、全然。じゃあ行こっか。」
僕はいつものようにパステルカラーのポロシャツにスラックスという適当な格好だったが、二人で並んでいると仕事終わりにデートをするカップルにも見えなくはない気がした。
しかし実際には僕らはそのような爽やかなカップルではなく、酒の席で音羽の愚痴をただうんうんと聞いてるだけの関係だ。
お酒が飲める年齢になってからは、僕らは三ヶ月に一回くらいペースで、金曜日の夜に駅前の居酒屋で一緒に飲むようになっていた。
僕も音羽もそこまでお酒は強くはないが、飲むことは好きなので、会う時には食事だけということはなく、必ずお酒を飲んでいた。
「あーあ。なんかもうあっという間に二十五になるんだね。私たち。」
ハイボールをぐっと飲みながら、音羽が言った。
「そうやってあっという間に三十歳になるんろうね。」
僕もビールジョッキを手にして、相槌を打った。
「本当にね。いやでもさ、過疎化が進む中で、今年もこうやっていつものメンバーで獅子舞が出来るって本当にありがたい話だよね。」
「まあね。ただ瑛助くんがいつまで天狗をやれるかの問題はあるよね。」
「それね。今年二十一でしょ?あと一、二年がギリかなあ〜。」
「大学を卒業するまでは続けてくれるって言ってたけどね。」
僕の言葉に音羽は「う〜ん。」と唸りながら、ハイボールをお代わりした。
瑛助くんの話題から、また別の話になった。
「そういえば、奈々ちゃん。今付き合っている彼氏に結婚を迫られているらしいよ。この前たまたま会う機会があって、ちょっとだけ喋ってた時にそう言ってた。」
「ええ!奈々ちゃんって僕らの二個下だから、二十三だよね?あ〜。でもそうか。全然おかしくないか。」
「私ら四人を差し置いて先に行かれるパターンも全然あるよね。」
「全然あるね。そもそも僕は健人がまだ結婚していないことにちょっと奇跡を感じてるぐらいだよ。音羽には悪いけど、なんかいきなりデキ婚とかしちゃってもおかしくないイメージだから。」
「確かにね。あいつなー。さっさと結婚でもしてくれりゃあ、こっちも諦めつくんだけどなー。まじで嫌だー。片想い歴十五年目に突入したんですけどー。」
音羽の顔が少しずつ赤くなってきた。
僕はまずい、と思い始めた。
こうして少しずつ音羽がグタグタになってきて、最終的には僕が介抱するのが毎回の流れなのだ。
まずいとは思いつつも、さすがにもう慣れてきているから、今回も思う存分に愚痴を吐かせることにした。
「でも音羽さ、健人が帰ってきた時にいつかは思いを伝えるって言ってたけど、あれからもう五年も経っちゃったよ。どうするの?」
「うん。実はね、二十五歳が区切りだと思ってたんだ。つまりは今年だね。」
「え!?まじで?ついに今年?」
「うん。だってそうだよ。ただでさえ、女性はタイムリミットがあるんだよ。お姉ちゃんの子供とか見てるとさ、いいなあ、私も子供欲しいなっていつも思うし。手に入らないものをいつまでも追いかけてたら、あっという間に出来ることも出来なくなっちゃう。」
音羽がここまで話したところで、先ほど頼んだおつまみが運ばれてきた。
枝豆を食べながら「私、枝豆が一番好きな食べ物かも。こんなちょろいやつ他にいるのかな。」と彼女は呟いていた。
「じゃあ、告白するとしたら、今年の獅子舞の本番が終わったときくらいってこと?」
「そう。だからもしかすると、私がこの町の獅子舞に参加するのは、今年が最後になるかもしれない。ごめんね。」
「そうか。残念だけど仕方がないか。って、だからどうして結ばれる可能性をゼロとして考えるわけ?」
「だってそうじゃん。もし結ばれるんだったら、とっくに結ばれるって思わない?私と健人が出会ってから何年経ってると思ってんの?」
「でもどっちかが動き出したら、何かが変わることもあるよ。もともと健人は女の人に自分から行かないタイプなんだよ。中学の時の山内さんから始まり現在に至るまでずっとそうなんだから。」
「うーん。てか告白が実ったところで、その後別れるってことも普通にあるだろうしね。鈴木くんと結以ちゃんみたいにさ。あのジンクスもいまだに続いてることだし。私、トイレに行ってくるからレモンサワー頼んでおいて。」
「はいはい。」
僕も追加でお酒を頼もうと思い、メニューを手に取った。
そして、音羽が言ったことについて考えた。
もし健人に振られたら、自分は実家を出てこの町を去ると彼女は言っていた。
だがもしその前に、通くんが音羽に告白をしてそれが実ったとなれば、音羽はこの町を出て行くことはないかもしれない。
でもどうだろうか。
健人の面影が色濃く残るこの町で、いくら彼女が健人以外の人と結ばれて子供を欲しいと願ったところで、通くんを受け入れることはあるのだろうか。
考えすぎて頭が痛くなってところで、彼女が戻ってきた。
「頼んだ?」
「あ、ごめん。まだ何も頼んでない。」
「何してんだ!」
彼女はいつもの三日月目で笑った。
この笑顔を見れなくなる日が近いのかもしれないと思うと、余計に頭と胸が痛んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
