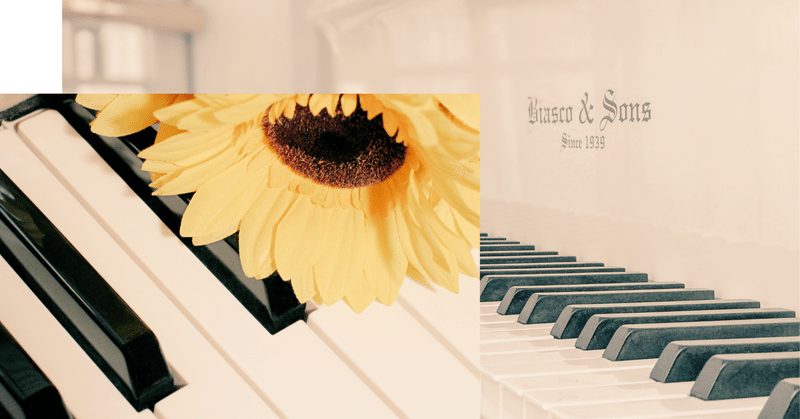
失くした指で花を摘む(2/2)
失くした指で花を摘む(1/2)第1楽章から第7楽章より
第八楽章 後悔
「仕事を続けられないのなら、私結婚できないわ。」
ハルは隆史と付き合って2年目にプロポーズをされた。
あのプレゼンのあとハルは社長の息子である隆史と交際を始めていた。
ハルが手がけたフラワーチャペルの企画は大当たりで、当初の計画を上回り、わずか2年足らずでその費用を回収してしまうほどだった。最初の頃、冷たい視線でハルを見ていた社長の篠塚幸子の目はみるみる変わっていき、ハルを見るたびに声をかけてきた。
「高梨さんのあの大胆な企画のおかげでうちのホテルも持ち直したようなものね」
「とんでもありません、社長。社長がご決断くださったおかげで弊社も名があがっておりますので感謝をするのはこちらのほうです」
ハルと篠塚幸子との関係は良好だった。
「あなたみたいな人が隆史の嫁になってくれればいいのに」
「いえいえ、私のようなものが、もったいないです。」
「ハルさ、仕事なんていくらでもできるよ。うちのホテルで」
「それは、ホテルの仕事でしょ。私は花しまフローリストをつづけたいの。花の仕事がしたいのよ。」
「それは、まぁ、社長には俺も言うからさ。会社辞めてもうちのホテルで専属的にフラワーなんとか、やればいいじゃん。」
「そんなことお母様が許すはずないわ。私は自由に花を活けることができるこの仕事がとても気に入っているし、いずれは自分の店を持ちたいと思っているのよ」
「社長とあんなに仲が良かったじゃないか。うちの嫁にほしいって言ってたし。少しぐら言うことを聞いてくれるんじゃない?」
「あれは、仕事上の仲、社交辞令でしょ。本当に嫁と姑になったらそれは立場が全く違うことになるじゃない。私は花と一緒にすごしていたいのよ」
「花なら家の庭で自由にすればいいよ。それに店なんていつでもやればいいし、俺といた方がなにかと便利だったりもするだろう?」
こうしてハルは押し切られ結婚を決めた。
いつもそうだ。最後の一言がいつも言えない。そして押し黙り何度も言葉を飲み込んできたのだ。
結婚の話をしに篠塚家を訪れた時、義母は孫が弾くピアノを聴きながら庭を眺めているだけだった。
「母さん、母さんだってハルのこと気に入ってただろ?」
隆史が何度か声をかけたが義母は答えなかった。ハルの中で何かが崩れる音がして、でもそれはいずれ自分の姪となる朋美のかわいらしいピアノの音色が少し柔らかなものにしてくれた。
篠塚幸子とは、取引先の社長と花屋の社員という関係から、嫁と姑という立場に変わりハルの人生は一変していった。
ハル自身の結婚式は、もちろんホテル・コーント・メルヴェで盛大に開かれる予定で段取りよく進んだ。花しまフローリストを寿退職することになるハルは、自分が手掛けたフラワーチャペルでの挙式からのアレンジをいくつか考えていたが、祝いとしてプランニングはすべてサプライズとさせてほしいとチーフに言われ渋々あきらめた。
だが随分あとになってから聞いたことだが「篠塚家の嫁となる人間が自分の結婚式の裏方をやることは許さない」と義母が花しまフローリストの社長に伝え、やらせたら契約を打ち切るとまで言ったらしい、と元同僚が話してくれた。
新居はいずれ持てば良いと義母となった社長に言われ同居も始めた。「花なら家の庭で自由にすればいい」そう隆史に言われていたこともあり、義母の言いつけを守りながら自分なりに楽しもうと前向きに考えていたが、そんなことは間違いだったと気づくのに時間はかからなかった。朝起きてから夜寝るまで自分の自由な時間は1分もなかった。ハルは常に義母の影で過ごした。
庭で花を育てたいという意見を聞き入れてもらえずハルはすでに結婚をしたことを後悔していた。自分の夢なんて自分の手で手に入れなければ何にもならないのに、あの時隆史と一緒にいれば店を持つことは容易かもしれないと、わかっていたのにそれ以上言うことが面倒になってしまった自分を悔いた。
自分の意思をここぞ、という時に言うことができないの悪い癖だと思っているが、なかなか克服することができないでいる。
朝起きて家の用事を済ませ、離婚をして戻ってきた義妹の子、朋美を幼稚園に送り、そのままホテルに向かう。ホテルでは常に義母の後ろに立ちながら経理の仕事を学んだ。これまで花と共に暮らしてきたハルは、今人生で一番花とは無関係な場所で過ごしている。
一度仕事を切り上げ朋美を迎えに行き、自宅で食事をさせる。月に2回通っているピアノ教室ヘ行くための準備をさせ送り届ける。それが終わるともう一度ホテルに戻り経理の仕事をしてから、社長(義母)の元で隆史としての妻ではなく、将来のホテルの社長の妻としての心得のようなものを延々と聞かされた。自宅に帰るのはいつも23時ごろ。隆史はほとんどホテルにいて家に帰ることは少ない。ただそれが仕事であればいいのだが。
隆史の隣にはいつも同じコンシェルジュが立っている。そのことがなんとなく気にはなっていた。よからぬ噂を耳にするがもちろん誰も私には声をかけてこないし、私自身「社長のしていることには目をつぶること」と義母に教えを受けていたため、それ以上詮索をすることはできなかった。
「何のために結婚したのだろう・・・」
ハルは義母でも、隆史でもなく、誰でもない、自分自身の浅はかだった心を呪った。
それでもハルは何とか自分の時間がとれるようになるまでと、必死で仕事を覚えた。いずれこのホテルを切り盛りできるようになれば前のように花を中心に生きることができるかもしれない。
ハルは、口に出してしまいたくなるあの二文字を何度も何度も飲み込み日々目の前のことを丁寧にこなしていくとに目を向けて、その他のことは目をつぶることにした。
どこにいてもハルはいつも義母から携帯電話で呼び出される。すべてを支配されたかのような毎日に最初は怯えていたが、いつのまにかそれは当たり前になり、自分が震えていることがわからなくなるほど麻痺していった。
ハルの携帯電話が鳴った。
また義母からの呼び出しかとおどおどしながら画面をみると朋美の通う幼稚園からだった。
「はい、篠塚です」
「すみません、かきのきざか幼稚園の佐藤です。朋美ちゃんがジャングルジムから落ちてしまって、申し訳ありません。お母様にお電話をしたのですがお出にならなかったもので」
「わかりました。すぐに向かいます。姪の様子はどんな感じですか?」
「ちょっとお膝を擦りむいた程度と思うのですが、ハルちゃんハルちゃんと泣いていて」
「朋ちゃん、、」
ハルは電話を切り、すぐに義妹に電話をかけた。
幼稚園の先生が言うように洋子は電話に出ない。ハルは取るものも取らずホテルの地下駐車場に向かって走り出していた。
第九楽章 覚悟
「しんちゃん、お花咲いてる?」
「うーん、、うん、小さな花が、えっーと、うんと、いくつか咲いている。ちょっとまって」
慎一はハルからもらった花の種を撒くため、庭に花壇を作りそれを撒いた。そしてハルに言われた通り毎日水をあげた。
確かにこの場所は日当たりが良い。植物にとっても人間にとっても日光浴をするにはもったいないくらいの日が降り注ぐ。花の種はすぐに芽を吹いて、剥げた芝生と雑草だらけだった庭が一気に明るくなっていった。いずみはその変わっていく庭の様子をみるため、以前よりベットから起き上がる回数が増えていった。
「ほら、みてごらん、確かこれはね、パンジーって言ってたかな?」
慎一は、スマートフォンで写真を撮りいずみに見せた。
「ちいさくてかわいい」
「花ってさ、おもしろいよね」
「きれいじゃなくて?おもしろいの?なんで?」
「だってさ、みんなこっち見てるみたいじゃない?」
「ふふふ、しんちゃんこそ、おもしろい。でもそうだね、みんなこっちみてるみたいだね。」
いずみは花を見るようになってから笑うことが増えた気がする。
「しんちゃんがお花屋さんに行くって、まだ信じられない」
「僕だって信じられないよ。でもいずみに元気なってほしかったから」
「私も行ってみたいな、そのお花屋さん」
「そうか、なら今度一緒にいこうか」
「うん、そうだね」
「友達が昔ね、お花屋さんをやるんだっていってて。必ず行くって約束したの。」
「うん」
「しんちゃん」
「うん」
「ピアノの上にあるお花、とって」
「あ、これいずみの宝物だって」
「うん、ここに置いておいて」慎一はいずみのベットサイドにそのブリザードフラワーを置いた。
「高校の時の友達がくれたの」
「そうなんだ」
「卒業式の日、その子は次の日から留学することが決まっていたんだけど、私が音大の受験に失敗したから言えずにいたの。」
「それから、なんとなく連絡できなくなっちゃたんだ」
「約束、したのに」
「私、素直じゃなかったから」
「会ってみたいな」
「うん、とっても元気で素敵な子。きっとしんちゃんも好きになると思うよ」
「そうか、いつか、会いにいこう」
「うん、いつかね」
いずみは病に倒れる前、一度だけその友人にハガキを送っていた。
「結婚をして海の近くに引っ越しました。また会いたいです」
と、海の写真の絵ハガキに一言だけ添えて。
あの日、少し気持ちがすれ違ってしまったまま別れた卒業の日。あの日を取り戻したくて願いを込めて書いた。
でも返事はなかった。
『やっぱり、嫌われちゃったのかな?』
「しんちゃん、ピアノ、弾きたい」
「うん、もう少ししたらね。」
「少し休んだら?」
「うん」
検査の結果、いずみは膠原病を患っていた。喫煙をしていることの多くが原因と思われる種類のものだと医師が言っていたが、僕ももちろんいずみも喫煙者ではない。禁煙が最も有力な治療法と言わるこの病気にいずみの治療は困難を要したようだった。いずみの母親もまた膠原病だった。膠原病と一口に言ってもいくつかの種類があって、いずみの病気は母親のものとは違ったがおそらく体質や遺伝的なこともあるかもしれないと言われた。
難病指定で有力な治療方法はなく、でもうまく付き合っている患者は多くいるという。しかしいずみの場合は合併症もあり徐脈のため慎重な治療が必要だと医師に言われていた。
慎一はパソコン開け、リストを流した。
いずみは、友人がくれたブリザードフラワーを見つめ、ベットの上で目を閉じ小さく指を動かした。
第十楽章 回想
「幼稚園のお迎えはいつもおばあちゃんだったな」
母親はハルが4歳の時に病気で亡くなっていた。父親は仕事が忙しくハルは母親が亡くなってから母方の祖母の家にひきとられていた。
「ハルちゃん、今日はねお花の種をとるよ」祖母はそう言ってよくハルを庭に呼び一緒に花の種を採った。
「お花さん、かわいいね、ハルちゃんみたいだね」
「この種を植えるとまたお花になって、そしてまた種を採ってね、そうやって命をつないでいくんだよ」
「ママ、」
「うん、ママはね、ここ、ハルちゃんのこころの中で命をつないで生きているんだよ」
「ハルの前にはこないの」
「そうね、でもちゃんと一緒にいるから大丈夫よ」
ハルと祖母は採った花の種を小さな袋に包んだ。
ハルが花をが好きになのはこの祖母の影響が大きい。いつもこの庭で花に水をあげ成長を見守った。こうして花は母を亡くしたハルにとって何よりも心を明るくしてくれる大切な存在になっていったのだった。
「おばあちゃん・・・」
祖母の葬儀を終えたハルは庭に立った。相変わらずたくさんの花が咲いている。
「ハル」
父と会うのは久しぶりだった。
「うん。お父さん、この家どうするの?」
「そうだね、ハル」
父はすでに再婚をして職場の近くに家を買っていた。ハルはこの家のことを思うと手放すという選択肢は考えたくなかった。
『ハルちゃん、お母さんもおばあちゃんもいつも一緒。いつもハルちゃんの「ここ」にいるから、大丈夫だよ』
祖母は亡くなる前そうハルに言った。
幼稚園の時、祖母と一緒に採った花の種を転園していく友達に渡した小さな記憶がふいによみがえる。
おままごとの時、いつも誰かに言われがまま『お父さん役』をしてくれたあの子。歌が苦手でみんなで合唱するときはいつも隅っこで小さな声で歌ってた。そうそう、運動会の時。一緒にかけっこして転んだ時、助けてくれたんだ。私一番だったのに転んじゃって、くやしくてその場で泣いてたら膝の砂をはらって手を引いてくれた。
おばあちゃんが作るお弁当はいつも渋め。みんなのお弁当はキャラ弁できれいな色をしていたからいつも隠れて食べてた。おばあちゃんのお弁当は最高に美味しいんだけどでもやっぱりちょっと恥ずかしくて。そしてたらあの子、気づいたら隣にいて一緒に食べてくれてた。「トマトがきらい」ってハルのお弁当箱に入れてきて、私はとっておきのおばあちゃんの卵焼きをあげて、ふたりで笑った食べた。
園庭でみんなで遊んでいるとき、あの子はいつも隅っこで絵本を読んでた。ハルはみんなと遊びたくてそのまま遊んでた。
「なんであの時いかなかったんだろう、いつも私のところにきてくれたのに」
あれはきっと小さな恋心だったのかもしれない。次は行ってあげよう、って思ったけどそれはもう叶わなかったんだった。
「お父さん、この家を売るの少しだけ待ってほしい。この庭の花の種が全部採れるまで。」
いつも私のところに来てくれたあの子。あのあと引っ越ししていなくなってしまう日にハルは祖母と一緒に採った花の種の包みを渡したことを思い出した。
「たまごやき、ありがとう。」
そういってあの子は私があげた包みを大切にポケットにしまってくれた。
ありがとう、って言わなくちゃって思っていたのに、ごめんねって思ってたのに。ちゃんと言葉にして言うことがどうしてもできなかった。
「しんちゃん」と呼ばれたその子は、母親に手を引かれ迎いの車に乗って行ってしまった。
ハルは、その車が小さく、小さくなって見えなくなるまで見送った。
『この花の種を全部とって次に命をつなげなくちゃね、おばあちゃん』
第十一楽章 事故
ハルは車に乗り込みエンジンをかけ発進させた。ホテルの地下駐車場から出ようとした時また携帯電話が鳴った。ハルは幼稚園からだと思い急いで電話に出た。
「ハル、ん、今日の、、、お客様、、聞いて、、、せんが」義母だった。ハルは車を止め、反射的にドアを開け外に出た。地下は電波が悪い。
「社長、実は朋ちゃんが幼稚園で怪我をしたようで、私、これから幼稚園に行こうと思うんです」
「なにい、、、いる、、、く、、ない、、、子に連、、、ない。あなた今ど、、の?」
「もしもし?とにかく洋子さんとは連絡がとれなくて、もしもし?・・・・あぁーもう!」
ハルは、車のドアをあけたままウロウロとした。
「電波が、、、」焦る気持ちを抑えようとしていた。
「とにか、、、、来て、、うだい。、、、、、まったく、、いのよあなたは。」
一方的に電話を切られたハルは茫然とした。
もう急ぐ気持ちをどこに置けばいいのかわからない。とにかくもう一度義妹に連絡をしようと携帯電話を取り出しリダイヤルをした。その時、後ろから大きな音でクラクションが聞こえた。「ヤバイ!」ハルは車のドアを開けっぱなしにしてその場を離れていたことを思い出した。
ホテルの制服をきていることもあり下手なクレームになったらまた叱られる、とハルは急いで車に戻った。
クラクションを鳴らした車に向かって会釈をして乗り込んだ時、洋子が電話に出た。
「ハルちゃん?何?なんかあった?」
プップップーっとまたクラクションを鳴らされて「あ、また」と気が焦る。洋子の声に答えようとした時、うっかり車の外に携帯電話を落としてしまった。車のドアを閉めながら携帯電話を拾おうしていると、クラクションを鳴らしていた車が急発進し、ハルは思わず手を引っ込めた。閉まってくるドアに一瞬間に合ったかと思われたが微妙に間に合わず、そのままハルは手の指を車のドアに挟んでしまった。
ークラクションの音が響くー
ハルは一瞬何が起きたかわらなかった。
そして痛みをこらえながら幼稚園へ向かうか、義母の元へ向かうかと悩み、悩みながら次第に気を失っていった。
いずみからハガキが来た。
『結婚をして海の近くに引っ越しました。また会いたいです』
郵便の転送期間のおかげでハルはそれをこの篠塚の家の受け取ることができた。ハルはうれしくてすぐに出かける準備をした。
いずみは私のこと嫌いになっていなかったんだ。よかった。
「ごめんね、いずみ、ずっと私、怖くて連絡できなかったの。」
鎌倉から江ノ電に乗り換えて、海の街を見つめながらきっとかわいらしい主婦となったであろういずみの姿を想像した。これを機会にまた交流をつづけたい。楽しかった日々をとりもどしたい、そう思った。
最寄りの駅に降り立ち、その駅の近くに涼子の店があることを思い出した。「そうだ、お花を買って行こう」
ハルが花しまフローリストで世話になった酒々井涼子の店「ヨー・ナポド」へ向かっていると、目の前から義母が現れ「ハルさん、ここでなにをしているの?」と言われた。
ハルはびっくりして、「あぁ、私はどこまでいってもこの人の呪縛から逃れられなくなってしまったのか」とビクビクして後ずさり。
鳴り響く踏切に向かって
走りだした。
・・・・意識がもうろうとする中で、ハルは義母と隆史の声を聞いた。
「ハルさんは不注意だし、要領がわるいのよ。自分の立場をわかっていない。だからこんなことになって」
「そんなこというなよ。母さんだってハルのことあんなに気に入っていたのに」
「そんな昔のこと。あれは篠塚家に入る前の話でしょ?うちにはうちのやり方ってものがあるんですから。こんなみっともないことになって」
「しかたないじゃないか」
「まったく、あんた、別れた方がいいんじゃないの?」
『あぁ、あれは夢だったのか』
『朋ちゃん、大丈夫だったのかな?』
目の前の視界がはっきりしてきて、ハルは自分に起きたことの記憶をたどりだした。
『そうか、あの時朋ちゃんの幼稚園に行こうとして、お義母さんから電話がきて、そして、後ろの車がうるさくて、洋子さんが電話に出て、そして車のドアが、、』
ハルの右手に傷みが走った。
自分の手が包帯に撒かれているのが見える。
ハルは、右手の人差し指を失っていた。
傷みはあったが、でも不思議と悲しいと思うことはなかった。
見つめる先の、指をひとつ失った自分の不格好な手は何とも滑稽で笑いが込み上げてきた。
『いずみ、チョップスティック、できなくなっちゃった』
そして、これまでぼんやりと思い、息を殺して向き合うことをしなかった言葉をやっと口にすることができた。
『別れよう、』
ハルは久しぶりに呼吸をした気持ちになった。
「あの日を、あの日々を全部、取り戻さなくちゃいけない」
バラバラだった何かがあることをきっかけに隣り合うピースを見つけて一つの絵になっていく様子が目に浮かんだ。いずみが弾くピアノの音色がそれを奏でる彼女の長くて美しい指が、明ける朝日を呼びに行ってくれて。
ハルは新しい日を迎えるための準備に取り掛かることにしたのだった。
第十二楽章 別れ
「その指はお仕事で?」
慎一とは店に来るたびたわいもない話をしてきたけれど、彼が指のことを聞いてきたのは初めてだった。
「いえ、ちょっとした事故です。」
「そうですか」
「お目ざわり、でしたね」
「とんでもない、すみません、急に」
「いえいえ、こちらこそ」
慎一は申し訳なさそうに、そして顔を伏せて
「妻が、」
「妻は、手足の動脈が閉塞をするよいう難病で、先日亡くなりました」
ハルは、慎一の潤んだ目を見つめ、しばらく言葉を失った。
「病気に早く気づいてあげられたらとも思ったのですが、どうやら遺伝的なものもあったらしく寿命とでもいうのでしょうか、あっけないものでした」
「あなたは、」
「あなたの命は、あってよかった」
「不謹慎かもしれませんが、僕はそのおかげであなたと出会えたようなき気がします」
店内にリストの「慰め」が聴こえ、ハルはひとつだけでボリュームを下げた。
「浜野さん」
「私、奥様お幸せだったと思います。あなたにこんなに愛されて」
「でも、僕は結局何もできなかった」
「お花を育てられたじゃないですか。命をつないで育てて、だからきっと奥様のお命は浜野さんのお心の中にまた芽吹いて、そしてこれからもきっと生き続けると思います。」
「ハルさん、あなたはやさしい人だ。本当に。」
「あぁ、」
「そういえば、この前思い出したことがあったんです」
「あなたにいつももらうこの花の種、実は昔、ずいぶん昔子供の頃、こうして誰かにも花の種をもらった気がするんです。その時のその種はどうしたかわかりませんが、でもなんとなく、ほんのりと心が温かくなったような、そんな記憶であった気がします。」
「今と同じように、」
「あの日、この店からリストが聞こえて、僕は妻の弾くピアノに誘われるようにここに立って、そうしたらあなたの声が聞こえた。」
「あれは偶然でも必然でもなくて、この海の街が作った自然、だったのかもしれません」
「記憶とは不思議ですね。どんなに辛く悲しいものでも、自分にとって都合の良いものしか、都合の良い場面しか覚えていない。前後がどうであっても、不思議とその一場面だけが残っていて、ずっと忘れていたのに急に思い出して。だからそう考えるとその場面は僕にとって都合が良い、いやきっと子供ながらに『大切』な思いのものだったのだと思うのです」
「あなたに会えてよかった」
ハルは指のない方の手で小さな袋に包まれた花の種を取り出した。
そして、慎一の手のひらに乗せ、そっとその手を包み込んだ。
「今日は、ひまわりの種です。あなたのお家に奥様の笑顔の様なお日様がたくさん咲きますように」
ハルが感じたあの幼い日の芽吹きが今、今やっと小さな蕾となった。
長い月日の中で、やっと花を咲かせる準備を整えることができたのだ。
失くした指はもとには戻らない。でも失くしたものは決して無くなったものではない。ハルの人生はあの日小さな少年を見送ったあの日、「ありがとう」も「ごめんね」も言えなかったあの日から今日まで、一ミリもズレることなく真っすぐに歩いてこれたのだ確信した。
海は広くそして空も広く。
母も祖母もハルの中でいつも花開いている。
そして、その花はいつまでも咲き続けるのだ。
「ありがとうございました」
「また、どうぞ、お越しください」
「お待ちしています」
「はい、また、」
「また、かならず、」
そして、その日を最後に慎一がヨー・ナポトに来ることは、もうなかった。
第十三楽章 ひまわり
ー10年後
「ハルちゃん、家みつかった?」
「なかなかないです。私には庭付きの一戸建てなんて贅沢なのかな?」
「テナントも契約したばかりだしね、安い方がいいもんね」
「そうなんです。贅沢かもしれないけど、自分の家の庭でも花を育てたくて」
「本当にお花が好きなのね」
「花は、私にとって母で、祖母でもあってそして大切な友達なんです」
ハルは、慎一のことを思い出していた。
ハルがあげた花の種を不器用にも育てて、愛妻ときっと楽しく笑っていたんだろうな、と。自分もそうして庭で花を育てることができたら、もしかしたら慎一が喜んでくれるんじゃないかと、そう思った。
そしてあの頃、祖母と一緒に花を育てたように、たくさんの思いを込めて花を育てたかったのだ。
「駅の向こう側にある不動産屋、私の同級生がやっているんだけどね、ちょっと古いけど海に近い一軒家なら紹介してくれるって言ってるんだけど、みてみる?」
「わーうれしいです!いいんですか?」
「もちろん、じゃ言っておくね」
「海の入り口にあるから木造だから傷みが早いんだけど、少し手を加えればまだまだ住めると思うよ。」
ヨー・ポナトの店主の涼子が紹介してくれた不動産屋は、海に長らく住む人らしく真っ黒に日焼けをしたサーファーだった。
「今から見れますか?」
「いいよ。涼子の紹介だから少しだけど安くするからね。」
「ありがとうございます。」
ハルは、ヨー・ポナトの店の2階に住まわせてもらっていたが、店のOPENが決まったため自分が住む家を探していた。
車に乗り、海の風を浴びながらハルは自分の手を見つめた。
ラジオから聞こえる「アヴェ・マリア」が美しい。
指を失った代わりにハルはたくさんのものを手にした。
ヨー・ポナト、涼子さん、自分の店、そして慎一。
慎一もどうか幸せでいてほしい、そう心から願った。
「ちょっと、空き家になってから時間が経っちゃって、手入れが行き届いて
いなくて申し訳ないんだけど」そう言って、きれいに日焼けをした手で涼子の同級生が家のドアを開けた。
明らかに人が住んでいない空気が漂い、歩くと所々でギシギシと音がして、少し湿気っぽい感じがした。海に近い家は潮で痛みが早い。手入れをしないとすぐにダメになっていくというからここは空き家になってから相当長いのだろうと感じた。
玄関から入ってすぐ右に古風なタイル張りの洗面所があった。お風呂は小さめだが自分一人なら十分だと思った。
飾りガラスが特徴の引き戸を開けると4畳ほど台所がある。少し暗い感じがするが、それはまぁ床の色が暗めだからかもしれないと思い使い勝手を確かめるように少し歩いてみた。
ガラガラガラガラ。
台所の隣の庭に面した居間の窓を不動産屋が開けた。
その途端、部屋は一気に明るくなった。
ハルは誘われるように隣の居間に入ると、吹き込む優しい海風が歓迎してくれる。
「ここだけは防音になっているみたいなんです。前に住んでいた人がピアニスト?って言ってたかな?」
「そうですか、」
ハルは庭にむかって縁側に立った。
先ほど歓迎してくれた海風が、さらにまたやってきて気持ちがよかった。
「決めてくれたら庭の手入れと、床のきしみとかいろいろ直しますよ。」
不動産屋がそう言った庭は、確かに雑草だらけで到底ハル一人できれいにするのは困難な状態だった。
でも「いえ、自分でやります」と、庭の隅に、背の高いひまわりが太陽に向かって背伸びしている様子を見ながら、ハルはそう答えた。
「決めるってことですか?」
「はい、ここにします」
ハルは言った。
庭に出てもう一度海風で呼吸を整えたハルは、振り返り、家を眺めた。青い屋根がかわいらしくてとても気に入った。
雑草にまぎれて何か落ちているのが見えた。
「リトル_リスト(little_Liszt)」とかわいらしくペイントされた看板はこの古びた家にずっとあったとは思えないほどきれいで、ペイントされている文字はうっすらと色を失っていたが、でもそう読むことができた。
「昔はここも人が多かったんですけどね。いわゆるリゾート地なんで別荘で持つ人が結構いて。でもね、最近はなかなかね。」
「一旦、店もどりましょうか?」
「あ、はい。ちょっと待ってください。」
ハルは落ちていた看板の土を丁寧にはらい、そして「これ、持ち帰っていいですか?色を、塗り直したくて」
「いいっすよ。なんですか?それ」
「たぶん、忘れ物です。昔の、私の、大切な親友の、」
「え?」
「いえ、なんでも」
「あ、はい、じゃ行きますか」
「はい」
ハルの親友の忘れ物は今、確かにハルの手の中に帰ってきた。
最終楽章
「ハルちゃんさ、私もここに住んじゃだめ?」
「え、朋ちゃん、ここからだと大学遠いでしょ?」
「いいのいいの。だってここ気持ちいんだもん、ねぇ、ダメ?」
隆史と別れた後、隆史の妹の洋子とは連絡を取り合っていた。そして朋美をたまに預かり交流をつづけていたのだった。「お母さんはうるさいから内緒よ。」洋子はハルの指がなくなったことは自分のせいだと責任を感じていた。ハルはそんなこと気にしなくても良いと言ったが、それでも洋子はハルに困ったことがあったらなんでも助けてあげたいと考えていた。しかしそんな義務はいつの間にか消え、ずっと良い関係で付き合うことができている。
ハルが離婚をした後、隆史はあのコンシェルジュと再婚をし無事ホテルの社長に就任したらしいが、義母は会長としてまだ現役でホテルの経営を担っているという。隆史が社長になってからホテルは大改修されハルが手がけたフラワーチャペルは無くなったそうだ。それが理由とまでは言わないがそのころに比べるとホテルの経営はあまり良くないらしい。隆史の再婚もあまり長くは続かなかったようで、やはりあの義母のせいかと少し気の毒に思った。
「ハルちゃん?」
「あ、ごめんごめん、うん、いいよ、朋ちゃん。っで?ピアノもおく?」
「ええ!いいのー!しかもピアノまで!」
「うん、この部屋防音らしいからピアノおいても平気よ」
「やった!ありがとう!ハルちゃん大好き!」
「私も、朋ちゃんのリスト好きだから、いつも聴きたいの」
「ハルちゃんのお店の名前もリストだよね」
「うん、リストは私の人生の中の一番流れている曲だからね」
あの時見つけた看板をハルは店先に飾った。
それはまるで誰かを待っているようだった。
そのひと月後、朋美が引越しをしてきた。ハルは中古店でアップライトの小さめのピアノを買い朋美にプレゼントをした。
ひとりの男性が七里ケ浜の駅に降り立つ。
久しぶりの海風に一呼吸おいて。
彼は迷わず海のほうに向かい歩きだした。
目的の場所はわかっているから
彼の足取りはゆったりとしていた。
しかしその家が近づくにつれ少し早くなる。
青い屋根が見えてきてうれしくなり、彼の足取りはさらに早くなった。
そして。
波の音にまぎれて聴こえるリストが心地よかった。
呼び鈴を押そうとして手のひらから伸びた彼の右の人差し指が、ためらいがちにもう一度手のひらの中に戻った。
『これを押すのは今聴こえている「ラ・カンパネラ」を聴き終えてからにしよう。』
了
この物語のスピンオフを一行物語にしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
