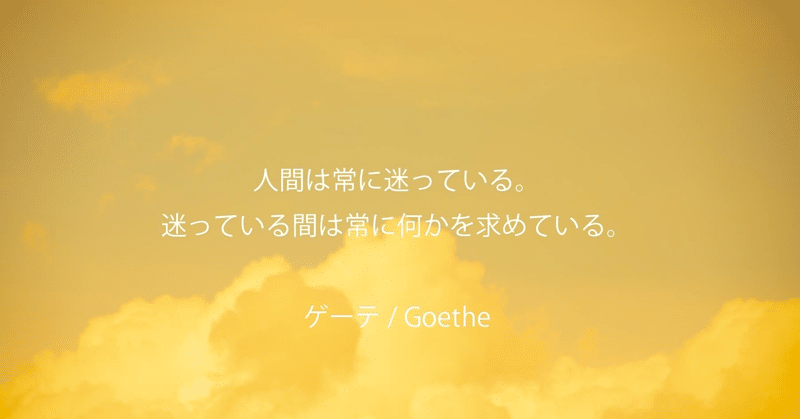
気をつけて!独学俳句あるあるその2
今日の記事は
昨日に引き続き、宇宙杯前に、俳句を独学ではじめたときはやりがちよねーということを、自戒も込めてまとめていく。
今日は初級編。
これが宇宙杯だっ!!
初級編
季語を入れ、五七五の定型を整えることができるようになると、世の中の見え方が変わってくる。
あれだけ難しそうと二の足を踏んでいた俳句を詠むことが楽しくさえなってきて、世の中を五七五に組み入れたくなる。
人それぞれだが、多分10句くらい詠むとそんな気になるんじゃないか🤔
俺は、始めるまでにプレバトを見たり図書館で本を借りたりしてテンション上がってたので、初めて読んだときからそうなってた笑
今日はそんな初級の方々に贈る初級編である。
1 文体統一問題
俳句の決まりは有季定型。
しかし、実際はもうちょっと自分に縛りを課す人も多い。
例えば、文体である。
俳句は文語といって、主に平安時代あたりから使われている言葉遣いで詠まれることが多い。
そもそも俳句が和歌→連歌→俳諧→俳句という流れで成立してきたものなので、文語が馴染み深いのもあるだろう。また、文語の調べが五七五に収めやすいのも関係しているだろう。
柿くえば鐘がなるなり法隆寺 正岡子規
文語に対し、現代の言葉遣いを口語という。
言文一致といって、話している言葉と文章を一致させようという流れが起こったのは明治時代だったと思うが、そこから私たちは話し言葉と書き言葉がどんどん近づいた。
近代俳句はその時期、正岡子規の革新運動に端を発しているので、むしろそこで文語を選択した経緯はあるのだが(このあたり想像です。欧化政策等で外国文学よかれというときに、日本の韻文文化も見直して、今風にアレンジしつつ蘇らせようぜ!ってのが短歌、俳句革新運動の骨だと思っている。)、そこから俳句は師事する先生によってどんどん枝分かれしていくことになる。
話が逸れたが、そういった無数の潮流の中で口語を良しとする流れも生まれた。
河東碧梧桐の新傾向俳句や荻原生潜水の自由律俳句などは、口語を用いて詠まれたものも多かった。
曳かれる牛が辻でずっと見廻した秋空だ 河東碧梧桐
空をあゆむ朗朗と月ひとり 荻原井泉水
と、このように俳句をどっちの文体で詠まなければならないという決まりはないので安心してもらいたい。
ただし注意点が一つある。
一句の中で文体を変えないこと。理由は変だからだ。
まあ、これもあえてならいいんだよ、自己表現なので。今話し言葉でも「このアイス良き!」とかいうもんね。
よくやるのが、口語俳句の中に、「や」「かな」「けり」という古語の切れ字を入れること。これ注意な😏
個人的には、無理に文語にして文法を間違ったり、言い回しも知らないような古語を使って間違えるくらいなら、口語で平易に詠む方がいいと思っている。
文語にするなら、こちらもネット上で古語辞典があるから、きっちり用法を調べて使うのがよい。
2 仮名遣い問題
仮名遣いには、歴史的仮名遣いと現代仮名遣いがある。
これは、1の文語と口語の違いと混同しやすい。
ざっくりいうと、文語と口語は平安時代ごろの文体なのか、明治以降の文体なのかの違い、歴史的仮名遣いと現代仮名遣いは、昭和21年の内閣告示以前の表記か、後の表記かの違いだ。
昭和21年までは、歴史的仮名遣い(旧仮名表記などともいう)を使っていたのである。
文語で歴史的仮名遣い,口語で現代仮名遣い以外に、文語で現代仮名遣い,口語で歴史的仮名遣いの句もあるということだ。
●「今さら聞けない俳句の疑問」
(1)旧仮名づかいは使った方がいいのでしょうか?
どちらにするかは、作者が選ぶもの。
文語を使う時:歴史的仮名遣い(旧仮名)OK
現代仮名遣いも(現仮名)OK
口語を使う時:歴史的仮名遣いOK
:現代仮名遣いもOK
○文語で新仮名の句
髪洗うまでの優柔不断かな (宇多喜代子)
文体は文語だが「洗う」は新仮名
○口語で旧仮名の句
雪まみれにもなる笑つてくれるなら(櫂未知子)「笑つ」
要するに、好みで使い分ければいいのだ。
混じってしまうのだけ気をつけるといい。
今日のまとめ
文体は文語か口語か選ぼう。
仮名の表記は現代仮名遣いか歴史的仮名遣いか選ぼう。
【追記】
なごみちゃんも以前このことをまとめていたのを思い出した。
こちらも見てね💁♂️
さらに追記
Rxちゃんもこのことに関する記事を書いていたので載せておく。
お読みくださりありがとうございます。拙いながら一生懸命書きます! サポートの輪がつながっていくように、私も誰かのサポートのために使わせていただきます!
