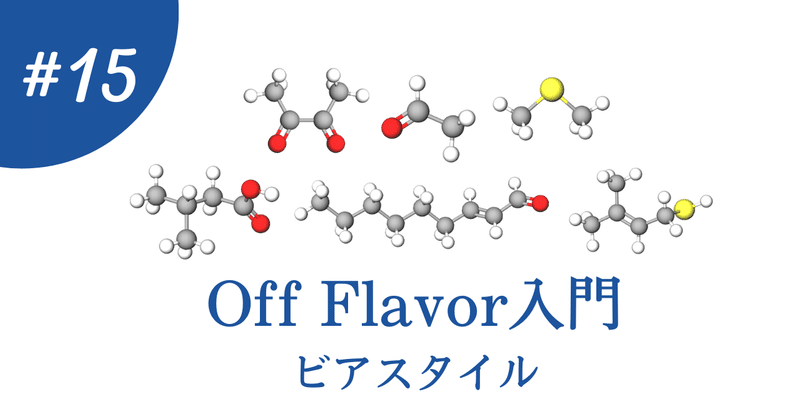
Off Flavor入門〜⑮ビアスタイル・ガイドラインの中のオフフレーバー
前回からの続き
前回はオフフレーバーに関する化学的な理解をまとめました。今回は前提知識編の最終回としてビアスタイルについて触れます。ビアスタイルは内容としては膨大なので、ここで扱える内容は網羅的ではありませんが、代表的なオフフレーバーとしてダイアセチルとDMSの傾向を見ていきたいと思います。
ビアスタイルとは
ワインや日本酒の分類との違い
ビール好きの人にはお馴染みのビアスタイルですが、ワインや日本酒の分類との違いに着目すると面白さがあります。日本酒は精米歩合と純米か否など製法による分類がメインです。ワインは分類の使い分けが特徴です。赤/白/ロゼ、Still/Sparklingなどのタイプの他にぶどうの品種と産地での分類、ボディや味わいによる分類を複合的に使い分けていると思います。ワインを探すときには産地や品種をキーにしたり、味わいをキーにしたりして様々な切り口で探しますよね。
それに対してビールにおけるビアスタイルは、味わい、製法、原材料、そして歴史と文化をすべて含んだ統合的な分類です。産地ではなく歴史と文化をキーにしているので、そのスタイルを受容すれば世界中に広がることができます。たとえばジャーマンスタイルのビールは日本で造ってもジャーマンスタイルです。審査会では本家のドイツ産のビールとドイツ国外のビールが同一カテゴリーで審査されます。
BAとBJCP
ビアスタイルは元々はビール評論家のマイケル・ジャクソン氏によって発案されたものをベースにしているとされます。現在ではヨーロッパやアメリカの団体がスタイルガイドラインを定義しています。その中でも最も普及しているのがBA(アメリカのBrewers Association)とBJCP(アメリカのBeer Judge Certification Program)のスタイルガイドラインです。ちなみに日本地ビール協会がベースにしているのもBAのものです。
BAとBJCP両者のスタイルガイドラインの違いは、その成り立ちにあります。BAは商業的な醸造者の団体なので、ビール愛好家(消費者)、小売業者、そして商業的な醸造所向けのガイドラインとなっています。一方、BJCPのガイドラインは、ホームブルワーやビール審査員向けに設計されています。個人的な印象ではワールドビアカップなどBAのスタイルガイドラインに準拠している国際コンペがが多いので、近年はBAのものがより影響力が高いように思います。というわけで、この後の説明はBAとBAに準拠して作成されている日本地ビール協会のものをベースにします。
スタイルガイドラインによって定義されるオフフレーバー
オフフレーバーというのは通常はどのビアスタイルにも共通しています。排水口の臭いといわれるメルカプタン、スカンク臭といわれる日光臭、こんな臭いが感じられたらどんなビールでも嫌ですよね。ところがいくつかのオフフレーバーはスタイルによっては許容されることがあります。それを定義しているのもスタイルガイドラインです。
ちなみに許容されるオフフレーバーがある場合でも、ビールを台無しにするくらい突出して感じられることは許されません。あくまでもビールの味わいのバランスの上で成り立つことが前提条件です。
ダイアセチルとDMS
ダイアセチルとDMSは数あるオフフレーバーの中でも特に有名ですが、スタイルによって存在が許されることがあります。なのでビアスタイル・ガイドラインではダイアセチルとDMSが許容されるか否か注意書きされていることが多いです。
ダイアセチルを許容するビアスタイルとして最も著名なのはおそらくボヘミアスタイル・ピルスナーではないかと思います。
ダイアセチルは、非常に弱いレベルに抑えられている限り、このビアスタイルのキャラクターとして相応しく、またモルト風味にアクセントをつけるうえで感じられてもよい。DMSがあってはならない。
ビアスタイル・ガイドライン2204、クラフトビア・アソシエーション 日本地ビール協会
日本地ビール協会の最新のガイドライン(2022年)では、「このビアスタイルのキャラクターとして相応しく」と記載されており、積極的に許容している書きぶりとなっています。ダイアセチルは許容していますが、DMSは許容していません。反対にジャーマンスタイル・ピルスナーやミュンヒナー・ヘレスはダイアセチルは「あってはならない」とされ、DMSは「非常にローレベルなら許される」となっています。
その他、イングリッシュスタイルのエール(ペールエール、ブラウンエール、ポーターなど)やベルジャンスタイルのエール(ヴィットエール、ブロンドエールなど)は非常に低いレベルであればダイアセチルを許容するスタイルです。
時代によって変わる定義
ダイアセチルやDMSの許容について、もう少し突っ込んで見ていきましょう。伝統的なビアスタイルでは許容する例が多いですが、最近生まれた新しいスタイルでは許容されないことが多いです。醸造技術の進歩によって、ダイアセチルやDMSに対する有効な対策がとれるようになったこと関係していると思われます。
また、伝統的なスタイルでもダイアセチルやDMSの許容度は年々変わっています。BAのスタイルガイドラインで、ボヘミアスタイル・ピルスナーの変遷を見てみましょう。
Very low levels of diacetyl and DMS flavors, if perceived, are characteristic of this style.
上記のとおり、実は2014年のガイドラインではダイアセチルだけでなくDMSも許容していました。
Very low levels of diacetyl, if present, are characteristic of this style and may accent malt character. Low levels of sulfur compounds may be present. DMS should not be present.
2019年からDMSは許容されなくなりました。ダイアセチルに関しては「characteristic of this style=このスタイルの特徴である」という肯定的な記載を維持しています。
Very low levels of diacetyl, if present, are acceptable and may accent malt character. Low levels of sulfur compounds may be present. DMS and acetaldehyde should not be present.
ところが最新の2023年版ではダイアセチルは「acceptable=許される」という一歩後退した記載に変更されました。つまり、最新のガイドラインによるとダイアセチルに関しては「このスタイルの特徴」ではなく「あってもなくてもいい」という中立的な位置づけになっています。このように同じビアスタイルでも時代が変わるとオフフレーバーの許容度が変わってきます。
次回へと続く
今回はビアスタイル・ガイドラインについてでした。通常オフフレーバーといわれるフレーバーでもスタイルによっては許容されることがあります。ただし近年は醸造技術の進歩で許容しない方向に徐々に変わりつつあります。
これで前提知識編は終了です。次回からはいよいよ個別編のスタート。初回はアセトアルデヒドです。
お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。
新しいビールの紹介です。ウエストコーストIPAのシリーズであるTriggerの第4弾がでました。クラフトビールの魅力を知るきっかけ=Triggerとなってほしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
