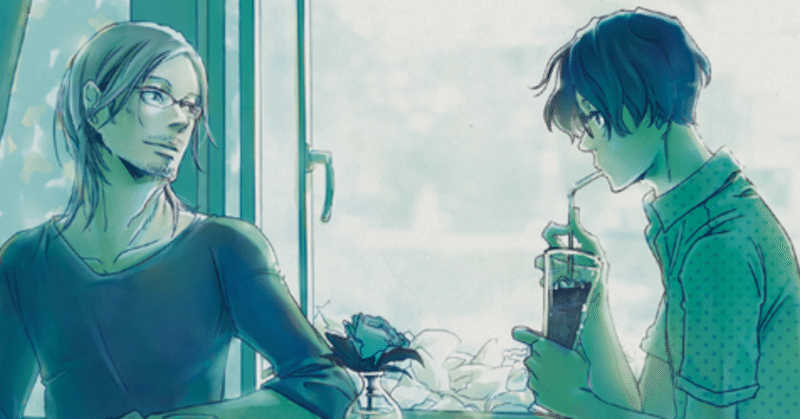
【創作小説】『よすが雪月風花』本文サンプル2【BL】
挫折感とともに帰郷した青年が出会った男は、彼にしか見えない存在だった…。
<基本情報>
座敷わらし・河童・雪女など、東北の妖怪をモチーフにした異界交流譚(BL/GL)です。主に岩手と東京を行ったり来たりします。
シリーズ再録『よすが雪月風花』より、主役二人のエピソードを中心に抜粋し以下に掲載しています。複数の男男、女女、男女の組み合わせが登場します。
BOOTH: https://rwks.booth.pm/items/1904146
一.縁(よすが)
ゆかり。えにしのあるもの。
十八歳までに嫌気がさしていたから出ようと思った。
離れていた二十代は、正直どうでもよかった。
今、三十を目前にして仕方なく戻ってきた故郷は、歓迎も拒絶もせずただそこに在った。
黒いスーツに黒いネクタイを締め、柳圭悟は引きつった笑顔で、顔も覚えていない親戚たちの相手をしていた。
「東京での仕事は辞めたそうだねえ」
「入院したって聞いたけど」
「ブラック企業ってやつかい」
「こっちにも仕事はあるよ、紹介しようか」
「ところで結婚は……」
正直、だれがだれだかさっぱりわからない。なまじ親戚同士で顔や雰囲気が似ているから、余計に混乱する。
座敷を逃げ出して台所を手伝おうとしても、女性陣からは「男の子なのに気を遣わないで」と体よく追い払われ、「男はどっしりかまえていればいい」と男性陣から叱咤される。さらに家事の苦手な妹からは嫌味を言われる始末だ。圭悟もそれほど得意なわけではないが、今は妹と代わりたい。
築百年を超えているらしい本家の屋敷は、不来方市内の住宅街に建っている実家の数倍はある。屋内のどこかへ隠れてしまうことは物理的には可能だった。しかしこの家を縦横無尽に走り回れたのは子供のころだけで、今はどの部屋にでも入っていいわけではないということはわかっている。
あのころのようにどこかの小部屋に潜り込んで、うるさい親戚連中が帰るまで待っていられたらよかったのに。
「久しぶりで迷った?」
不意に声をかけられ、はっと顔を上げる。薄暗い階段から、背の高い男が下りてきた。さっきの座敷にもいた気がする。
「小さいころは、よくこの下の納戸に入ってたよね。懐かしいでしょ」
歳は四十前後だろうか、ひょろりと背が高くて頼りない雰囲気だ。普通なら顔と名前が一致しない親戚の一人として、愛想笑いを向けるべきところだが。
圭悟は目を眇めた。
「……あんた、だれです?」
「え?」
男は笑顔を貼りつけたまま一瞬固まった。
「ほら覚えてないかな、子供のころよく遊んであげた……」
ありきたりな言葉を聞き流し、圭悟はじりじりと後ずさる。北側の日も入らない廊下で、その見知らぬ男はひどく不気味に見えた。
表情筋が慢性的運動不足なのが、今ばかりは助かる。動揺と恐怖を押し隠して口を開いた。
「ぼくね、昔からちょっと変な体質で。霊感とかいうのとはちがうと思うんですけど」
男は一瞬うろたえたかに見えたが、眼鏡を押し上げて圭悟の言葉に耳をかたむけることにしたようだった。
「……人がたくさん集まるところで、いつも不思議な体験をするんです」
「へえ」
「友だち六人で遊んでるのに、どう見てもぼくの他に六人いる。クラスの班で十人ぴったりのはずなのに、二人一組になると一人余る。でも知らない顔はだれもいないし、その場のだれも変だと思わない」
「十一人いる、か……」
男はくすくす笑った。
「でもね、ぼくにだけ『見える』んです。十一人目が」
だれも気づかないから、言い出せなかったけれど。なぜ自分だけがといつも不思議に思っていた。
圭悟は静かに息を吸い込む。
「あんた、親戚のだれでもない。だれも知らないのにだれも気がついてないだけでしょう?」
この家に住んでいない者が二階になど上がれるわけがない。そして特有の「違和感」が、彼は親戚などではないと圭悟に告げている。親戚どころか……。
「何百年ぶりだろうね、おれが『見えた』人間は」
腕を組み、長めの髪を揺らして男は笑う。
冗談には聞こえなかった。その言葉を聞く前から、圭悟には確信があったからだ。
「なんなんですか。妖怪? 幽霊? 神さま?」
もう半歩、後ずさる。
「好きなように呼ぶといいよ。今までみんなそうしてきた」
「この家に住みついてるんですか?」
「そうとも言えるし、違うとも言える」
男が動いた。圭悟は思わず数歩後ろに下がったが、彼は階段の一番下に腰かけただけだった。
「きみはちょっと特別みたいだから、教えてあげよう」
さすがに引きつっているであろう圭悟の顔を見上げ、男は自分のひざに頬杖をつく。
「おれは、この家が建つ前から、ここに……この土地に『在る』んだよ」
その答えでは何者なのか全くわからなかった。
「妖怪でも神さまでもなかったら、なんとお呼びすればいいんですか?」
「人間には教えちゃいけない決まりなんだ」
どこの「決まり」なのか、嘘か真実かも見当がつかない。
「だから、時雨って名前で通してる。圭悟くんもそう呼んでくれていいよ」
圭悟の名を知っていることは驚かなかった。彼がここにいる以上、それは当然なのだと思えた。気になるのはそこではなくて。
なおも口を開こうとしたとき、廊下の向こうから妹が呼ぶ声が聞こえた。
「あんた……」
一瞬目を離しただけだったのに。
階段に座っていた男はどこにもいなかった。古い階段を上る軋んだ足音もなく、がたついた襖一枚すら開け閉めせずに、彼は消えてしまった。
「こういう古い家って、おばけとか妖怪とか出るって話ありませんか」
食事をしながら、隣に座っていた叔父に訊いてみる。今はよそに住んでいるが、彼もこの家で育ったというから、なにか知っているかもしれない。
叔父は大声で笑った。ばかばかしい、子供っぽいと言われるのかと思いきや。
「そりゃあ、あるに決まってる。座敷わらしくらいはいるさ。なあ」
もちろんだと隣にいた大叔母がうなずく。
座敷わらしは聞いたことがある。着物でおかっぱの子供……少なくとも一般的なイメージでは。だがあの男とは似ても似つかない。
「ひいばあさんの若いころには、鬼が夜這ってきたって話も聞いたなあ」
「ちょっとやめてください、子供の前で」
小学生の子を連れている従姉が口を挟む。たしかにあまり楽しい話ではないが、座敷わらしよりはあの男に近い気がすると圭悟は思った。それでもまだ、鬼という言葉から受ける荒々しい印象とはほど遠い。
「ねえ、さっきなんか見たの?」
妹が気味悪そうに尋ねてくる。廊下の突き当たりに、一人きりでぼんやり立ちつくしていた兄の姿がよほど不気味だったのか。
「いや……ひいじいさんが帰ってきてるんじゃないのかな」
今日は、曽祖父の十三回忌だった。ごまかすつもりでそんなことを言うと、妹は眉間に皺を寄せて「早く帰りたい」と呟く。昔気質で厳しいだけだった老人に好印象がないのは、圭悟も同じだった。
さっきの男がせめて曽祖父の幽霊ならばわからなくもないのだが。あいにく生前の曽祖父は小太りの丸顔で、壁に掛かっている若いころの写真も、彼とは全く一致しない。
あの男は、こんな田舎では目を惹きそうな、飄々とした端正な佇まいだった。
ふと顔を上げると、末席にいる従弟の嫁の隣にあの男が座っている。彼は素知らぬ顔でビールを飲んでいた。
あまりにも自然で、さっきの不気味さは少しもなかった。
家事手伝いの妹と、週二回しかパートに出ない母と、定年退職間近の父を相手に実家で過ごすのは、控えめにいっても針のむしろだった。
無職は体裁が悪いから地元で働き口を探せとか、働けないならカウンセリングを受けるべきだとか、果ては独身だから自己管理ができていない、早く結婚するべきだとか。圭悟の事情も内心もおかまいなしに、皆が好き勝手なことを言う。
そんな状況だったから、高校の先輩から住み込みのバイトを紹介された時には、一も二もなく飛びついた。実家を出られるならなんでもいい。家族のほうもぎこちない現状を持てあましていたのだろう、強く反対はされなかった。
下宿先は、古い一軒家の二階だった。一階には季刊雑誌「よすが」の編集部が入っている。
「二階は好きに使っていいよ。でも資料とか紙モノ多いから、火の元だけ気をつけてね」
凛々しい顔つきが魅力的な桜舘眞樹は、圭悟のほとんど唯一といっていい地元の知己だった。数年に一度帰省したときは、必ず彼女と会うことにしていた。このバイトも飲みの席でもちかけられた話だ。
その編集部は、地元の広告代理店「河童企画(かつぱきかく)」が運営している。編集部員たちは正式には河童企画の社員ということになるらしい。編集長は河童企画の社長。いわゆる本社はこの近くの表通りに面していて、本業が忙しい編集長は週に数度しか顔を出さない。
編集部は女性三名だったが、一人が産休に入ったため一時的にでも入ってくれるメンバーを探していたとか。圭悟も東京では大手の広告出版社に務めていたから、即戦力とまではいかなくても手伝いくらいはできそうだということで即採用となった。
桜舘があわただしく取材に出ていったあとで、一人残された圭悟は部屋をぐるりと見渡す。
台所や風呂は一階で、二階は階段を上がった先に和室が四部屋。そのうち北向きの二部屋は編集部の荷物置き場になっていた。南側の二部屋は、ほぼなにもない。だが最近全部隣の部屋へ持っていったというのは、畳の焼け具合でわかる。
「広くはないけど、慣れれば住みやすそうだ」
思ったけれど口にはしていない言葉が、不意に背後から聞こえた。
ぎょっとしてふり向くと、窓辺にひょろりとした長身が立っていた。
「あんた……!」
先日、本家で出会ったあの男が、同じ笑みを浮かべてそこにいる。
「本家に住んでるんじゃなかったんですか!?」
「二十四時間体制であの家にいるとは言ってないよ」
彼は押し入れを勝手に開け、おもしろそうに中を覗きはじめた。
「神さまじゃなくて、鬼っていうのも聞きましたけど」
「ああ、そういう呼ばれ方もあったね」
あいかわらずまともな答えは返ってこない。
「人間が思うよりおれたちは自由でね。どこにいなきゃならないなんて決まりはないの。お気に入りの場所や人はあるけど」
時雨は圭悟に歩み寄ってその肩に手を置いた。そして秘密を打ち明けるかのように声をひそめ、囁きかけてくる。
「当座のお気に入りは、きみにしよう。柳圭悟くん」
「そんな、勝手に……」
彼は薄い唇を横に広げ、人差し指を当てた。
「だれかにおれのことを言ってもむだだよ。わかってると思うけど」
「……脅しですか」
老けた座敷わらしか角のない鬼か知らないが、面倒なモノにとりつかれてしまった、と圭悟は深いため息をついた。
二.因(よすが)
よるべ。たよりとなること。
目覚ましをかけなくても、目が覚める。
会社勤めだったときにはベッドから出るのがあんなに嫌だったのに、と枕元の眼鏡を探りながら思った。
あのころは眠った気がしなかった。実際、連日の徹夜などざらだったから。それに比べると今は不安になるくらい健康的で規則正しい生活をしている。
「……なにしてるんですか」
「おはよう」
ときどき布団に妙な男が入り込んでいるのを除けば、だ。
寝覚めがいい朝にかぎって、時雨はいつのまにか圭悟の横に寝ている。そのくせ眠らないのか、にこにことこちらを覗き込んでいたりするのが気味悪い。
「……おはようございます」
そちらを見ないようにして布団から抜け出ると、彼は不満げな声を上げる。
「もうちょっと寝てようよ」
「自堕落な妖怪といっしょにしないでください」
彼を認識できるのがどうやら自分だけらしいというのがまた面倒だった。透明人間のように見えないわけではないのだが、そこにいてもだれも気にしないのだ。不審者がいますと周囲に訴えることもできない。
「せめて女の人ならいいのに」
「あれ、圭悟くんってそうだったの」
意外そうに言われて、たぶんわかっているのだろうなと思いながら言い返す。
「ちがいます、ぼく女の人に興味ないんで、そっちのほうが気楽だったなって」
「だよねえ。そうじゃないかと思ってた」
無神経な妖怪はあっさり応じた。そして眼鏡をかけながら思い出したようにつけ加える。
「やっぱり小野さんじゃないとイヤ?」
「!」
起き抜けでまだ完全に焦点が合わないまま、時雨の顔を見つめる。その表情はいつもと変わらない。
「……妖怪って、人の心読めるんですか」
「ううん、寝言聞いただけ」
こともなげに答えて伸びをする相手から、むりやり目を逸らした。
「……すみませんね、寝言うるさいでしょうから布団入ってこないでください」
「おれは気にしないよ」
そっちはどうでもこっちが気にするんです、と突っかかりかけて言葉を飲み込む。朝食前から腹を立てて余計な体力を使いたくない。
洗面所やトイレ、台所などの水場は全て一階にある。編集部の皆も使うから、タオルや歯ブラシといった私物は都度二階から持って下りる。食事は台所のダイニングテーブルで。調理器具や食器もあるが、今のところ買ってきた弁当や惣菜がメインだった。
「小野さんって?」
テーブルに頬杖をついてそう尋ねてきた時雨は、なにも食べないで圭悟の正面に座っているだけだ。
「向こうでいっしょに暮らしてた人です」
昨日近くのスーパーで買ってきたおこわを口に運びながら、彼のほうを見ずに答える。
「恋人?」
「さあ……ぼくはそう思ってましたけど」
「相手はちがった?」
どうして朝っぱらからこんな話をしなければならないのかと苛立ちながら、箸を置いて茶を一気に飲み干す。
「そうです、同棲解消されて住む場所がなくなったから戻ってきたんですよ。仕事しすぎで体こわしたなんて、言い訳です」
時雨が口を開く前に、立ち上がって空のパックをゴミ箱へ捨てにいく。
体調不良は、全てから逃げ出すきっかけに過ぎなかった。
増えていく業務も理不尽な依頼も、皆不平不満を言いながらなんとかこなしている。もちろん脱落者も少なくはないが、だれも責めない代わりに同情もされない。
圭悟も先月までは見送る側だった。業務中、ふともたらされる報せに一瞬眉を寄せ、しかし数秒後には自分と縁が切れた者のことは忘れ、メールとタスクの山へと戻っていく。それが普通の状態だと思っていた。どんなに睡眠時間が減っても食事する余裕がなくても、上司やクライアントに怒鳴られても、仕事をつづけていられれば正常……達成感や充実感など、存在すら頭をよぎらなかった。
だが突然足下が崩れはじめた。最初はただの風邪だったはずなのに、体調不良を押して仕事をつづけた結果、入院沙汰になってしまった。
恋人の心が完全に離れていることに気づいたのも、そのときだった。数日の入院とはいえ、出張と言って見舞いにも来てくれなかった。別れ話を切り出されたのは退院直後で、一方的に捨てられたと感じた圭悟に相手は一言でとどめを刺した。
『先に捨てたのは、どっちだと思う?』
あのまま仕事をつづけることができなかったとはいわない。だが心がついてこなかった。
「全部放り出して、逃げてきたんですよ」
湯呑みを洗いながら独り言のように呟く。東京から逃げ、今こうして実家からも逃げ……。
「いいじゃない、逃げる先があるんだから」
「え……」
思わぬ応答にふり向いたが、時雨は戸棚に入っていたせんべいを勝手に取り出して一人で食っているだけだ。
「……ピーナッツだけ食べないでくださいよ。先輩はピーナッツ派なんです」
「ごまもおいしいのにね」
「じゃあごま食べてください」
間の抜けたやりとりに、落ち込みかけた気分がしらけてしまい、圭悟はため息をついて湯呑みを水切りかごに置いた。
布団を上げてから、掃除を始める。
圭悟がやってきた当初は家自体の古さもあってお世辞にもきれいとは言いがたかったが、ここ半月ほど業務時間外にあちこち手を入れていたおかげで、かなり清潔感が出てきた。自分がそれほど掃除嫌いではないというのもちょっとした発見だった。今までは忙しすぎて手が回らなかっただけだったらしい。
十時を過ぎたころ、二人の編集部員が出勤してくる。先輩の桜舘と、圭悟より年下の鹿内、二人とも女性。編集長の藤原が顔を出すこともある。
圭悟の仕事はたまった伝票や資料の整理、取材先や本社とのやりとり、記事の校正など。大手企業の広告制作とはずいぶん勝手もちがうが、今のところやり方もわからない未経験の作業はない。
昼はコンビニやスーパーの弁当。だったのだが、それを見た編集部員や河童企画のスタッフたちから、半ば強引に外へ連れ出されるようになった。
今日は、ちょうど取材から戻ってきた桜舘と評判の蕎麦屋まで。それも近所ではなく、車で二十分ほどかかる場所だ。桜舘のこういう方向に関する執念にはときどき驚かされる。
「午後は写真選び手伝ってね」
「……わかりました」
蕎麦をすすってから答えた。
その店は看板もないのに、昼時だからかほぼ満席だった。かといって行列まではできない。立地の不便さと車社会の中にできあがった、絶妙なバランスなのかもしれない。挽き立ての十割蕎麦はたしかに美味かった。
「雪んこ本舗、来月で閉店だってさあ」
「え、それって高校の近くの」
桜舘と二人で寄ることもあった店の話に、思わず箸が止まる。高校生のデートスポットとしては渋い和菓子屋だが、桜舘のお気に入りだった。
次号はスイーツ特集らしい。圭悟がいないあいだにできていたケーキ屋から、だれでも知っている老舗の和菓子店、地域の小さな駄菓子屋まで、ネタ集めの最中だった。
「おみやげ系は強いんだけど、地元向けってなると今の代で終わりって多いんだよね……もう閉店特集にしちゃおうかな」
「なんか暗くなっちゃいますよ、それ」
しかし新しい店ばかりを載せていては、ただの情報誌になってしまう。雑誌「よすが」のコンセプトは、不来方市周辺の「日々を記し、残し、継いでいく」。古いものも失われていくものも記録して広め、人々の記憶を呼び起こすことを目的としている、と聞いた。
圭悟自身は、生まれ育ったこの土地に格別の愛着を持っている自覚もない。だが一般論として、その発想は理解も共感もできる。この仕事を手伝っているときも楽しいことは認める。
ただ、自分自身が積極的に関わっていけるかという話になると、二の足を踏んでしまうのだった。
「というわけで、今日のお茶菓子は雪んこ本舗のきりせんしょとおちゃもちです」
午後三時を過ぎたころ、桜舘が冷蔵庫から出してきたのは懐かしい和菓子だった。それを見て鹿内が勢いよく立ち上がる。
「えっ! あたし、がんづき買ってきちゃいました!」
「そうなの?」
きりせんしょは砂糖醤油を練り込んだ餅菓子。おちゃもちは胡桃醤油をかけた団子。がんづきは黒糖味の蒸しパン。つまり。
「茶色いですね……」
「茶色いです……」
「誌面的にも地味だわ……」
そう言いながらも、桜舘はカメラをかまえている。
日持ちがしない上に華やかさがないため、土産品や名産には向かない。しかし「よすが」が取り上げるのは、地域のこんな面だった。
編集長の私物なのか台所にあった鉄瓶で三人分の茶を淹れてから、圭悟は写真データをチェックしていた。
ふと、鮮やかな紫色が目に飛び込んでくる。自家製の和風スイーツが売りというカフェの外観だった。
「この暖簾って……」
桜舘に尋ねると、彼女はおちゃもちの串代わりの割り箸を舐めながらうなずく。
「ああ、前の号読んだ? そう、染色家の猪野さんの作品」
「やっぱりそうですよね。東京から移住してきたっていう……」
「よすが」のバックナンバーは暇に飽かせて創刊号まで遡って読んだ。地域の伝統的な染色業に新風を吹き込んだアーティストについては、先週目にしたばかりだから覚えている。
「猪野新一郎、でしたっけ。岩手の風土に惚れ込んだとかなんとか」
桜舘が茶をすすってからにやっと笑う。
「理解できない?」
「いやべつに……」
他人の選択に文句をつけるつもりはない。人口が増えるのは単純に喜ばしいことだとは思う。ただ、感覚的な部分で納得しきれないのも事実で、桜舘はそれを知っている。
「だいじょうぶ、みんなちゃんと苦労してる。いい面だけじゃないのも知ってるよ。全部わかった上でここが好きって言える人は本物だから」
取材でいろいろな人に会っている先輩は、笑顔でそう言う。安易なイメージや憧れだけでやってきた人は、長く居つづけられないのだと。厳しい自然、交通や流通の不便さ、排他的な村社会……。
がんづきをほおばっていた鹿内が、少し不安そうな顔をして尋ねてきた。
「柳さん、不来方は好きじゃないですか?」
桜舘も鹿内も、不来方の生まれではない。近隣町村の出身だが学生のころから不来方で過ごすことが多く、当然のように不来方で就職した。
「べつに嫌いじゃないですよ」
だが迷わず好きとは言えなかった。
この菓子も、美味い酒も、緑と山に囲まれた風景もなつかしく、ほっとさせてくれる。
だがこの土地そのものを好きと言い切るには事情がありすぎるのだと思う。女性陣二人はその事情を地元に置いてきているから、不来方をてらいなく愛せるのかもしれない。
「嫌いじゃないけど、そのうち出ていく?」
夜、二人が帰ったあとで、時雨が尋ねてきた。あいかわらず興味本位にしか見えない。
「……他に行きたいところがあるわけでもないですし、しばらくはここにいますよ」
大都会はたしかに生活するには便利で、他人の煩わしい干渉も少ない。ただ仕事と恋人を失ったばかりの圭悟には、都会にしがみつくほどの思い入れも残っていなかった。
「しばらくは……」
ここでの仕事はそれなりに楽しいが、先のこととなるとイメージができない。
「おれは、圭悟くんがずっとここにいてくれたらうれしいな」
「……なんでですか」
さらりとそんなことを言う相手に、つい反論口調で尋ねてしまう。
「うれしいのに理由はないよ」
「……………」
謎の妖怪にそんなことを言われて喜んでいいのか。それ以前に喜び方もよくわからない。
圭悟の表情筋は、あいかわらず動いてくれなかった。
三.天狗【前篇】
山に棲み、人を誑かし、ときにはおびやかす。
その山へ入るのは初めてではない。
土地の権利者から、山菜や草木も自由に採ってかまわないと言われていた。ただあまり奥へ行くなと。
小さな山だが、遭難の可能性もある。ましてや自分はこの土地を知りつくしているわけではないのだから、禁止事項はいずれも納得ずくだった。
だから、最後に冗談交じりにつけ加えられた言葉も、きっとその危険を婉曲的に伝えるものなのだろう。
「このあたりには、天狗が出るから」
それでも猪野新一郎は山へ分け入る。
染色に使う植物の中には、庭では育てられないものもある。危険は承知でそれなりの装備もして、時折こうして季節の素材を採集にやってくる。「天狗」とやらに気をつけながら。
鬱蒼とした樹冠に覆われ、森の中は昼間でも薄暗い。道といっても獣道に近く、山の所有者が杭を打って綱を張ったラインを目印に歩くしかない。
足下では萩が育ちはじめている。秋になれば、そこかしこに赤い花が見られるようになるだろう。
不意に、強い風が木々のあいだを吹き抜けた。
「!」
舞い上がる枯葉や枝の屑が眼鏡にぶつかる。あわててそれらを払いのけ、顔を上げた新一郎はぎょっとして息をのんだ。
道から外れたところに、男が立っていた。
一瞬前は確実にいなかった。それ以前に、ここで他人と出会ったことなどない。いったいどこから……。
「こ……こんにちは」
新一郎はおそるおそる声をかける。
村に住む人間はだいたい知っているが、この男には覚えがない。一度でも見れば忘れないはずだ。
繊細ながら凛とした顔立ち、透けるような白い肌。危うい色香すら感じさせる、切れ長の瞳。
山の中だというのにそれらしい恰好もしていない。白い半袖の開襟シャツとスラックスは、どこか時代がかって古めかしく見える。
彼は藪の中に立ちつくし、じっと新一郎を見つめていた。
「あの……」
話しかけようとしたが言葉が出てこない。日が傾いて肌寒くなってきたというのに、服の下に汗が滲んだ。
「よそから来たね」
不意に青年が声を発した。赤い唇が開く様から、目が離せなかった。
「は、はい」
かなり年下であろう相手に、つい敬語になる。見覚えはないが、この土地の者にちがいない。
「ではわたしのことも知らないはずだ」
「すみません……よろしければ、お名前を伺ってもよろしいですか」
青年は少しためらうように目を伏せた。新一郎の足下で、萩の葉が揺れる。
「……萩緒、とでも」
超然的な雰囲気に飲まれながらも、新一郎は現実的な方向へと思考をめぐらせた。
身なりの良さから見ると、旧家の子息なのかもしれない。それにしてもこの尊大さは浮世離れしている。事情があって家から出られないでいるが、家の者の目を盗んで徘徊しているとか……それならば村まで連れ帰らなければならない、と手を差し伸べかけたとき。
彼はわずかに口角を上げた。ほんとうにかすかな、しかし見惚れて言葉を失うには充分すぎる妖艶さで。
「もっと、この地を知ってほしい」
「は……」
その言葉の意味を尋ねようとしたとき、ざあっと強い風が吹き過ぎる。
乱れた前髪に視界を遮られた一瞬ののち、青年の姿はなかった。
知人のつてをたどって、白鹿市のはずれにある小さな山村へ移住してきてから五年。
集落の大半は還暦過ぎの老人で、当時三十代半ばだった新一郎は「若者」として歓迎された。新一郎も村になじみたくて、あれこれと力仕事や行事を手伝った。大柄な体つきもあって、肉体労働はそれほど苦ではなかったから。言葉や文化の面で未だ距離を感じることは多いにしても、少なくとも表立って新一郎を拒む者は今のところいない。
子供や若者の数は二桁もいかないほどだから、あの青年は見たことがないと断言できる。野菜を持ってきてくれた隣の老人に尋ねてみたが心当たりがないという。
「天狗だろう。昔はよくそんな話があった」
冗談交じりでそう言った老人の言葉が妙に引っかかった。あの山に入るときにも聞かされたけれど、なにかの比喩程度に思っていた。
美しい鼻筋は通っていたが、外国人のように高いというわけではない。肌の色は赤みを感じない白だった。白い服が山伏の衣装と言われればこじつけられなくもないが、全体的にイメージがちがいすぎる。
「天狗か……」
その言葉が引っかかり、日用品を売っている小さな商店の老婆にも尋ねてみた。村に唯一の店だ。
ちょうど井戸端会議に花を咲かせていた老人たちも、口々に自分の知っている昔話を教えてくれた。たとえばこんな話だ。
何度橋をかけても流されてしまう流れの速い川に、橋を造るよう頼まれた大工がいた。大工が川辺で思案していたところ、天狗が現れて大工の命と引き換えに橋をかけてやると持ちかけた。ただし、天狗の名を言い当てれば命は助けてやると。大工は必死に天狗の名を当てようとしたがわからず、橋の完成と同時に命を落とした。
だがちがう結末も聞いた。
大工は山の中で天狗の子が歌っているのを聞いて、隠されていた名を知った。大工に名を呼ばれた天狗はその場で消えてしまい、二度と村に現れることはなかったという。
皆笑ってはいたが、「そんなものはいない」と否定する者がないのが奇妙だった。
しかし不思議と嘘くささは感じなかった。首都圏の住宅地で育った新一郎には、この村そのものが民話や神話の舞台だ。人でない存在が跋扈していても、あるいはすぐそばで暮らしていてもおかしくないと思えた。
山で採ってきた蔓の根が煮え立つ釜をかき混ぜながら、懸命にあの瞬間のことを思い出そうとする。
あまりに唐突で、そして刹那で、非現実的すぎて夢のようだった。実際に白昼夢だったのかもしれないと思う一方で、あれは現実だったと信じたい自分もいる。
釜の中では鮮やかな紫の汁が煮出されていく。この色をそのまま布に写しとることはできない。さまざまな工程や加工を経て、たいへんな遠回りの末にこの色の布ができるのだ。十年以上この仕事をやっていても、思いどおりの色をたやすく作り出すことはできない。
青年の白い肌が思い起こされた。彼にはこの紫より、もう少し赤みが強いほうが似合うだろう。彼が名乗った萩の花はまだ季節ではないが、萩よりも黄みがかった、紅に近い色……。
「茜だろうか」
ぼんやりと呟く。
それから半月ほど、新一郎は一心不乱に色を作りつづけた。
染めた布が乾いて、風にたなびいている。
布を竿から下ろそうとしたまま、新一郎は暫しその色に見入っていた。鮮やかな紅ではなく落ちついた紫でもない。心をざわつかせる、妖艶な赤。
だがこの色だろうか。薄れかける夢のような記憶を必死にたぐり寄せ、彼に似合う色を追い求めてきた。実際に見た色なら記憶し再現することはできる。しかし正解は彼に再び会うことでしか得られない。
「美しい色だ」
はっと顔を上げる。
庭の立木の陰に、白い服の青年が佇んでいた。まぎれもなく、山で出会った彼だ。門から入ってきたのではない、不意にそこへ現れたかのようだった。
「……ここの草木と土は、いい色を出します」
とっさにそんなことを答えていた。他では作れない、この土地が出した色なのだと伝えたかった。
「だからここへ移り住んだのか」
彼は新一郎のことを知っている。ぞくりと肌が粟立った。それは彼に認知してもらえたという歓喜だった。
青年は木陰から出て、新一郎のすぐそばまで歩いてきた。
からからになった喉の奥からなんとか声を絞り出す。
「村の人が、あなたを天狗だと言っていました」
青年は肩をすくめて笑みを浮かべる。
「皆、好きに呼ぶ」
こうやって向き合っているあいだにも、あのときのように消えてしまったら……。不安に駆られて衝動的に白い手を掴んでいた。彼はふり払うどころかわずかにも身を引かない。
「よかった……あなたはたしかにここにいるのですね」
「お望みならば、今すぐ消えよう」
新一郎の心などわかっているくせに。天狗には見えないが、魔性にはちがいない。
「……ずっとここにいてほしいと望んだら?」
彼は目を細めて微笑んだ。
「わたしに、この地のことを教えてくれないか」
「あなたのほうが詳しいのでは?」
戸惑いながら尋ねると、彼は静かに首を振る。
「人の営みについて知りたいのだ。この地で生きてきた者たちのことを」
「ぼくは、なにも知りません」
五年前に比べたら、日々の事柄にはかなり詳しくなっているとは思う。だが村人たちは口が達者なわけではない。こちらから尋ねて初めてわかる。
「山に天狗が棲むということも、知ったばかりなんですよ……」
掴まれた手の上に己の手を重ね、彼は息がかかるほどに近づいた。こちらをまっすぐ射抜く目には、有無を言わせぬ意志が感じられる。
「ならば、わたしに代わって調べてほしい」
「あなたが、望むなら……」
答えの代わりに、青年は紅い唇を押し当ててきた。
四.迷家【前篇】
運良く辿りついた者はもてなしを受ける。
編集部近くのアパートに、その老婆は住んでいる。
一人暮らしではなく孫が介護をしているようだ。圭悟は自分より若そうな男が、いつも笑顔で老婆の曲がった腰を支えて歩いているのを、引っ越してきてから何度も見た。
今日も彼は献身的に祖母の散歩につき合っているようだ、と川沿いの道をゆっくり歩いている二人を見ながら思う。
「なんで時雨さんまでついてくるんですか」
「天気がいいから、散歩でもと思って」
近くのスーパーに買い物に行くだけなのに、圭悟の下宿先に住みついてしまった妖怪かなにかわからない男は、あたりまえの顔をして隣を歩いている。
前から歩いてくる老婆は、皺だらけの顔に濃い化粧をしていた。薄い白髪頭もきちんと整えられ、足を引きずっていなければもう少し若く見えたかもしれない。
すれちがいざま、青年は圭悟と時雨に明るい笑顔を向けた。日に透けたふわふわの髪が揺れる。彼のさわやかさと、老婆が身にまとう少しきつめの香水とは、妙な齟齬があった。
「こんにちはぁ」
「……」
とっさに声が出なかった圭悟は、精いっぱいの反射として頭を下げた。それから時雨を見やる。彼は黙ってうなずいた。
「あの子……ぼく以外の人に見えてますか?」
「どうかな。孫と思ってる人もいるだろうし、彼女が一人でいると思ってる人もいるだろうね」
なにか人と見た目がちがうというわけではない。
圭悟自身もうまく言葉にできないのだが、外見でも匂いでも感触でもない、五感とは別の部分が、彼らを見分けてしまうのだ。今の青年は、時雨と同じ種類の存在だった。
ふり返って彼らを見送った時雨は、ぼんやり呟いた。
「五十年前は、だれの目にも夫婦に見えたのになあ」
「え……」
圭悟も遠ざかっていく彼らの背中を見つめる。
「あなたたちは……歳をとらないんですね」
「場合によるけど。彼女は、連れ合いが若いままでいることを望んだのかもしれないね」
厚化粧にきつい香水……。このあたりは繁華街も近いから、以前は夜の街で働いていたのかもしれない。
彼女はどんな思いで、人ではない者と連れ添っているのだろうか。
休日の夕暮れ、圭悟は時雨がいないのを確かめてから一人で出かけた。
車も自転車もないから、移動は徒歩かバスで行ける範囲に限られている。それでも実家から離れた町の中心地は、知らない場所がまだたくさんあった。
突き当たりの神社となにか関係があるのか、その飲み屋街の入り口には古く大きな鳥居が立っている。どこに入ると決めていたわけではないが、ふと古ぼけた看板が目についた。表に出ているメニューもなく、なぜ入ろうと思ったのか自分でもわからない。
身を寄せ合って建っている店のひとつの、狭い階段を上って二階。暖簾には「まよひが」と染め抜いてある。下にあった看板と同じ、これが店名にちがいない。
「いらっしゃい……」
無愛想な男の声が出迎えた。狭い空間をぐるりと見回す。店内は明るくもなく暗くもない。カウンター席と、小さなテーブル席が二つ。そっけない店なのに、テーブルは埋まっている。
店主にカウンター席を勧められて足を踏み出したとき、カウンターの端によく見知った長身がいるのを見つけた。
「また……」
「やあ、来ると思ってたよ」
手招きしてみせる時雨の、スツールをひとつ置いて隣に座る。
「ぼくがこの店に入ったのは、あなたの罠ですか」
時雨はいつもどおり目を細めて笑う。
「ちがうよ。ここは、きみが自分で見つけて入ってきたんだから。たまたまおれが常連客だったってだけ」
見上げるほどに背の高い店主が、長い腕でおしぼりを差し出してきた。
「めずらしいお客だと思ったら、時雨さんのお手つきとはね」
「え……」
目の前の相手をまじまじと見つめる。とても背が高くて一見スマートなのに、自分が言うのもなんだが冴えない風体の、ぼんやりした印象だった。わざと自分の輪郭をぼかしているような気さえする。
あわててふり向いた。テーブル席には苦み走った壮年の男と、ゆるふわOLといった感じの若い女がそれぞれ別の席に座っている。だがどちらも時雨と同種だとわかった。
つまり、人間は圭悟一人ということになる。
「ここ……妖怪酒場ですか?」
「なにそれ」
時雨が愉快そうに口を曲げた。
「皆さんも、人間じゃないんですよね」
違うことはわかるのだが、結局彼らが何者なのかは教えてもらっていないため、そんな言い方しかできない。
「時雨さん、彼……」
二人のやりとりを聞いていた店主が眉を上げた。
「うん、めずらしいでしょ。うちの圭悟くん」
居候しているのは時雨なのだから、「うちの」はおかしい。そう思いながら、メニューを探してあたりを見まわす。しかしそれらしいものは壁にもカウンターの上にもない。
「飲めるクチか?」
いきなりそんなことを尋ねられて驚く圭悟の横で、時雨が代わりに答える。
「圭悟くんはお酒強いよ。だから美味しい日本酒出してあげて」
「え、あっ、お願いします……」
「おう、ちょっと待ってな」
つい任せてしまったが、メニューのない店でいったいいくらかかるのだろう。そんな心配がよぎった圭悟の心を読んだかのように、店主は厨房へ向かいながら奇妙な言葉を残していった。
「代金なら気にすんな。人間はいくらでも飲み食いしていい」
「は!? それって無料ってことですか! なんで……」
思わず大きな声が出てしまったが、周りの「人でない者たち」は咎める気配もない。
店主が戻ってきて、圭悟の前にグラスを置いた。ラベルのない一升瓶から目の前で酒を注がれる。
「ど、どうも……」
背が高い上に少しも笑みを見せないから、かなり上から睨まれている気がする。縮こまっている圭悟に、時雨が横から声をかけた。
「彼、葉月くんね、人間をもてなすのが趣味なの」
そう紹介された男はきまり悪そうに首をさすり、また厨房へ引っ込んでしまった。
「料理も勝手に出てくるから、待ってるだけでいいんだよ」
「え……」
さすがに気味が悪くなった。時雨を危険だと思ったことはないものの、鬼とも呼ばれていたと自分で認めていたではないか。こういう場所に足を踏み入れた人間は、無事に帰れるものなのか……。
血の気が引いた圭悟の顔を見て、時雨が朗らかに笑った。
「怖いことでも考えてるんじゃない? 自分が酒の肴になるんじゃないか、とか」
「!」
時雨の言葉に、後ろの二人も声を上げて笑った。だが気まずさや恥ずかしさより、恐怖が先に立つ。
「いや、だって……」
時雨は手酌でビールを注ぎながら、店内をぐるりと見まわしてみせた。
「ここは、おれたちの寄り合い所でね。普通の人間は入り口も見えない。でもたまにこうして迷い込んでくる人間もいる。レアだから、思いっきりごちそうするのさ。下心なんかないよ。少なくとも葉月は、人間のお客さんが来るのを心待ちにしてるね」
「人間くさいんだよねえ、葉月はさ。世話焼きだし」
テーブル席の若い女性が、肩をすくめてカクテルを飲んでいる。
「そう言うなよ。この前、川に落とした靴拾ってもらったじゃないか」
「小梅頼んでないもん、葉月が勝手に拾ってきたんだもん」
見た目より幼いしゃべり方をする彼女からは、花の香りがする。
「聞こえてるぞ小梅ぇ」
不機嫌そうな声とともに、湯気の立ち上る料理が出てきた。葉月は客の前にそれぞれちがう器を置いていく。圭悟の前には黒塗りの重箱。
「え、鰻!?」
「好きなだけ食え」
高いところからそう言う葉月はあいかわらずぶっきらぼうだが、どうやらこの中ではいちばん親切らしい、と圭悟は口に出さず思う。
最後に食べたのは何歳の時だっただろう、と考えながら味わう鰻の蒲焼は、記憶よりもずっと美味かった。はじめに出された酒ともたしかに合う。
「……それで結局、あなたがたはどういう生き物なんですか」
酒も進んで少し気安い雰囲気になってきたところで、圭悟は時雨に尋ねてみる。しかし彼は肩をすくめただけだった。
「その土地に『在る』もの、としか言えないな。どこにでもいるよ。東京では会わなかった?」
「いえ……」
そういえば、出会った記憶がない。大学のキャンパスでも、オフィスビルの中にも、満員電車やスクランブル交差点でも。子供のころに「見えた」ことさえ忘れていたほどだ。
「おれたち的にも過密地域なんだけどな、あそこは。人が多すぎると遭遇する確率も下がるのかもなあ」
葉月が自分と圭悟のグラスに酒を注ぎながら首をかしげている。
「気づかなかっただけかも。顔を上げなきゃ、人もなにも目に入らないからね」
のんびり言う時雨の言葉は、なぜか圭悟の胸に刺さった。
たしかに、都会ではずっとうつむいていた気がする。周囲を見渡すのはなにかを探すときだけで、人の波は背景と化す。目に映る人間を全て認識してしまったら、きっと数分で心が疲れてしまうだろう。
「まあ大都会だと、普通にしてても人の中にまぎれちゃうんだろうけどさ。すごい田舎だとたまに見つかったりして、妖怪とか神さまとか言われるから、そういうことにしてるわけ」
「ほんとはちがうんですか」
「うん……人間と同じ見た目じゃないやつらもそこそこいるから、見当ちがいともかぎらないけど。あ、人間みたいな寿命はないね」
そういえば先日出会った「夫婦」も、歳のとり方が奇妙だった。きっと彼は青年のまま、彼女を看取るのだろう。
とすると、ここにいる面々も見た目どおりの歳ではないことになる。考え込む圭悟を横目に、時雨は厨房の奥へ「ビールもう一本」と声をかけた。
「見た目なんていくらでも変えられるからね」
時雨の言葉に、新しいビール瓶を持ってきた葉月も、栓を外しながらつけ加えた。
「初めの百年くらいは、人間みたいに年を経ていきたいんだよな。でも一度老人までいくと飽きる。そのあとは好き勝手だ」
では実際は皆何歳なのかと尋ねようとしたとき、戸が開いた。
「こんばんはぁ」
元気な挨拶とともに暖簾をくぐってきた客を見て、圭悟は目を見開く。あの老婆と暮らしている青年だった。
「あれ、時雨さん! この子って……」
圭悟のすぐ隣に座った彼は、にこにことこちらを覗き込んでくる。
「いいなあ、うちの奥さんここ入れないんだよなあ」
大学生くらいの若者が「奥さん」などと言うと違和感がある。しかもその相手は、祖母どころか曾祖母といっても通じるくらいの老婆なのだ。
圭悟を挟んで時雨が彼に声をかけた。
「雁夜、この前おれをスルーしたよね」
「挨拶したでしょ! だってこの子がいたから……」
見るからに年下の青年から「この子」などと呼ばれ、圭悟は少し複雑な気分になった。だが、彼も他の連中と同じだとすれば、年上というレベルではない。あの老婆との関係がそれを物語っている。
「ねえ、おれも飲みたい」
「奥から勝手に持ってこいよ」
「えー、今日入り口から来たじゃん、お客さんじゃん。出してよぉ」
「うっせえな……」
結局、葉月が酒を取りにいった。邪険にしているようにも見えるが、二人のやりとりにはどこか馴れ合った甘さのようなものがある。時雨はと見れば、そんな二人を薄い笑みで見守っているようだった。
酒も料理も絶品で、桜舘を連れてこられたらと何度も思った。食通の彼女のほうが、圭悟よりもこのもてなしにふさわしい気がする。だが、ここに入れる人間は一握りなのだ。
雁夜に絡まれながらもかなりの量を飲み食いし、葉月や周りの奇妙な人々に重ねて礼を言って店を出た。
くたびれた風体の男が、きょろきょろと見まわしながら歩いている。このあたりは店が建て込んでいて、目当ての店がどこにあったかすぐに見つけられないことも多いのだろう。
彼が「まよひが」の看板を通り過ぎるのを横目に、今出てきた店を見上げた。中ではまだあの連中が酒宴を開いている。
時雨は自分たちが土地に『在る』ものだと言った。土の中から這い出てきたのか、自然の中から発生したという意味合いなのか。彼の言葉を完全に理解したわけではない。今まで見てきた世界とは別の世界があると認識できたばかりだ。
「今夜はよく晴れてるねえ。月もないし、星がきれいに見える」
当然の顔で隣を歩いていた時雨が、夜空を見上げながら呟いた。うつむきかげんだった圭悟も、つられて顔を上げる。
久々に星を見た気がした。満点の……とまではいかないが、町中でも繁華街から少し離れればそれなりの星空が見える。
明るすぎて星も見えない大都会で何年も暮らすうち、星があったこと自体忘れてしまっていた。見上げて目を凝らせば見えたのかもしれない。時雨の仲間が人混みにまぎれているのも気づいたかもしれない。
見えるのと、見えないのと、どちらがまともな状態なのか今のところ判断が難しいけれど。
少なくとも「まよひが」の酒と料理は美味かった。

続きは『よすが雪月風花』でお楽しみください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
