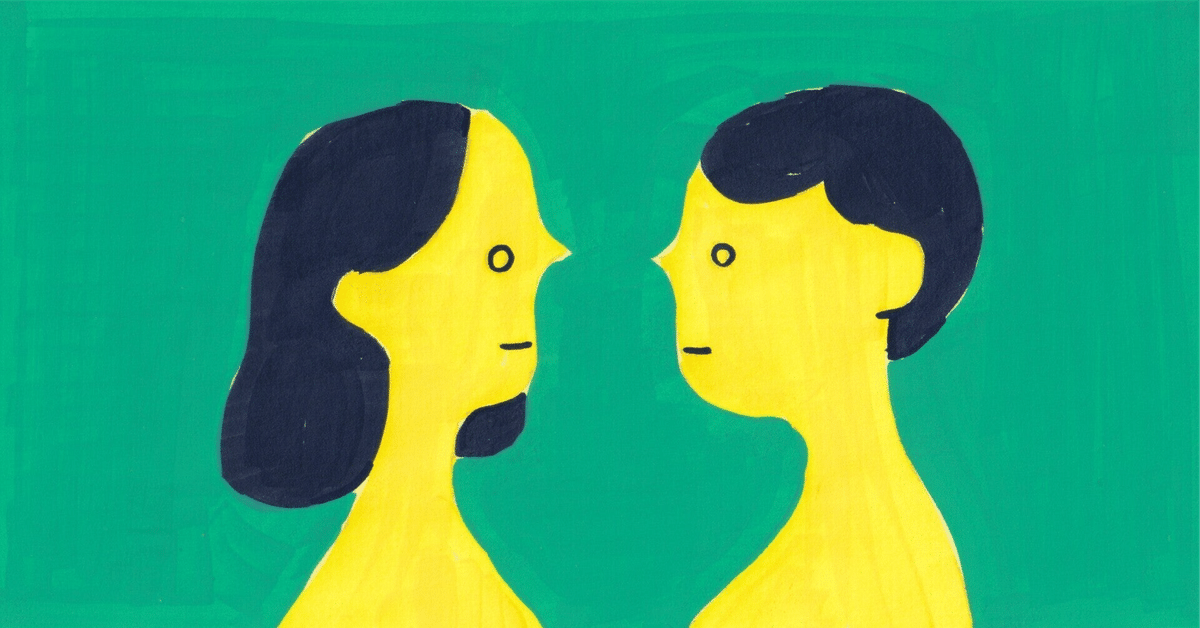
Photo by
noouchi
一人目が「男の子で良かった」と感じた自分に、酷くガッカリした話。
「股の間からチョンって飛び出てるでしょ、男の子ですね。」
担当医に言われながら目線をやった先のモニター越しに、確かに朧げながら小さな息子の息子を視認した。本当にこれが?と思うぐらいのサイズではあったのだが、よくよく聞いてみるとほぼ間違いないらしい。
青天の霹靂とまではいかなかったものの、これで我が子孫の身体上の性別が「男の子」だということが発覚した決定的瞬間であった。それは妊娠6ヶ月をすぎた、梅雨入り前の季節であった。
(男の子、か。)
どうにも全然実感が湧かなかった。わたしは診察台で横たわりながら、3秒ぐらい無言で固まった。そして程なくして反射的に「よかった」という心の声が脳内を走り抜けた。それは遅れてわたしの感情の中に、ドアの隙間から入り込む紙切れのようにスルリと入り込んできたように思えた。
そしてそれをちゃんと理解するまで、そこから10分ぐらいは有にかかったんじゃないかとも思う。診察室を出て、私は気が抜けたように椅子に座り込むと自分の中で湧き上がった感情の扱い方に戸惑っていた。
わたしは、確かに「一人目が男の子でよかった」と感じたのだ。
わたしは自分が描いていた自分の思考とその間に刻まれたあまりにも深い渓谷に橋をうまくかけることが出来ず、静かにひとり混乱をしていた。同時に、これほどまで「自分にガッカリした」のも随分と久しぶりのように思えた。
今日はそんな私の「一人目の性別」に対して反射的に感じてしまった「良い」という社会的圧力と「自己意識の境界線」について少し筆を取ろうと思う。
意識は自由だと思っていたのに
読んでいただいただけで十分なのですが、いただいたサポートでまた誰かのnoteをサポートしようと思います。 言葉にする楽しさ、気持ちよさがもっと広まりますように🙃

