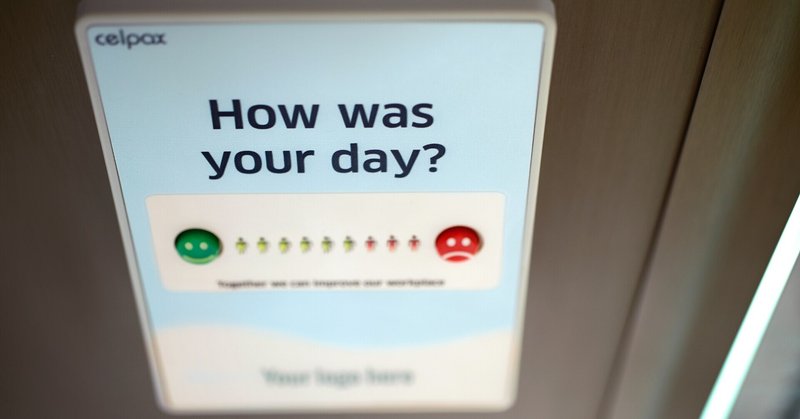
元サッカー選手がなぜか仕事ではそこそこうまくいった理由2つ
こんにちは。
プロサッカー選手としての3年間、私は全くと言っていいほど芽が出ませんでした。鳴かず飛ばずで引退後ビジネスの道に進んだのですが、そこではこの5年くらい、まあまあうまくいってるんじゃないかなと思うわけです。
もちろん私は成功者じゃありませんし、まだまだこれからも頑張っていかないといけない立場ですが、サッカー選手時代の地獄のような結果の出なさ、他者評価・自己評価ともに0で、自分に全く価値を感じられず誰かの役に立っている実感もこれっぽっちもない日々に比べれば、随分とましになったなと思っています。
ビジネスキャリアとしても、最初はセールスに始まり、マーケ・企画、業務改革やシステム改革など色々やって数社転職を繰り返し今はFobusなんちゃらとかFortuneなんちゃらのようなグローバル企業でなんとかやっていけてるので、まあアスリートのセカンドキャリアとしてはそんなに悪くないと言っていいのかなと。
そこで今回のnoteでは、からっきしダメだったサッカー選手時代に比べて何が変わったのか、なぜセカンドキャリアはサッカーと違いうまくいったのかを考えてみようと思います。
想定読者はいつもの通り10代後半から20代前半の若手サッカープレイヤー(プロ・アマ問わず)で、セカンドキャリアの一つの例として情報を得て欲しいというのはもちろん、なにかひとつでも現役のプレーに良い影響を与えるヒントになれば幸いといったところです。
私は仕事柄さまざまなクライアントや同僚・同業者と接する機会が多いですが、アスリートから転生して私のようなビジネスキャリアを積み重ねている人にはほとんど会ったことがありません(風の噂で似たような境遇の人がいるよと聞いたことは何度かある)。
なので、アスリート目線から見たビジネスキャリア、というところにこのnoteのバリューがあるのかなと思っています。
そもそも、何かを変えるべき?
サッカー選手の世界とビジネスの世界は全然違うし、求められる能力も環境も異なるのだから、そもそも何かを変えるべきなの?サッカーではだめだったかもしれないけど、そのままのやり方でビジネスでは通用するかもしれないじゃん。
はい。そうですね。ただ私の意見を言うとこの考えは明確に間違っています。確かにサッカー選手とビジネスの世界は違います。ものすごく簡略化して言うとサッカーがより肉体的な能力を問われるのに対し、ビジネスは相対的には肉体よりも頭脳や精神を問われる場面が色濃いので、求められる能力が違うというのはその通りです。
しかし、プロスポーツやビジネスなどのカオスかつ複雑な領域で未経験のことを0から始めようと思ったら、他の分野のやり方、しかもうまくいかなかったやり方をそのまま持ち込んでそれが機能するなんてことはほとんどありません。99.9%は何かしらの壁にぶつかるでしょう。あえてストレートに言ってしまうと、サッカー選手を引退した人というのは、多くの場合、壁にぶつかって最終的に解決できなかったから引退するのです(もちろん、チームの主力のまま、まだ現役選手としてプレーできるのに引退するという中村憲剛選手のような例も存在します。が、そのようなスペシャルな存在はほんの一握りです)。
自分の課題を解決できないままサッカー選手としてのキャリアを終えた人が、そのやり方をそのままビジネスに持ち込んですんなりうまくいくほど、ビジネスの世界は甘くはありません。サッカー選手が子供の頃から何十年も練習でスキルを磨いてきたのと同じように、ビジネスで一級線で活躍する人たちは、知的訓練を何十年も積み重ねてきているのです。まずここに対してリスペクトを持つことがセカンドキャリアの第一歩です。
よって、私の考えでは、サッカー選手時代に得たスキルアップの知見は自分の資産として持ちつつ、良くなかったことは何なのかを真摯に顧みて、変化するところは変化させていくのが、より成功に近づく心構えかなと思います。
ちなみに私はサッカー選手時代が完全にだめだったので、全くの失敗だったと逆にすべて切り捨てることができました。プライドもクソもなく、次のキャリアでは0ベースで積み上げていこうと思えたことが結果的には良かったのかもしれません(もちろんただの一個人の例なので、すべての人に当てはまるとは思いませんが)。自分が持っている資産のうち95%ぐらいを断捨離してしまって、5%の汎用的に使えるコア資産だけを次のステージにも連れて行くような感覚でした。
大事なところなのでもう少し詳しく書きますが、セカンドキャリアに進む際には一度自分という存在を0から曇りなく見つめてみるということが大切なように思います。
自分はどういう価値観を持っていて、成功のためにはどのようなアプローチを踏んでいたのか。そもそも自分にとっての成功とはなんだろうか。セカンドキャリアに何を望むのか。どうなりたいのか。あるいは、どうありたいのか。
そして、自分の核として変えないところは変えずに、変えた方がうまくいく可能性が上がりそうなところは大胆に変えていく、そんな柔軟な考え方が求められます。
自分を変えるなんて、今までの自分を否定するようで嫌だ。
よくわかります。でも自分が何を考えていてそれがどう結果に結びついたのか、分析できるのは自分だけなのです。どんなに優れたアナリストでも、チームのことは分析してくれても、あなた一個人の成功については分析してくれません。自分自身でやるしかないのです。
それに、自分のありのままを見つめることから目を背けていると、結局は何かの現象を通じて、自分が否定される局面を見ることになります。当然です。自分が自分を否定している状態に蓋をしているようなものですから。現象は何度でもやってきます。根本的な解決をするために、自分自身のありのままを洗い出すことは、相当な痛みを伴いますが必要だと思います。
むしろこれをちゃんとやったからこそ、ビジネスキャリアではそこそこうまく続いているのかなとも思うぐらい、この工程は非常に重要な意味を持ちます。気象シミュレーションで初期パラメータが0.1%違うだけで晴れになったり雨になったり現象が180度変わるように、新しいキャリアの動き始めに自分のエンジンをどう設定するかは、長きにわたって重要になってくるのです。
今までのサッカー選手人生を通じたアプローチやスタンスについて、変えられるところは変えた方がいいということはわかりました。では具体的に何を変えたのか。私は大きく2つありました。
①努力の方法が間違っていたから変えてみた
努力の方法。どんなに努力をしていても正しい方向を向いていないと意味がない、というのはよく言われることですね。でも具体的に正しい方向とは何なのでしょうか。私はわからなかったので、まずはサッカー選手時代、どういった努力をしてきたのかを考えました。
・居残り練習:シュート練習、パス練習、走り込み、ディフェンス練習、1 on 1、ヘディング練習、など。
・サッカー観戦:Jリーグや海外のサッカーを観戦し、戦術に対する考察やスタープレーヤーの良い面を盗む。
・読書:サッカーに活かせるように、様々なスポーツの成功者や起業家の本などを読む。サッカーの戦術に関する本も。
こうして見ると、やっていることそのものに何か大きな間違いがあるというものでもないように思えました。居残り練習は練習についていくのに必須だったし、海外のサッカー観戦や読書はピッチの練習では得られない視点や考え方をもたらしてくれました。
では何が足りていなかったか。こうやって文字にしてみるとより一層際立つのですが、まず努力の目標がきちんと定義されていない。そして、肝心のピッチ内での努力が足りないところを埋めるだけの練習になっており、他選手と差別化できる要素がない。この2点だと思いました。
努力する目標の定義は、回りくどいですが非常に大事です。これがないと、行き先がわからない船に乗っているようなものです。あえて言うなら、最初のうちは「試合に出ること」だったのが、日々の厳しい現実の中でいつの間にか、現役時代には気付いていませんでしたが「日々の練習で少しでも怒られないようになること」が目標になってしまっていた気がします。
目標を立てる時、ビジネス界には便利なフレームワークがあります。フレームワークとは考えを整理したり、ぱっとしたひらめきに説得力を持たせたり(笑)する際に使うものです。
目標設定のフレームワーク「SMART」
・具体的か(Specific)
・測定可能か(Measurable)
・達成可能か(Achievable)
・関連性があるか(Relevant)
・期限はあるか(Time-bound)
興味のある方はリンクから詳細を見て頂くとして、私のサッカー選手時代の努力目標は具体的か(Specific)、関連性があるか(Relevant)という観点で弱かったのかなと思います。
つまり、目標は「怒られないこと」という抽象的なものではなく「今年のX月までに少なくとも1試合に出る」とか「年間得点数10ゴール」とか、具体的に定義しないといけなかったし、自分が達成したいことに密接に関連づくものじゃないといけなかったのです。
目標を正確に定義することで、その後の解決策や打ち手も明確になります。目標が「怒られないこと」であれば、他のより怒られるプレイヤーがチームに新たに加入してしまえば目標達成となってしまい、本来望んでいた「試合で活躍すること」からかけ離れた方向に努力することになってしまいます。これが努力の方法が大事と言われる所以です。
目標をきちんと定義できていなかったので、打ち手が「もっと練習する」のような曖昧で主観的なものになってしまい、「もっと」の部分は自分の気分次第、モチベーション次第となってしまいました。
監督や先輩にきつく怒られたから練習量を増やす(ように見えるようにする)、いい本や考えに巡り会えた時だけモチベーションが上がり頑張る(ただし長続きしない)といったように。
整理すればわかるのですが、これでは努力の方法を間違えているとしか思えません。でも難しいのは、これでも本人は必死にやっているのです。必死に食らいつき、なんとか少しでも良い状況になろうと日々模索しているのです。何もわからずもがいているうちは、何にもがいているかにも気付けないのです。
あとからありのままを見つめて考えると頭の中はこうなっているのですが、当の本人は努力の方法を間違えているとは気付けません。なぜなら努力の方法が合っていようが間違っていようが、本人は苦しいからです。いやむしろ間違っている方が苦しくなるかもしれません。結果という精神安定剤を得られませんから。その分、「これだけ苦しいのだから俺は努力している」という罠に嵌りやすいのです。
これが現役を終えた後に自分のありのままを振り返った方が良い理由のひとつです。現役時代には見えなかったことを引退後はより俯瞰して見ることができるのです。
他方、ビジネスキャリアを歩む上では努力の方法をどのように変えたのか。
選手時代の反省を活かし、目標を正確に立てました。「今期締めの時点で売上XX円」「来年のこのタイミングで一階級上に昇進・昇格する」など。具体的で、測定可能で、自らが成し遂げたいことともしっかり合致するような目標としました。
そしてその目標に沿って、達成するには何をすればいいのか、具体的な行動まで落とし込みました。売上XX円ということは、成約数がXX件は必要。成約数XX件を得ようと思ったら、商談はXX件必要で、そのためには見込み客がXX件必要。見込み客を随時XX件抱えようと思うと、日々の訪問数をXX件にすればいい。
ここまで具体的にすれば、あとはそれに従ってやるだけなので迷いがなくなります。モチベーションに左右されることもない。やるだけですから。これをやるだけでも日々の苦しさは少し軽減されていきます。
また定性的な目標(昇進・昇格など)を立てた場合は、「何をしたら昇進できるのか?」という理想をまず定義し、理想と現実とのギャップを埋めていく作業を、やはり行動にまで落として考えました。
例えば、
・理想:大勢の前でプレゼンテーションができる
・現実:プレゼンテーションスキルがなく、経験もない
・打ち手:プレゼンテーションスキルを”資料作成スキル”と”スピーキングスキル”に分け、資料作成スキルは社内のおすすめ本を読みテンプレートをXX個作ってみる、スピーキングスキルは得意な先輩のプレゼンについていって良いところをメモして次のプレゼンで真似してみる。など。
さっきから差別化の観点が書かれてないじゃないかと思うかもしれませんが、ここまでやると量で差別化できます。適切な目標を立て、目標に従った行動をトライアンドエラーを繰り返しながら量をこなすことは、誰にでもできることではありません。
正しい目標を定義して量をこなすことで、特に奇抜な策を講じなくても差別化というものはできるのです。そうした過程で他の人より少し得意だなと感じる領域をより磨いていくと、今度は本当の意味での自分だけの武器、差別化ができるようになるのです。
もし私がサッカー選手をもう一度やるなら、この通りにやるだろうと思います。
具体的な目標を立て(例:7月末までに3試合に出場する)、そのために必要な行動に落とし込むため、策を練ります。
・どのポジションで出る?
→ボランチで出たい。ずっとやってきたポジション。
→今のフォーメーションは4-4-2。ボランチには絶対的中心のXXさんがいる。前年の監督の選手起用の傾向、今期の方針を考えるとXXさんはまず揺るがない。とするとその横のポジションを他の5人で争うことになる。
→チームにとっては、XXさんが自由にプレーしてもらうことが絶対に良い。XXさんはどのようなボランチがやりやすいと思うのか。本人に聞いてみよう。
→XXさんは圧倒的なテクニックを持つ一方、運動量はそこまで多くない。XXさんの運動量を補いつつ、守備面でも貢献し、攻撃面でもアタッカーの枚数となれるダイナモタイプが横にいると嬉しいのではないだろうか(仮定)。
→監督もXXさんをどう活かすか考えているに違いない。そうなればその横にいる自分をイメージさせれば使ってもらえる可能性は上がる。
→上下動の回数とボール奪取数。この数字でアピールしていこう。
→この数字を上げるため、自主トレは上下動を繰り返せる持久力と、ボール奪取確率を上げるための筋肉増加に費やそう。
→検証・改善・・・
ここまで行動に落とし込めると、自主トレが自発的なものになります。わからないところはどんどん他人に聞くようになります。XXさんとも頻繁にコミュニケーションをとり、良いところは何でも盗むようになります。
こうなれば勝ち筋が見えてきます。以前と比べると、シンプルで、練習が自分の向上にダイレクトに結びついているのがわかります。
②結果との向き合い方を変えてみた
先程は具体的な行動の話でしたが、今度はそれと同等か、もしかしたらそれより大事かもしれないマインドの話です。
サッカー選手時代の私は、毎日の結果に一喜一憂していました。練習でうまくいった日は喜び、紅白戦のメンバーから落ちては悲しみ、たまたまミニゲームで得点を決めれば喜び、メンバー外になって絶望し・・・。
そこには指針となるものがありませんでした。他人や世界から与えられる結果によって、自分が幸せかどうかを決めていました。怪我人が出てたまたまメンバーインしようが、結果が出ているのでそれでよしとするということですね。これでは永久に自分で自分を幸せにできません。結果の奴隷です。
この考えで最終的に結果を掴めればそれはそれで良かったのですが、残念ながら私は結果を掴めないまま引退しました。全てを懸けていたサッカー人生が失敗に終わりました。だからこの考えではうまくいかないんだなと思うようになりました。
結果は運の要素にも大きく左右されます。神様の気分次第で良い方にも悪い方にも転ぶので、コントロールできません。これに自分の幸せを委ねるのはどうも悪手だなと思いました。もちろん世間は結果で評価します。プロなのだから当たり前です。結果が全てです。これは事実で私がどう考えようが変わるものではありません。
でもだからこそ、結果が全てだからこそ、自分の心の中は過程を拠り所にしようと決めました。自分が100%を出せたかどうか。自らが決めた指針に従って行動できたかどうか。昨日の自分に少しでも勝てたかどうか。
この考えは楽なようで厳しくもあります。なにせラッキーパンチを許しません。誰かの怪我でメンバーインしても、自分の指針、100%を自分の中で越えられなければ自分の中では失敗になります。改善策を見つけないといけなくなります。ある意味、偶発的な結果に頼るよりシビアな世界です。
ただ、結果がコントロールできないのに対し、過程はコントロールできます。自分の自己ベストを更新するために頑張ることは、完全に自分ひとりだけによってコントロールすることが可能です。ここが大きな違いです。
だからこそ良かったときには素直に自分を褒められるし、ダメだったときには改善策を考えられるのです。全ては自分が”どうあるか”の範疇だからです。
結果を指標とした、”誰かとの比較”は、他人が勝手にやってくれます。自分は昨日の自分自身に勝てたかどうかだけを見ていればいいのです。自分が指針とした行動をちゃんと今日も守れたか、毎日チェックするだけでいいのです。
結果を無視して過程だけにフォーカスすれば、結果は出なくなるんじゃないの?
そう思いますよね。怖いですよね。でも考えてみてください。そうやって結果を拠り所にし続けて、結果を得ることができたでしょうか?私は結果に拘って拘ったけど、最後まで結果を得ることができませんでした。
引退というはっきりとした結果が出たから、この考えを手放すことができたのかもしれません。でも勇気を出して手放して、自分に勝つことだけにフォーカスしてみたら、いつしかあれだけ欲しがっていた結果があとからついてくるようになりました。
そこには少しのタイムラグがあります。過程を100%頑張る→結果が出るの間には少し待ち時間があるのです。
毎日毎日、自分で決めた指針に沿って昨日の自分より少しずつ向上していると、ある日突然、空が変わって小さな結果が出始めます。最初に気づくのは自分。あれ?少し前より良くなったのかも。まず自分が思います。
小さな成功をいくつか続けていると、次に身近な人が気付き始めます。最近なんか変わったよな。敏感な人は言ってくれたりもします。
そんなことが何個か重なり、それでも昨日の自分に勝つことを続けていると、ある日突然、大きな成果となって現れます。少し遠くにいた人が、成果に気付いて褒めてくれるようになります。自分としては毎日同じことをしているだけなのにです。これが「結果はあとからついてくる」の意味です。
サッカーで置き換えるとおそらくこんな感じになるでしょう。
・自分自身に勝つこと(自分で決めた指標を100%達成すること)を1ヶ月-6ヶ月ぐらい続ける
↓
・練習で得点やアシスト、タックルなどプレー面の結果が出る(が、自分しか気付いてない)
↓
・身近な先輩から変化を指摘される
↓
・少し上の先輩から変化を褒められる
↓
・監督から変化を褒められる
↓
・練習で得点やアシスト、タックルなどプレー面の結果が出る(みんながそれを指摘する)
↓
・メンバー選考に変化の兆しが見える
↓
・練習試合で結果が出る
↓
・メンバー選考に変化が出る
↓
・試合で結果が出る
私はサッカーで結果を出せなかった立場なのでイメージでしか言えませんが、おそらくこんな流れを辿るだろうと確信しています。ビジネスもサッカーも、結果が出るまでの過程の根本は変わらないからです。
まとめ
以上2つが、私がビジネスキャリアではそこそこうまくいっている理由です。
またいつうまくいかなくなるかもしれませんが、その時もやることは同じです。
自分はどうありたいかを定義して、現状の自分とのギャップを洗い出し、真摯に向かい合います。
そしてギャップを埋めるための行動を決めて、あとは毎日その指針に従い自分に打ち勝っていくだけ。なんでもそうです。
私は、サッカー人生に破れた自分自身の才能は信用していませんが、才能のない人間が生き残っていくためのこの方法論に関しては信頼しています。
若手アスリートがセカンドキャリアを考える上での一助になればと心から思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
