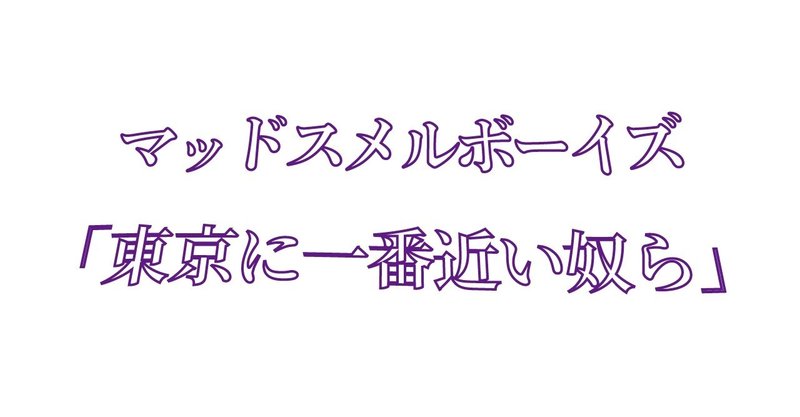
マッドスメルボーイズ「東京に一番近い奴ら」
千葉県松戸市、人々に平穏が訪れた頃、バボ、常習犯、イクター博士が集まった。ここは八柱霊園、東京に一番近い場所。
「始業式で3Pしようぜ」
芝生が広がる区画で3人は座り込んで話す。
「どうして始業式なんだよ」バボの提案に常習犯は笑いながら返す。
「始業式がつまらないからに決まってるじゃん」そう言うバボの目はニタニタしながらイクター博士を見ていた。
「また嫌な予感がするんだけど」イクター博士は言う。
「博士、大丈夫だって。それに気持ち良いから」
「気持ち良いのはバボだけじゃん」
イクター博士の言ってることは正しかった。だけどバボには口説き文句があった。
「俺にはお前らが必要なんだ。面白くなくちゃつまらないんだよ」
常習犯とイクター博士はやれやれと思いながら、バボから詳細を聴いた。
高田芳樹はイジられキャラだ。式になると後ろのやつがちょっかいを必ず出してくる。高田は校歌斉唱に伴う起立に乗じて後ろの奴にやり返そうとした。そのとき、ナニが目に入った。
ナニの持ち主は隣のクラスの安蒜だった。横目に入った安蒜の股間から相当のブツの持ち主であることを高田は察した。
高田の脳みそは安蒜のブツことでいっぱいになった。もしスクールカーストがブツの大きさで決まるなら橋川を抜いて一気にこの中学の頂点に躍り出るかもしれない。校歌なんてどうでもいい。もう一度、制服のズボン越しでも分かるあの大きさを確認したい。だけどあからさまに見つめたらヤバイやつだって思われるかもしれない。なら校歌が終わって座る時にチラッと見よう。それなら姿勢を変えようとしただけに思われるはずだ。早く拝ませてくれ。安蒜の大ブツを拝ませてくれ!
校歌が終わる。教頭の着席の声が響く。座ろうとしながら頭を下げて斜め後ろを覗く。
「え、」高田の頭は真っ白になった。股間の膨らみはそのままに腹までもが大きくなっていたからだ。「妊娠したのか......?」高田はまだ自分の知らない保健の領域があるのかもしれないと思いながら前を向いた。
始業式はその最もつまらない部分である校長先生の話にまで進行した。起立を強制するなら話を短くしろよと多くの生徒が考えている。下を向く者や爪をいじる者、かかとを踏むいたずらをする者、退屈のしのぎ方は人それぞれだ。ただ橋川定秀だけは目の前に広がる頭の海をじっと見ていた。
橋川はこの学年で一番背が高い。早熟な彼は小学校の修学旅行で股間を見られ「モジャンポ」というあだ名をつけられてしまった。そのあだ名は中学校でも使われ続け、そのうちに学校に行くのが嫌になり、遅刻が多くなった過去がある。
またいじられるのかと思いながら教室のドアを開ける日々。それを救ったのは安蒜だった。
「よう常習犯!!調子どうよ?」
橋川と安蒜は仲が良いわけではなかった。だが安蒜はクラス中に響くように話しかけてきた。
その定秀という名前と遅刻が多くなった自分に対して2つの意味がかかった常習犯というネーミングはモジャンポを上書きした。正直言って常習犯も最初は嫌だったが女の子の前でモジャンポと呼ばれるよりはマシだった。
その後、橋川は安蒜とその友人の生田と仲良くなり、互いを常習犯とバボ、イクター博士と呼ぶようになった。
イクター博士は周りを見ていた。みんながみんな、退屈な表情をしていた。バボも常習犯も自分を待っている。早くいかなくちゃいけないという焦りがイクター博士の呼吸を早くさせる。
「生田くん大丈夫?具合悪いの?」さっきまで退屈そうな表情をしていた早川さんが心配の表情で聞いてきた。
「大丈夫」イクター博士は心配の声に焦りながら答える。
保健室にいくのだけは駄目だ。ここで逝かなくちゃいけないんだ。バボと常習犯のためにも。そう思いながらイクター博士は斜め後ろに倒れた。校長の話はまだ中盤だったがイクター博士の倒れた音で中断された。
聞き慣れない人の倒れる音に全校生徒、全職員が注目した。ただバボと常習犯は違った。
バボは後ろを向き、膨らんだお腹からピンクのボールを取りだした。股間に忍ばせた空気入れで校歌斉唱中に膨らませたボールだ。目指すはバスケットゴール。その下で常習犯が待っている。
「これが俺の奇跡体験だ」
バボはボールを放った。
常習犯は自分をめがけて飛んでくるピンクのボールに笑みがこぼれた。
しかしピンクのボールの軌道が変わった。保健室へと先生を呼ぶために誰かが体育館の引き戸を開け、風が吹き込んだからだ。ボールはゴールと回収担当の常習犯から逸れ、バボのクラスの女子へと直撃した。
始業式での3Pは失敗に終わった。ボールが当たった女子が倒れるという事件も起こして。
放課後の校長室は校長室の匂いがする。バボと常習犯とイクター博士は二人がけ用のソファーに3人で座っていた。革張りの高級そうなソファーだが八柱霊園の芝生に比べると窮屈で居心地が悪い。
「どうしてあんなことをしたのですか?」
この校長の問にバボがなんて答えるかは常習犯とイクター博士は分かっていたし、その答えが大人を怒らせることも分かっていた。
「始業式がつまらないからです」バボは正直に答えた。
しかし校長は怒りもせずにただ対面のソファーから立ち上がり、何十年も前の校庭で全校生徒が校章の形に並んでいるところを空中から撮った写真の前に向かった。
「どうして始業式をやるかは知ってる?」こちらを向かずに校長は聞いてくる。
「慣習だからじゃないですか?」イクター博士が答えた。バボに答えさせると怒らなかった校長を逆撫でして怒られるような気がしたからだ。
「それもそうだけど、春休みで緩んだ気を引き締めて、事故なく学業に励んでもらうためだと先生は思います」
「僕たちはそんな事故を起こすほど馬鹿じゃないです」あきらかに先ほどを事故を起こしておきながらバボは言った。
「じゃあ小林さんが倒れたのは事故じゃないのかい?」バボの期待した答えが返ってきた。
「それは校長先生の話が長くて貧血を起こしてる時に、僕らのボールが当たっただけです。人に当たっても大丈夫なように柔らかいボールをちゃんと選びました。話が長い校長先生が悪いんじゃないですか?」
「安蒜くんの言いたいことは分かります。これからは座ったままで話を聞いてもらうようにしますし、なるべく話を短くもします。これが私の反省。でも、君たちも責任が取れないような結果を招くことはやるべきじゃなかったね。小林さんが後ろの人にもたれかかったから良かったけど、直に頭を床にぶつけてたら危なかったかもしれない。私だって命に関わることがあったら責任は取れない。だから今日のことは反省してるし、君たちも反省してほしい」
バボはばつが悪かった。喧嘩腰で受け答えをして責任を押し付けようとしたら、校長が自らの長話を反省した上でこちらを諭してきたからだ。大人を見せつけられたような気がした。
「実は私もここの中学生だったんだ」校長が突然語りだした。
「この空中写真には中学生だった頃の私が写っていてね。ちょっと探してみてよ」
三人は窮屈だったソファーから立ち上がり写真の前に移動した。校長の顔を何度か見つつ、くすんだ色のした写真の中から探そうとした。しかし、結構な高度から撮った写真では人の顔を判別するのは難しかった。
「分からないですね」常習犯が言った。
「ここにいるのが私なんだけど何か気づく?」校庭の上の方を指を指差す。正直、答えを示されても校長かは分からなかった。
「このときフルチンだったんだよ」
意外な告白に三人は固まった。確かによく見ると学ランの下に肌色がある。何も履いてないと言われれば履いてないように見える。
「どうしてそんなことしたんですか?」まるで立場が逆転したかのようにバボは質問した。
「つまらなかったのかなあ。忘れちゃった」
校長によるフルチン告白への動揺と校長は味方という安心を覚えながら三人は校長室を出た。もちろん向かう先は八柱霊園だった。
「まじでごめん」バボが二人に言った。声のトーンからバボが相当に凹んでいると二人は察した。
バボは始業式で3P作戦失敗と校長室でのやりとりから自らがまだ子供であることを実感したことが悔しかった。
「俺も結局はマツドなんだな」
マツドはバボの口癖だった。大抵は周りの人を馬鹿にするときに使っている。
「バボならトーキョーになれるって」常習犯が言う。
トーキョーもバボの口癖だった。大抵は面白い人を褒めるときに使っている。
「それにトーキョーになるためにここに来るんでしょ」イクター博士が続けた。
三人が八柱霊園に集まる理由は居心地の良さだけではなかった。八柱霊園は都立の霊園だった。マツド嫌いのバボはそこが気に入って八柱霊園を三人の拠点にしていた。
「そうだな。俺らがトーキョーに一番近くなくてどうすんだよ」
アスファルト、団地、住宅地を撫でた風が八柱霊園に吹いた。そのとき泥の臭いも知らない彼らからマッドスメルが漂った。
バボは次の作戦を考えた。
新作ボードゲーム製作中です。応援よろしくおねがいします。
