
YA「ハチミツレモン」(10月号)


後藤彩はさっきから何度も、一年A組の教室の時計を見ている。あと五分で、夕方の臨時ホームルームが終わる。教壇では、体育委員の児玉ヒカリが力説している。体育祭の目玉であるクラス対抗リレーで、優勝しようと。
彩はため息をつく。彩はジャンケンで負けて、リレーの選手になってしまったのだ。
体育祭まで、あと一週間だ。放課後の練習は、ヒカリが中心になって二週間前から始まっている。彩は一度も参加してない。帰宅部の彩は早く家に帰って、テレビを見たい。リレーの練習なんてしたくない。
「練習をさぼる人がいるので、まだ、リレーを走る順番すら決まりません。男子も女子もリレーの正式メンバー五人と補欠の二人は、正当な理由がない限り、必ず、自主練習に参加してください!」
ヒカリの演説に、アツイねぇと、野次がとぶ。
「当り前でしょ! この一年A組での体育祭は一生に一度しかないんだから。絶対、優勝したいじゃない!」
クラスメイトの反応は、うなずく声と、しらけたため息と半分半分だ。彩は深いため息をついた。運動会は、小学校のリレーで転んでから大嫌いになった。痛い思いをして頑張って、最後まで走ってもビリだった。
おまけに、膝小僧の傷は大きなカサブタになって、治るのに一カ月くらいかかった。もう誰も運動会の話題をしてないのに、彩の悲しい運動会はいつまでも胸の内にあった。
「正当な理由って、何だよ?」
一番前の席の天野が、珍しく発言した。
「運動部で試合前なら、自主レン免除で。文化部は参加で。塾に通っている人は、塾のない曜日には参加してください」
「それなら、オレは免除だな」
終業のチャイムと同時に、天野は野球部のスポーツバックをかついで立ち上がった。

彩は中腰のまま椅子を引いた。席替えのせいで、彩の席は窓側の一番すみの一番後ろだ。よりによって、出入口から最も離れている。昨日のようなことは、ごめんだ。
「あやっち、助けて! 自主レンに連れていかれちゃうー!」
森沢ヒナに声をかけられたのだ。
ヒナとは椿小学校以来の友だちだけど、なかよく自主レンに参加するなんていう思いは、彩にはない。最近、ヒナは、松浦小学校出身の向井さんたちとつるんでいることが多い。
助けてなんて言いながら、ヒナは笑っていた。日蔭で幅跳びの練習をするだけなのだから、さっさと連れていかれればいい、彩は心の中で毒づいた。
昨日は、スキを見て教室を抜け出す予定が、ヒナのせいでヒカリに気が付かれた。挙句の果てに校門まで追いかけられた。
彩は小太りだが、実は足は遅くない。全速力でダッシュして、長身でスリムなバレーボール部のヒカリから逃げた。
それでも、息は切れるは、汗まみれになった。今日こそ、こっそり教室を抜け出してのんびり帰りたい。
ところが、
「あやっち、頑張って逃げろ!」
思わぬ声援が飛んできた。
ヒナだ。
彩は舌打ちすると、教室のドアを飛び出した。
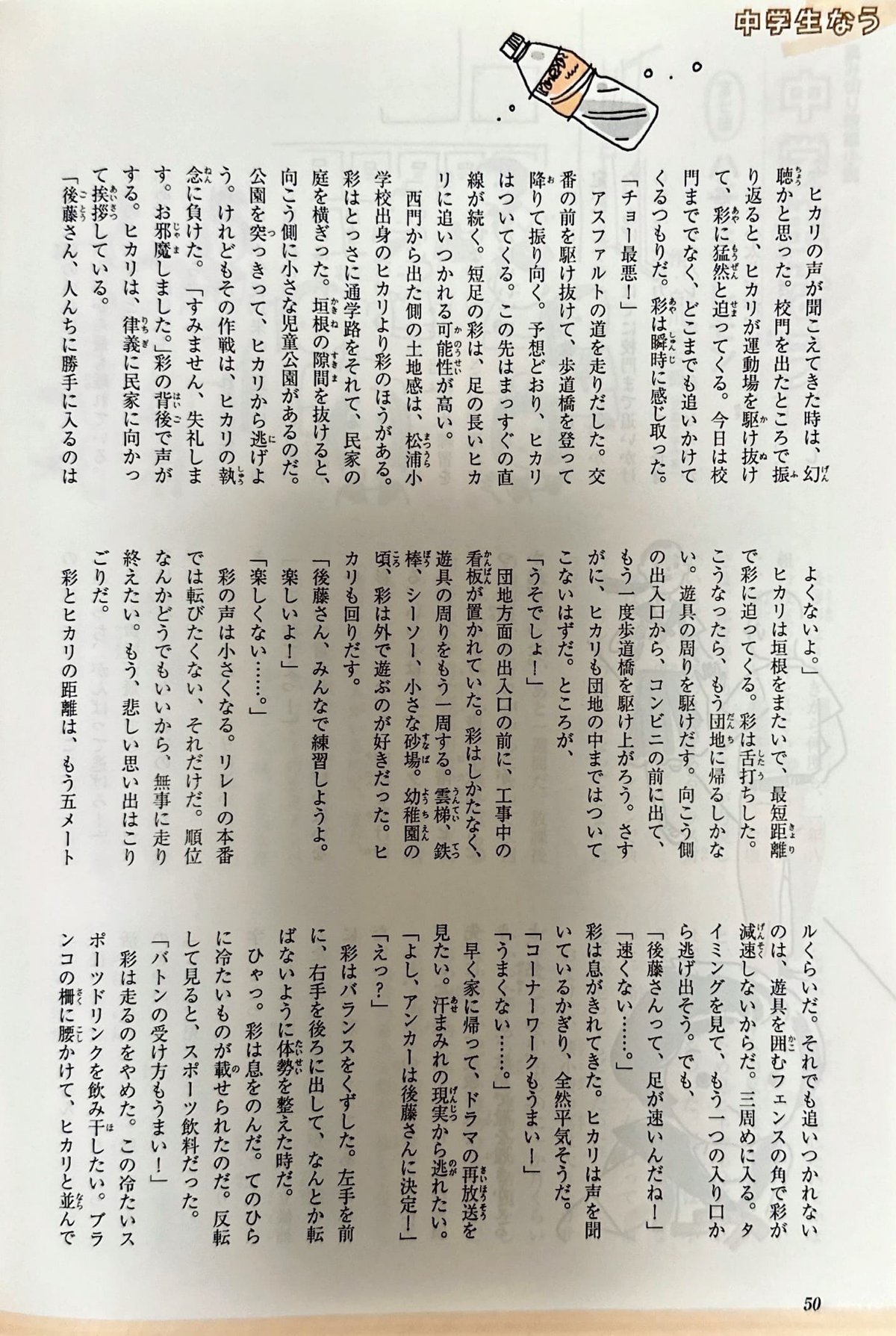
当然のように、ヒカリは追いかけてきた。
「待て、待てーっ!」
「待てって言われて、待つバカはいないよ」
彩はつぶやきながら、階段をかけ降りる。いつもはコンプレックスの短足が小回りに役立つ。昨日も、階段でヒカリとの差をあけて、一階の下駄箱でもたついて捕まりそうになって、なんとか加速して逃げた。
「こら、廊下を走るんじゃない!」
後ろから怒鳴り声がした。げっ。生活指導の鬼頭先生だ。一瞬、彩は走るのを止めようか迷ったが、
「こらーっ、児玉!」
鬼頭先生は、彩ではなく、ヒカリの名字をどなった。ヒカリは緑ヶ丘中学校の一年生で唯一、生徒会役員に立候補した。結果は落選だったが一躍有名になった。彩はクラスでもあまり目立たない。
ふと、ヒカリの気配がないことに気付いた。ふりむくと、ヒカリは鬼頭先生に捕まって説教されていた。ラッキー! 彩は下駄箱で靴を履きかえると、悠々と歩き出した。
ヒカリの声が聞こえてきたときは、幻聴かと思った。
校門を出た所で振り返ると、ヒカリが運動場を駆け抜けて、彩に猛然と迫ってくる。今日は、校門まででなく、どこまでも追いかけてくるつもりだ。彩は瞬時に感じ取ると、
「チョー最悪!」
アスファルトの道を走り出した。交番の前を駆け抜けて、歩道橋を登って降りてふりむく。予想通り、ヒカリはついてくる。この先は、真っ直ぐの直線が続く。短足の彩は、足の長いヒカリに追いつかれる可能性が高い。
西門から出た側の土地感は、松浦小学校出身のヒカリより彩の方がある。とっさに、彩は通学路をそれて、民家の庭を横切った。垣根のすきまを抜けると、向こう側に小さな児童公園があるのだ。
公園を突っ切って、ヒカリから逃げよう。けれども、その作戦は、ヒカリの執念に負けた。
「すみません、失礼します、お邪魔しました」
彩の背後で声がする。
ヒカリは律儀に民家に向かって挨拶している。
「後藤さん、ひとんちに勝手に入るのはよくないよ」
ヒカリは垣根をまたいで、最短距離で、彩に迫ってくる。
彩は舌打ちした。こうなったら、もう団地に帰るしかない。遊具の周りをかけだす。向こう側の出入口から、コンビニの前に出て、もう一度歩道橋をかけあがろう。
さすがに、ヒカリも団地の中まではついて来ないはずだ。ところが、
「ウソでしょ!」
団地方面の出入口の前に、工事中の看板が置かれていた。

彩は仕方なく、遊具の周りをもう一周する。
雲梯、鉄棒、シーソー、小さな砂場。幼稚園の頃、彩は外で遊ぶのが好きだった。
ヒカリも回り出す。
「後藤さん、みんなで練習しようよ。楽しいよ!」
「楽しくない……」
彩の声は小さくなる。リレーの本番では転びたくない、それだけだ。順位なんかどうでもいいから、無事に走り終えたい。もう、悲しい思い出はこりごりだ。
彩とヒカリの距離は、もう五メートルくらいだ。それでも、追いつかれないのは、遊具を囲むフェンスの角で、彩が減速しないからだ。三周目に入る。タイミングを見て、もう一つの入り口から逃げ出そう。
でも、
「後藤さんって、足が速いんだね!」
「速くない……」
彩は息が切れてきた。
ヒカリは声を聞いている限り、全然平気そうだ。
「コーナーワークも、うまい!」
「うまくない……」
早く家に帰って、ドラマの再放送を見たい。汗まみれの現実から逃れたい。
「よし、アンカーは後藤さんに決定!」
「えっ?」
彩はバランスを崩した。左手を前に、右手を後ろに出して、何とか転ばないように大勢を整えたときだ。
「ひゃっ!」
彩は息を飲んだ。手のひらに冷たい物がのせられたのだ。反転して、手のひらを見ると、スポーツ飲料だった。
「バトンの受け方もうまい!」
彩は走るのを止めた。
この冷たいスポーツドリンクを飲み干したい。ブランコの柵に腰かけて、ヒカリと並んでドリンクを飲む。おいしい。ちらっと、ヒカリを見ると、重そうなスポーツリュックを背負っていた。
「あきれた、そんな荷物しょって走ってたの?」
「だって、この方がトレーニングになるでしょ」
「トレーニング……って、まさか」
彩はヒカリの顔を見た。ヒカリはわざと、彩に追いつきそうで追いつかない距離を保っていたのだ。そして、彩を走らせていた。彩は知らない内に練習させられていたのだ。
ヒカリはリュックからタッパーを取り出した。
「うわっ、レモン!」
「おいしいよ、食べてみてよ」
ヒカリはフォークにレモンの蜂蜜漬けを刺すと、彩にさしだした。酸っぱくない? と疑いながらも、彩はレモンをかじってみた。おいしい。ヒカリは彩がレモンを食べ終わると、じゃあねと立ち上がった。
「明日からは、みんなで食べようよ」
彩の返事を待たずに、ヒカリは走って中学校に戻っていく。彩は親指についた蜂蜜をなめる。やっぱりおいしい。
ヒカリが褒めてくれた言葉を思い出す。足が速い。コーナーワークがうまい。バトンの受け方がうまい。それから、練習の後に、みんなと一緒に、蜂蜜レモンをかじる自分を想像してみた。
おいしいかな?
彩は一人、ブランコに乗ってこぎはじめた。正面からぶつかる風が気持ちいい。優勝の後の蜂蜜レモン。どんな味だろう。想像すると、悲しい思い出は小さくなって、ちょっとだけわくわくしてきた。
#YA #小説 #短編小説 #教育雑誌 #言霊さん #言霊屋
〜創作日記〜
私は幼い頃は運動会が好きではありませんでした。それは順位がつくからです。でも、背が伸びて、ストライド大きくなり、中長距離走が得意になると運動会や体育会が好きになりました。嫌いと好きと、両方の思い出があるのは嬉しいです。
新人さんからベテランさんまで年齢問わず、また、イラストから写真、動画、ジャンルを問わずいろいろと「コラボ」して作品を創ってみたいです。私は主に「言葉」でしか対価を頂いたことしかありませんが、私のスキルとあなたのスキルをかけ合わせて生まれた作品が、誰かの生きる力になりますように。
