
YA【春までなんぼ】(3月号)


明日から春休みだというのに、荒谷翔はため息ばかりついている。
終業式が終わってもだらだらと教室に居残っているのは、二年B組の仲間と、クラス替えを惜しんでいる訳ではない。一分でも長く教室にいたいからだ。
翔の家は団地で、両親と姉の夏樹と四人暮らしだ。いや、四人暮らしだったと、過去形にするべきかもしれない。姉は第一希望の芸大に合格して、来月、東京の大学の女子寮に入ることが決まっている。
今まさに、引っ越しの準備の真っ最中だ。
これまでは、六畳の部屋を天井から一枚のカーテンで仕切って、無理やり二人部屋にしていた。その部屋から姉の荷物が消える。
お調子者の翔は、姉の前では飛び跳ねて喜んでみせた。
「やった、オレだけの部屋だ!」
「よかったわね」
姉の返事はそっけなかった。
黙々とダンボール箱に荷物を詰めていた。ダンボール箱の宛名は二ケ所ある。一ケ所は大学の寮、そして、もう一ケ所は母親の実家の関西だ。
翔もすぐ必要でない物を実家に送るよう、母に言われた。
両親が離婚する。
その事実は翔の知らない所で決まっていて、晩御飯のミートスパゲッティーを食べている時に知らされた。口の中いっぱいにほおばった麺を、翔は上手く飲み込めずに激しくむせた。
姉は黙ってテーブルを離れた。
父親は家にいなかった。それは別に珍しいことではなかった。トラック運転手の父は車中や会社の寮に泊まることが多く、たまに家に戻ってきても、日中は布団を敷いて寝ていることがほとんどだった。
六畳の両親の部屋を、母は父の仮眠部屋と呼んで、あまり近づこうとしなかった。
母が仮眠部屋へ入らないのは、寝ている父を起こさない為だと、翔は思い込んでいた。
けれども、実状は違っていたみたいだ。
「お母さん、そんなところで寝ていたら風邪をひくよ」
姉はそう言って、よく居間のソファーで眠る母に毛布をかけていた。
「お母さん、また痩せたよね?」
と姉に尋ねられても、翔は、そっかあ? としか答えられなかった。
翔の目には、母親は毎日、フツウにご飯を作って、掃除、洗濯をしているように見えた。
それに、両親は激しい喧嘩をする訳でもなかった。
昨日まで、両親の離婚という事実は、翔には実感すらなかった。
けれども、姉の荷物より先に父親の荷物が運び出されて、仮眠室は空っぽになった。
開け放たれた襖の前で、しばらくの間、翔は動けなかった。
消えたのは父と、父の荷物だけではない。そこにあった何かが、確かにすっぽり消えて無くなっていた。

学校から帰ると、翔は家のチャイムを押した。
専業主婦の母は、いつだって家にいて内側から鍵を開けてくれる。
ビーッ!
もう一度、チャイムを押す。あれっ? 家に人がいる気配がしない。仕方なく、翔は鞄から鍵を出してドアを開けた。
「ただいま、母さん? あっ、手紙……」
台所のテーブルの上に白い便箋と、五百円玉が置いてあった。
「夏樹と買い物へ出かけます。帰りが遅くなるので、おかずを買うなり作るなりしてください。ご飯は炊飯器にあります。母より」
翔は便箋を読み上げた。それから、五百円玉をつまんで、顔の前に放り投げてキャッチした。好きな物を買って食べられるのに嬉しくない。
鞄を置きに自分の部屋へ入ると、しきりに使用していた黄緑色のカーテンが取り払われていた。
「広いなぁ……」
思わず、翔はつぶやいていた。
これまで狭いと文句を言っていたのに、姉の荷物が箱の中にまとめられただけで、部屋はがらんどうに見えた。なんだか居心地が悪い。
翔は鞄を置くと、そのままUターンして外へ飛び出した。
団地の階段を小走りでかけ降りながら、昨夜の母の言葉を思い出していた。
「ここ愛知でも、関西でも、好きな高校に行きなさい。お姉ちゃんもお父さんも別々で暮らすことになったから。あんたと二人ならどこへでもすぐに引越しできるよ。できれば公立だと家計が助かるけど」
母はそう付け加えて、少し笑った。
翔は漠然と、地元の公立高校への進学を希望している。普通科で今の自分の成績で無理なく入学できる高校だと、自ずと候補は絞られた。もちろん、地元以外の高校への進学など考えたことはない。
選択肢が広がったなんて受け止められない。みんなと同じような進路でいいと安易に考えていた。
翔は、突然、空にでも放り出された気持ちだ。将来の夢だとか目標だとか、空を飛ぶ為のエネルギーを持たないまま。
足元を見つめて階段を降りていた翔の目の前に人影が現れた。避ける間もなく、
ドスン!
踊り場で人とぶつかってしまった。
「いってぇ……、あっ、ご、ごめん!」
尻もちをついていたのは、クラスメイトで団地の同じ棟に住む三浦里緒奈だった。
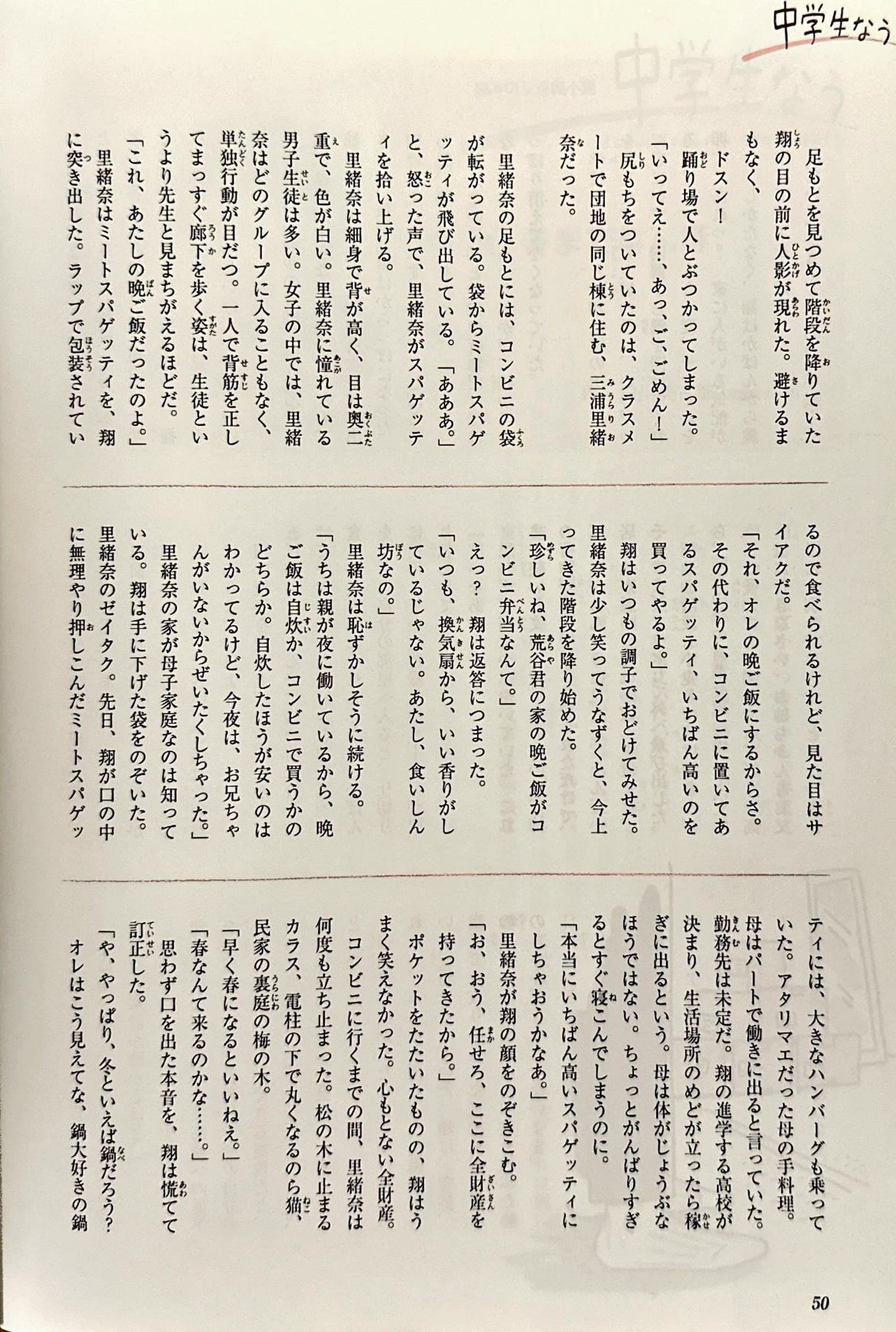
里緒奈の足元にはコンビニの袋が転がっている。袋からミートスパゲッティーが飛び出している。
「あーあ」
怒った声で、里緒奈がスパゲッティーを拾い上げる。
里緒奈は細身で背が高く、目は奥二重で、色が白い。里緒奈に憧れている男子生徒は多い。
女子の中では、里緒奈はどのグループに入ることもなく、単独行動が目立つ。一人で背筋を正して真っ直ぐ廊下を歩く姿は、生徒と言うより先生と見間違えるほどだ。
「これ、あたしの晩御飯だったのよ」
里緒奈はミートスパゲッティーを、翔に突き出した。ラップで包装されているので食べられるけれど、見た目はサイアクだ。
「それ、オレの晩御飯にするからさ。その代わりに、コンビニに置いてあるスパゲッティー、全部、買ってやるよ」
翔はいつもの調子でおどけてみせた。
里緒奈は少し笑って頷くと、今登って来た階段を降り始めた。
「珍しいね、荒谷君の家の晩御飯がコンビニ弁当なんて」
「えっ?」
翔は返答に詰まった。
「いつも、換気扇から、いい香りがしているじゃない。あたし食いしん坊なの」
里緒奈は恥ずかしそうに続ける。
「うちは親が夜に働いているから、晩御飯は自炊か、コンビニで買うかのどちらか。自炊した方が安いのはわかってるけど、今夜は、お兄ちゃんがいないから贅沢しちゃった」
里緒奈の家が母子家庭なのは知っている。
翔は手に下げた袋を覗いた。
里緒奈のゼイタク。
先日、翔が口の中に無理やり押し込んだミートスパゲッティーには、大きなハンバーグも乗っていた。
アタリマエだった母の手料理。
母はパートで働きに出ると言っていた。
勤務先はまだ未定だ。翔の進学する高校が決まり、生活場所の目処が立ったら稼ぎに出るという。母は体が丈夫な方ではない。ちょっと頑張り過ぎるとすぐ寝込んでしまうのに。

「本当に一番高いスパゲッティーにしちゃおうかなぁ」
里緒奈が翔の顔を覗き込む。
「お、おう、任せろ、ここに全財産を持ってきたから」
ポケットを叩いたものの、翔は上手く笑えなかった。
心もとない全財産。
コンビニに行くまでの間、里緒奈は何度も立ち止まった。松の木にとまるカラス、電柱の下で丸くなる野良猫、民家の裏庭の梅の木。
「早く春になるといいねぇ」
「春なんて来るのかな……」
思わず口を出た本音を、翔は慌てて訂正した。
「や、やっぱり、冬と言えば鍋だろう? オレはこう見えてな、鍋大好きの鍋将軍なんだよ。でかい土鍋に白菜をどばーっと入れて、牛肉をどかーんと乗せて、うどんを無理やり突っ込んで食う! これが上手いんだなぁ」
里緒奈は笑い出した。
「ぜんぜん鍋将軍じゃないじゃない。鍋の将軍様は、野菜をどばーっとか、お肉をどかーんとか、ましてや、最初におうどんを入れないわよ。のびちゃうじゃない。でも、いいよね、お鍋って。みんなで囲むと温かいもの」
歩き出した里緒奈に、翔は遅れた。
荒谷家では、もう二度と家族四人で土鍋を囲むことはない。鍋将軍というのは嘘だけど、鍋大好きというのは本当だ。
父が家にいると、母はよく鍋の用意してくれた。しめの雑炊は父が作ってくれた。
「荒谷くん?」
里緒奈が驚いた顔で、翔を見ている。
顔の前に白いハンカチを差し出されて、翔は自分の涙に気が付いた。
「お、おれ、花粉症でさ……」
里緒奈は黙って頷いた。それから、コンビニでたっぷり時間をかけて、スパゲッティーを選んだ。
里緒奈が選んだのは、やっぱりミートスパゲッティーだった。
別れ際に、里緒奈は翔に約束してくれた。
「今度、激安のスーパーを教えてあげるね。ちょっと遠いから自転車で行こう」
こくんと、翔は頷いた。
帰り道、また梅の木の前を通った。里緒奈の視線の先に、翔も目をやった。硬い蕾がいくつも付いている。春になったら蕾は開く。何色の花が咲くのだろう。春まであとどのくらいだろう。
〜創作日記〜
離婚に巻き込まれる子供が減りますように。
新人さんからベテランさんまで年齢問わず、また、イラストから写真、動画、ジャンルを問わずいろいろと「コラボ」して作品を創ってみたいです。私は主に「言葉」でしか対価を頂いたことしかありませんが、私のスキルとあなたのスキルをかけ合わせて生まれた作品が、誰かの生きる力になりますように。
