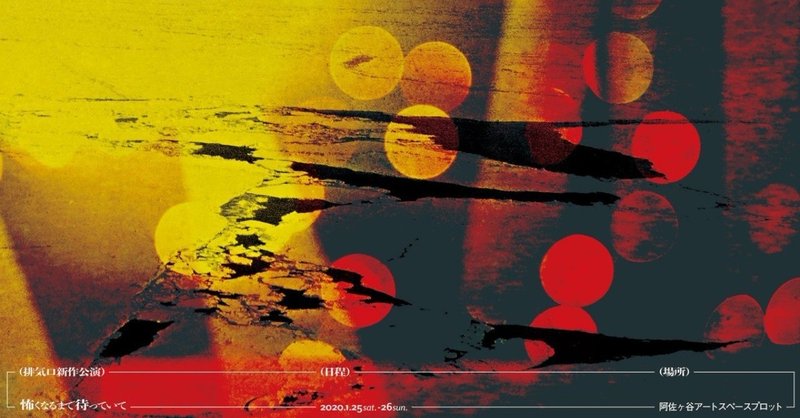
排気口『怖くなるまで待っていて』
1月26日(日)13:00~ @阿佐ヶ谷アートスペースプロット
初めて来た劇場。受付がレトロな感じで好きだった。
排気口という劇団の『怖くなるまで待っていて』を観た。
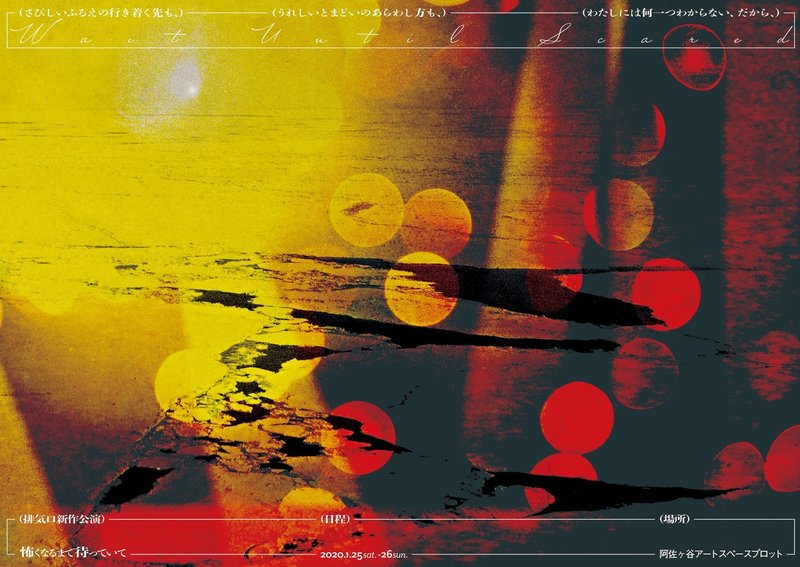
フライヤーの雰囲気からはちょっと取っ付きにくそうな印象も受けるけど、全然そんなことはなかった。
大学の学園祭を舞台にした青春群像
<大学のゼミの生徒たちが学園祭の出し物としてお化け屋敷の準備をする>というのが本作の基本的な設定。
前半では、ゼミの学生たち・文化祭実行委員、ゼミ長の父母・ゼミOGの女性・謎の女などが入り乱れながら、テンポ良いコメディシーンが続く。
コメディのテイストはナンセンスなものもあれば、ワーディングで笑わせるもの、フリオチがしっかりしたものまで結構バリエーションが豊かで、めちゃくちゃ笑ってしまった。
そんな感じで時間は過ぎていくのだが、肝心の物語はなかなか進展しない、話の中心が見えてこない。
やがて、物語の冒頭で示唆された「ある学生が殺された」という噂話を発端に、劇の焦点は登場人物たちの葛藤へと当たっていく。この劇がストーリー展開よりも人物の関係性や内的な感情に重きを置いていることに気づく。
この辺りの焦点の切り替えがとても上手くて、自然と彼らの内面へと気持ちが移っていった。
この演劇は、人のつながりの「始まり」と「終わり」を描いた凄くピュアな青春群像なんだと思う。
つながりの「始まり」と「終わり」
劇中ではいくつもの人間関係の終始が描かれていた。
・両親の離婚を控えている家族
・別れた大学生カップル
・ゼミの仲間に加わろうとする女
・大学の教授に実らない恋をするゼミのOG
・お化け?の女性に一目惚れをする男
と、それぞれに切なかったりするのだけど、特に印象的だったのはゼミ長の両親の離婚のエピソードだろうか。
夫と箱根旅行に行くために新しく買った高性能のスマートフォン。箱根旅行はなくなって、手元に残ったスマートフォンがマナーモードにできなかったり。
夫と息子に他人行儀な態度をとったかと思えば、「他人になる練習をしている」と口走ったり。
彼女の行動がいちいち悲しくて可笑しくて、表面的には笑える構図なのだけど、一方で凄くかき乱された。
そこまでドラマチックではないが、手触り感が凄くあったのは別れた大学生カップルの話。
家に残った彼女の荷物を早く片付けて欲しいと彼氏が主張している。でも彼女はなかなか取りに行かない。
これで「彼女側が別れを告げられた彼氏に対して未練がある」とかならよくあるドラマって感じだけれど、振ったのは彼女の方で彼氏も困惑しているとか、そういうディティールがいちいち冴えていて心にズバズバと入ってくる。
繋がりの終わりの後に、再び始まりを持ってきてくれているのも素敵で、家族の別れを体験したゼミ長は、文化祭実行委員と恋人(?)になったりする。
つながりを求める
この劇がピュアだな、と思ったのは、「繋がりが欲しい」「でも一方で失うのが怖い」と言う凄く真っ当な、人間的な欲求をちゃんと表現していると思ったからだ。
ゼミの人たちとは無関係な<女>が出てくる。役名もそのまま<女>だ。三森麻美さんという方が演じていて、これが超はまっていて最高だった。序盤は「ゼミのメンバーとは一切無関係なのになぜかいる」という不条理ギャグ要員として機能しているが、後半はキーマンになる。
ゼミの仲間になるために、お化け屋敷のシフトに入ると主張する<女>。その時に言い放った「シフトって居場所じゃん」が個人的には名言過ぎた。
<女>はゼミの仲間になって、そこで初めて名前をつけられる。
名前と呪いの話
「あそこに花が咲いているであろう。あれに人が”藤”と名を付けて、みながそう呼ぶようになる。すると、それは”藤の花”になるのだ。それが最も身近な”呪 ”だ」
(夢枕獏『陰陽師』より)
名前というのは、もっとも短い「呪い」だという話がある。
名前というのはだいたい親からつけられていて、そこには親の「期待」が入っている。
あだ名とかも同じで、ゼミでだけ通用するあだ名、会社で、クラスで、サークルで通用するあだ名には、その場所に応じた期待やキャラクターが反映されていて、それが時には呪いみたいに自分を縛り付けたりもする。
「ひとめぼれは一つの目で見てるから、ちゃんともう一つの目で見ないといけない」というようなセリフがあった。
これも本当にいい言葉。劇中に登場した<一度被ったら取り外すと爆発する「一つ目小僧」の被り物>と重なりながら、凄く多層的な捉え方ができる言葉だった。
選挙の場でダルマに一つ目を入れて当選を祈願して、成就したらもう一つの目を入れるという風習がある。
一目惚れというのも、案外「呪い」的な要素があったりするのかもな、と思った。
阿部共実を思い出す
作品のテイスト・テーマ性は、漫画家の阿部共実作品を連想させた。
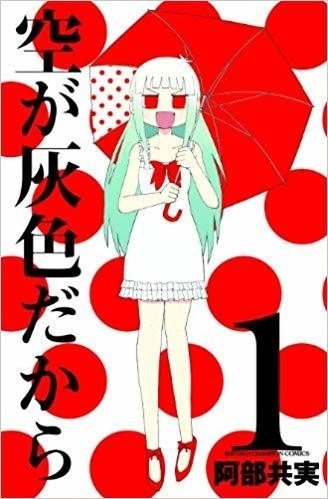
ポップでコメディテイストで、キャラキャラしくって青春で、それで結構人間の本質的な問題を堂々と机に上げてくる感じ。
メイドのメルちゃんの「自分より可愛いOGを見るとゲロを吐く」なんてまさに阿部共実作品に出てきそうな話じゃないかと思った。笑
繋がりが欲しい、繋がるから怖い、そんなピュアな感情を、不条理なコメディを織り交ぜながら提示するスタンスがとても好みだった。
役者のこと
役者の力は大きかった!
メル役を演じていた久芳晴香さんは以前に、どろんこプロレスという劇団の「パーティーに誘われて」という芝居で拝見したことがある。今作もとても凄くて「ぶりっ子の演技を貫きながら、ぶりっ子の奥にある人間性を見せる」という離れ業をやっていた。
ゼミ長の父を演じるケンタウロス骨さんもちょっとサイコパスな父親がとてもよくて、目が印象的だった。
実行委員会のププ井を演じていた東雲しのさんはキャラクタライズされた世界観に的確に馴染んでいて実際にはあまりいないけど脳内にはいるクラスの女子でしかなかった。
OG役のはぎわら水雨子さん、僕自身社会人だから「そうそう」と同意する部分と「いや、それはそうとは限らないんじゃ」と反論できる部分と、すごい等身大の造形で共感度は一番高かった。
群像ものは役者の力が大事なんじゃないかと思うけれど、みんなそれぞれの方向に尖っていて見応えがあった。
脚本・演出の菊池穂波さんはてっきり女性かと思っていたけど、男性みたい。noteの記事が面白い。
インプットの多さがアウトプットの引き出しを作るんだろう。
誰かと観たかった
この芝居は一人で観たが、誰かと観ればよかったと思った。
お互いに感じたこと。
誰に共感したとか、あのセリフどう思ったかとか、誰が嫌いだったとか、どのエピソードがあるあるだよねとか、可愛かったとか、かっこよかったとか、そういう話をしたくなった。
それを通じてなんかすごい距離が近くなれるような、そういう芝居だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
