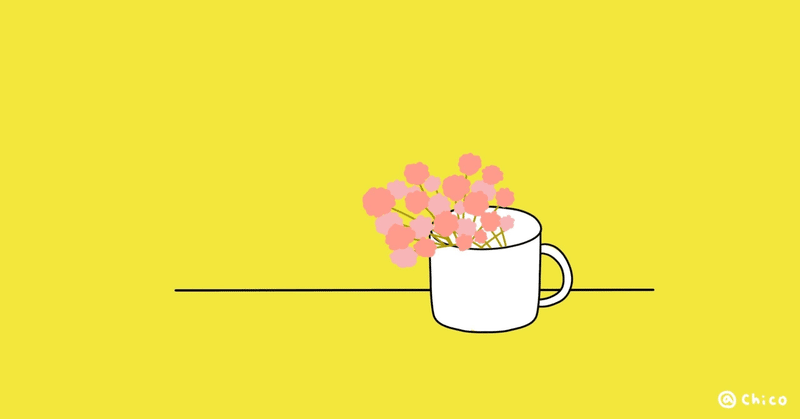
命名センスからの解放かな?
年末に図書館で借りて、返却期限が迫ってきた「すごいタイトル㊙️法則」を駆け足で読みました。この本から、現業でのプロジェクト名やサービス名を馴染みやすく、印象深い命名センスのヒントを得たいと読んでみました。
「自分にはセンスない」と思っていたことが、「できそう」と思える気づきを得られました。
この本から学んだこと
いろいろ法則が紹介されていましたが、マスコミで利用された「タイトル」を売上や視聴率という結果から”正解”を導き出すような内容でした。
そして、法則はあれども、最終的には目で見て、口に出して、耳で聞いて、理解できるか、誇張し過ぎていないかをチェックする必要があるとのこと。
学んだことからの解釈
表面的に読んだだけだと、今のビジネスにそのまま適用できなさそう・・・と思いました。
しかし、この本で得た知識を実践するとしたら・・・と考えると2点が思いつきました。
略称で呼ばれるとヒットする
1つがやらないこと。法則の1つに略称で呼ばれることがあります。キムタク、プレバトなど、略称で呼ばれると親しみが沸き、ヒットするという法則です。
現在担当している業務内に複数のサービスがありますが、略称としてアルファベットの頭文字をピックアップしたものが多いです。しかし、このアルファベットだけの略称は覚えられない・・・
この略称で呼ばれると親しみが湧くには、略称から正式名称や内容が想起される前提があるように思います。私の業務で呼ばれているアルファベットだけの略称では、もとのサービス名が何か”復元”できず、覚えられない、どういうサービスかわからない、親しみを持てないという状態になっています。
この”何のサービスかわからない”というのは、名詞として機能していません。なので、このアルファベットだけの略称は使うべきではないと思いました。
言葉を編み出す
もう1点の気づき。現在担当しているプロジェクト内の取り組みに名前をつけたらどうなるかを考えていました。そう考えてみると、お客様にどのように見てほしいかを考える必要が感じられました。
すると、ある業務経験を思い出しました。
それは英語のマニュアルから日本語に訳す作業。パワーポイントで表現が限られる英語の内容を和訳する業務がありました。この限られた表現を直訳するといまいち意味が通らないときがあり、解釈を踏まえた日本語を当てていました。
お客さまに理解しやすく、印象に残りやすい言葉を選ぶ、という意味では、キャッチーな名前をつけることと和訳することは同じなのではないか、と思えました。
やってみたいこと
タイトルやプロジェクト名をつけることは、「私にはセンスないわ〜」と思っていました。一方で、マニュアルからの和訳は、私にとっては「楽しい」と思える作業でした。この2つがリンクしたことで、名前をつける作業を楽しんでできるのではないか??と自分に期待を持つことができました。
和訳と命名の違いは、事前に伝えたい意味合いが定義されているかという点だと思います。和訳はスタート時点で伝えたい意味合いは定義されているので適切な日本語を選んでいきます。そして、命名の場合は伝えたい意味合いを定義するところから始めます。何を伝えたいのかを絞るのが難しいんですね。
まずは、社内向けに現在担当している取り組みについて、何をコアメッセージとして共有したいか定義して、名前をつけてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
