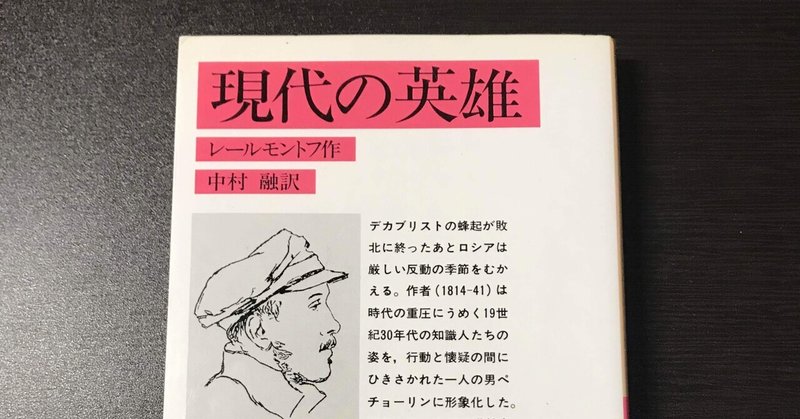
書評:レールモントフ『現代の英雄』
ロシア文学における英雄とは?
0.雑談
たまにはくだらないことから書き始めることをお許し願いたい。
「英雄」と聞くと、皆様はどんな人物像を思い浮かべるだろうか。具体的な歴史上の人物において英雄と謳われることが多いのは、ナポレオンではないかと思う。
ナポレオンと言えば、ある界隈では、男性のシンボルが非常に短小だったという伝説が、鬼の首を取ったかのように語られることがある。妻や死体を確認した医師の証言も残っているのだそうな。
ナポレオンを覇道へと走らせた原動力はシンボルのコンプレックスだったのでは?などという、如何にもナポレオンの英雄性にコンプレックスを抱く精神的短小の男性諸氏、および私を含む精神的さくらんボーイの男性諸氏が作り上げていそうな説(≒勝手なイメージ)すらあるのだ。
ナポレオンクラスの英雄になると、良くも悪くもシンボルのことまで語り継がれてしまうというのは、何だか複雑である(←何が?)。
対して、シンボルの立派さが語り継がれる人物の例としては、日本の道鏡が挙げられるだろう。風呂場で椅子に座るとシンボルが床に届くレベルだったとも言われており、平時のサイズ感としてはもののけの域だと言えよう。流石は日本三悪人の1人である。
※日本史における「悪人」には明確な定義があり、時の天皇に反逆した人物がこれに当たる。
他の2人は、平将門と足利尊氏である。
※足利尊氏は「KING王的泣ける小説No.2」の吉川英治『私本太平記』の主人公の1人でもあり、個人的には複雑だ(←だから何が?).
1.本題
さて、あまりにデリカシーを欠いた小学生男子並みの下ネタから話を転じ、今回ご紹介するロシア文学は、レールモントフ『現代の英雄』。
主人公ペチョーリンは、自他ともに認める非凡さを有する青年。しかしその非凡さ故に、彼を満たすものは世の中に存在しないという考えを抱いており、やり場のない厭世感が彼を苦しめている。
本作の解説によると、彼は抑圧された時代に屈服してしまった一青年の代表的な存在として描かれたものだとのことです。
だが、私は少し異なる捉え方をした。
きっと誰しもが、自分は何かしらにおいて特別な存在であり、ペチョーリンのように達観して生きていく才能もあるに違いないと望む心理はあるのではないかと思う。特に青年期はそうした意識が強くてもおかしいことではないだろう。過大な自己評価、ボヴァリズムも、働き方次第では生きる活力となるであろうし、こうした自身の「非凡さ」を望む心理はそう特別な意識ではないと言えるだろう。
ならば当然、多くの人にとってはいつしか自分が「凡庸」であることに気付き、それを受け入れざるを得なくなる時が来る。これはそれまで生きる活力の源泉であった自己評価を毀損しかねない認識の転回であるため、多くの場合このタイミングにおいてこそ「非凡な精神力」が求められるのだ。
この「自己受容」というテーマは古今東西問わず本当に多くの作品のテーマとして取り扱われており、私がこれまでに紹介した範囲でもいくつもそれはあった。
私なりの読書の経験と、中年に至るまでの私自身の経験から言えることは、人との繋がり、絆がある人ほど「勇気ある自己認識」に踏み出すことができるように思う。
ペチョーリンのような厭世観はある種の致し方なさや、場合によっては潔さ・カッコよさまで感じてしまうかもしないが、厭世という麻薬に毒され続けてしまうと、人との交わり・絆からどんどん離れてしまい、いつしか後戻りできなくなってしまう。そしてその先の変化の可能性は失われてしまいかねない。
主人公ペチョーリンを指して『現代の英雄』とは、なかなかにして皮肉の効いたタイトルだと思わずにはいられないものだ。
読了難易度:★★☆☆☆
一周回って今っぽい度:★★★☆☆
中二的には軽く憧れる度:★★★★☆
トータルオススメ度:★★★☆☆
#KING王 #読書好きな人と繋がりたい#本好きな人と繋がりたい#読書#読書感想#読書記録#レビュー#書評#書籍紹介#本紹介#海外文学#ロシア文学#レールモントフ#現代の英雄
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
