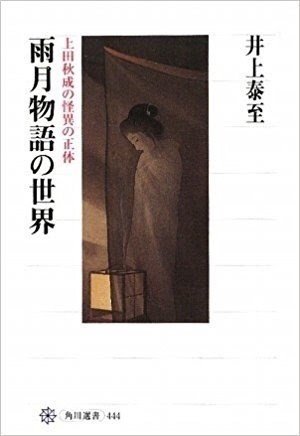皮肉たっぷりな上田秋成の『雨月物語』
上田秋成の名作『雨月物語』。怨霊やお化けや魔王が出るというのは知っているけれど、どんな話なのかはよく知らなかったので、『雨月物語の世界』を読んでみることにした。ただのホラー小説なのか、探求してみる。
◆9篇の怪異小説
そもそも雨月物語は、上田秋成によって安永5年(1776年)に刊行された読本(よみほん)のこと。日本や中国の古典を模した怪異小説9篇から成っている。以下、9篇の概略である。
□ 白峯(しらみね)
僧侶・西行が崇徳上皇の亡霊と論争する話。保元の乱がメインテーマ。
□ 菊花の約(きつかのちぎり)
戦国時代の出雲(島根県)、約束の契りを結んだ義兄弟の幽霊の話。
□ 浅茅が宿(あさぢがやど)
室町時代後期、戦乱に向かった男が幽霊となって妻に会う話。
□ 夢応の鯉魚(むおうのりぎよ)
平安時代中期、昏睡状態にある僧侶が夢の中で鯉になって泳ぎまわる話。
□ 仏法僧(ぶつぽふそう)
江戸時代初期、怨霊となった豊臣秀次の切腹の話。
□ 吉備津の釜(きびつのかま)
色好みの夫に浮気され、裏切られた妻が、夫を祟り殺す話。
□ 蛇性の婬(じやせいのいん)
男が蛇の化身である女につきまとわれるが、最後は僧侶に退治される話。
□ 青頭巾(あをづきん)
室町時代後期、鬼と化した僧侶を旅の僧である禅師が解脱へと導く話。
□ 貧福論(ひんぷくろん)
豊臣政権下、金銭の精が小人の翁となって現れ、金とそれを使う主人との関係を説く話。
なんだかお化けが大活躍の物語ばかり。とにかく怨み辛みのオンパレードである。なんで、秋成はこんな物語を書いたのだろうか?
◆徳川体制の正当化としての雨月物語
これらは実は、中世の戦乱から終焉というおおまかな時代設定で編集されている。戦国時代が家康の登場でピリオドを打ち、平和な時代がやってきた、という流れなのだ。つまり、「徳川体制の正当化」という意図もあった言われている。そんな裏テーマがあるらしいのである。
雨月物語が「保元の乱」から始まっているというのも、この戦乱が天皇・貴族の力を衰えさせ、武士の時代・戦乱の時代に入っていった、という時代区分の意識があったからかもしれない、と著者は分析している。さらに最後の「貧福論」では、豊臣秀吉の晩年、徳川家康の天下を予言する言葉で締めくくられている。上田秋成は体制への目配せをしながら、『雨月物語』を描いていたのだ。しかし、これが徳川体制を全面支持しているからかどうかは、上田秋成の人物像を知ると、その正体が見えてくるらしい。
◆風刺作家としての上田秋成
33歳のとき上田秋成は小説家としてデビューする。処女作『世間妾形気』を刊行後、翌年に『諸道聴耳世間狙』、さらに翌年に『雨月物語』の序文を書くまでになる。作家としての特徴としては、世相への風刺や、噂のあった人物を戯画化して描く点にある。
たとえば、『世間妾形気』では、当時の風聞(ゴシップ)として有名だった悪女・お梶を題材にしている。お梶は、鴻池などの複数の豪商の愛人ともなり、諸芸に通じ、贅沢三昧は並外れたものだったという。それを秋成は、かぐや姫のイメージを借りながら物語を構築している。「梶」の葉は七夕に飾る、という伝統から連想し、かぐや姫が渡る「橋」の連想から、主人公の名前は「お橋」という名前にされている。お橋のわがまま具合は、かぐや姫が求婚者たちに投げかける難題「火鼠の皮衣」ならぬ、「火鼠の蒲団」をねだるほど。
さらに、後半では小野小町の伝説を利用し、小町の謡曲や歌を踏まえたような文章が散りばめられる。連想的に古典の文学を引用しながら、古典の用語を捻じ曲げることで、読者の笑いを誘う。こうした秋成の古典へのこだわりは、次第に国学への興味に向かって行くことになる。『雨月物語』にも万葉集からの引用がそこかしこに見られるのもそのせいだ。
◆闇と平和
「仏法僧」の逸話では、戦国の世に散っていった豊臣秀次の霊が登場する。これは、太平の裏には強い怨念を抱き続ける〈闇〉があるということを示している。この〈闇〉の世界への恐怖は、逆に〈平和〉が一種の罪悪感に近いものであることを思い起こさせる。つまり、現在の平和がいくつもの争いと死の上に成り立っているということを思い出させるのだ。
現代でいうと、夏になると戦争映画を放映するのと同じようなもので、平和は戦乱の上に成り立っている。ここから、秋成はいわゆる「正史」が、本当に正しい歴史なのかということに疑問を持ち続けたとも考えられる。その裏側に隠された〈闇〉にこそ目を向けさせたかったのかもしれない。
さらに、「白峯」にも「菊花の約」にも「浅茅が宿」にも共通するのは、主人公たちのどうしてもすれ違ってしまう心の悲劇だと著者はいう。各編のテーマは、政治、友情、夫婦とそれぞれ異なるが、秋成にとっては「心の一致は可能か」という点に集約される。そこに、『雨月物語』を単なるホラー小説にはくくれない理由があるという。なぜそのことにばかり執着したのかは明らかではないが、秋成自身の孤独と薄幸が作用しているかもしれないと著者は想像する。親に捨てらた過去、指の不具など、一般の人よりも孤独の感情が強かったのかもしれない。
◆もどきの語り口
本書には第六章「もどきの語り口」という章がある。秋成はどんな「もどき」を使っていたのだろるか。
たとえば「白峯」では、『太平記』などの軍書でしばしばみられるような話法を使い、他の作品でも、すでに歴史叙述としては権威を失っている話型などを、あえて戦略的に借り、あからさまな虚構の中に学者としての史観を盛り込んでいた。この筆法は、後続の歴史小説(=読本)に受け継がれていく。
「蛇性の婬」ではロマンチックな恋物語の展開を、表層では展開しつつ、そうした物語から生まれる愛の倒錯性を浮かび上がらせている。禅師が鬼を解脱に導く「青頭巾」は、一見寺社の神秘的で宗教的な功験を伝えているように見えて、「語り」によって虚構を展開し、僧侶の偽信心を明らかにしている。そこには現世仏教への批判が隠されているという。
このように、あまりに皮肉な毒が効いた文体によって、雨月物語は書かれていたのである。物語のフィクションにもアイロニカルな視線を導入し、さらには「語り口」すら軍記や恋物語や仏教をもどいて、メタ物語を構築していた。このことこそ、上田秋成を唯一無二の作家にしているのである。
◆上田秋成の「歴史もどき」
上田秋成の晩年の作に『春雨物語』がある。その冒頭の短編小説「血かたびら」は「薬子の変」を扱ったものだ。薬子の変とは、平安朝前期、皇位を降りて奈良に移った平城天皇が、不倫関係にあった妖姫・藤原薬子や兄仲成らとともに、京の朝廷に反旗をひるがえし、結果朝廷に敗れて、平城天皇は落飾、仲成は殺され、薬子は自ら毒をあおって亡くなったというものである。平城天皇の陰謀による一連の謀反だ。
しかし、秋成の解釈は全く異なるものだった。
一般的には平城天皇は知略に長け、猜疑心が強く、政敵を死に貶めるような人物とされていた。しかし、「血かたびら」では、知性や理性に疎く、薬子らに押されるかたちで、本意ではなく朝廷と対立する状況に流される存在として描かれているのだ。それは「善柔にして消極的」とも表現される。
秋成は「血かたびら」で歴史叙述の「もどき」を行ったと著者は言う。当時の歴史叙述の方法を踏襲しつつ、「虚」を描くことで、正史をもどいていたのだ。では、何をもどいていたのか?
それは、欲と力にまみれた正史へのアイロニーだったと著者は見抜く。平城天皇の性格を「善柔」に設定することで、欲と力の政治の世界に翻弄される平城天皇がより浮き上がってくる。そうすると読者は、政治の世界が偽善に満ちた粉飾と、善をも悪として描く「欲」と「力」の世界のなせる業なのだと実感せざるを得なくなるのである。秋成の皮肉と毒舌の極みである。
◆天皇とフィクション
雨月物語にも春雨物語にも「天皇」がしばしば登場する。日本を統べる天皇がどんな怨霊になったのかを描いている。これにはどういう意味があるのだろうか?
そもそも、天皇が現実の権力をもたず、なおその権威を得るには、宗教的伝統に裏打ちされた連綿たる皇統とその伝統を回復・保持していく必要がある。そこで、和学や国学は、「儀礼」に関心を向け、先例を求めて「史書」を調査する。「正史」を探っていくのだ。本居宣長が『古事記伝』などで探求したのは、まさにこれだった。
ところが、その史書を秋成は「欲と力を粉飾する側面をもつ」とした。平城天皇が翻弄されたような、ドロドロとした政局がそこにはある。そんなところに秋成は天皇の本性を求めようとはしなかった。そうではなく、あえて理想の世を幻視すしようとしたのだ。それが平城天皇の「善柔」につながっていく。秋成にとって、理想の天皇とは「政治的に無力」な善なる人物であったのだ。ここには賀茂真淵の理想「直き」も踏襲されている。
これは秋成だけの理想ではない。近松浄瑠璃でも理想の天皇は、「弱く欠点があるとしても、どこか犯しがたい清さ、透明さを具えた人格」として造形され、「善であり、理想につながるものをもつが、権力や体制とは別の存在」として描かれている。
同じように天皇のルーツを探ろうとした本居宣長は、「史」の神話について独自の神学を打ち立てた。一方の秋成は、あくまで虚構として、虚構の中に「古代」を描いたのだ。二人は実際に、当時論争を起こしており、「日の神論争」と呼ばれている。
秋成は「あえて」政治の世界、国学の世界を脱落した。脱落を演じるが故に、「物語」のフィクションにもアイロニカルな視線を導入し、「正史」を批判していたのだ。その皮肉たっぷりな手法こそが、上田秋成の真骨頂なのだった。
ただのホラー小説だと思っていたのに、『雨月物語』は日本の正史さえも揺るがすほどの、アイロニカルな問題作だった。こんな奇書を読まないなんて、だいぶ損しているかもしれない。せっかくなので、そんな奇書を現代のミステリーの名手・円城塔が訳した『雨月物語』を読んでみるしかない。ということで、池澤夏樹監修の日本文学全集を買うしかない!
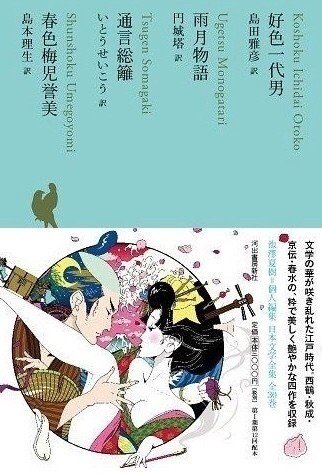
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?