
コカ・コーラ12年の経験から導きだしたビジネスに失敗する人の10の法則の裏側を「未来を実装する」と「世界標準の経営理論」で考えてみた
「ビジネス名著大全」という、ビジネス名著90冊を厳選し、1冊6ページくらいでまとめてくれている、ありがたい本があります。それを横暴にもさらにスライド1枚にまとめてみました。第三章 失敗・危機・衰退の四冊目は「ビジネスで失敗する人の10の法則/ドナルド R キーオ」です。
1枚まとめと学び

「ビジネスで失敗する人の10の法則」です。経営者でなくともビジネスパーソン全般に共通する内容だな、とおもいました。
3, 8などは職位が上がっていくと現れてくる課題ですね。4のように自分は判断ミスをしないと、成功しているほど思い、自分の考えに反対したり、意見するものを遠ざけるようになると、3, 4が現れそうです。そうすると自ずと柔軟性はなくなり2になりそう。
1と10は関係してるように感じます。将来を恐れるからこそ、リスクを取れない。ある程度のリスクを取らないと、なかなかうまくいかなくなり、思いつきのアイデアに走り出し、9のようにメッセージの一貫性が失われそうです。また、思い付きのアイデアを従順に遂行してくれる、専門家やコンサルタントに依存するようになり、7も発現してきそうです。また、思いついたことを自ら実行するというよりも人を使うのに慣れてしまい6のように自分で考えることが少なくなってしまうのではないでしょうか。
そうこうして、追い詰められてくると、ときとして5のように倫理観を失い、反則すれすれの戦いに足を踏み出してしまうのではないでしょうか?
つまりは、これは箇条書きの個別の項目として眺めるよりも以下のように、システム図で捉える必要があるんだな、というのが大きな気付きでした。

これは「勝って兜の緒を締めよ」ってことだな、と思うとあまりに短絡的なんですよね。じゃあ、どうすればいいんだろうな、と。私は2つのヒントを得ました。
一つは、「未来を実装する」です。もう一つは「世界標準の経営理論」です。「未来を実装する」の中で、先進国のような成熟社会では、なかなか大きな課題・ニーズがないが、それは、高い理想を掲げることでつくりだすことができるとしています。つまり、以下のよいな数式が成り立つと。

これは、つまり、成功した、なんて思えないくらい高い理想をぶち上げるということなんだろうな、と思いました。例えば、Google社のミッションは同社のページに書いてある通り
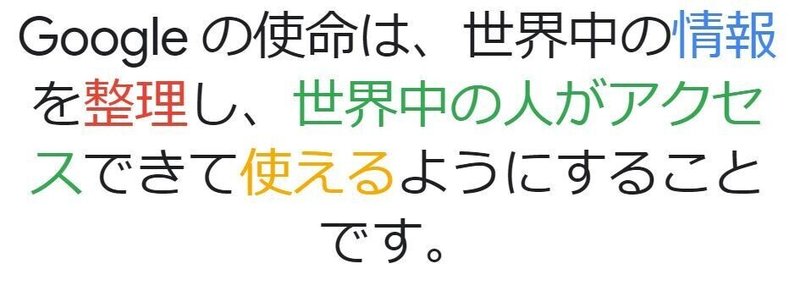
これは、終わりのない理想なので、成功して慢心することを抑制する力をもっていると思います。
さて、もう一つのヒントといった「世界標準の経営理論」からは、組織意思決定の循環プロセスを取り上げます。これは、先ほどの「未来を実装する」で紹介した、高い理想を掲げることの大切さを理論で説明しています。
以下の図の右下にあるアスピレーションというのが高い目線のことです。それが、組織が満足することを抑制し、その不満足の状態がサーチ活動を促します。サーチとは「認知の範囲を広げ、新たな選択肢を探す行動」とされています。そうして、新たな知見を得て、業績が上がることが期待されます。そうすると現状に満足して、サーチ活動をしたくなくなる、というジレンマを抱えています。

今回とりあげた「ビジネスで失敗する人の10の法則」では、この左側の負のループにフォーカスを当てた10の教訓だとわかりました。それと同時に、右側の正のループをどうやって取り込んでいくか考えることのほうが本質だな、と思いました。
PDF or スライドデータ欲しいという方へのお願い
❤️マークが、10個ついたら、喜びのあまりまとめのPDFファイルをアップしますので、是非、❤️とSNSなどへのシェアよろしくお願いします!スライドデータの方がよい、という場合はコメントいただけると嬉しいです。
以下のようなアンケートもやってます(2021/4/13時点)良かったら、アンケートご協力ください
紹介本
ネタ元
本コンテンツについて
ビジネス名著まとめの記事はこちらのマガジンにまとめていきますので、ご参照ください。
ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。
しのジャッキーでした。
Twitter: shinojackie
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
