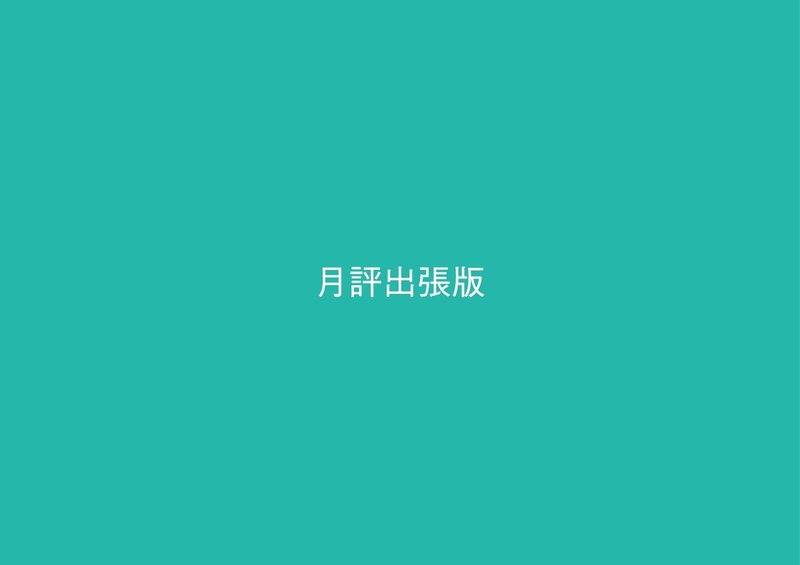
「月評」は前号の掲載プロジェクト・論文(時には編集のあり方)をさまざまな評者がさまざまな視点から批評するという企画です.「月評出張版」では,本誌と少し記事の表現の仕方を変えたり,…
- 運営しているクリエイター
#デザイン

閉鎖系建築家と開放系建築家 ─ 特集/「環境住宅」その先へ 地球と共存する住まいのアイデア─『住宅特集』2018年4月号月評
『新建築住宅特集』では、毎月、さまざまな作品や論考、記事を掲載し、広い射程をもって住宅から明日を拓く建築の可能性を伝え記録しています。しかし重要なことは、議論の場をつくることにあります。限られた誌幅の中で示されたものから何を考えていくべきか、それぞれの読み解きや発見を共有し、建築を取り巻く多くの事象や環境と共に議論を重ねること。この座談月評は、その場を広げていくことを目的に掲載します。2018年1~12月号は、西沢大良さん、吉村靖孝さん、西澤徹夫さんを評者として、1年を通して













