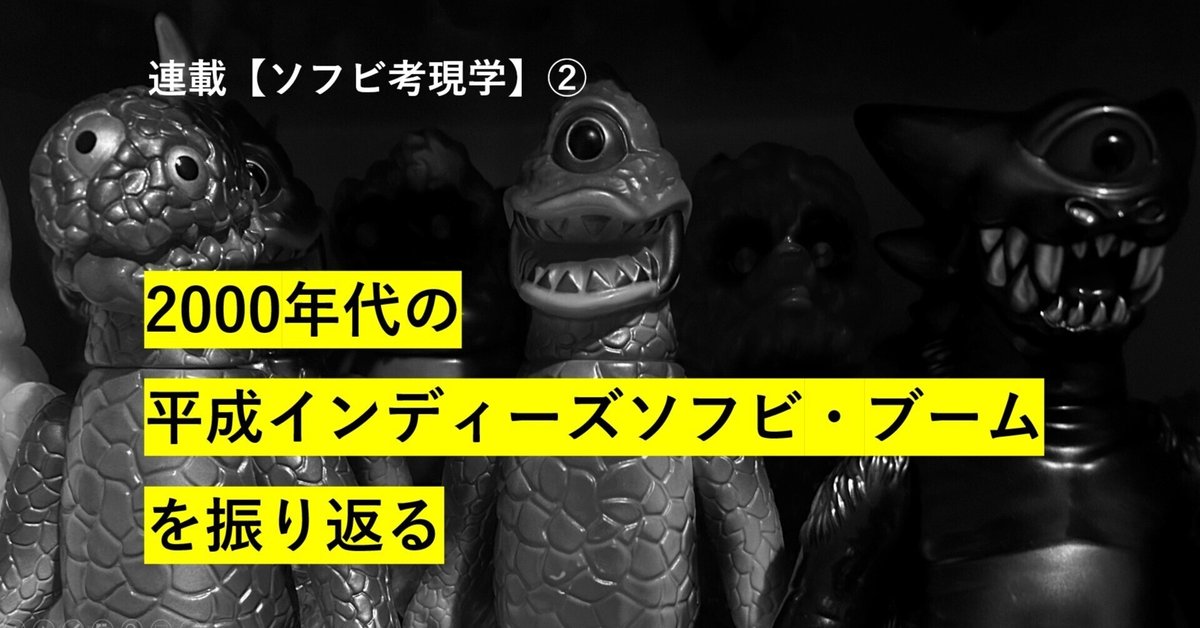
2000年代の平成インディーズソフビ・ブームを振り返る | 連載:ソフビ考現学②
20年ほど前の平成時代後期に、インディーズ・ソフビがブームになったことがありました。現在のソフビ・ブームと比較すると、メーカーの数はまだまだ少なく、イベントの数や規模も控えめでしたが、自作のソフビを発表する小規模メーカーが次々と旗揚げし、シーンは新しいムーヴメントを生み出す活気にあふれていました。
今回は、当時の象徴的な資料を手掛かりに「平成のソフビ・ブーム」を振り返ることで、現在の「令和のソフビ・ブーム」の特徴を浮かび上がらせてみたいと思います。
■平成のソフビ・ブームの源流は昭和の怪獣ソフビ
当時のブームを象徴するメディアがあります。愛媛県に存在したソフビ専門オンラインショップ「怪獣太郎」が発行していた、『怪Zine』というフリーペーパー(ミニコミ)です。2006年に創刊し、2009年に休刊するまで11号まで発刊され、主に全国のトイショップやまんだらけで配布されていました。

このフリーペーパーは、その名前からも想像できるように、怪獣や怪人のインディーズ・ソフビの紹介がメインの専門誌でした。ニッチな専門誌が毎号3000部も発行されていたわけですから、当時のソフビ人気がいかに過熱していたか、ご理解いただけると思います。
創刊号の冒頭では、スペシャル対談としてガーガメルとRUMBLE MONSTERSの対談が掲載されています。ガーガメルは2002年に高円寺を拠点に誕生し、2005年に法人化したメーカーで、当時発売した怪獣ソフビ「ザゴラン」は国内外で大ヒットしました。RUMBLE MONSTERSは2004年に誕生し、アメリカのB級SF怪奇映画テイストを取り入れた怪獣ソフビで知られたメーカーです。どちらも当時のブームを代表する存在で、いまでもソフビを発表し続けています。

RUMBLE MONSTERSの代表は1968年生まれで、1970年代の第二次怪獣ブーム、すなわちブルマァクやマルサンの怪獣ソフビ・ブームを幼少期に体験した世代です。ガーガメルのメンバーは1977年生まれで、幼少期に怪獣ソフビで遊んだわけではありませんが、彼らを触発したのは1990年代にM1号が発売したレトロ(マルサン)タイプのウルトラ怪獣のインディーズ・ソフビでした。
つまり、この平成インディーズソフビ・ブームの源流は、1970年前後に一世を風靡したブルマァクやマルサンの怪獣ソフビであったことは明白でした。そのことを裏付けるように、『怪Zine』ではヴィンテージ怪獣ソフビを検証するコラム「ソフビ怪獣オーパーツ」が連載されていました。トイグラフというインディーズ・メーカーを主宰していた「かじもとしゅうじ」氏による、マルサンやブルマァクの怪獣ソフビの多角的な研究・分析は、歴史的価値のある貴重な資料だったと思います。
■アメリカで共振したソフビの魅力
『怪Zine』の連載陣には、かじもと氏やガーガメルの他に、アマプロの喜井竜児氏やサンガッツ本舗など、現在でも活動を続けるメーカーを主宰する、怪獣ソフビ好きの面々が名を連ねていました。
その連載陣の中で異彩を放っていたのが、アメリカのソフビメーカーであるMAXTOYを主宰するマーク・ナガタ氏です。ナガタ氏は、幼少のころに遊んだ日本の玩具に魅せられて、世界的な日本玩具コレクターとなり、自らもソフビを作り始めたという日系アメリカ人のアーティストです。
彼が『怪Zine』創刊号に寄せたコラムは、当時のインディーズソフビ・ブームの活況を端的に記録しています。1970年代の怪獣ブームを知らない若い世代がインディーズの怪獣ソフビを作り始めていること。それらはマルサン、ブルマァクなどのレトロなスタイルに影響されつつ、都会的で洗練されていること。そして、近い将来に異国の地でたくさんのアーティストが新しい怪獣を作り出すであろうと示唆しています。いま読むと、その予言は見事に当たっていると思います。

ナガタ氏はアメリカ西海岸で2001年に創刊された『SUPER 7』というポップ・カルチャー誌の共同創業者でした。この雑誌は日本のヴィンテージ玩具紹介がメインのコンテンツで、怪獣やヒーローのソフビ、中島製作所のアストロミューなどの魅力をパンク/スケートといったストリート文化の視点から再発見するという、当時としてはとても斬新なメディアでした。そこではシークレット・ベースやリアルヘッド、ガーガメルといった、日本のストリート系インディーズソフビの魅力も積極的に発信されていったのです。『怪Zine』は『SUPER 7』のオマージュだったともいえます。

InstagramやTwitterといったSNSが存在しない時代に、アメリカの玩具マニアたちは『SUPER 7』やskullbrain.orgという掲示板を通して、日本のソフビの魅力に覚醒していきました。雑誌は既に休刊していますが、バックナンバーは公式サイトから全て無料でダウンロードできるので、興味のある方はぜひご覧ください。ちなみにSUPER 7は、今ではアクションフィギュアの製造・販売からイベント開催まで幅広く手掛ける、かなりの規模の会社に成長しています。
前述のガーガメルは、SUPER 7のバックアップにより、2006年7月にサンディエゴで開催される大規模コミックコンベンション(通称コミコン)に出店し、その後もコミコンに継続的に参加します。その背中を見て、世界という広い舞台に目を向ける日本のメーカーが増えていくことになります。
■怪獣からキャラへ、アメリカからアジアへ
こうして振り返ると、平成のインディーズソフビ・ブームの特徴は ①ヴィンテージ怪獣ソフビの強い影響下にある ②主要な海外マーケットはアメリカ という2点だったといえるでしょう。それでは令和のソフビ・ブームはどうでしょうか。
まず①に関して。現在の令和のソフビ・ブームでは、昭和の怪獣ソフビどころか平成ソフビ・ブームすら体験していない若い世代が多く参入し、自由な発想でソフビを発表しているように思います。特に目立つように思えるのが、イラストレーターや美大生が表現の領域を広げ、自分が描くキャラクターを立体化・ソフビ化するケースです。
「怪獣・怪人」から「キャラクター・動物」へとソフビのモチーフが拡大したことで、ファンシー系やPOP系、アート系まで、いまや多種多様なインディーズ・メーカーが登場し、結果的に女性層も多く流入してファンのすそ野が拡大しています。それはまるで、1980年代にパンクを中心に巻き起こったインディーズ・ブームが、1990年代に音楽のジャンルを問わないバンド・ブームへと発展していった、あの光景を思い出させます。
そして②に関して。現在のブームは、中国、香港、台湾、マカオ、タイなど、アジアの国々がけん引しています。高額なインディーズ・ソフビを売買したり、新興のソフビ・イベントが盛り上がったりしているのは、北米よりも圧倒的にアジアの人々だというのが私の肌感覚です。
中国経済の急速な発展と購買力増加が背景にあるのは間違いありませんし、急成長するアジアの国々にとって、日本伝統のソフビ玩具というものがノスタルジーを喚起させる絶妙なモチーフとして受容された、という見方もできると思います。平成ソフビ・ブームの頃に『SUPER7』が発信した英語情報が香港に届き、そこからアジア各国にソフビの魅力が伝わったのかもしれません。
個人的に、2000年代に開花したインディーズソフビ・ブームは、日本では2010年代にいったん沈静化したとい記憶があります。『SUPER 7』や『怪Zine』が休刊し、人気イベント「パチモンサミット」は2011年に終了しました。また、ブログや掲示板からSNSへとメディアがシフトする過渡期となり、ソフビ関連情報を紹介する個人ブログが更新停止や閉鎖、移転をするなどして、情報が希薄化します。なにより影響が大きかったのが2011年の東日本大震災でしょう。多くのクリエイターやコレクターがダメージを受け、ソフビへの情熱が沈下したように思います。
2010年代に日本のソフビ・ブームがいったん沈静化する裏側で、Instagramの普及によってソフビの魅力が言語を超えて世界に伝わる環境が整い、長く着実にクオリティの高い活動を続けていたHxSや、インテリアとしての「映えるソフビ」に着目したInstincToyなどが、アジアを中心に爆発的な人気を獲得します。その盛り上がりを受けて、逆輸入的に日本のソフビ・シーンにも再び火が灯り、2021年からの佐田ビルダーズによる拡散が業火にした、というのが私の見立てです。
■インディーズからヴィンテージへ
令和のソフビ・ブームを支えるショップのひとつである「T-BASE」は、ソフビを紹介するフリーペーパー『T-BASE NEWS』を2021年から発行しています。創刊号の特集「ソフビの世界のスゴイ人」で紹介されたソフビは、伊藤俊彦氏、レッドシャーク&スイングトイズ、かっこわらい雑貨店、暗黒エンターテイメントとバラエティに富んでいます。そこには昭和怪獣ソフビの影響から距離の離れた、自由なキャンバスとしてのソフビを見ることが出来ます。

第3号ではアートソフビ専門店であるT-BASE渋谷道玄坂店、第4号ではT-BASE銀座ギャラリーのオープンが紹介されていますが、ヴィンテージを扱う古物玩具店でもなく、平成インディーズを扱っていたストリート系ショップでもない、全く新しい空間であることが一目瞭然です。いまやインディーズソフビは昭和のヴィンテージ怪獣ソフビの引力から開放されて、新しい世代の文化にトランスフォームし始めているといえるでしょう。マーク・ナガタ氏が過去に透視した以上の未来が、まさに今なのです。

最近話をした年下のソフビ・コレクターが、20年前のインディーズソフビのことを「ヴィンテージソフビ」と呼んでいて、とても新鮮な気持ちになりました。考えてみれば1990年代のコレクターたちは1960~70年代のマルサンやブルマァクのソフビを畏怖すべきヴィンテージだと思っていたわけですから、新しいソフビ・ファンにとって、平成のインディーズソフビはもう価値が熟成されたヴィンテージとなっているのでしょう。
『怪Zine』創刊号を読み直すと、ガーガメルの池田圭郁氏はインタビューの最後でこんな発言をしていて、なんだかグッときてしまいました。
「何十年か後に、僕らが作ったものが捨てられてしまうんじゃなく、ビンテージになっていることを目指して創ってますから」
(真実一郎)
ソフビ考現学① 「ソフビ」ブームが世界を席巻!玩具とアートの融合が生んだ日本発の文化現象
