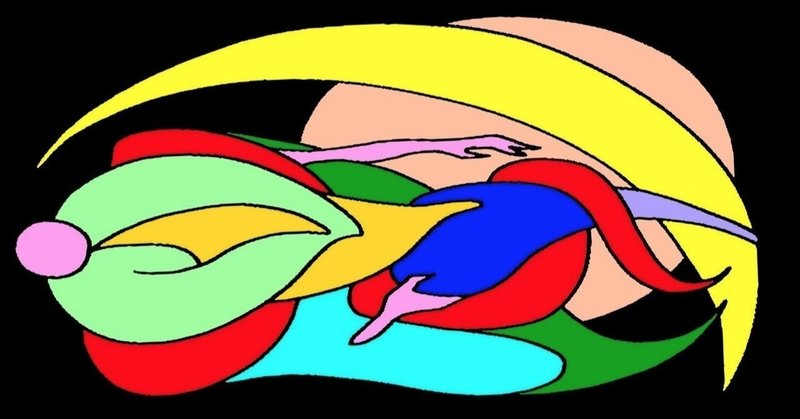
ふつうの男
おすそわけです。たくさんとれちゃって。ほら、うち2人だし腐らせるのもなんだしね。隣に住んでいるらしい(らしいというのは何年もここに通っているのに初めて顔をみたから)60代くらいであろうとても品のよい女性から潮干狩りにいってきたらしくアサリをたんまりともらった。
わぁ、ありがとうございます。と蔓延の笑みでお礼の言葉を述べる。いいんですかぁ? などと謙遜の声まで交えて。嬉しいです。さらに喜びを表す。
「いいのよ。まあ、そんなに喜んでくれるならもっと持ってこればよかったかしら」ほほほと女性は品よく口元をおさえながら笑った。
しかし男が住んでいる新興住宅は皆同じようなうちばかりで今だに男はうちを間違える。嘘でしょ? と誰しもがいうけれど本当に似たようなうちばかりで正直あたしでも今だに間違える。
「アサリをいただいたの。お隣に」
日曜日。今日はないも予定がなく珍しく一緒に布団の上でゴロゴロとしていた。朝6時に目が覚めて缶ビールを1本飲んでyoutubeで下町ロケットを見終えてからあたしが眠っている布団の中になだれ込んできて、パンツだけを下ろしバックの態勢で後ろからなにもいわずにきかずに入ってきた。あっ、声を出そうとすると男は口を押さえる。黙れ。声がうるさい。近所があまりにも静かなので声を押し殺す逢瀬はなんというか逆に興奮を煽る。
「へえ。珍しい。よっぽど取れたんだな」
布団から這い出てきてアサリの入った入れ物に目を落とす。わっ、デカイ。驚くのも無理はない。なにせデカイのだ。どれもこれもが。
「大アサリかな。これって」
「大アサリだよな。だってデカイもんな」
あたしと男は顔を見合わせてプッと吹き出し大笑いをした。以前日本海の方に大アサリを食べにいったことがある。そのとき迷子になってあたしは迷子放送をされてしまい男がそれはそれは恥ずかしそうにあたしを迎えにきた。そのときのことを多分お互い思い出したのだろう。
「七輪あったっけ?」あったよな、と呟いて倉庫におもむく。ドアの向こうはすぐにテラスになっており倉庫もそこにある。炭があまりないけどまあいっか。男はブツブツいいつつも火を起こし始める。
手にはハイボールを握りしめ火を起こす姿はまるでアル中のおっさんのように見える。出会って6年。初夏の日差しの下の男はなんとなく老けた気がしてならない。年月は残酷だ。けれど性格や体躯はまるで変わってはいなく性格はわかりきっているから喧嘩も全くない。そもそも喧嘩をしたことがないし喧嘩の理由がない。こんな男は初めてだ。普通は些細なことで喧嘩をするだろうに。
「おーい」
気がそれていて名前を呼ばれてはっとなる。なに?
「アサリを持ってきて」
あ、うん。頷いてボールさら持ってゆく。ボールの中の貝は動いていて口を半開きにしていたり目を出しているものもいる。生きているんだねぇ、と心の中で呟いてみる。食って食われて。弱肉強食。
「●肉●食の中に入る4文字熟語ってなーんだ」
「焼肉定食」
男は以前なにもひねりのないこたえをくれた。まあそうだけれどね。あたしはついクスクスと笑いがこみ上げる。
アサリを七輪の上にのせてハイボール片手に貝の口が開くのを待っている。あたしは部屋の中から男の視線を待っている。鳩よりも平和な日々にときおり慄く。怖いときがある。出会いと別れは背中合わせ。あたしはいつか来る別れに怯えている。それは今じゃないけれどいつかは来るのだ。いくら婚姻の事実を結んだとしても。
ジュっという音がし始めた七輪におうといいながら目を向ける。
「わわっ。あいたー! 貝があいた」
ひとつあいたら次から次へと伝染するようにぱかんとあいていく。香ばしい匂いと磯の匂いと男の酒の匂いがミックスされてもいい匂いに食欲がそそられる。
お皿にとりふたり並んで貝を食べる。醤油をちょっとだけ垂らして。
「うまい!」
大アサリとはなんとなく違ったけれど貝はそれなりに美味しかった。
「あら? 七輪なんて」
匂ったのだろうか隣の上品そうな奥さんと温和そうな旦那さんが声をかける。
あたしはおもてに顔を出し、はい! 焼きました。美味しかったです。と声をかける。奥さんは破顔して、それは良かったわと目を細める。
「ねぇ、」
すっかり食べ終わった男の横顔に声をかける。
「ん?」
「また、またね、今度大アサリ食べにいきたいな。いい? いや?」
いいよね。あたし男の返事など待たずに決めつめる。いいでしょ?
「うん」
あたしは炭のついた無骨な手のひらを手に取り、あ、炭ついてると伝え、手洗っておいでよとつけたす。
「うん。あ、お皿も洗うわ」
何気ない家事の配分はちょうどよく男が今なにを考えているのかが手にとるようにわかる。
「あのさ、ローソンに行ってビール買ってきて」
「だと、思った」
冷蔵庫の中にはもう缶ビールのストックがなかったのだ。あたしは財布を握りしめながら草履をはきおもてに飛び出る。
すでに夕刻の時間になっていた。太陽は今にも沈みそうでそれでいてあたりを燃えるような色でおどろかし裏の世界に消えようとしている。太陽は毎日同じ繰り返しをしあたしも男も同じ世界で生きている。
足取りが軽い。どこまでも歩けそうだ。あたしは男が好きで。それでいいじゃないか。
明るい店内の前にたくさんの虫が群がっている。
明日は雨かもなぁと呟いた声は定員の『いらっしゃい!』の声にかき消されあたしは店内に足を入れる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
