
『くまのプーさん』翻訳版
このノートは、深堀鑑賞会用に、グーテンベルグ電子ブックが公開しているテキストをもとに作成したのノートから、ノート筆者がつけた仮訳を単独でも読みやすいように編集したものです。朗読等でお使いいただけますが、商業的な使用、及び、複製、転載はしないでください。ご使用の際、及び、引用等はnote筆者に連絡をお願いします。
(深堀鑑賞会用のノート)
グーテンベルグ電子ブックのテキスト。使用の許諾条件もご確認ください。
https://www.gutenberg.org/files/67098/67098-h/67098-h.htm
クリストファー・ロビンの詩(『我々がとても若かったころ』1924)
息子、クリストファー・ロビンが3歳になるころ、子供のための詩を書き始め、それをまとめたもの。その後、クリストファーが6歳のころ、『わたしは六歳(1927)』という詩集が出ています。両者を合わせて、『クリストファー・ロビンの世界』という本にもなっています。
この詩集の前書きにおいて、ミルンは、当初、英国の有名な詩人ワーズワースの作風をまねて、詩の一つ一つにちょっとした注を付けようと思ってたことを記述しています。
「この詩集の中に白鳥についての詩(『鏡』というタイトルの詩)がでてくるとき、そこで、脚注をつけて、「クリストファー・ロビンは、毎朝えさをやるこの白鳥に、「プー」という名前をつけました。これは白鳥に対してはとてもよい名前でしょう。なぜなら、白鳥は呼んでも来ないときがあります(白鳥はよくそういうことをしますね)。そんなとき、あなたは、別に大した期待をしていなかったことを示すために、「プー」といったとうそぶくことができます。・・・湖の白鳥のことを考え始めると、最初は、かれの名前がプーであることがとても幸運だと思いました。それ以上のことは考えませんでした。・・で実際の詩のほうは、自分が意図していたものとはかなり変わったものとなりました。そして、今、いえることは、クリストファー・ロビンがいなかったらば詩を書いていなかっただろうということです。」
ということで、クマのプーさんの話にでてくる、白鳥にプーという名前を付けたという話は、この前書きにのみ登場し、詩のほうには出てきません。また、37番目の詩『テディ・ベア』は、名前にはプーはでてこないものの、「クマのプー」のキャラクターとなっています。
以下、『鏡』と『テディーベア』のノート筆者がつけた仮訳です。元の詩が韻を踏んでいることを踏まえて七五調にしてみました。
鏡
午後の林に うっとりと
とどくは光 金色に
静かな空の 太陽は
静かな水面を 見つめてる
木々は静かに 枝をまげ
静かな森で 重なって

そこでみたのは 白い鳥
水面にうつる 白鳥と
胸と胸とを 寄せ合って
波ひとつない 水面では
じっと動かず 風を待つ
テディベア

どんなことでも してみても
運動しなきちゃ 太っちゃう
われらがクマさん 太っちょだ
不思議と思う までもない
自分でできる 運動を
しては椅子から 落っこちて
どうやら力が 足りないな
這い上って 戻るには
太っちょなんだ そうなんだ
なんだろなぁと 友達は
思いめぐらす そのことが
とても気になる テディだが
確かに彼は 太ってる
「痩せてたらな」と 思うクマ
だけどどっから 始めよか?
外で運動 しろという?
できるわけない フェアじゃない

何週間も 窓に鼻
おしつけてみた むなしくも
羨んだのは あるく人
太らないように 歩くのを
どの人見ても 見つからない
自分のような 太っちょは
自分のように 太っちょは
足置きの上 夜もすがら
寝てるのだから クマさんは
ほかにもたくさん どうぶつと
ほかには絵ほんと いろいろと
親せきたちの ものもある
昔ばなしも なん冊も
歴史をかたる 詩の本も

それはある夜の ことだった
クマが絵本を 見ていると
偶然みつけた その中に
フランス王の すがたの絵
太っちょ男の 下のほう
ルイ王様とか 書かれてた
ニックネームは ハンサム王
だけども彼は 太っちょだ!
大喜びの クマさんは
読んでみました ものがたり
ハンサム王と 呼ばれてた
けれども彼は 太っちょだ
ハンサム王と 呼ばれてた
けれども彼は ふとっちょだ
それだったらば クマだって
ハンサムクマと 呼べるかも
呼ばれてたかも そんな名で
心配になった 少しだけ
ルイ王様は 生きている?
時代で変わる 流行は
日々、いちにちと 変わってる
ハンサム王は 今も居る?
忘れちゃったよ わからない

次の朝きて 窓に鼻
こすりつけては 考えた
だいじょうぶかな ほんとうに
王さま生きて いるのかな?
窓にお鼻を こすりつけ
も一度クマは 考えた
窓はかるく 開いていて
急に開いて 驚いた
クマは下へと 消えてった
そのときやって 来たおとこ
目が輝やいて 太っちょな
落ちたクマを 見つめてた
礼儀正しく 立ち上げて
優しく耳に ささやいた
やすまる言葉 はげましの
やれやれなんと いうべきか
なんともひどい 落ちかただ

クマはなんにも 答えずに
聞いたことさえ 疑わしい
クマはただただ 見るばかり
太っちょおとこだ 本に居た
あのハンサム王 この人が?
わけがないよね でもしかし
聞いてしまおう それならば

もしやあなたは ひょっとして
王さまですか フランスの?
返事はなんと ”その通り”
帽子をとって かしこまり
「失礼ですが あなたさま
クマの紳士の エドワード?」
そこでクマは ふかぶかと
お辞儀を返した 「そうですよ」
二人は立ってた 窓の下
フランス王と エドワード
ハンサム同士 ちょい太り
話を交わす あれこれと
そして王さま 言いました
わたしそろそろ 帰ります
ベルを鳴らして 尋ねるに
「あなたのクマさん そうですね?」
戻っていった 来た道を
一生懸命 頑張るが
体操なしは 太るんだ
われらがクマは ふとっちょだ
おどろくまでも ないけれど
だけどクマさん 気にしてる?
痩せてないこと 気にしてる?
いやいやそんな ことはない。
誇りにしてるさ 太っちょを。

クマのプーさん
献呈の辞
彼女のために
クリストファー・ロビンと私は手をつないで来たんだ。
この本を君の膝の上に置くために。
驚いたかな?
これ、好きかな?
これ、欲しかったかな?
だって、これは君のだからーーー
私たちはあなたのことが好きだから。
注:「彼女」とは、クリストファー・ロビンの母でAミルンの妻

はじめに
もしも、君がクリストファー・ロビンについての別の本を読んでたなら、彼には白鳥がいて(あるいは、白鳥にクリストファー・ロビンがいたのか、しらないけど)、それを「白鳥のプー」って呼んでたことを覚えてるよね。とても昔の話だったね。白鳥にさよならを言ったとき、名前はもらってきた。だって、白鳥がその名前を欲しがるとは思わなかったから。クマのエドワードが、わくわくするような名前が欲しいと言ったとき、クリストファー・ロビンは、すぐに、考えるために立ち止まることもせずに、プーだと言ったんだ。そして、そうなった。これで、プーの名前の部分は説明したので、残りの部分を説明しよう。
ロンドンにいて動物園に行かずに長く過ごすことはできないよね。ある人は、はじめに「入口」というところから動物園巡りを始めて、「出口」というところに行くまでに、すべての檻をささっと通り過ぎていくね。でも、いちばん良い人たちは、まず、自分の好きな動物のところにまっすぐに行って、そこでときを過ごすね。だから、クリストファー・ロビンが動物園に行くときは、ホッキョクグマのところに行って、左から3番目の動物園の係りの人に何かささやくとドアの鍵が外されて、暗い通路をさまようように歩いて急な階段を上り、特別な檻のところにつくんだ。そうすると、その檻が開けられて、なにか茶色でふわふわしたものが小走りで出てきて、クリストファー・ロビンは、「あぁ、クマちゃん」と喜びの声をあげるや、急いで近寄り抱きかかえるんだ。それで、このクマの名前はウィニーで、クマにとってはとても良い名前だけど、不思議なことに、プーの後にウィニーなのかウィニーの後にプーなのか覚えていないんだ。わかってたこともあったけど忘れてしまった・・
ここまで書いていたら、ピグレットが見上げて、「ぼくはどうなったの?」とキィーキィー声で言ったんだ。そこで、「ピグレット、本全体が君についてなんだよ。」と私は言ったんだ。「だけど、プーについてなんだ」と、彼はキィーキィー声で言ったんだ。ピグレットはねたんでたんだね。ピグレットは、ここの前書きでの大きな紹介はぜんぶプーのためだと思っていたからね。プーは、もちろん、好みさ。否定のしようもない。だけど、ピグレットはプーが居なかったいい場面にたくさん出てくるんだ。だって、プーを学校に持っていったらみんなが気づいてしまうよね。ピグレットは小さいからポケットの中に忍び込める。そして、君が7かける2が12か22かよくわからないときに、居心地よくしているんだ。ときどき、彼はポケットから抜け出しインクツボを見るんだ。そして、こうして、プーよりも勉強することができるんだ。でも、プーは気にしないよ。頭脳をもってる人もいれば、そうじゃない人もいる、とプーはいうんだ。そして、「あるよ」って言うんだ。
一番いいのは、ここで前書きを書くのをやめて、本の本文に行くことだね。
A. A. ミルン

(第一話)クマのプーとミツバチに会って物語が始まるところ

さあ、ここにいるのがクマのエドワード。クリストファー・ロビンの後ろで、頭の後ろを階段にゴツン、ゴツンとぶつけながら降りてきました。階段を下りてくるやりかたはこうしかないのだろうけども、ときには別のやり方があるのじゃないかとプーは思うことがあったんだ。もしも、ゴツン、ゴツンとぶつけるのを止めて考えさせてくれるなら。そして、たぶん、そうじゃないなと感じるのだけど。ともあれ、彼は階段の下までおりてきて、皆さんにご紹介できる準備ができました。くまのプーさんです。
私が初めてかれの名前を聞いたとき、きみも言おうとするだろうけど、「だけど、男の子だと思ったの?」と言ったんだ。
「そう思った」とクリストファー・ロビンは言ったんだ。
(父)「じゃあ、彼のことウィニーとは呼べないね?」
(ク)「そうだね」
(父)「だけど、ウイニィーって言ったよねーーー」
(ク)「だから、ウィニーのプーさまだってば。さまってどういう意味か分かる?」
「あぁ、そうだね」と私はすぐに言いました。で、多分、きみもわかるよね。だって、これが説明のすべてなんだから。
注:ウィニーは、「優れた」という意味の女性の名前で、男の子ならウエィン、ウィム等々です。なので、「ウィニー・ザ・プー」だと、女の子の名前になるねとお父さんに指摘されて、息子のクリストファー・ロビンは、「ウィニー・ザー・プー」だと言っています。「ザ」を「ザー」と言うんだといって、男の名前だという屁理屈をこねたものです。日本語にはなりにくいので、ここでは「ザー」を、音の響きが似ているs「サー」(閣下)にみたてて「さま」と訳しておきました。)
一階に降りてきたとき、あるときは、くまのプーは、ゲームをしてあそびたいと思い、あるときは、暖炉の前で静かに座って物語を聞きたいと思うんだ。この夜は---
「物語はどうかな?」と、クリフトファー・ロビンが言ったんだ。
そこで、私は、「物語はどうかな?」と言った。すると、
「お願いだから、プーになにか話してくれない?」
「たぶん、できると思うけど」と私は答えたね。「どんな物語がすきなのかな?」
「自分自身のことさ。だって、そんなクマだものね」
「そうか」
「だから、とてもやさしくお話しできる?」
「やってみようか」と私は言った。
それで、私は試してみました。
* * * * * * * * *
昔あるとき、とっても昔のこと、そう、先週の金曜日くらいかな、クマのプーはサンダーという名前のもとで森の中に一人で住んでいました。

(「名前のもとで、ってどういう意味?」とクリストファー・ロビンが聞きました。
「それはね、扉の上に金色でかかれた表札があって、その下に住んでたってことだよ」と私は答えました。
「クマのプーはそのことわかってたのかな?」とクリストファー・ロビンが言った。
すると、「いま、わかった」と、うなるような声が言いました。
「なら、続けるよ」、と私は言いました。)
ある日、プーが外を歩いていると、森のまんなかの開けたところに来て、そこのまんなかにはおおきな樫の木があって、木のてっぺんから大きなぶんぶんいう音が聞こえてました。

クマのプーは、木の根元に腰を下ろして、手で頭を抱えて考え始めました。
最初に、プーは自分自身に言いました。「あのぶんぶんいう音はなにか意味あるぞ。意味がなくてただぶんぶんという音を聞くことはないよね。もしも、ぶんぶんいう音がして、だれかがその音をだしていて、その理由がぶんぶんという音をだすだけというなら、ミツバチだからだよ。」
そして、長い間考えてから言いました。「そして、ミツバチであることのただひとつの理由は、はちみつを作るからだよ。」
すると、彼は起き上がって言いました。「そして、はちみつをつくるただひとつの理由は、僕がたべることができるからさ。」そして、彼は木を登り始めました。

彼は、鼻歌を歌いながら、木を登って、登って、登って行ったんだ。
おかしくないか なぜだろう?
クマははちみつ 大好きだ
ぶん、ぶん、ぶん! なぜだろう?
クマははちみつ 大好きだ
そして、彼は、少しだけ、少しだけ、そしてほんの少しだけ先の方へと登ったんだ。それまでに、別の歌を考え付いてね。
クマがミツバチ だったなら
根元のほうに 巣を作る
クマがミツバチ だったなら
登らずにすむ 階段を
かれは少し疲れてきたので、「不満の歌」を歌いました。かれはもうちょっとのところまで来てたんだ、そしてその枝に立てば・・・
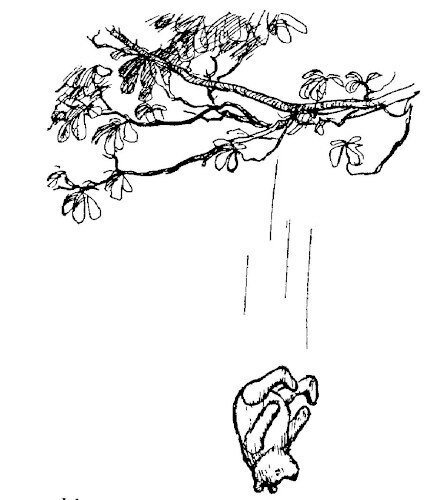
ボキッ!
「おぉ、たすけて」と、3メートルほど下の枝に落ちたところで、プーは言ったんだ。
「もしも、こうしてなかったらーーー」と、5メートルつぎの枝に跳ねたところで言ったんだ。
「ほら、じぶんがしようとしてたのは」と、頭とかかとがひっくり返って15メートル下の別の枝にぶつかったときに、彼は説明しようとしたんだ。「じぶんがしようとしていたのはーーー」
「もちろん、それはちょっとーー」と、続く六つの枝をさっとすり抜けたときに、彼は認めたんだ。

「どうも、みんなそうだ」彼は、最後の枝にさよならと言て、三回ほどぐるっと回って、ハリエニシダの茂みに優雅に飛びこんだときに結論を得たんだ。「これは、みんな、はちみつがとっても好きだからだ。あぁ、困った」
彼は、ハリエニシダの茂みから這い出て、鼻についてトゲをブラシをするように落として、また、考え始めたんだ。それで、最初に思い付いたのがクリストファー・ロビンだったんだ。
(「それが僕だったの?」とクリストファー・ロビンは、信じられないという風に、恐れ入った声で言ったんだ。
「きみだったんだよ」
クリストファー・ロビンは、何も言わなかったけど、目を大きく大きく見開き、顔を赤く赤くさせたんだ。)
そうして、クマのプーは、森の別のところにある緑の扉の向こうに住んでいる、クリストファー・ロビンのところに行ったんだ。

「おはよう、クリストファー・ロビン」
「おはよう、クマのプーさま」と、君が言った。
「ひょっとして、風船のようなものをもっていないかな?」
「風船?」
「そう、風船のことを思いながら、どうかなと思いながら、「クリストファー・ロビンが風船のようなものを持っていないかな?」と言ったんだ。
「で、なんで風船が欲しいの?」って君が言った。
クマのプーは、誰も聞いていないことを確かめるようとあたりを見回してから、手を口につけて、深くため息をするように「はちみつ!」って言ったんだ。
「だけど、風船じゃはちみつを手に入れられないだろう?」と君が聞いた。
「できるさ」と、プーは言ったんだ。
うん、君は、昨日、友だちのピグレットの家であったパーティにいって、パーティでは風船をもってたよね。君はおおきな緑色の風船をもっていた。そして、ウサギのなかまのひとりは大きな青いのをもってたけど、残していった。そもそも、パーティに行くには幼すぎたからね。だから、きみは、みどりのと青いのを家に持って帰ったね。

「どっちをほしいんだい?」ときみはプーに聞いた。
かれは、両手であたまをかかえてとても慎重に考えた。
「こんなかんじなんだ」、と彼は言った。「風船をつかってはちみつを追いかけようとするとき、大事なことは、ミツバチにきみが近づいているときづかせないことなんだ。さて、もしも、緑の風船なら、ミツバチは木の一部だと思って君のことに気づかない。そして、もし、青い風船なら、ミツバチは空の一部だと思って君のことを気づかない。だから、問題なのは、どっちの方が確かかなってことなんだ。」
「風船の下にいる君に 気がつかないかな?」と君は聞いた。
「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」と、プーは言った。「ミツバチのことは分かりようがないものね。」彼は、ちょっと考えてこう言った。「自分は、小さな黒い雲にみせかけることにするよ。そうすればだませるよ。」
「だったら、青い風船の方が良いね」と君は言った。それで、そう決まったんだ。

うん、君たちは、青い風船を持って出かけて行って、君はいつものように万が一にそなえて銃を持っていき、プーはすごくぬかっているところに行って、体中が黒くなるようにそこで寝転がり、それから、風船をできるだけ大きく膨らませて、君とプーはひもを掴んでたんだ。とつぜん、君が手を離すとクマのプーは優雅に空に上がっていってそこでとどまったーーそれは、木とほぼ同じ高さでそこから5メートルほどのところだった。
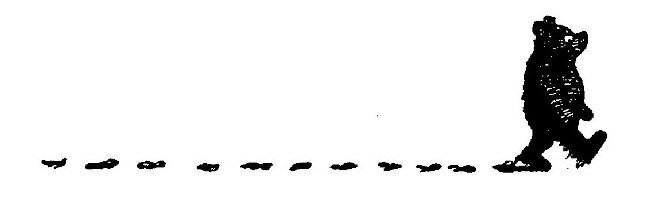
「ほーれ!」と君は叫んだ。
「これ、とてもいいんじゃないかな!」とプーは君を見下ろして叫んだ。「僕はどんな感じに見える?」
「クマが風船につかまっているように見えるよ」と君は答えた。
「えぇ?」と、心配そうにプーが言った。「ーー青空に浮かぶ小さな黒い雲に見えないかな?」
「そうは見えないなぁ」
「あぁ、多分、そこから見るのとでは違って見えるんだ。僕が言ったように、ミツバチのことはわからないだろう」
彼を木の近くまで運んでくれる風がなかったので、彼はそこにとどまったんだ。かれは、はちみつを見ることも、その匂いをかぐこともできたけど、はちみつにたどり着くことができなかった。
ちょっとしてから、彼は、下にいる君を呼んだんだ。
「クリストファー・ロビン」かれは、大きな囁き声で言ったんだ。
「ねぇねぇ」
「どうも、ミツバチが何か疑っているみたいなんだ」
「なんのことを?」
「よくわかんないけ。だけど、ミツバチが疑っているよって何かが自分に言うんだ」

「たぶん、ミツバチはきみがはちみつを狙ってると思ってるんだろう」
「そうかもしれない。ミツバチのことはだれもわからないからね」
また、ちょっと静かになって、それから、プーは上からきみに言ってきた。
「クリストファー・ロビン!」
「なんだい?」
「きみの家に傘はあるかな?」
「たぶん」
「それを取ってきてもらえるかな。そして、行ったり来たりしながら、ときどき僕を見上げて、こう言うんだ「ちぇっ、どうも雨みたいだ。」 もしも、そうすれば、ミツバチのことを騙そうとしていることがうまくいくかもしれない。」
ほぅ、と君は笑ったんだ。「クマのおばかさん。」でも、そのことは大きな声では言わなかったのさ。だって、君はかれのことをとても好きだからね。そして、きみは君の家に傘を取りに帰った。

君が木にもどるやいなや、「おぉ、もってきてくれたんだ!」と、クマのプーが上から言ったんだ。「ちょっと心配になってきてたんだ。ミツバチは間違いなく疑っていることがわかったんんだ」
「傘を上にあげようか?」と君は言った。
「うん、だけどちょっと待って。練習しなくちゃ。だまさなければいけない大事なハチは女王バチなんだ。下から見て、どれが女王バチかわかるかい?」
「いいや」
「それは残念。では、君は傘を持って行ったり来たりしながら、「ちぇっ、雨みたいだ」と言ってくれれば、自分は、ちいさな雲の歌を歌うんだ、雲がうたいそうなやつ・・さぁ」
それで、君が行ったり来たりして雨かなと思っているとき、プーはこんな唄を歌った。
雲になるのは 素敵だな
青ぞらのなか ふわふわと
ちいさな雲の みなさんが
大きな声で 歌うのさ
雲になるのは 素敵だな
青ぞらのなか ふわふわと
感じるんだよ 誇らしく
小さな雲に なったなら
ミツバチはいぜんとして疑い深くぶんぶんうなっていた。ハチの何匹かは、巣を離れて、雲が2番目の歌詞を歌おうとするときに、雲の周りを飛んで、一匹は雲の鼻にちょっととまり、また、飛び上がった。

「クリストファーー痛ぃ!ーーロビン」と雲が叫んだ。
「うん?」
「ずっと考えていて、大事なことが分かったんだ。これらは、悪い種類のミツバチなんだ」
「そうなの?」
「とっても悪いやつらだ。だから、きっとわるい種類のはちみつを作っているに違いないよね?」

「そうなの?」
「そうだよ。だから、降りたほうが良いと思うんだ」
「どうやって?」と、君は聞いた。
プーは、そのことを考えていなかったんだ。風船のひもから手をはなせば、彼は落ちてーーどんーーだから、彼は、そうするのは嫌だったんだ。それで、彼は長いあいだ考えてから、こう言った:
「クリストファー・ロビン。君がもっている銃で風船を撃ってくれる。君は銃をもっていたよね?」
「もちろん、持っているよ」と、君は言った。「だけど、そうすると風船がだめになっちゃうよ」と、君は言ったんだ。
「だけど、もしもそうしないと」と、プーは言った、「風船を手放さなければならなくて、そうすると、自分をだめにしちゃうから」
かれが、こういうふうに言ったとき、きみはどうかなと考えて、とても注意して風船を狙って、そして撃ったんだ。
「痛っ!」とプーが言った。
「外したたかな?」と君が聞いた。
「正確には、外したわけじゃない」と、プーは言ったんだ。「だけど、風船にはあたらなかった」
「ごめんね」と君は言って、もう一度撃ったら、今度は風船に命中して、風船から空気がゆっくりと抜けて、プーは地上にふわっと降りてきた。
だけど、彼は腕で風船のひもを固くずっと握りしめていたので、腕は一週間以上空に向いたままとなって、ハエが鼻先にくるたびに、それを吹き払わなければならなかった。なのでーー自分はたしかではないけどーーかれはいつもプーと呼ばれてるんだ。

「これでお話はおしまいなの?」とクリストファー・ロビンがたずねた。
「この話はここでおしまい。他にもお話はある。」
「プーと自分のこと?」
「そして、ピグレットとラビットと君たちみんなのこと。忘れたかい?」
「覚えているよ。で、思い出そうとすると忘れるんだ。」
「それは、プーとピグレットが、ヘラファンプをつかまえようとした日のことだよーーー」
「つかまえられなかったよね?」
「できなかった。」
「プーは、脳みそがないからできなかった。自分はできたんだっけ?」
「それは、お話の中ででてくるよ」
クリストファー・ロビンは頷きました。
「覚えているよ。」と、彼は言いました、「プーはよくは覚えられなくって、だから彼は話をしてもらうのが好きなんだ。なぜなら、それは本当の話で、ただ、作り話を覚えているってものではないからね。」
「わたしも、そう感じているよ」と、私は言いました。
クリストファー・ロビンは、深いため息をつき、クマの足を掴み、ドアのところまで行き、プーを後ろに引きずっていきました。ドアのところで振り返って、「お風呂に入るの見に来る?」と、言いました。
「かもね」と、私は言いました。
「銃を撃ったときに、プーを傷つけなかったよね?」
「ちっともね」
彼は、うなづいて、出て行きました。そして、すぐに、プーがゴツン、ゴツンと音を立てて、彼の後ろで階段を上っていくのを聞きました。

(第一話の終わり)
(第二話) プーが友達を訪ねて狭いところに引っかかってしまう

ウィニー・ザ・プーとして知られてるクマのエドワードは、ある日、森の中を、誇らしげに鼻歌を歌いながら歩いていました。彼は、朝、ガラスの前で痩せるための体操をしているときに、その歌を思いついたのです。できるだけ高く体を伸ばして、トララ、トララ、そして、指先を足に伸ばそうとしてトララ、トララーーおぉ、助けて!。朝食を食べたら、なんどもなんども繰り返して呟いているうちに、すっかりと覚えて、いまは、鼻歌でちゃんと歌えるようになったんだ。こんな感じなんだ。
トララ、トララ、
トララ、トララ、
ランタン、タンチン、
チンタン、チンタン、
チンタン、チンタン、
ランタン、タンチン。

クマは鼻歌を歌って、陽気に歩いていて、ほかのものたちは何をやっているのかと思いながら、もしも自分が他人だったらどうかと思っていると、突然、砂の土手が現れ、そこには大きな穴がありました。
「あぁ」とプーは言いました(ランタン、チンタン)”もしも自分がしっていることが正しいなら、この穴にはウサギがいるということだね”と彼は言いました。「そしてウサギということは仲間だ」と言いました。「そして仲間ということは、食べ物があって、鼻歌を聞いてくれるということだ。ランタン、チンタン」
それで、彼は前かがみになり、頭を穴に突っ込んで、叫びました。
「誰かいない?」
穴の中では、突然、慌てたような音が聞こえ、そして静かになりました。
「私が言ったのは、「誰かいない?」だよ、と、プーはとても大きな声で言いました。
「いないよ!」と声が聞こえました。そして「そんなに怒鳴ることないよ。初めからちゃんと聞こえているよ!」
「なんと」とプーは言いました。「ここに誰かいない?」
「いないよ!」
クマのプーさんは、穴から頭を抜いて、少し考えて、そしてまた考えました。「あそこには誰かがいるに違いない。だって、誰かが「いないよ」いったはずだから」。そこで、彼は、頭を穴に戻して言いました。
「こんにちは。ウサギだよね?」
「いいや」とウサギが、少し違う声で言いました。
「だけど、ウサギさんの声じゃないかい?」
「違うと思うよ」とウサギは言いました。「そういう意味じゃなくって」
「おぉ!」とプーは言いました。
彼は、穴から頭を抜き、もう一度考えてから戻り、言いました。
「ウサギさんがどこにいるか教えてくれませんか?」
「友達のクマのプーに会いに出かけているよ。プーはとてもよい友達なんだ」
「だけど、それは僕だよ」と、とても驚いてクマは言いました。
「僕ってどんな?」
「クマのプーだってば」
「本当かい?」と、もっと驚いてウサギは言いました。
「もちろん、確かさ」とプーは言いました。
「じゃぁ、お入り」

それで、プーは、巣穴に体を押し込んで、押し込んで、ついに入り込みました。
「ほんとうだ、言うとおりだ」と、彼を見つめながらウサギは言いました。「きみだね。会えてよかった」
「ほかの誰だと思ったの?」
「自信がなかったんだ。森に居るってどういうことか知ってるよね。家に勝手に人をいれちゃいけないんだ。注意しないと。で、なにか食べるかい?」
プーは、いつも、午前11時ころ、ちょっとだけおやつを食べるのが好きでした。なので、ウサギがお皿とコップを持ってきたのを見て喜びました。そして、ウサギは「はちみつかコンデンスミルクをパンにつけるのはどう?」と言いました。プーはとっても喜んで、「両方とも」と言いました。そして、欲張りと思われないように、「けど、パンはなくてもよいけども」と言いました。そして、しばらくの間、プーは一言も言いませんでした・・・そのあと、もぐもぐさせて鼻歌を歌うと、立ち上がり、ウサギを愛想よく握手して、もう帰らなければと言いました。
「もうお帰りですか」とウサギは礼儀正しく言いました。
「えぇ」プーは、食料が置いてあるところをじっくりと眺めながら「もしも、あなたがどうしてもというなら」と言いました。
「実はなんですけど」とウサギは言いました。「これから外に出たいのですが」
「あぁ、そうですか。なら、私もです。さようなら」
「はい。さようなら。もしも、これ以上はいらないということならば」
「ほかに何かあるの?」とプーは直ちに聞きました。
ウサギは皿の上にかかっていたカバーをどけで「いや、なにもないよ」と言いました。「ないと思ったんだ」とプーはうなづきながら言いました。「それでは、さようなら。もう行かなくっちゃ。」

そして、彼は穴のほうへと昇っていきました。腕で体を引っ張り、足で体を押すと、鼻が外に出て、それから耳、そして腕、それから肩、それからーー
「おぉ、助けて!」とプーは言いました。「戻ったほうがいいかな」
「なんてことだ」と言って、「このまま出るほうがよさそうだ」
「どっちもできなくなっちゃった!」とプーはいいました。「おぉ、助けて!」
ウサギは外に散歩に出たかったのですが、玄関が詰まってしまっているのを見て、後ろのドアから出ていきました。そして、ぐるっと回ってきてプーを見ました。

「どうした?詰まっちゃったかい?」とウサギは聞きました。
「いいや」と、プーはのんきに言いました「ちょっと休んでて、考えてて、鼻歌を歌っているのさ」
「腕を出してごらん」
プーは腕を伸ばし、ウサギは、引っ張り、引っ張り、引っ張り
「痛ぃ!」とプーは言いました「痛いじゃないか」
「どうやらね」とウサギが言いました。「君は詰まっちゃったんだ」
「それはね」と怒ってプーは言いました「玄関を十分に大きくしておかなかったからだよ」
「それはね」とウサギは厳しい顔で言いました。「君が食べすぎたんだよ。そう思ったんだけど」、「我々のうちどっちかが食べすぎたって、言いたくはなかったからさ」とウサギが言いました。「そして、自分ではないからね」。「さあ、クリストファー・ロビンのところに行って連れてこよう」
クリストファー・ロビンは、森の反対側に住んでいました。ウサギといっしょに来ると、プーの前半身が穴から出ているのを見ました。「おばかさん」と愛情を込めて彼は言ったので、みな、希望を持ちました。
「それではまた玄関が使えるようになるかな」とウサギは言いました。
「もちろん、また、玄関を使えるようになるさ」
「それはよかった」とウサギは言いました。
「もしもプーを引っ張り出せないなら、押し込ん見ようか」
ウサギは、ひげを思慮深げに撫でて、プーが押されて戻るなら、プーは部屋に戻ってくるということで、それは嬉しいことではあっても、プーがずっといるということであって、木の中に住むか、地中に住むかーー」
「つまり、もう出られないということかい」とプーは言いました。
「いやつまり」、「ここまできてるんだから、それを無駄にしたら惜しいよね。」とウサギは言いました。クリストファーロビンも頷きました。
「なら、やらなきゃいけないことは」「プーが痩せるまで待つことだね」と彼は言いました。
「どのくらいかかるかな」と、心配そうにプーが聞きました。
「一週間くらいかと思うけど」
「だけど、ここに一週間もいられないよ」
「居てもだいじょうぶさ、お馬鹿さん。そこからだすの、とっても難しいんだよ」
「お話を読んであげるさ」とラビットは楽し気にいいました。「雪がふらなきゃいいけどね」と付け加えました。「そして、友よ、君は我が家のかなりの部分をつかっちゃってるんだ。だから、足をタオル掛けにつかってもよいだろう?だって、足は何もできないんだしーータオルをかけるのにはちょうどいいかんじなんだ。」
「一週間も?」とプーはしゅんとして言いました。「食事はどうなるの?」
「食事はだめだよ」とクリストファー・ロビンは言いました。「早く痩せるためにはね。だけど、本を読んであげるよ」
クマはため息をつこうとして、それができないことに気づきました。あまりに窮屈に詰まっていたからです。そして、涙が落ちてきました。
「それじゃ、元気がでるような本を読んでくれる。きつきつに挟まったクマの慰めになるような」

それで、一週間の間、クリストファー・ロビンは、プーの北のはずれでの手の本を読み、ウサギは、プーの南はじに洗濯物をかけていました。その間でクマは、少しずつ痩せていくと感じてました。
それで、かれはプーの腕をつかみ、ウサギはクリストファー・ロビンをつかんで、ウサギの友達と親せきたちがウサギをつかんで、みんなで一緒に引っ張りました。
そして、長い間、プーは、ただ「うぅ!」と・・・そして「痛ぃ!」と言っていました。
そして、突然、彼は、「ポン」と、あたかも瓶からコルク栓が抜けたようになりました。
そして、クリストファー・ロビンとウサギとウサギの友達と親せきは、後ろにのけぞり重なって、その上に、クマのプーが乗っかりました。
それで、うなづいて彼の友達に感謝して感謝、クマは森の中を歩いていきました。自慢げに鼻歌を歌いながら。だけど、クリストファー・ロビンは、彼を優しく気にかけて、「おばかなクマさん」といったのです。
(第2話の終わり)
(第三話) プーとピグレットが狩りにでてウーズルを捕まえそこなう
ピグレットはブナの木の真ん中にあるとっても大きな家に住んでて、そのブナの木は森の真ん中にあって、ピグレットは家の中の真ん中に住んでいました。彼の家の横には壊れかけた表示板があって、「侵入禁次」と書かれてたんだ。クリストファー・ロビンがその意味を尋ねると、彼は、それはおじいちゃんの名前で、長い間家族とともに合ったものだと言ったんです。それで、クリストファー・ロビンは、「侵入禁次」とは言えないよと言うと、ピグレットは言えるともと言って、なぜなら、彼のおじいちゃんは、「侵入禁次郎」を短くしたもので、それは、「侵入禁治衛門」を短くしたものだと。おじいさんは、名前をなくさないようにと二つ持っていて、そのおじさんに因んで「金次郎」というのと、「禁治衛門」っていうのをだと。

「自分も二つも名前を貰ったんだ」と、クリストファー・ロビンが不注意にいいました。
「ほら、そうじゃないか。それが証拠だよ」とピグレットが言いました。
ある晴れた冬の日、ピグレットが家の前に降った雪をブラシで払おうとしていたとき、彼が見上げると、そこにはクマのプーがいました。プーは、何か別のことを考えながら円を描くように歩き回り、ピグレットが声をかけたときも歩き続けていました。
「こんちには」「何してるの」とピグレットが言いました。
「狩猟さ」とプーが答えました。
「何を捕まえようとしてるの?」
「何かを追っかけてんだ」とくまのプーさんが謎めいた返事をしました。
「何を追っかけてんだって?」とピグレットが近寄って聞きました。
「それがなんだが、自分に尋ねてんだよ。」
「答えは出そうかい?」
「見つければわかると思うんだけど」とクマのプーさんが言いました。「あそこを見てごらん!」と目の前の地面を指しました。「何が見えるかい?」

「跡がある」とピグレットは言いました。「足跡だ」、と彼は興奮して小さなキイキイ声をあげました。「プー!、これ、ウーズルなんじゃないかな?」
「かもしれない」とプーは言いました。「そうだというときもあれば、そうじゃないときもある。足跡のことはわからないよね。」
こんなことを言ってから、プーは足跡をたどり続け、ピグレットは、プーのことを一二分見た後で、彼を追いかけました。プーは突然立ち止まり、当惑したような仕草で足跡に前かがみになりました。
「どうしたんだい?」とピグレットがたずねました。
「とてもおかしいんだ。」とクマが言いました。「どうやら、今は、動物が二匹いるようなんだ。いったい、何なのかはわからないけど、ここでもう一匹やってきている。何なのかはわからないけども。一緒に来てくれるかい?ピグレット。まんいち、敵愾心を持つ動物だったときに備えて。」
ピグレットは、耳をよい感じでかいて、彼は今週の金曜日まではなにもすることがないと言い、喜んで一緒に行くと言ったんだ。それがウーズルかもしれないから。
プーは「つまり、ウーズルが二匹いるかもしれないということだよね」と言ったらば、ピグレットは、ともかく、金曜日まではやることがないといったんだ。なので、二人は、一緒に行くこととなりました。

そこにはカラマツの雑木林があって、ウーズルが2匹いそうでした、もしもいるとして雑木林をぐるぐる回っていたとしてですが。なので、プーは雑木林の周りをまわりピグレットがそのあとを追いました。ピグレットはプーにおじいさんの「侵入禁治」が追跡のあと体の凝った部分をほぐすのに何をしたのかとか、おじいさんが晩年苦しんだ呼吸困難の話とか、ほかに面白そうなことを話して暇をつぶしていたけれども、プーはおじいさんってなんだろうと思いながら、でも、多分、いま追跡しているのは2人のおじいさんで、そうだとすると、そのどっちかを連れていけるかどうかと思い、そうしたらばクリストファー・ロビンがなんというかなど思いを巡らせていたんだ。そして、追跡を続けていました・・・
突然、プーは立ち止まり、興奮して彼の前の方を指さしました。
「見て!」
「なに?」とピグレットが飛び上がって言ったんだ。そして、それから、彼が怖がっていないことを示そうとしてもう一二度、興奮しているようなさまで飛び跳ねました。

「足跡が!」とプーは言いました。「三匹目の動物が加わっている!」
「プー!」とピグレットが叫びました。「もう一匹ウーズルがいるのかい?」
「いいや」とプーは答えました。「だって、違ったマークができているよ。だからウーズルが二匹と別のが一匹か、ウイズル一匹と違うのが二匹か、ウイズル二匹と別の一匹か、そうなら、それはウーズルだよ。もう少し追ってみようよ」
それで、二人は追跡を続けました。もしも、敵愾心のある動物たちが先にいるとすれば、ちょっとだけ不安を感じますが。そして、ピグレットは、おじいさんの「侵入禁治」がそこにいればよかったなぁと切に思い、プーはもしも、偶然、クリストファー・ロビンに会えたらいいんだがなと思いました。だって、プーはクリストファー・ロビンがとても好きだったからです。そして、突然、プーは立ち止まり、鼻の頭を冷やすように舐めました。それは、かれが、これまで生きていた以上に熱く心配に感じていたからです。なんと、目の前には4匹の動物がいます!
「みてごらん、ピグレット!これらの足跡を。これまであった三つ、つまり、ウーズル2匹とほかの一匹だったけど、また新たなウーズルが増えちゃった」
そして、そのように見えました。足跡は、互いに交差して、そこでごちゃごちゃになってましたが、ときどきはっきりと4匹分の足跡が見えるのでした。

「思うに」と、鼻の頭をなめて、それがあまり安らぎにはならないことに気づいて、ピグレットが言いました。「昨日、やろうとして忘れてたことをちょうど思い出したよ。明日にはできないことさ。だから、いまから帰ってそれをしなきゃいけないと思うんだ。」
「そう。じゃあ、午後にやったらいいよ。君と一緒に行くから」とプーが言いました。
「午後にできるようなことじゃないんだよ」と、ピグレットがすぐに言いました。「それは、とても特別な午前中のもので、午前中にやらなきゃならないんだ。もしも、できることなら、この時間の間ーーきみ、いま何時といったっけ?」
「十二時ころだよ」とプーがお日様を見ながら言いました。
「言おうとしたのは、12時と12時5分の間ってことだよ。だから、プー、ごめんねーーなにかな?」
プーは空を見上げて、それから、口笛をもう一度聞くと、彼は大きな樫の木の上の方の幹を見上げて、そこに友達をみつけました。

「クリストファー・ロビンじゃないか」と彼は言いました。
「あぁ、そうだよ」とピグレットが言いました。「彼がいると安心するね。さようなら」そして、できるだけ早く家へと駆け戻っていった。あぶないことから離れることができて嬉しかったのです。

クリストファー・ロビンは、静かに木を降りてきました。
「くまのおばかさん」と彼は言って「なにをしていたんだい?最初は、雑木林を二度回って歩いて、それから、ピグレットが君のことを追っかけて一緒に回って、それから、君は、四回目を回ったーー」
「ちょっと待って」と手を持ち上げてプーが言いました。
彼は、できるかぎり思慮深く、座って考えた。それから、自分の足を足跡の一つに合わせて・・そして、鼻を二回ほどひっかいて起き上がりました。
「うん」とプーが言いました。
「わかったよ」とプーが言いました。
「自分はバカで思い違いをしてたんだ」と言いました。「そして、脳みそがないクマだったんだ」
「君は世界で一番素晴らしいクマだよ」とクリストファー・ロビンがなだめるように言いました。
「そう?」とプーは希望をもって言った。そして、急に明るくなりました。
「ともかく」と彼は言いました。「もう、おひるごはんの時間だよ」
そして、彼は家へ帰っていきました。
(第3話の終わり)
(第四話) イーヨーがしっぽをなくして見つける話
年取った灰色のロバ、イーヨーは、森の角のアザミが茂ったあたりに一人で立っていて、かれの前足をいっぱいに広げて、頭は反対側に傾けて、何やら考えごとをしていました。ときどき、悲しそうに「なぜ?」と思ったり、ときどき、「なんのため?」と思ったり、ときどき、「なにと同じくらい?」と思ったりーーときどき、何を考えているのかもよくわからなかったりでした。なので、くまのプーさんが話をしにやって来ると、イーヨーは、陰気な感じで「こんにちは」といいつも、しばらく考え事をしなくてよいのでとても喜ぶのでした。

「ちょうしはどうだい」とくまのプーさんがいいました。
イーヨーは、頭を横に振り「それほどじゃないな」、「ながいことそんな風に感じたことはなさそうだ」と言うのでした。
「おや、おや」「それはお気の毒に。ちょっと見てあげよう」とくまのプーは言いました。
なので、イーヨーはそこに立って、まわりを悲しそうに見渡し、くまのプーさんは彼の周りを一周しました。

「どうしたのかな?しっぽはどうしたんだい?」と彼は驚いて言いました。
イーヨーは、「なにが起こったっていうのだい?」と言いました。
「それが、ないんだよ!」
「本当かい?」
「うーん、しっぽがあるのかないのか。それに間違うことなんかないよね。で、ないんだよ。」
「じゃあ、なにが?」
「なにもないんだよ」

「どれ、見てみよう」とイーヨーは言って、ちょっと前までしっぽがあったところにゆっくりと振り向いてみて、そこにはたどり着けないので、もとのところに行きつくまで逆側から回ってみて、それから、頭を下げて前足の間を見て、最後に、長く、悲しそうにため息をついて「どうやら君が正しいようだ」と言いました。
「もちろん、自分がただしいさ」とプーは言いました。
「それでわかったよ」と、陰気にイーヨーはいいました。「それで、なにもかも説明がつ。まちがいない」
「どこかに落としてしまったんだろうね」とくまのプーが言いました。
「だれかがとっていったにちがいない」とイーヨーは言いました。そして、長い沈黙の後で、「あいつららしいさ」と付け加えました。

プーは、何か役に立つことを言わなくてはと思いましたが、それが何かがわかりませんでした。なので、なにか助けになることをしようと決めました。
「イーヨー」「自分、くまのプーは、君のしっぽを探してあげる」と厳かにいいました。
「ありがとう、プー」とイーヨーは答えました。「君は真の友達だ」と彼は言いました。「あいつらとはちがう」と言いました。
それで、くまのプーはイーヨーのしっぽを見つけに出かけました。
プーが出発したとき、森はお天気のよい春の日でした。青い空にやわらかな小さな雲がたわむれ、ときおりお日様の前を、お日様の光を消そうとするようにスキップして通り過ぎ、次の雲がそれに続くのでした。雲を通して、そして雲の間からは、元気強くお日様が輝き、ブナの木が美しく身に着けている新緑のレースのわきで、一年中毛皮を着ていた雑木林は古くやぼったくなっていました。雑木林とやぶを抜けて、くまは行進しました。ハリエニシダとヒースが生えた開けた斜面をおりて、清流の岩っぽい川底を超えて、左岸の急な土手をあがってヒースのところに戻り、そして、疲れてお腹をすかせて、最後に百エーカーの森にたどり着きました。そこには、百エーカーの森にはフクロウが住んでいるからでした。
「そして、もしもなんでも知っているのは誰かと言えば」、とくまは自分に言いました。「それは、フクロウで、なにかについてなにかをしっているんだ」、と言い、「じゃなきゃ、自分がくまのプーという名じゃないさ」と言いました。「そうだから」と付け加えました「そうなのさ」
フクロウは栗に木に住んでいて、とても魅力的で、だれよりも年季の入った古風なたたずまいで、あるいは、くまにはそう見えたのであって、それは、玄関にノッカーと呼び鈴がついていたからです。ノッカーの下には、張り紙があって
「もし、応答 いりなら 鳴らして くださ」
と書かれていて、呼び鈴の下には、
「もし、応と 欲 いっぱって くださ」
と書かれてました。これらは、森の中だただ一人、字を書くことができるクリストファー・ロビンが書いたものでした。いろんな意味で賢く、「フクロ」と書いて読むことはできるフクロウではあったけど、「はかし(はしか)」とか「バタードースト(バタートースト)」のような精緻な言葉には参ってしまうのでした。

くまのプーさんは、2つの注意書きを、初めは左から右へと、そのあとに、何か見失うことがないようにと、右から左へと、注意深く読みました。それから、しっかりと確かめるため、ノックして、ノッカーを引っ張って、呼び鈴をノックして引っ張り、「ふくろうさん!応えて遅れ。じぶんはクマだよ。」ととても大きな声で叫びました。するとドアが開いて、フクロウが中から用心深く外を見ました。「こんにちはプー」、「ちょうしはどうだい?」と彼は言いました。
「ひどくて悲しいんです」とプーは言いました。「それは、友達のイーヨーが、しっぽをなくしちゃったからです。そして、彼はふさぎ込んでいるんです。なので、彼のために、どうしたら探すことができるか教えていただけないでしょうか?」
「そうか」とフクロウが言いました。「このようなときの慣習的方法(customary procedure)は・・」
「その、ぱりぱりマネー、進行ケーキ(Crustimoney Proceedcake)って、なんでしょうか?」とプーは言いました。「私は、脳みそがとてもちっちゃいクマなので、長い言葉には手を焼いてしまうんです」
「つまり、どうするかということだよ」
「そうなら、気にはしません」とプーはつつましやかに言いました。
「やらねばならぬことは、こういうことである。まず、報償を出すとの知らせを出すこと。そしてーーー」
「ちょっとまってください」とプーは手を挙げて言いました。「どうしたらよいのでしょうーーなにを言ってらっしゃるのでしょうか?話をしたときにくしゃみをされたので」
「くしゃみなどしてはおらんが」
「いいえなさいました。フクロウさん」
「いいや、していない。知らず知らずにくしゃみをすることはできないもんだ」
「では、なにかくしゃみがされたことなく、それを知ることはできないというのですね」
「私が言ったのは、「まず、報償をだす」ということだよ」
「あなたは、もう一度されましたよ」とプーは悲しそうに言いました。
「報償だ!」と、フクロウは大声で言いました。「イーヨーの尻尾をみつけたものには大きななにかをあたえると、張り紙を書くのだよ」

「あぁ、わかりました」とプーは、うなづきながら言いました。「何か大きななにかのことですが」と、夢心地で続けました。「自分は、だいたい、朝のこの時間、何かをちょっとだけ食べています」そしてフクロウの居間の角の食器棚をもの欲しそうに眺めて「ただ一口のコンデンスミルクか何かと、はちみつかなんかをひとなめーー」
「それでは、」とフクロウは言いました。「張り紙を作って森中に張ろうではないか」
「はちみつのひとなめ」とくまは一人でつぶやきました「もしも、そうでなければ、そうなるときに」
そして、大きなため息をついて、フクロウの言うことを一生懸命聞こうとしました。
しかし、フクロウは、長い長い言葉をつかって、ずっとずっと続けて、しまいには、また、始めのところにもどって、彼は、この張り紙はクリストファー・ロビンが書いたのだと説明しました。
「私の玄関の前にあるこれらは彼が私のために書いてくれたものなのだよ。わかるかね、プーよ」
プーは、しばらくの間、フクロウが言うことすべてに対して、目を閉じて「はい」と「いいえ」と交互に言い続けていて、最後に、「はい、はい」と言った後だったので、今は、フクロウが何をいったのかよくわからずに「いいえ、まったく」と言いました。
「わからないのかい?」とフクロウは少し驚いて言いました。「来て見てみたまえ」
それで、二人は外に出ました。そして、プーはノッカーとその下の張り紙を見て、呼び鈴ひもとその下の張り紙を見て、呼び鈴ひもをもっと見ると、こういうのをどこかで、いつだったか、見たことがあるなと感じました。
「きれいな呼び鈴ひもだろう?」とフクロウは言いました。
「なにか思い出すのです」とプーは言いました。「だけどなにだか思い当たらない。これはどこで手に入れられました?」

「森で見つけたんだよ。茂みに引っかかっていたので、そこに誰か住んでいるのかと思って、ベルを鳴らしたけれどもなにもおこらなかった。それで、もう一度、大きな音で鳴らしたのだ。そして、手に落ちてきた。だれも欲しがっているようには見えないので、家に持ち帰った。そしてーー」
「フクロウさん」と、プーは厳かに言いました。「あなたは、間違いを犯しました。それを欲しがっている人がいます」
「誰だい」
「私の親友の、イーヨーです。かれは、それがとても好きなのです」
「好きとは何が?」
「そこについているものです」と、くまのプーは悲しそうに言いました。

このように言葉を交わして、それを外して、イーヨーのところへ持って帰って、そしてクリストファー・ロビンが正しいところにもう一度釘で打って留めました。イーヨーは、森の中を飛びまわり、とても楽しそうに尻尾を振りまわしたので、くまのプーはおかしくなりました。そして、いそいで家へもどって、スナックをちょっとたべて腹を足しました。そして、三十分後に口を拭って、誇らしげに歌いました。
だれがしっぽを見つけたかい?
「僕がさ」とプーが言う
「2時15分前」にね
(ほんとうは、11時15分前でしたね)
僕がしっぽを見つけたよ!


(第4話終わり)
(第五話) ピグレットがヘファランプに出会う
ある日、クリストファー・ロビンがくまのプーさんとピグレットが集まってお話をしていた時、クリストファー・ロビンが一口食べ終えてからうっかりと「ピグレット、今日、僕はヘファランプを見たよ」と言ったのでした。
「なにしてた?」とピグレットが尋ねると、
「のっしのしとしてた」とクリストファー・ロビンが言いました。「多分、僕のことは見てなかったと思うんだ」
「僕も一度見たことがある」と、ピグレット。「少なくとも、そう思う」、「あるいは、そうじゃないかもしれないけど」と言いました。
「ぼくもだ」と、プーが、ヘファランプってどんんだものだろうと思いながら言いました。
「そうそう見れるもんじゃないよ」とクリストファー・ロビンがうっかりと言いました。
「いまはないかな」と、ピグレットが言いました。
「今時分はないかな」と、プーが言いました。

それから、プーとピグレットが一緒に家に帰るまで、みんなで別の話をしていました。最初に、百エーカーの森の際にある道をとぼとぼと歩いていたとき、二人はあまり話はしませんでしたが、小川まできて互いに助け合いながら飛び石を伝って渡った時、そして、ヒースの原を並んで歩いていたとき、二人は、あれこれと親しそうに話し始めました。そして、ピグレットが「もしも、君がみたなら、つまりね、プー」と言い、プーは、「僕もおんなじことを考えていたよ、ピグレット」と言いました。そしてピグレットが、「だけどさ、プー、覚えておいていないとね」と言ったので、プーは、「その通りだよ、ピグレット。僕はちょっとの間、忘れてはいたんだけども」と言いました。それから、六本松のところまで来たときに、プーは周りを見て誰も聞いていないことを確かめてから、とてもおごそかな声でいいました。
「ピグレット、ぼくは、決めたよ。」
「なにを決めたんだい、プー?」
「ヘファラントを捕まえることさ」
プーは頭をなんども振りってうなづきました。そして、ピグレットが「どうやって?」とか、「プー、できやしないよ!」とか、そんな感じの助けになるようなことをいうのを待っていましたが、ピグレットは何もいいませんでした。実のところは、ピグレットは、そのことをプーより先に考えてればなぁと思っていました。
すこし長く待った後で、「やってみせるさ」とプーは言いました。「罠を使うんだ。そして、それは、ずるがしこいやつなんだ。だから、僕のことを手伝ってくれないとね、ピグレット」
「プー」と、また喜んだピグレットは言いました。「やるよ」。そして、彼は、「どうすればいいのかい?」と言いました。そして、プーは「それをどうするかなんだ」。そして、二人は座り込んで考えました。
プーが最初に思いついたのは、とても深ーい穴を掘ることでした。そして、ヘファランプがやってきて穴に落ちる、するとーー
「なぜ」とピグレットが言いました。
「なぜってなに?」とプーが言いました。
「どうしてヘファランプが落ちるんだい?」
プーは前足で鼻をさすって、ヘファラントは一匹で歩いてきて、ちょいと鼻歌を歌っていて、空を見上げていて、ひょっとして雨がふるかななどと思っていると、穴の半分くらいのところまでくるまで深い穴には気づかないだろう、その時は、もう手遅れさ、と言いました。
ピグレットは、それはとてもよい罠だけれども、もしも雨が初めからふってたらどうなると思う?と言いました。
プーは、また、鼻をさすって、そのことは考えてなかったっていいました。そして、目を輝かせて、もしも、初めから雨だったら、ヘファランプはいつ晴れるだろうと思って空を見てるだろうから、穴の途中まできて手遅れとなるまで深い穴には気が付かないだろうと言いました。
ピグレットは、問題だった部分が解決したので、なるほどずるがしこい罠だなと思いました。
プーはそれを聞いてとても誇らしげに思い、ヘファラントはもう捕まえたようなものだと思ったのですが、他にもう一つ考えておかなければならないことがあり、それはこれでした。いったいどこに深ーい穴を掘ればいいのでしょう?
ピグレットは、ヘファランプがいるところで、ヘファランプが落ちるちょっと前、一歩くらい先のところがもっともいい場所だと言いました。
「だけど、それじゃ、僕たちが穴を掘るところをみられちゃうよ」とプーが言いました。「空をみてたら気づかないかな?」
「きづいちゃうだろうな」とプーは言いました。「もしも下を見たらば」
彼は、長い間考えてから、悲しそうに付け加えました。「考えていたほど易しくはなさそうだね。だからヘファランプはこれまで捕まえらられなかったんだろうね」
「そうにちがいないね」とピグレットが言いました。
ふたりはため息をつき、起き上がりました。そして、二人がハリエニシダのとげを少し抜きながら、もう一度座りました。そして、ずっとプーは独り言を言っていました。「なにかできればなぁ」なぜなら、彼は、とっても賢い脳みそがあって、うまくやるやり方さえ知っていればヘファランプを捕まえられるに違いないと思ったのでした。
「もしも」彼はピグレットに言いました。「もしも、僕を捕まえようとするなら、君はどうする?」
「そうだね」とピグレットは言いました。「自分だったらこうするな。罠をつくってそこにはちみつの壺をおくんだ。そうすると、君はそのにおいをかいで、そこに行こうとする。そしてーーー」
「そして、僕はそれを追っかけるんだ」とプーは興奮して言いました。「怪我をしないように十分に気を付けてだけども。そしてはちみつの壺をっとって、まずは、その縁を舐めて、もう残っていないというふりをして、その場を離れちょっと考えてから、戻ってきて壺の中の舐め始めるんだ。そしてーー」
「うん、それはどうでもいいよ。そこに君は行くから僕が君を捕まえる。となると、最初に考えるべきことは、ヘファランプは何が好きなのかだね。どんぐりかと思うけど違うかな。たくさん採ってこないとねーープー、起きて!」
幸福な夢の中に入っていたプーは、目を覚まして、蜂蜜の方がドングリよりも罠としては良いだろうと言いました。けれども、ピグレットはそうは思いませんでした。そして、二人はそのことで口論しそうになりましが、ピグレットは、もしもドングリを罠に仕掛けれるならドングリを探さなければならないけど、蜂蜜ならばプーが持っているものを少し分けてもらえばよいことを思い出して、「わかった。じゃあ、蜂蜜にしよう」と言いました。プーもそのことを思い出して「わかった。ドングリにしよう」と言うところでした。

彼は家に戻るとすぐに、食べ物置き場のところに行って、椅子の上に立って、もっとも上の棚からとても大きな蜂蜜の壺を下ろしました。壺には、「はちゅみつ」と書かれていましたが、確かめるために、紙の覆いをとって中に蜂蜜らしいのがあるのを見ました。「だけど、わからないさ」とプーは言いました。「そういえば、自分のおじさんは、いつだったか、ちょうどこれと同じ色のチーズを見たことがあると言ってた」それで、彼は、下を入れて大きなひとなめをしました。「うん!」と彼は言いました。「かれだ。間違いない。そして、蜂蜜が壺のそこにある。もちろん」と彼は言いました「だれかが、悪ふざけで底にチーズを置いていなければだけど。多分、念のため、もう少しだけ・・もしも、ヘファランプが、自分のようにチーズが嫌いで・・あぁ!」そして、大きなため息をつきました。「間違いない。ここのあるのは、まさしく蜂蜜だ」

確かなことが分かったので、かれは、ピグレットのところに壺を持って行きました。ピグレットは、彼が掘った大きな穴の底から見上げて、「もってきたかい」といいました。プーは「うん。だけど、壺いっぱいではない」と言いました。そして、ぷぐれっとにそれを投げて渡しました。ピグレットは、「いっぱいではないね。これが君がもっている全部かい?」と聞きました。プーは、「そうだよ」と言いました。実際にそうでしたから。それで、ピグレットは、穴の底に壺を置きました。そして、よじ登ってきて、二人は家に帰りました。

「さてと、おやすみ、プー」とピグレットはプーの家に着いた時に言いました。
「そして、明日は、朝の6時に松の木のところで会って、ヘファランプが沢山罠にかかっているか見ようね」
「6時にね、ピグレット。君はひもは待っているかい?」
「いいや。なんでひもが欲しいの?」
「かれらを引っ張って家に連れてくるためさ」
「おぉ!・・多分、ヘファランプは口笛を吹けばついてくるんじゃないかな」
「そういうのも居るしそうじゃないのもね。ヘファランプのことはわからないよ。さてと、おやすみ!」
「おやすみ!」
そして、ピグレットは彼の「侵入禁治」の家にとぼとぼと歩いていき、プーは寝る支度をしたのでした。
数時間して、夜が更けてきたころに、プーは、突然、落ち込んだ気分で起き上がりました。かれは、以前も落ち込んだことがあり、それがどういう意味か知っていました。彼は、お腹がすいていたのです。それで、食糧棚の方へ行き、椅子の上に立って最上段の棚を探しましたが、何もありませんでした。
「これはへんだ」と彼は思いました。「ここにはちみつの壺があったことはしっている。縁までいっぱいだった。そして、「はちゅみつ」と書かれていた。だから、ハチミツと知ってたんだ。おかしいな」そして、それから、上へ下へとうろうろし、どこにいっちゃったんだろうとぶつぶつ言ったのです。こんな感じに。
とってもとても 不思議だな
ハチミツあると 知ていた
壺にはラベルが ハチミツと
とってもおいしく 壺いっぱい
いったいどこに いったんだ
いったいどこに いったんだ
とってもとても 不思議だな
プーは3回ほど歌うように独り言をつぶやきながら、突然、思い出したのです。プーは、ヘファランプを捕まえるためにずるがしこい罠の中にハチミツを入れたのでした。
「あらま」とプーは言いました。「ヘファランプに親切にしようとしたことからこうなったんだ」そして、ベッドに戻りました。
しかし、プーは眠れませんでした。寝ようとすればするほど寝られなくなりました。眠ろうとするときにときどきはよいやり方となる、ヒツジの数を数えましたが、うまくいかなかったのでヘファランプの数を数えてみました。そしたら、もっと眠れなくなりました。なぜなら、数えたヘファランプの皆がプーのハチミツにまっすぐに向かって食べ尽くしてしまうからです。数分間、惨めな思いで横んあっていましたが、587匹目のヘファランプが壺をなめていて、「これはとてもよいハチミツだ。こんなもの食べたことがない」と独り言を言ったときに、プーはもう我慢できなくなりました。プーは別途から飛び起き、家を走り出て、まっすぐに六本松のところに走っていきました。

太陽はまだ眠っていましたけれども、百エーカーの森の上の空には薄明かりがあって、太陽が起き上がってきてもう間もなく寝間着を脱ぎ捨てるように見えました。夜明けの明かりの中で、松の木は冷たく淋しく見えました。そして、とても深い穴は実際よりも深く見えて、プーのハチミツ壺は形だけが見えてどこか神秘的でした。しかし、穴に近づくにつれて、彼の鼻は確かにそれがハチミツがあるとプーに伝え、準備万端に、プーの舌が口からでてきて舐めまわすのでした。

「なんと」と、壺の中に鼻を入れてプーは言いました。「ヘファランプが食べている!」そして、彼はちょっと考えて「んじゃない、自分がたべたんだ。忘れてた」
実のところ、プーはほとんど食べてしまっていたのでした。しかし、壺のずっと底の方にちょっとだけ残っていたので、プーは頭を入れて舐めようとしたのです・・・

やがてまもなくピグレットが目を覚ましました。起きるとすぐに「おぉ」と独り言を言いました。そして「そうだ」と勇敢に言いました。それから、もっと勇敢に「まったくもってそうだ」と言いました。しかし、彼はあまり勇敢には感じていませんでした。なぜなら、彼の頭の中でいったりきたりしている言葉は「ヘファランプ」だったからです。
ヘファランプはどういうものだろう?
獰猛(どうもう)なのかな?
口笛を吹いたらついてくるかな? そしてどうやってついてくるのかな?
ブタのこと好きかな?
もしもブタが好きだとして、ブタの種類で違うのかな?
もしもブタに対して獰猛だとすると、ブタと「侵入禁治」と呼ばれていたおじいちゃんとで違うのだろうか?

ピグレットはこれらのどれもわかりませんでした・・そして、彼は、一時間かそこらで、ヘファラントを初めて見ることとなるのです。
もちろん、プーが一緒にいってくれるので、二人ならもっと友好的だろうと思うのでした。しかし、もしもヘファランプがブタとクマにたいしてとっても獰猛(どうもう)だったら?頭痛がすると仮病をつかって、今日の朝は六本松に行くことができないと言った方がよいかな?でも、今日は良く晴れた日なのでヘファランプは罠には入っていないから、午前中はずっとベッドの中に居てなにもせずにいるのがいいかな?
そして、ピグレットは賢いことを思いつきました。六本松に静かに言って、ヘファランプが居るか確かめるため、注意して罠の中を覗き見るのはどうだろう。もしもいれば、家のベッドに戻り、そうじゃなけれそうしない。
なので、彼は出ていきました。最初は、罠にはヘファランプはいないだろうと思い、それから居るだろうと思い、罠に近づくにつれ居るに違いないと思いました。なぜなら、それらしきヘファランプの音が聞こえたからです。
「あれ、まぁ、あれ、まぁ、あれ、まぁ」とピグレットはつぶやきました。そして、逃げようと思いました。でも、彼はヘファランプがどんなものかとにかく見なければと思って、なんとか近くまで行きました。そして、罠の脇まで這っていき、中をのぞくと・・・

そして、その間、くまのプーはハチミツ壺を頭から外そうとしていました。振れば振るほどきつく嵌っていきました。
「おやまぁ」と壺の中で彼は言いました「おぉ、助けて」そして、ずっと「痛い!」と言っていました。そして、壺をあたりのものにぶつけてみましたが、そもそも何にぶつけているかがわからず、役に立ちませんでした。それで、彼は、罠からよじ登って出ようとしましたが、壺しか見ることができなかったので、というかそれすらあまり見ることができなかったので、どこを登っていけばよいのかわかりませんでした。なので、ついに、彼は頭を上げて、つまり壺ごとあげて、悲しみと絶望で大きな叫び声を上げました・・そして、ちょうどそのとき、ピグレットが見下ろしたのです。

「助けて、助けて」とピグレットが叫びました。「ヘファランプだ。恐ろしいヘファランプだ!お、お、おっそろファランプ、オソロファント、そふぇランプ!」
ピグレットは、叫ぶのが止まらず、クリストファー・ロビンの家まで慌てて走っていきました。
「いったいぜんたいどうしたんだい、ピグレット?」と、ちょうど起き上がろうとしていたクリストファー・ロビンが言いました。
「ヘフ」と、息が切らして声がなかなか出ずにピグレットが、「ヘフ、ヘフ、ヘファランプ」と言いました。
「どこに?」
「あそこ」とピグレットが、指を指すように振って言いました。
「どんなかんじなの?」
「えっと、えっと、いまま見たもので頭が一番大きなかったよ。クリストファーロビン。ものすごく大きなものでーーたとえようがないんだ。とんでもなく大きくてーーなんというかーーとにかく巨大な、壺みたいな」
「ふーん」とクリストファー・ロビンが言って靴を履きました「行ってみてみよう。さあ、行こう」

ピグレットはクリストファー・ロビンがいれば怖くはないので、二人で出かけました・・・
近づいてきたとき、「自分は聞こえたけど、聞こえるかい?」と不安げにピグレットが聞きました。
「なにか聞こえるよ」とクリストファー・ロビンが言いました。
それは、プーが見つけた木の根に頭をぶつけている音でした。
「そら」とピグレットが言いました。「怖くない?」そして、クリストファー・ロビンの手をしっかりと握りました。
突然、クリストファー・ロビンは笑い出しました。・・・笑って笑って・・そして笑いました。まだ笑っていた時に、ヘファラントの頭が木の根にぶつかって、壺がぶつかって、プーの頭が出てきました。

して、ピグレットが、自分がなんとおばかだったかがわかり、とても恥ずかしくなって自分の家に直行して頭痛で寝てしまいました。でも、クリストファー・おロビンとプーは一緒に朝食を食べに家に行きました。
「クマ坊」とクリストファー・ロビンは言いました「大好きだよ!」
「ぼくもさ」とプーが言いました。
(おわり)
第6話以降は、後日、追加していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
