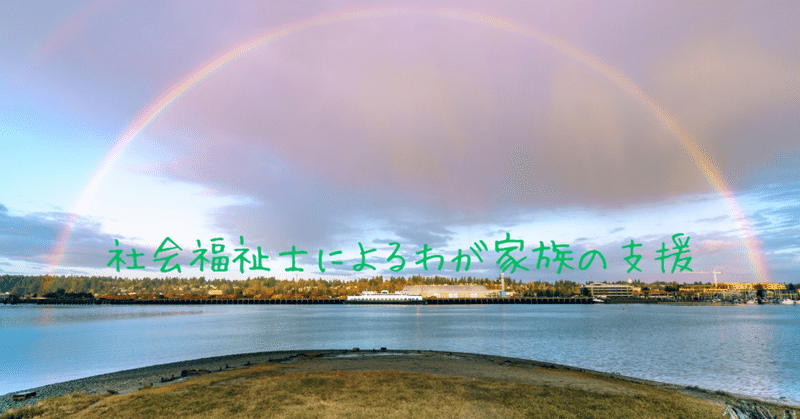
MSWという専門職としての役割
この仕事をしていて、自己決定ができるための支援って本当に大切だと思ってます。
言われたことじゃなくて、自らいくつかの選択肢から選んだことってあとから不満になりにくい。誰かのせいにもしづらい。
私は基本的にどんな状態でも在宅介護はできると思ってます。
もちろん誰でもできるわけじゃなく、希望したらできるって言ってるわけでもなく。
でも、できると思います。
やから、「この状態では家には帰れないです。」という言葉は使いません。
本人が家族がどんな条件を最優先に考えるのか。それ次第かなと思ってます。
以前も書いたけど、私は面談の後その人が笑顔で終われるように話をしたいと思っています。
家族が「家は無理です」と言っても本当にそうなのかなって。
それを今から相談するために私たちいるのになって。
家族の協力がどれくらいできるのか、経済的負担はどれくらい可能なのか。
家じゃない選択肢はどんなふうに考えているのか。
反対に「施設は嫌です。」と言われた時に
施設ってどんなところのことを言ってるのかな。
施設ってどんなところと思っているのかな。
施設じゃなくて転院だったらいいのかな。とか
私たちMSWが思う在宅と家族が考える在宅は違うし、私たちが考える施設のイメージや状況と本人や家族が考える施設のイメージや状況はかなり違うことも多いです。
せっかく私たち専門家と話す数少ない機会なので、正しい知識と情報を持って欲しいし、きちんと知識と情報が入れば今の選択肢もこれからの選択肢も変わっていくかもしれない。
そうやって自分自身(患者さま本人だったりご家族だったりすると思うけど)が知識を増やして、しっかり考えて、自己決定したことってクレームになりにくいです。
何も知らない時に質問って難しいと思うから。
MSWと最初に面談をした時にたくさん質問なんてできないです。
だからこそ、質問できるくらいの情報はこちらから先にお伝えしたいなと思ってます。
それから、ちゃんと考えてもらって期限を決めてお返事いただくように。
だからその前に、どちらを選択しても、どんな生活になるかを説明できるくらいの患者さんや地域の社会資源の情報収集は面談までに必ず準備しておきます。(専門職として話ができるようにするのも、大切な心構えやと思っています。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
