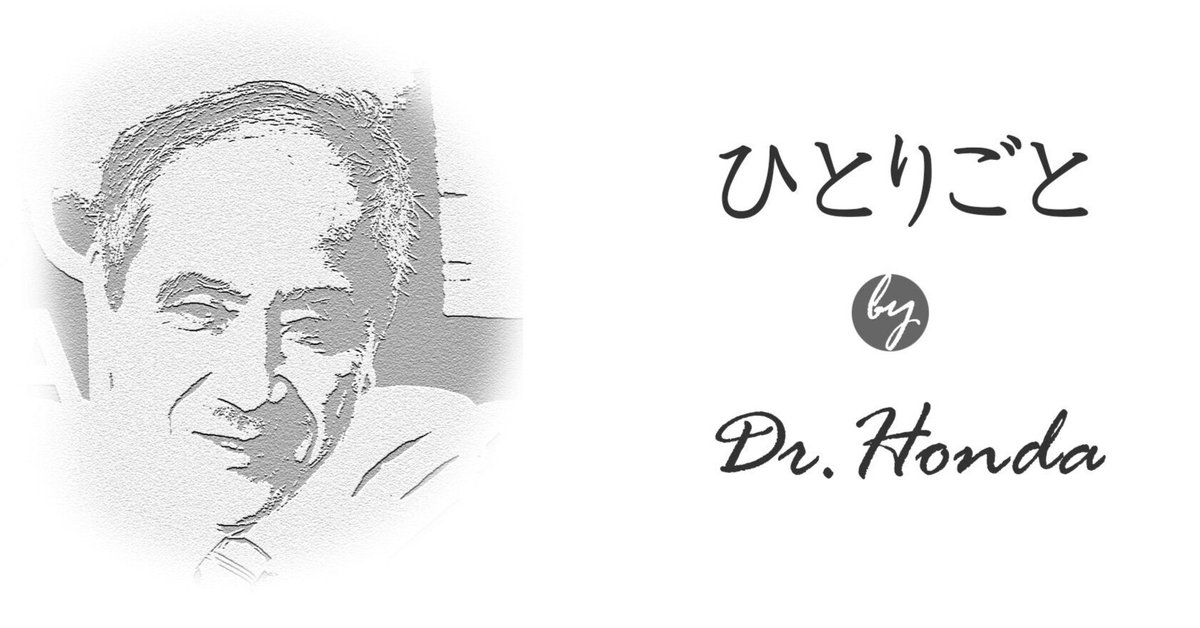
Dr.本田徹のひとりごと(26)2008.6.25
プライマリ・ヘルス・ケア30周年
- 振り返りと21世紀の新たな課題に向かって(その1)
またまた長のご無沙汰で申し訳ありませんでした。
去年の後半数ヶ月間、世界一周の保健紀行に出かけ、30年あまりの臨床医「稼業」から来た心身の疲れと「垢(あか)」を落として元気を取り戻し、新年早々から、東京下町山谷・浅草地域の医療に復帰しています。訪問看護ステーションコスモスと連携した在宅診療や、病院での外来、療養病床ケア、山友クリニックでのボランティアなどで急に忙しくなり、睡眠時間を削って帳尻を合わせる、以前の生活に戻ってしまいました。1年足らずのうちに医療崩壊が誇張とも言えなくなってしまった現場に身を置いて、あらためて<未完の課題>プライマリ・ヘルス・ケア(PHC)の今日性と切実さを思い知る毎日です。

1978年9月、中央アジア、カザフスタンのアルマ・アタ市(当時は首都)で開かれた、プライマリ・ヘルス・ケアの世界会議で出された歴史的なアルマ・アタ宣言から、今年はちょうど30周年を迎えます。2008年はその意味で記念すべき年なのです。海外では、21世紀に入ってから、WHOやPAHO(汎アメリカ保健機構)と言った国連機関、EU、アフリカ諸国などで、PHC再評価のさまざまな会議、またLancetのような有力医学雑誌でのPHC特集が継続して企画されていますが、日本では、厚生労働省や日本医師会がPHC30周年を公式に祝ったとか、国民の関心を喚起するような催しを開いたといった話はまったく聞きません。社会階層間や地域間、年齢による医療格差の増大、制度上また医療サービス提供面での「崩壊」が現実化している今こそ、日本がPHCの精神を思い起こし、1961年、国民皆保険制度創設時の原点に立ち返った改革を必要としているだけに、国際社会と日本の間に横たわる、PHCへの認識や取り組みの落差は、一層悲しいことと言えます。
プライマリ・ヘルス・ケアの源流とは?
PHCの原点や由来については、今年1月~4月に世界銀行東京センターで開催された私の連続セミナーや、他の場所でも説明させていただいてきました。繰り返しになりますが、PHCは20世紀後半の世界的な保健思想の集大成と呼ぶべきもので、単に開発途上国にだけ当てはまる原理原則に留まるのではありません。
PHCはまず、「基本的人権としての医療・保健」という原則に立ちます。これは1948年の世界人権宣言以来、1966年の国連社会権・文化権規約(いわゆるA規約)などに脈々と
受け継がれてきた普遍的な人権思想を、保健という視点から体系的に謳い直し、位置づけたものと言えます。
2番目に、PHCは1950~70年代に途上国で、必ずしも互いに関連なく行われてきた、保健・医療活動の卓越した事例をWHOが数々集積し、そこから共通して読み取れる、草の根の医療・保健状況改善のための多様な「成功要因」を例示・抽出したものと言えます。たとえば中国の文化大革命前後に有名となった「はだしの医者」は、保健ボランティアという、地域で基礎的な保健活動を担う人材を育成し、活躍してもらうという、現在につながるPHC戦略の雛形(ひながた)となりました。当時WHOの保健サービス強化局長だったK.W. Newell氏がまとめた”Health by the People”(1975)は、中国を含むアジア、アフリカ、ラテンアメリカ9カ国の事例をまとめた本で、その内容はアルマ・アタ宣言の中に生かされていきます。ただ皮肉なことに、中ソ対立の厳しい時代の中で開かれたアルマ・アタ会議に、中国は参加を見合わせたのでした。
3番目に、PHCは開発論としての側面をもちます。第二次大戦後、ヨーロッパの旧宗主国から次々と独立を果たしていったアジア、アフリカの多くの途上国の発展・自立を、いかに援助していくべきかについて、1950年代からさまざまな理論や試みがなされてきました。これについては、日本の開発教育の生みの親・育ての親でもあった、故・室靖先生が分かりやすく説明してくれています。室氏によると、開発援助についての先進国側からの最初の提案は、1949年のトルーマン米国大統領の就任演説で、「ポイント・フォア計画(Point Four Program)」と呼ばれ、世界の低開発地域の改善と成長を、米国の主導による工業化と物質的援助によって進めていく決意を述べたものでした。開発を、西欧化・工業化とほぼ同義に捉え、経済成長の恩恵を途上国の国民全体に押し及ぼすことで低開発から脱却するという、「浸透理論」(Trickle-down Theory)は、第一世代の開発論として1950-60年代を風靡(ふうび)していたものです。
しかし、60年代後半になると、絶対的貧困や格差の増大、都市のスラム化などの問題が深刻化し、米国防長官としてベトナム戦争に失敗し、「悔い改めた」マクナマラ氏が1968年世界銀行の総裁に就任したころから、開発思想の新しい流れが生まれてきます。1970年代になって、ILO(国際労働機関)を中心に「基本的人間ニーズ」(Basic Human Needs: BHNs)という考え方が提唱され、その充足をすべての人々に保障していくことを開発の基本に置く、第二世代の開発論が主流となっていきます。「もう一つの開発」(Alternative Development)、内発的発展論といった言葉も、この世代の開発思想を特徴づける言葉となりました。PHCは、こうした第二世代の開発論に属するものとして位置づけることも可能です。
1980年代の後半になると、人口爆発、環境破壊、エイズのような感染症(しばしばパンデミックと呼ばれる)と言った地球規模の問題が深刻になり、一国内の開発問題としてより、国境を越えた、地球市民社会の共通課題として捉えることが必要だという認識が生まれてきます。この第三世代の開発思想を特徴づけるのは、「持続可能な開発」(Sustainable Development)という考え方です。現実の「開発」プロセスは、これら3つの世代の開発アプローチが、ない交ぜになって進められてきたというべきなのでしょう。一方で、開発や援助行為自体を、途上国の人々の暮らしに対する侵略・収奪として、まるごと否定する、イヴァン・イリッチのような人の考え方もあったことを、忘れないでおきたいと思います。
4番目に、PHCとつながるもう一つの流れとして、自立生活運動(Independent Living:IL)や地域リハビリテーション(Community-based Rehabilitation:CBR)に代表される障害者の当事者運動を欠かすことができません。ILは1970年代初頭のアメリカで、CBRは1970年代末WHO主導のもと、途上国の各地で始まったとされます。PHCとCBRの間には、(1)施設・病院よりも地域に根ざした活動を重視すること、(2)住民の主体的参加や当事者性を求めること、(3)専門家の役割を「命令者」から、住民にとって真に役立つファシリテータに変えようとしたことなど、多くの共通性が認められます。
またデビッド・ワーナーの著作から明らかなように、1960年代からメキシコの山の中で、村の人々の保健活動を助けてきた彼は、まず、PHCに関わる「Where There Is No Doctor」(スペイン語の初版は1970年ころ、英語の初版1977年)、「Helping Health Workers Learn」(1982)という2冊の本をプロジェクト・ピアクスラの経験から作り、ついで、「Disabled Village Children」(1987)、そして「Nothing About Us Without Us」(1998)の2冊を、世界的に見てCBRの最も草分けの活動である、プロジェクト・プロヒモから生み出すという具合に、PHCとCBRは完全に地域住民の同じニーズの中から生まれ、発展してきたものと捕らえることができます。
デビッド・ワーナーと彼のメキシコでの活動については、この「ひとりごと」#23、「君の名はプロヒモ」にもまとめてありますので、関心のある方はお読みください。さて、去年9月、米国東部ニューハンプシャーのデビッドの家に一泊お世話になったとき、彼が1968年だったか70年ころ、スペイン語ではじめて「Donde No Hay Doctor」(医者のいないところで)を書き上げ、出版したときのことが話題になりました。その本をジュネーブのWHOに贈ったところ、本部のエリート、専門家たちは、「素人のくせにこんな本を書き上げ出版するなどもってのほかだ。訓練も教育も受けていない村人に、基本的なことに限っているとは言え、医療行為を任せるなど危険きわまりない」というひどい反応だったよ、と彼は笑って回想していました。
それから、10年足らずで、WHOはアルマ・アタ宣言を出し、むしろデビッドの考え方に大幅に近づいていったのですから、歴史の皮肉と言う以上に、「医者のいないところで」の作者の先見性を驚くべきなのでしょう。

最後の5番目にPHCは、参加型の保健教育活動としてありました。それについては、ブラジルの教育学者・哲学者で成人識字教育において革命的な方法を編み出し、実践した、パウロ・フレイレ、1970~80年代、多くの途上国で住民自身による学びを追及し、参加型農村調査法(Participatory Rural Appraisal:PRA)や参加型学習法(Participatory Learning & Action:PLA)を、ワークショップや著作を通して普及・啓発していった、サセックス大学のロバート・チェンバース、そして、デビッド・ワーナー自身、最後に、戦後信州の佐久病院で、芝居を使った住民教育やその他さまざま独創的な予防活動に、アルマ・アタ宣言の30年も前から取り組んできた、佐久病院の若月俊一先生がパイオニアとして輝いています。

シェアにとっての恩人二人
シェアはプライマリ・ヘルス・ケアを、創立時から会の指導的な理念として掲げ、タイでも、カンボジアでも、東ティモール、国内でも、最近の南アフリカでも、活動に生かしてきました。シェアの事業はその意味で、デビッド・ワーナーと工藤芙美子という二人のすぐれたプライマリ・ヘルス・ケア・ワーカーの働きなしには考えられないほど、多くの学びを彼らに負ってきたのです。
その工藤さんは、長年の中米での活動を終え、いま東ティモールで、再び、アイレウ県、エルメラ県の保健教育・保健ボランティア養成活動の助言者、トレーナーとしてがんばってくれています。また、デビッドさんには、去年10月、アメリカで私がお会いした際、2008年11月シェア創立25周年の記念に来日、講演やワークショップをしてくださるお約束をいただき、以降、ご連絡を取りつつ着々と準備を進めてきていたのですが、残念ながら、今年春、病気が見つかり、現在治療・静養中です。来年春以降には、ぜひ回復して来日の念願を果たしたいとおっしゃっていますので期待したいと思います。

PHCをめぐるお話は、まだ語り尽くせないので、「その2」、「その3」くらいまで続けていきたいと思います。とりあえず、今日はこれくらいで切り上げさせいただきます。
(2008.6.25)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
