
資本主義から見るE-waste
2021年最初の記事はこのタイトル、「資本主義から見るE-waste」で書いてみたいと思います。数か月前にあるセミナーでE-waste問題に関して講義依頼があり、その準備ノートとして「あなたのそのスマホ、いずれE-wasteになります。」を書きましたが、今回はちょっと違うアプローチで書いてみたいと思います。
書こうと思ったきっかけは、年末年始休暇中にいくつかドキュメンタリー番組を見たこと。番組を見ながら色々と考えていたので文字にしようと思いました。環境経済系をいくつか見たのですが、どの番組のトーンも、石油産業をベースとした資本主義から、石油に代わる新たな資源、データをベースとした資本主義社会を目指すべき、というような議論がいくつか行われていました。僕はこの意見に同感です。振り返れば資本主義というのはここ250年くらいの歴史しかなく、それまでは物々交換や労働の対価としてのモノを獲得することから始まり、それが希少価値の高い貴金属、つまり金や銀と労働やモノの交換となり、いつの間にか、お金を基にモノを作りお金を増やす、お金を増やすことが目的の資本主義社会の世の中です。

この250年間における資本主義社会はGDP換算では莫大な伸びを見せて、物欲社会としての人間社会を構築し、少なくともここ日本ではモノにありふれた豊かな生活を送っています。でもこの豊かな生活を得た裏では、不可逆的に陥りつつある甚大な環境汚染を引き起こしています。2015年に採択されたパリ協定が目指している今世紀末前に気温上昇を1.5℃に抑えるためには、今後30年間で1京(10,000,000,000,000,000)円もの環境投資が必要ともいわれています。もし人類が、産業革命当時からしっかりと環境対策を取っていたら、この1京円は必要なかったでしょう。この250年間の資本主義がもたらしたと富は、1京円より少ない、ということはありうるでしょうか?もしそうなら、富を得る価値よりも富を得るために犠牲にしてきた環境負荷の方が多いということになり、資本主義は人間のエゴにしか過ぎなかったとも言えるでしょう。
そしてコロナの2020年においては、日本もようやく重い腰を挙げました。2050年までにカーボンニュートラルを遂げて、脱炭素化社会を構築することを宣言しました。いわゆる先進国と呼ばれている国、しかも過去の日本の技術大国としてのイメージを踏まえると日本はすでに周回遅れになっている感はありますが、そこは同一性の高い日本人、その努力が集結し、日本人が持っている「小さなことをコツコツと」精神で、トップ集団にすぐに追いつくと思います。脱炭素化社会に重要となるのは新自由主義において、環境・サステナビリティをそのど真ん中に置いたビジネス主導型による脱炭素化社会、循環経済、分散型社会の3本柱を推し進めていくことです。そこに必要な法律の策定や足かせになっている法制度の改正等を、中央政府がバックアップしていくというチームワークが重要です。

では今後の資本主義はどこに向かうのか。それは、デジタル化社会による無形資産ベースの社会です。今までの資本主義というのは、物欲を満たすために地球資源を富に変えていく、モノを大量に生産して売りさばく、いらなくなったものは捨てていくという大量生産・大量消費が当たり前の社会でした。それが変わりだしていたのが1990年代、2000年代に入り日本でも循環経済が必要と言い続けてきましたが、それから20年経って少々リサイクル産業が整いだしてきたところだと思います。日本は少なくとも資本主義の多大な恩恵を2回(高度経済成長期(1955年から1973年)とバブル期(1985年から1991年))受けています。この2回の経済的恩恵、特に最初の高度経済成長がもたらした資本主義による経済発展の鮮明な記憶が日本社会、特に産業界に資本主義の魔法として根付いているので、脱炭素化社会という新たな軸に対して日本社会は周回遅れになったと言えるでしょう。
さて、前置きが長くなりましたが、今までの議論とE-wasteがどう関係するのでしょうか?高度経済成長期に各家庭に入ってきたのが、当時三種の神器と言われたテレビ、冷蔵庫、洗濯機を含む家電製品。家電製品の開発とともに私たちの暮らしも劇的に変化しました。2021年の皆さんの暮らしはどうでしょうか?家電を使っていない瞬間はありますか?見つける方が難しいですよね。逆を言うと、家電を製造している家電メーカーが私たちの暮らしを作っているのかもしれません。技術を開発したのは人間であり、暮らしを豊かにするアイデアを技術に取り入れたのも人間ですが、いざ使う立場になると、家電製品に人間が使われているかもしれません。皆さんの将来の暮らしは家電メーカーが握っている、かもしれませんね。
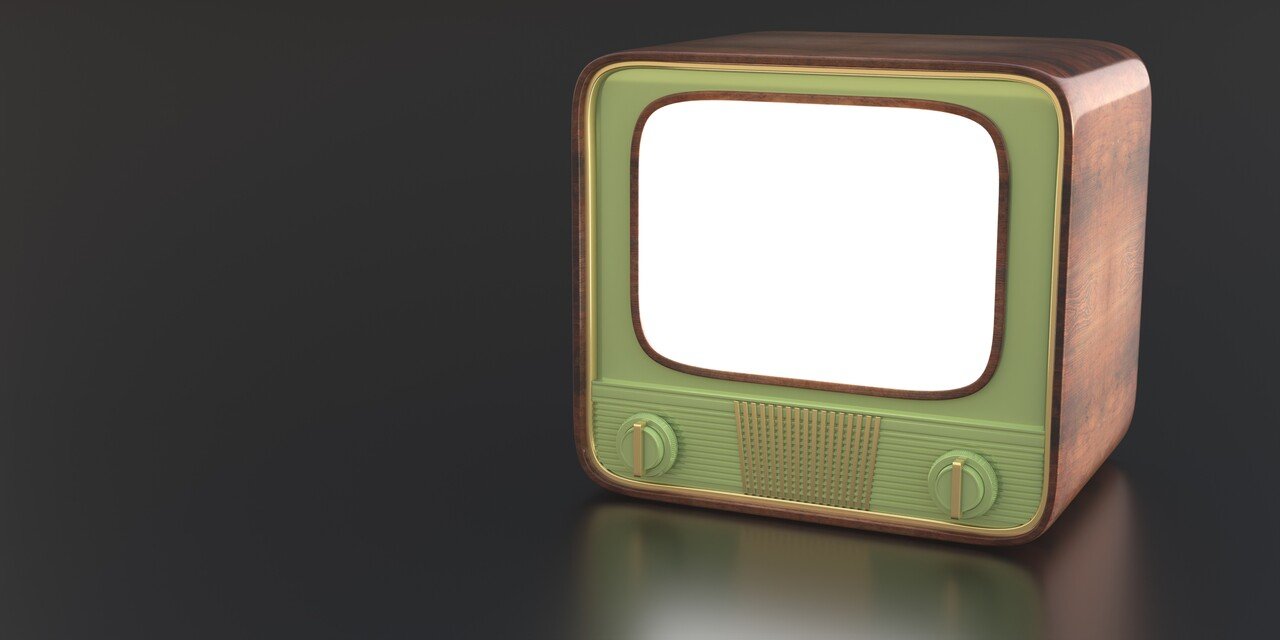
家電製品が使われるようになると自動的に問題となるのが、その廃棄物、電気電子機器廃棄物、略してE-wasteです。日本でも1990年代まで中古市場に回らない家電製品は埋め立て処分、と今から考えれば恐ろしい捨て方をしていました。埋め立て処分場がひっ迫してきたという理由から、1990年代にようやく家電リサイクルを行うべしという議論が始まり、1998年に通称家電リサイクル法と言われるのが制定され、2000年には循環経済社会の基盤となる各種リサイクル法が一通りそろいました。この時代は経済停滞期ではありましたが、社会は資本主義まっしぐらの物欲社会、モノを作って使用して、できる範囲でリサイクルをするという日常でした。
ではこの物欲を満たすためともいわれている、言い換えるとお金を目的としている資本主義は今後どう変わっていくのか?それが大きく見ることができたのが2020年、コロナの年です、日本は行動を自主的に制限する緊急事態宣言でしたが、世界の大都市では都市封鎖、ロックダウン、人間が都市国家を形成してから初の事態となりました。そこで人々が感じたのは、モノはいらない、でもデジタルでつながるのは重要ということです。デジタルの0と1を無限大に電気・電子的に結びつける仮想オンライン社会で過ごすのが、当面の私たちの未来社会ではないだろうか、という現状を認識するようになりました。人間の精神の欲望が資本主義で物欲になり、人間が自然破壊を進めた結果として現れた新型コロナウイルスにより物欲社会がデジタル社会へ突き進んでいる中、必要なのは、データです。

このデジタル化の流れと脱炭素化の流れば交わるとき、私たちの世の中の潮流は何に向かうのでしょうか?極端な言葉を使うと、モノのミニマリズム、必要最低限のモノさえあればあとはいらない。それを反映しているのがサブスクリプション方式、略してサブスク、シェアリングエコノミーが徐々に拡大しています。例えば自動車や自転車、洋服、そして家電も一部で事業がスタートしています。モノを保有するからモノを共有する、なるべくモノを持たず必要に応じて借りる、というのが今後の一つの流れとなるでしょう。それでも物欲がなくならないものはあるでしょうか?
それはスマホ。スマホがないとデジタル化社会の恩恵を受けることができません。日本のスマホ利用者は約7000万人、年代別みると10歳代から40歳代まで82~95%の保有率、インターネット利用者を見ると中学生以上から50歳代まで90%以上、60歳代でも約73%の人がインターネットを利用しています。これが答えでしょう。スマホとインターネットは私たちの暮らしのインフラです。ちなみに僕の場合は、仕事中はパソコン、読書はほぼ100%電子書籍、テレビはほとんど見ずに、スマホでNews PickesやNHKオンデマンドを見ています。

では世界ではどうなるか?全世界での携帯電話加入者数は約8億人、全人口の1/10程度でしょうか。でもこの数値も爆発的に伸びると思います。日本は固定電話からガラケー、スマホ、そしてこれから5G時代と半世紀以上かけて進化してきましたが、低所得国ではいきなりスマホ社会です。スマホのインフラ整備は、もはや必要のなくなった固定電話のインフラ整備費と比べれば格段に低いです。しかも、Google等は地上にアンテナを立てることなく、宇宙空間に衛星を飛ばしてそこから電波を飛ばすという構想もあるので、将来的には、貧困国でもある日この瞬間からスマホをみんなが使いだす未来が来るでしょう。
このような国において、かつて日本や欧米が見た資本主義の魔法を見ることなく、いきなりデジタル化社会をスタートすることができます。そうなった場合、日本のような物欲にまみれた資本主義が発展するのか、それともデジタル化社会に沿ったミニマル物欲社会となるのか、それとも別な形となるのだろうか?もちろん物欲の資本主義には、ある程度、GDP換算で2000ドル程度の生活レベルにならないと、そもそも物欲があっても経済的に余裕がないので物欲主義になりえないかもしれません。でもこのデジタル化社会という、今までの資本主義が経験してない社会を最初から構築していくことになる現在の低所得国の今後の経済成長パターンに、注目したいと思います。

となると、やはり残るのが、E-waste問題と新たに登場してくるのがデジタル廃棄物、つまりいらなくなったデータを誰がどう処分するべきか問題です。前者の方は、少なくともこの30年間ぐらい「E-wasteは問題である」と言い続けてきています。後者の方は、デジタルプラットフォーマーを含めた現在の我々の社会が直面している問題です。果たしてE-waste問題に解決が見えるのでしょうか?
資本主義における廃棄物もエンドレスな問題点です。ここ日本ではほぼすべての廃棄物が法律に則り適正に管理・処理・リサイクル・処分されていますが、道端を見るとポイ捨てが多く見られます。必ず落ちているたばこの吸い殻、プラごみ、PETボトル、心を痛めます。たまに家電も不法投棄されています。海外を見れば、日本のように適正に廃棄物管理を行っている方が少なく、高所得国が中心です。日本もかつてそうだったように、低所得国ではなかなか廃棄物管理まで手が回りません。このまま同じことをしていても今後加速度的に進むデジタル化社会においても廃棄物問題、特にE-waste問題は解決されずにきらびやかのデジタル化社会の闇となるでしょう。
ではどうするのか?この問いは国際社会においても既に30年くらい使い続けています。解決しないのです。何を持って解決かという論点もありますが、少なくとも環境負荷をかけない、そして脱炭素化社会を構築するために必要な循環経済の一部に組み込まれることが、解決したと言える瞬間です。私は廃棄物分野で仕事をしていますが、物欲の資本主義社会においては廃棄物問題は解決しない、と考えています。なんせ、資本主義社会においては、それが必要とする経済成長によって自然環境破壊を完全にやめることができた例はないので。法律、規則、ルールで廃棄物を管理することは重要ですが、それはあくまでも小手先の技にしかすぎません。物欲の資本主義からデジタル化の資本主義に移行したとしても、廃棄物問題は解決せず、E-waste問題もそのままあり続けるでしょう。「ではどうするか?」、その答えを深く考えるためにはこの式、経済学 x 哲学 x 社会学 x サステナビリティ学が必要になります。社会人類学者・民族学者レヴィ・ストロースも言っていました、「そんなのは西洋人の思い上がりで、ただの勘違いにすぎない」、と。今自分たちが目にしている問題を違う目線から考えないといけません。僕は日本生まれの日本人で高所得国の価値観の頭ですが、これが非現実であると考え、今日本人が持っている社会、今後進むデジタル化社会、ではなく、その要素も入りつつも低所得国や低位中所得国が必要としている未来社会を描き、そこにアプローチしなければなりません。このポイントをど真ん中において、今年の僕の仕事の挑戦としたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
